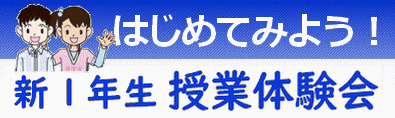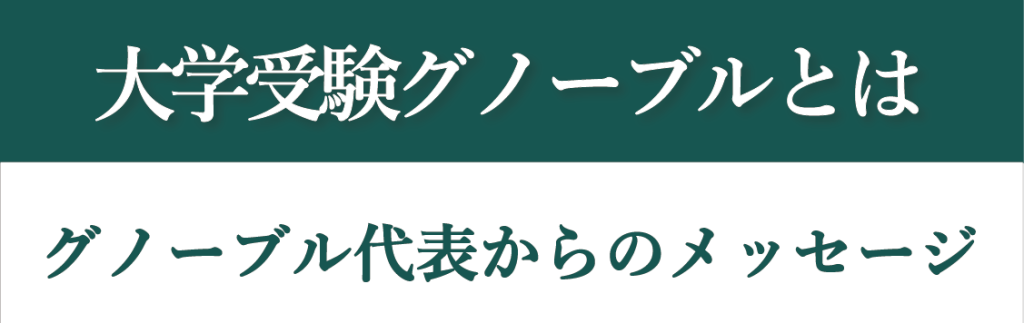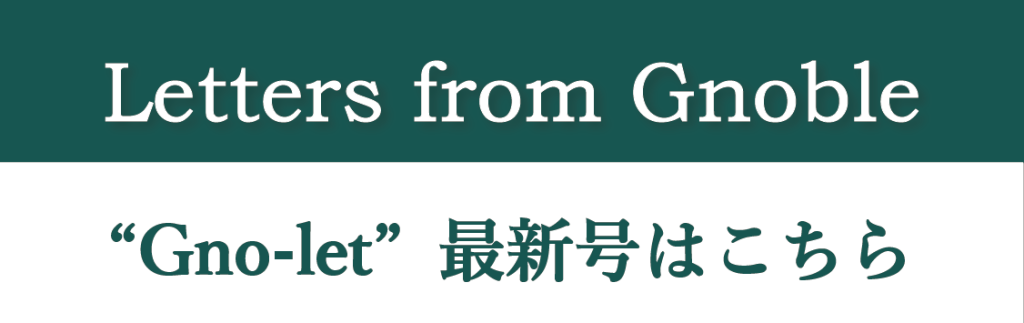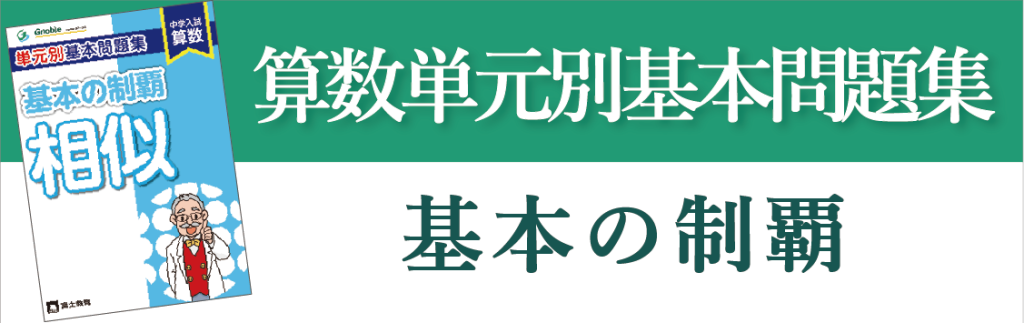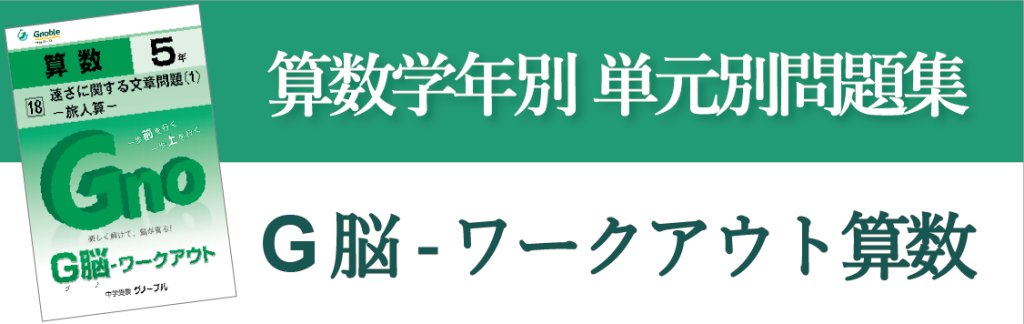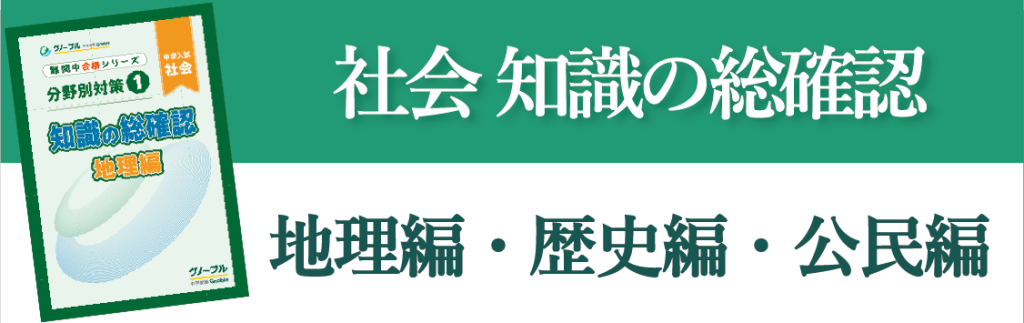目次
〈男子校編〉
浅野中学校
麻布中学校
栄光学園中学校
海城中学校
開成中学校
慶應義塾普通部
攻玉社中学校
駒場東邦中学校
サレジオ学院中学校
聖光学院中学校
世田谷学園中学校
筑波大学附属駒場中学校
東京都市大学付属中学校
桐朋中学校
武蔵中学校
早稲田大学高等学院中学部
早稲田中学校
〈女子校編〉
桜蔭中学校
鷗友学園女子中学校
吉祥女子中学校
女子学院中学校
田園調布学園中等部
豊島岡女子学園中学校
フェリス女学院中学校
雙葉中学校
立教女学院中学校
〈共学校編〉
青山学院中等部
開智日本橋学園中学校
川口市立高等学校附属中学校
慶應義塾湘南藤沢中等部
慶應義塾中等部
渋谷教育学園渋谷中学校
渋谷教育学園幕張中学校
千葉県立千葉中学校
筑波大学附属中学校
桐蔭学園中等教育学校
東京都立小石川中等教育学校
東京農業大学第一高等学校中等部
広尾学園小石川中学校
広尾学園中学校
三田国際科学学園中学校
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校
早稲田実業学校中等部
はじめに
学ぶことは本来、楽しくわくわくするものです。自分で考えたり表現したりする楽しさ、さまざまなことを知る面白さ、理解できた喜び、これらを感じながら学んでいくことは、他の人の考え方や感じ方が分かるようになることであり、自分の世界が広がることであり、夢を叶える力を育てていくことにもつながります。
しかし、12歳の子どもたちとそのご家庭にとって、初めての受験となることがめずらしくない中学受験においては、時に自分が正しい道を歩んでいるかどうか、不安に感じることがあるかもしれません。
ここに第12期生の生徒・保護者さまの「合格者の声」をまとめました。
今年もいくつも印象深い子どもたちの「声」が登場します。
「小学生になっても手をつないで歩けば良いじゃない」
「先生が面白いの!あの先生に習いたい!」
「やらない後悔より、やって大成功」
「わかったわかった、じゃあ最後は気楽に楽しんでくるね」
第12期生の先輩たちの体験の中には、今後の勉強法や心構えなどで参考になることがたくさんあるはずです。ぜひ全編に目を通されることをお勧めします。
この「声」が皆さんの良き「道標」、「元気の素」になれば幸いです。皆さんも夢に向かって一歩一歩進んで行かれることをお祈りいたします。
また、第12期生の生徒・保護者さまからいただいた「声」は、私たち職員にとっては大きな喜びです。これらの「声」を励みに、私たちはさらに情熱を持って皆さまの夢の実現に向かっていきます。
Gnoble職員一同
浅野中学校
先生にめぐまれた
浅野中学校進学A君
4年生の後半〜5年生の前半までに知識と基礎を身につけないと、6年生では大変なことになります。面倒くさくても本当に読解などを集中して読んだ方が良いです。そうすれば6年生の授業はとても楽しくなります。楽しくなると点数が40点は上がります。僕は先生にめぐまれていたので、合格することができました。
グノーブルで過ごした息子の時間
浅野中学校進学A君の保護者様
塾を検討し始めたのは、3年生の夏でした。複数の塾の体験授業を受け、いちばん楽しかったグノーブルへ通う!と本人が決めました。息子は、習い事のロボット教室を5年生の冬まで、サッカー部を6年生の夏合宿まで続け、勉強時間を多く取ることができない分、宿題は集中して取り組みました。そんな状況の中、分からないことは決して持ち越さないようにしようと決め、特に算数は授業前に質問に行きました。4年生の最初のころは恥ずかしかったようですが、そのうちに慣れてきて、自分から「今日はグノに早めに行くね」と行動するようになりました。共働きのため、親が勉強をみることはありませんでしたが、保護者会には必ず参加し、各教科の先生に改善点を相談しました。成績は不思議なくらい、ずっとBブロックでした。そのため、いつも授業を担当いただくのは同じ先生方で、息子の性格や弱点を理解してくださっていました。授業中怒られたことは何度もありますが、最後までグノーブルだけを頼り、授業が楽しいので行きたくないと言ったことは一度もありませんでした。
ずっと親子で心掛けていたことは、
・グノーブルの授業に全集中
・漢字と「基礎力テスト」は朝やる
・毎日やるべきことの可視化
・保護者会で国語科の先生がおすすめされた本はすべて親子で読む
・寝る前に理科・社会の暗記ものをやる
・塾のない日は21時に寝る(睡眠大事)
過去問は先生にご相談して、計画したスケジュール表に沿って進めることができました。特に苦戦していた社会は、息子の信頼する先生に記述を添削いただき、モチベーションアップをしていきました。入試本番前日、大好きな理科の先生から激励してもらい、「僕は先生に合格を報告する」と、良い緊張感で挑むことができました。
志望校へ挑む朝、校門前で言った私たち家族の合言葉は「やらない後悔より、やって大成功」。グノーブルで過ごした息子の時間は、大成功でした。息子を支えてくださった先生方、グノーブルの仲間のみなさん、最後まで一緒にがんばってくださって、本当にありがとうございました。

楽しんだもの勝ち
浅野中学校進学B君
僕が、グノーブルに入ったのは3年生の時でした。
グノーブルに決めた理由は、テスト後の体験授業が面白く、勉強の本質を初めて理解できたような感覚を得たからです。
グノの授業は単に暗記しろと言うのではなく、この現象や変化がなぜ起こるのかを分かりやすい例を出して説明してくれることや、複数の解法の中でなぜこの解法の方が良いのか、まで教えてくれるものでした。毎回の授業が、理解を深める面白いものだったので、長時間の授業も退屈にならず、短く感じるほどでした。興味をもって先生の話を聞くことで集中力が上がり、成績も上がると思います。
各教科の面白いポイントを教えます。
■算数:グノの問題は難しいですが、正解した時の喜びはとても大きいです。
■国語:授業の翌日などにグノの問題の文章を読み返すと速読の練習にもなり、先生の面白い話を思い出すことができます。「漢字道場」の内容が面白いです。
■理科:先生が徹底的に教えてくれ、解けない問題でも、先生に解説をしてもらうと理解できます。
■社会:授業を聞いていく中で、先生劇場が開幕したり、例を出してもらったりするので非常に面白いです。
【入試直前】意外と落ち着いていました。普段のグノレブテストと同じように緊張しすぎないようにしていました。前日には先生から電話があり、その電話が自分を落ち着かせてくれました。
【入試本番】入試問題は、誰もまだ解いていない‘‘クイズ‘‘として楽しみながら過度に緊張せずに解きました。
【入試を終えて】僕は4科目それぞれに新しい気づきがあり、生涯役に立つ、勉強の面白さをおしえてくれたグノーブルを選んで正解だったと思います。
そして、先生が授業の合間にしてくれる面白い話は、受験勉強で苦しい時に思い出し、つらさを吹っ切ることができました。
浅野の発表で合格だと聞いた瞬間、喜びが爆発し「やったぁーーー」と叫んでしまいました。ここまで支えてくれた先生方、本当にありがとうございました。
楽しかった人生初の受験
浅野中学校進学B君の保護者様
中学入試が終わったある日、中学受験を題材にした漫画を熟読中の息子に聞いた。
「中学受験はどうだった?」息子は漫画を置いて言った。
「なんかねぇ、楽しかったぁ」
私はこの言葉を聞いて、我が子の人生初の受験が大成功だったなと感じた。
「小学生らしく」—お世話になったグノーブルの先生方からこの言葉を何回も耳にした。
無駄な競争やプレッシャーをかけず、受験校は本人の意思を最優先にしてくれるグノーブルに毎週楽しく通い、マウント合戦もなく、しっかり睡眠もとりながら小学校での行事も満喫し、本当に小学生らしい受験ができたと思う。
「受験」と聞くと、深夜までピリピリしたムードの中でガリガリ勉強をするイメージを持っていたが、それは大人の「受験」であり、小学生の「受験」は全く違うことに気づかせてくれたのもグノーブルの先生だった。
グノーブルのテキストと楽しい授業で各教科の基本・考え方を身につけられたおかげで、6年生の秋以降の演習・過去問対策は本当に楽しそうだった。
キッチンに立つ私に「こんな問題出たよ~」「これ知ってる?」とたくさん話しかけてくれた。好奇心のアンテナの感度が上がっていて、ワクワクが伝わってきた。集中して問題を解く息子の横顔を見ているのが大好きだった。
夕飯時には日曜特訓や通常授業・土曜特訓でのクラスのお友達や先生の話(物真似)で食卓が彩られ、気がつけば入試直前期となった。
GnoRevテストや外部模試で上がり下がりを経験し、親の腹も据わってくると共に、「この子は緊張しない方が良い結果を出せる」予感がした。子どもを緊張させないためには、まず自分が緊張しないこと。
中学校はたくさん見学し、可能な限り先生や生徒さんと話し、各学校のここが素敵!を集めた。結果、受験した学校は偏差値で言うと幅広く、息子が大好きな学校ばかりになった。
「入試期間中は、合否結果を知りたくない。空気で感じてしまうから親にも見てほしくない」という要望に応えて、入試結果は息子が次の入試に向かった後に見た。これは親の精神安定上非常に良かったと思われる。
また、SNSで評判だった問題集は山のように買ったが、結局やったのはグノーブルのテキストだけだった。SNSでは、すごく勉強をしていることを匂わせる書き込みが目につき、心配・不安になることもあったが、入試前によく聞いた嵐の曲「Are you ready?完璧なんてない Sweet,sweet」のところを親子で熱唱して吹き飛ばした。
そう!小学生なのだから完璧なんてない!それよりもグノーブルで学ぶことの楽しさ、考えること、伝えることの楽しさを知ることができたのだから、その力を存分に発揮して自分らしく楽しんでおいで~!と笑顔で入試に送り出した。
結果、大好きな志望校からたくさんの合格をいただくことができた。全てグノーブルで身につけた息子の“実力”で掴み取った桜だった。
最後に、親の立場からグノーブルの教科別の楽しみ方を書いてみたい。
中学入試までの学習期間はとても長く、山あり谷ありだ。辛くて投げ出したくなることもあるだろう。でも、子どもも親もみんな個性があるのだから合格への道程はみんな違っていていい。
つらくなったとき、少しでも明るい気持ちになれるヒントになれば嬉しい。
■国語:グノーブルの教材は優れたお話が多く、時々一緒に読んで感動を共有していた。宮沢賢治の詩に親子で大号泣した夜は一生忘れられないだろう。設問を解き、解説を読むことで本文の内容が深められる体験は子供の精神的成長に大きく役立った。また、6年生になって気がついたのだが、GnoRevテストの解説の結びに心打たれることが多いので、親子で読むことをお勧めしたい!
■算数:子どもが乗り気で無い時は、ストップウオッチ片手に全ての問題を計測して記録した。1回目より2回目の方が速く解けることが殆どなので、そのたびに褒めて盛り上がる(但し、じっくり考える癖もつけたいので、行き詰った時のみの限定処置)。
■理科:グノラーニングチェックをやりこみ、先生の授業を楽しむ!親は授業動画で楽しめる。テキストのレベルの高さに舌を巻くこともあるが、「マニアックだわぁー」と笑いながら先生から指定されたところのみをきちんとやれば大丈夫。
■社会:息子が大好きな教科で、5年生の時から自主的にテキストにある記述問題を取り組み、添削してもらった。添削で活を入れられたり、応援メッセージがあったりで楽しかった。地理・歴史・公民を単なる暗記科目にせずにじっくり学べるのがグノーブル社会の良さ。6年生夏の理社特訓テキストが感動ものなのでお楽しみに!!
グノーブルの先生方、スタッフの皆様、本当にありがとうございました。後輩の皆様、どうか楽しみながら桜を咲かせてください。がんばって!!!応援しております。
麻布中学校
勉強してください!
麻布中学校進学A君
僕は3年生の11月からグノーブルに入りました。グノは良い意味で個性的な先生が多く、授業はとても楽しかったです。
また、日曜特訓のコース昇降では発奮しました。友達同士で、刺激し合いながら向上していく場があったのも、グノのおかげです。
6年生の夏からは僕なりに頑張り、9月は比較的良い成績が取れました。しかし11月の模試で、算数偏差値44、4科偏差値50を取ってしまい、12月にはさらに算数偏差値42、4科偏差値48。このときは、「なんで麻布なんか目指したんだ。もっと簡単なところを目指せば良かった。麻布みたいなハイレベルなところを目指すからつらいんだ!」と泣きわめき、親を困らせました(ちなみに、このときの麻布の合格可能性は30%)。
12月の終わりには冬期講習、正月特訓も始まりました。このあたりから、やるしかないと腹をくくり、きちんとやりました。算数が苦手で、算数さえ克服すれば・・・という状況だった僕が1月にやったことは、
①これまで解いた算数の過去問の苦手分野を集めた過去問セレクト
②ときどき、日曜特訓・冬期・正月特訓の算数
です。直前期はとにかく過去問をやる。しつこいぐらいにやる。これが、自信にもなりました。
ここからは、麻布の各科目の感想を書きます。
■国語:長文に慣れよう。空欄を埋めよう。漢字は絶対に間違えない。
■算数:極端に難しい問題はそれ程出ない。過去問を解いてれば割とできる。丁寧に解けば、その過程を麻布の先生が読み取ろうとしてくれます。試験が始まったら、まずは全体の問題を見渡してから着手する(大問1が難しくて、それ以降が簡単だったときに詰みます)。
■理科:日常の何気ない光景に興味を持とう(いわゆるおばあちゃんの知恵など)。僕は、『Newton』で読んでいた「素数ゼミ」が出題されて、ウキウキで解けました。リード文をしっかり読もう(そこに答えが書かれていることが結構ある)。
■社会:すごく有名ではないけれどときどき目にする社会問題について考えよう。おすすめは、『中高生新聞』のニュース捜査班や、NHKの7時のニュースのあとにときどきやっているニュース解説など。僕は『中高生新聞』で出てきた書店の話が出題されて、ウキウキでした。さらに、一年前はNHKのニュース解説でやっていた水道について出題されていました。
本番は、周りからシャーペンの音が聞こえても気にしない。目の前の問題に全集中。せっかくの入試なので、最後の一秒まで、思いっきり楽しみましょう。
「何やってるんですか、勉強して下さい!」(教育系YouTuberの言葉より)祈 合格
子どもの学力は試験当日まで伸びるというのは本当でした
麻布中学校進学A君の保護者様(父)
文字通り自由奔放マイペースを絵に描いたようなうちの次男ですが、制服がなく自由な校風で、自宅からも通いやすい麻布を第一志望にすることは、グノーブルに通い出した4年生の頃から、本人の中にも漠然としたイメージとしてあったと思います。
ただ、1年生の時から少年野球を続け、6年生の時には主将を務めていたこともあり、本格的に麻布を意識した勉強をスタートできたのは、少年野球を引退した6年生の夏以降になってからかもしれません。算数があまり得意ではなく、国語と社会で点を稼いで理科はほどほど、というスタイルでしたが、9月頭の外部模試の結果までは算数も含めて比較的順調でした。
しかし、夏の疲れが出たのか、11月から12月にかけての外部模試では、算数を中心に4科目での偏差値が10くらい下がる大スランプに陥り、本人も親も大いに焦りました。何をどうしたら良いか全く分からない大変な状況でしたが、グノーブルの先生方にもご相談しながら本人ともよく話をして、この際もう一度徹底的に基本に立ち返ろうと、6年生になってからの「基礎力テスト」をもう一度やり直し、間違えた問題はさらに何度も繰り返すという、「基礎力テスト」の復習を徹底しました。また頻繁に出るようになった計算ミスについては、基本的な計算練習を何度も再確認しました。その甲斐あってか、12月の終わりくらいにはようやく最悪の状況からは脱しつつある兆しが見えてきました。
そこからは毎日本人を励ましながら、冬期講習・正月特訓・日曜特訓・土曜特訓・通常授業の課題をこなすことに加え、麻布の過去問をとにかく解かせました。特に算数については、明らかに苦手か理解が甘いと思われるタイプの問題だけを抜粋した過去問セレクト集を作り、それを何度も解き直しました。結果的に、算数は20年分を10回以上は回したと思います。またその他の科目についても、基本知識の再確認に加えて、できなかった記述問題の書き直しの徹底など、1月は本当に本人も頑張っていました。日を追うごとに麻布仕様の力が付いてきているのがこちらにも伝わってきて、実際に一番伸びたのは最後の1週間だ、と言っても良いくらいの感覚がありました。この頃には親子喧嘩の回数も減り、親子ともに秋の大スランプの時とは打って変わった穏やかな気持ちで試験当日を迎えることができました。これが一番大きかったです。
そして本番のあとは、これまでめったにテストの感触や手応えを語らなかったのに、理科の問題が面白かった、算数は過去問と比較して今までで一番できた、自分の持っている力を全て出し切ったからどんな結果になっても悔いはないけど絶対に受かっていると思う、と自信満々でした。そして迎えた2月3日15時、掲示板に受験番号を見付けた時の感動は、言い表す適切な言葉が見当たらないくらいのものでした。秋以降のあの大スランプを克服し、何とか結果に繋げた本人の頑張りを誇りに思いますし、そしてそれを支えてくださったグノーブルの先生方には感謝しかありません。
保護者の皆様も、日々の成績に一喜一憂し、子どものやる気のない態度にイライラする毎日かと思いますが、子どもとグノーブルを信じて、そして勝負は本当に直前期に決まると言っても過言ではないので、最後まで駆け抜けて下さい。
マイペースな子どもと両親を支えて下さったグノーブル
麻布中学校進学A君の保護者様(母)
グノーブルには、3つ上の長男が4年生のときからこの度受験を終えた次男まで、計6年間お世話になりました。本当にありがとうございました。
マイペースな次男は、通塾開始直後は楽しく通っていましたが、自分のやりたい遊びに夢中になってしまうと切り替えられず、今日は行かない!と毛布にくるまってしまったり…。通塾の習慣を当たり前のことにするまで、勉強の中身以前のところで、グノの受付の方や先生方のお手を煩わせたことも一度や二度ではありませんでした。
土日祝はほぼすべて少年野球の活動で自由時間や勉強時間がほとんど取れませんでしたので、5年生終了までは、通塾が平日週2日の夜のみというグノーブルのシステムは我が家にとってありがたいものでした。
野球以外にも趣味・関心対象が多い子なのであれこれ忙しく、4年生と5年生の間は、基礎力テストと通常のテキストの最低限の家庭学習すらもままならない日もありました。苦手な計算マスターは一度に解くのは左半分だけ、ときには左上7問だけ、という工夫をして、遅ればせながら6年の11月になって全ての計算マスターを終えたような状況でした。
6年生の6月のグノの保護者面談にて、第一志望に「麻布」と書いていたら、着席するなり担当の先生から「この志望校はどれくらい本気ですか?」と単刀直入に聞かれました。それくらい、その時点での成績は合格圏から遠く乖離していたのだと思います。先生の言葉を本人に伝えたら、10段階のスイッチの2~3くらいは入ったように思いますが、それでもまだ受験が「自分ごと」にはなっておらず、隙あらば勉強から逃げて好きな遊びをしていました。
いざ勉強するとなると、機械的に勉強を進めることには抵抗があるのか、自分のアタマで考えることへのこだわりを見せ、教えようとする親と衝突することも何度もありました。知的好奇心はあるかもしれないけれど、受験日という期限や試験の解答時間が決まっている中学受験には向かないタイプなのかもと本人も親も幾度となく悩みました。
野球チームを休部した6年生夏からは本人なりに頑張り、9月に成績が伸びて、これなら麻布を目指すと言ってもおかしくないと思ったのも束の間、10月11月とあらゆるミスを連発してどんどん成績が下降していき、深刻なスランプに。「麻布なんてハイレベルなところを目指すからこんなにつらいんだ」と言って自ら偏差値表を持って来てラクに入れそうなところはないかと探したりして、私も一緒になって大変苦しみました。何度もグノの先生に電話で相談し、本人にも直接声をかけていただき、さらには、近所の先輩(グノと野球チームの先輩で、現麻布生)にも来てもらって麻布の様子を聞かせてもらったり…。もがき苦しんだ末、やっぱり麻布に行きたい!という思いを新たにし、12月前半は算数基礎力の復習・反復、(せっかく全てやり終えたと思ったばかりの)計算マスターに再び取り組み、急がば回れとばかりに基礎固めに徹しました。
正月特訓と冬期講習の期間は自分で勉強する時間が取りにくく、後半は息切れ気味でしたが、ようやくこの頃から「やるしかない」という覚悟が見えてきたように思います。
それでも1時間ほど勉強しては好きな趣味で息抜きして、ついつい休憩時間が長くなることも。そんな時は、中3長男が「オマエ、やばいぞ。それで本当に受験生か? そんなんじゃ落ちるぞ!」とムチを打ってくれました。(次男が頑張っているときには「自分に合う学校に受かるように出来ているんだから何とかなるだろ」と励ましたりもしてくれました)家族ワンチーム、さらには近所の先輩やグノの先生方まで大いに巻き込んでの総力戦でした。
1月最後の日曜特訓から帰宅すると頭痛、37.5℃あったときは本人も親も内心大いに焦りましたが、とにかくすぐに寝させて、次の日もゆっくりさせたら解熱したのでヤレヤレ…。
2月1日の4日前に最後の通塾(火曜夜)が終わってからは、思いっきり早寝早起きに切り替えました。1月31日の晩は20時過ぎにはベッドに入ったものの、緊張からでしょう、珍しくお腹が痛いと言いました。何年も前から憧れてきた麻布、しかも両親とも是非入れてあげたいと熱望していることを本人も重々承知していて、相当なプレッシャーだったと思います。12歳には荷が重すぎるのではないかという心配と、この子ならきっとやってくれるという信頼の間を揺らぐ親心で、相当精神的につらい最後の数週間でしたが、母親としては表面上はとにかく穏やかににこやかに頑張りを見守って、元気に試験を受けさせることに注力しました。
当日は、どんな問題が出るのか楽しみだ!と元気に会場に向かい、終了後は、同室にグノ麻布コースの知り合いがいたとのことで、笑顔でおしゃべりしながら退出してきて「やれることは全部やった! ベストを尽くした。これでダメなら実力不足」と晴れ晴れとした顔で、その後も「大丈夫、麻布受かってる」と自信ありげな様子。過去のグノレブでも、外部模試でも、こんなに手応え良かったと話したことはなく、「試験ハイ」みたいなものかもしれないと、笑顔でねぎらいながらも合格発表を見るまでは不安に押しつぶされそうでした。14:59にまず2日に受けた併願校の不合格を見て、落ち込む間もなく、麻布の合格発表のページへ。合格受験者番号の一覧から、本人がいち早く「あった!」と見つけたときの喜びと安堵は何度思い出しても熱い涙がこみ上げてしまいます。本当によくがんばったと我が子を誇りに思うとともに、こんなマイペースな次男と熱血すぎる両親を根気強くサポートしてくださったグノの先生方に心から感謝申し上げます。

受験生のみなさん
麻布中学校進学B君
僕の経験上、人前で度胸がつく経験をすると良いと思います。
僕の場合、ピアノの発表会を何度か経験し、失敗しても誰も責めやしないことに気づいたおかげで、受験当日も一切緊張しないで受けることができました。そういう経験をたくさんすることで、受験本番の緊張感を少しでも減らせます。
〇4年生では社会・理科の知識や漢字、算数の植木算・和差算・消去算など5、6年生の土台となる部分への理解を深めることが大切です。
〇5年生では知識系全般+算数の応用の仕方や、理科の典型問題、国語の読解に力を入れると良いです。僕は算数と理科の典型問題は得意でしたが、暗記系と読解が苦手でした。だから暗記系は家族に単語帳を作ってもらったり地図や年表に書く練習をしたりしました。これは6年生でも続けた方が良いです。しかし読解は何をしても伸び悩み、5年生が終わってしまいました。
〇6年生前期では、算数の問題が急に基礎から応用に変わって、得意教科だった算数の成績が少し下がってしまいました。でもそれはみんなそうなのであまり落胆しなくて良いです。そして通常授業の内容を復習、実践、応用する土曜特訓が始まり、勉強量が増えます。また、このころついに伸び悩んだ国語の偏差値が上がり始めました。それは今まで全くつかめなかった「文脈たどり」と「傍線部に合わせる」と「本文全体の流れや変化をとらえる」が少しずつできるようになったからです(このためには授業に出た文章だけでもいいので何度か読み返すことが大切です)。そして、このころには志望校の問題の特徴や時間配分を知っておくと良いです。
〇6年生後期は日曜特訓が始まり、同じ学校を目指す人が分かって、その人たちと比べて自信を無くしてしまうことがあるかもしれません。しかしどのコースにも天才はいて、その人を基準にする必要はないので大丈夫です。僕も麻布コースに明らかに自分よりも頭の良い人がいましたが、こうやってその人たちと一緒に麻布に受かることができています。直前期や当日は、短期記憶でも良いので暗記をすることが大切です.
息子と歩んだグノーブルでの受験生活
麻布中学校進学B君の保護者様
息子は3年生の終わりからグノーブルにお世話になりました。最初は受験をするか決めかねていましたし、遊び盛りの年頃なので宿題に慣れず、4年生が親子共に一番精神的に大変だったように思います。それでも授業は面白かったようで、ほぼ休むことなく通うことが出来ました。送り迎えの時に息子が授業について楽しそうに話してくれることが私の楽しみでもありました。
志望校は自分で選択してほしかったので、4年生から文化祭や説明会に参加しました。どの学校も魅力的でしたが、中でも麻布中学に惹かれたようでした。自由な校風の一方で、謙虚でしっかりと地に足がついた感じが印象的でした。早めに目標が出来た事で、受験に対する迷いはなくなったようでした。また、グノーブル卒業生の麻布生のお話も息子に大きな影響を与えたと思います。
6年生の夏まではリビング学習で親子一緒に勉強をしていましたが、夏からは本人の希望もあり、一人部屋で勉強するようになりました。部屋で勉強するようになってからは集中力に欠けることもありましたが、12月頃になると本人の自覚も芽生え、不得意な国語も書く力がついて来たように思います。
授業や勉強についてはグノーブルの先生方にお任せしながら、家庭ではコピーと丸付け、スケジュール管理、最後の方は間違いノートや不得意な漢字の単語帳を作ってサポートしていました。
心配もあり受験校を多めに申し込んだので、1月はほぼ毎日過去問を解いておりました。
試験が近づくにつれ、段々何を勉強するべきか分からなくなってきたので、間違えた所を中心にやり直しをしました。最後は今まで頑張ってきたことに自信を持って、やるべきことはほぼやったから、これで落ちたら仕方ない! と子供と納得して本番に臨みました。
受かっていても落ちていても良い経験になると思い、合格発表は学校まで見に行きました。番号を見つけた時の息子の嬉しそうな顔や感動は忘れられません!
グノーブルは少人数なので先生との距離も近く、厳しくもメリハリのある指導をしていただき、また最後までしっかりとサポートしていただきました。お陰様で受験校全て合格という想像以上の結果となりました。
グノーブルの先生方にお任せして本当に良かったと感謝しております。ありがとうございました。

受験体験記
麻布中学校進学C君
僕は4年生の時にグノに入塾しました。最初のグノレブテストでは、いきなり偏差値60台になりました。それは、恐らく社会で100点を取れたからだと思います。そのため、社会はとても自信がつき、得意科目となりました。社会が得意になったのは、父が僕を旅行に連れて行ってくれたからだと思います。本当は海外旅行にもっとたくさん行きたかったようですが、コロナ禍だったので国内旅行ばかりとなりました。しかし、中学受験の地理の範囲は日本国内だけなので、地理がとても得意になりました。一方で、6年生になると理科が得意になり、麻布の過去問では(40点満点中)30点台を取るのが普通になりました。理科が得意になったのは、科学の本をよく読んでいたからだと思います。父は本を買ってきては机の上におき、僕が興味をもって本を開くよう誘導していました。
5年生の秋ごろ、算数の偏差値が50台前半になることが何回も続きました。そこで、今までやっていなかった30枚ほどたまっていた「計算マスター」(裏表両方あり)を1日1枚やるようにしました。表が100点だったら裏をやらなくて良いルールにして、一か月計算をやりこみました(ちなみに、裏が100点だったことは1回だけで、表が100点で裏をパスしたことは一度もなかった。毎回90点台で100点を逃していた)。また、今までは、数日ため込んで、たまってしまった日に一気にやることが多かった「基礎力テスト」を、6年生になると毎日やるようにしました。すると、計算力が飛躍的に伸び、6年生の5月ごろに算数の偏差値が63となって開花しました。そして、理科の成績も良かったのでαコースに行くことができました。
しかし、αに行くと、全然時間が足りず、しかも自分の苦手な速さの問題だったので、打ちのめされてクラス昇降によって一回で落ちました。そのあとは算数中心で勉強していきました。
そして、地獄の夏期講習がやってきました。夏期講習が始まった時から2月5日までは、日記をつけていました。お盆は旅行に行きましたが、他の夏休み期間はずっと勉強をしている状態でした。そのあとは夏期学校別特訓がありました。2日間だけなので勉強量はあまり多くはありませんでしたが、1日の密度としては夏期講習より濃かったです。秋もたくさん勉強しました。最後に理系の授業でまたαになりましたが、その時は授業についていくことができました。
冬期講習・正月特訓は、すべて麻布コースを受講しました。正月特訓は、夏期学校別特訓や日曜特訓が4日まとめて来た感じで、受験生活の中で一番大変でした。
入試の時はあまり緊張しませんでした。僕は麻布は第一志望ではなく、2月2日の受験校が第一志望でした。2日の受験校の合格発表が3日にあり、3日の入試を終えてすぐに合格発表を見ました。結果は不合格。とてもつらい時間でした。
そのあと昼食(焼肉)を食べ、すぐに麻布に合格発表を見に行きました。結果は合格。とても安心しました。
がっつり伴走した中学受験
麻布中学校進学C君の保護者様
「君達が合格できたのは、父親の『経済力』そして、母親の『狂気』」
人気漫画に出てくるこの言葉を聞いて、私は父親の狂気をなめるな、中学受験伴走は母親の専売特許ではないぞ、と思いました。
当初、私は中学受験には反対でした。ただ、息子と妻はなんとなく受験する方向に気持ちが傾いていました。それならばがっつり伴走してやろう、と思いました。戦はやるなら勝つ気でやらねばなりません。
たいていのプロジェクトは始まる前に成否が決まっていると思っています。なので、事前の情報収集は入念に行いました。まずはブログ、YouTube、小説、先述のセリフが出てくる漫画等から数か月間、中学受験に関する情報を浴び続けました。そこで理解したことは以下のとおりです。
・勉強で子供を追い詰めてはいけない
・合格よりも学ぶことを好きになってもらうことが一番
・おそらく我が家は麻布、渋渋、都立小石川のいずれかを第一志望とするであろう
早速上記3校の過去問を見て、私は驚嘆しました。難しすぎる。
どうやったらこの問題を3年後に解けるようになるのか。息子はまだ九九もまともに言えません。通常の方法では無理だ、と思いました。テストの問題を解く力の前に、根本的な好奇心や教養、総合的な読解力の育成が必要だと感じました。また、この問題が解けるようになるまでどうやって勉強のモチベーションを保つのか。
まずは社会と理科が好きになるような活動に集中しました。グノーブルのテキストを片手に、旅行に連れていき、山脈を見せつけ、河川に足を浸し、城に上り、戦争博物館で戦禍の記憶を刻み付け、名産を貪り食べる。天の川を仰ぎ、鉱石を掴ませ、フーコーの振り子の前で30分鎮座し、地層に頭を突っ込む。
また、漫画(「Dr.STONE」、「実験対決」)を部屋にそっと置いておくと、勝手に読みふけってくれました。その後も「面白くて眠れなくなる」シリーズ等をそっと差し入れしておくと勝手に貪り読むようになっていました。これで理科が得意になったのが大きかったです。
あと、こっそり息子が好きそうな本を買ってこれみよがしに夫婦で読んでいると、のそのそとあとに続いて読んでいます。そうそうそうやって読解力をつけて語彙を吸収しろ~と念じながら後ろ姿を見ておりました。
しかし、ここまでしても、算数だけはなかなかできるようにはなりませんでした。やはり算数が中学受験の鬼門。息子は計算が遅くミスも多く、どうしても算数の点が伸びません。そこで、5年生の冬に息子と“会談”を持ち、地獄の計算特訓を開始することに決定しました。溜まった計算マスターや問題集を毎日一気に解く日々を続けました。
その結果、ついに新6年生になったあたりから算数の点数が伸びていきます。
6年生の秋以降は、まるで原子力潜水艦に乗って深海にいるような感じでした。まさに勉強のみに集中している状況。静かでした。
6年生の秋から冬にかけて集中力が発揮できる状態に持っていくために、それ以前の期間があるのだと思います。ここからは父親の狂気が息子の邪魔にならぬよう、私は粛々とテキスト整理とスケジュール管理と過去問コピーに集中しました。ここまでくると問題が難しすぎて、教えることなどとてもできません。この半年間は家族が一体となった素晴らしい期間でした。
最終的には、私の“狂言”が現実化し、麻布を受験することになりました。
息子は本当にグノーブルの授業が好きなようでした。単に暗記や問題処理を促すのではなく、どの科目も好奇心をくすぐる授業を行っていただいたようで、とても感謝しております。
親に関して言えば、父と母二人で、事務処理と健康管理と狂気の分担を無理なくしていくことが重要かと思います。

みんなで頑張った中学受験
麻布中学校進学D君
僕は5年生の時に入塾をしました。算数が得意、社会は歴史が好きで地理は少し苦手、理科は単元による、国語は大の苦手でした。国語においては、最後まで先生を心配させたと思います。
そんな国語が苦手な僕の勉強法です。
通常授業では、復習テストで100点を取ることを心がけていました。1月の最後の授業まで、学校別特訓よりも日々の復習に力を入れていて、親に心配されたほどです。
麻布中の問題については、科目関係なく「相手に伝える力」が必要だと思います。
🔳国語:国語が苦手な僕にとっては漢字が得点源のため、落とさないように間違いノートを作りました。僕は物語文が得意だったので、麻布中の問題は他校よりも比較的解きやすかったのですが、誤字脱字・字の大きさ・同じ文言の繰り返しなどに気をつけて文章を書くのが下手でした。なかなか直らなかったので、冬に先生からセルフチェックをするように言われました。忘れないために表を作り、トイレ、塾のノートなどに貼って毎日確認できるようにしました。本番直前もこのセルフチェック表を見ていました。
🔳算数:僕の一番得意な科目でしたが、どの教科よりもたくさん問題を解きました。塾の授業でやったところ以外も解いて、特に苦手な図形は復習を何度もして、初見の問題も解きました。夏の確認テスト、直前期の学校別でも、良い成績を取ることができました。
🔳理科:麻布中は問題が独特なので、慣れるために過去問と日曜特訓でやった問題を繰り返し復習していました。また、捨て問があるので、それを意識しながら解きました。
🔳社会:5年生から入塾すると、すでに授業では地理が一通り終わっています。そのあとも学ぶ機会はたくさんありますが、地理に不安があったので、直前期まで基礎の復習をやりました。麻布中合格のためには、リード文を読んで、問題のヒントを探す練習をし、知識問題は落とさないようにすることが大切です。
僕はグノーブルで先生に言われたことだけを頑張ってきました。国語が苦手な僕でも先生のおかげで合格することができました。温かい先生ばかりで、この塾に出会えて本当に良かったと思います。本当にありがとうございました。
受験生のみなさん頑張ってください!!

グノに感謝
麻布中学校進学E君
今日、僕は3年生から6年生までのテキストを集めて、ひもでくくりました。全部積み重ねると、自分の身長を軽々と超えるほどのテキストが出てきて、こんなにたくさん勉強してきたのだと思うと驚きました。
テキストを見ると、そのときの授業の様子が思い起こされました。先生方の話はいつも面白く、家でよく両親に授業の内容を話しました。雑談と思うような話も、全てが大事な話なので、毎回の授業では全力で耳を傾けました。
家庭学習では頭の中に先生方が住んでいるイメージで、授業の様子を思い出したり、家族を相手に授業を再現したりして理解を深めました。社会でなかなか点が取れないことを先生に相談したところ、一問一答の問題などでは、問題に答えられるようにするだけでなく、答えとなる単語の説明も出来るようにすることが大事だと言われました。それを心がけて勉強することで、単語が覚えやすくなり、記述問題も答えやすくなったように感じます。
受験当日には今までイメージしていたような「緊張で張り詰めたピリピリした雰囲気」というものはあまりありませんでしたが、やはり緊張はしました。だから、この学校にいる人の中で自分が一番頭が良いと信じ込んだり、先生方からのアドバイスを思い出したりして自分に自信を付けました。また、休憩時間には毎回欠かさずトイレに行ったり、深呼吸をしたりして緊張を和らげました。それでもやっぱり少し緊張しましたが、普段の力を発揮できたと思います。
最後に、グノーブルの先生方や友達に出会えたことは本当に良かったです。本当にありがとうございました。

3年間のGnolife
麻布中学校進学F君
僕は、新4年生のタイミングでグノに入塾しました。これから僕の3年間のGnolifeとおすすめの勉強法を紹介します。
まず、僕は3年生まで中学受験のための勉強をしていなかったのですが、3年生の間は理科の授業で習うものの実物を見てみたりすると良いと思います。社会では、なんとなくどこの地方ではこれが有名だ、などというイメージを持っておくと良いと思います。また、勉強に偏らずスポーツをやると良いと思います。
4年生では、まず毎回できるだけ楽しくグノに通いましょう。僕は近所の友達と都道府県庁所在地を覚えるゲームをして遊んでいたため、社会は得意でした。このように、得意科目はあった方が良いと思います。
5年生になると勉強が難しくなり、授業時間や復習時間も長くなりますが、復習テストのための勉強をしていれば次第に力が付きます。それでも、長期休みの間は、合間に苦手な単元の復習をやっておくと良いと思います。
6年生では土曜特訓が始まります。しっかりと復習の曜日を決めて取り組むようにしましょう。そうすれば適度な息抜きができます。
6年生も後期になると日曜特訓が始まり、勉強時間が増え、自由時間が減ることになります。そのうえ、教室もよりピリピリした感じになってきますが、負けずに勉強を続けてください。この頃に勉強をさぼるかさぼらないかで差がついてしまいます。志望校のための模試なども増えていき、思うようにいかないことがあると思います。そこで大事なのは、「本番モード」に自分の心を切り替えることです。これは入試本番でも言えることですが、勉強以外のことを一度忘れ、目の前の教科で気を付けるべきことだけを考えるようにすると良いです。
そして、入試本番についてですが、麻布のように1日午前が第一志望の人が多いと思います。ここでは適度に緊張感をもって、それでも今自分がやるべきことを念入りに行いましょう。午前のあとに午後校を受ける場合は、午後眠くて集中できないことを防ぐために寝るか、本番の緊張感を保つため、知識の確認をするようにしましょう。ここでも頭を「本番モード」に切り替え、午前校のことは忘れて試験を受けましょう。
2日は人によって過ごし方が変わりますが、麻布の場合まだ結果が出ないため、落ち着いてこれから受ける学校のことを考えましょう。第一志望のことで焦ったり油断したりしてはいけません。目の前の試験に集中するため、学校に着くまでは、知識の確認のために持ってきたテキストや参考書を読み、「本番モード」に入りましょう。
その後、3日も同じように過ごしました。そして、僕はその日の午後麻布に合格したため、書類を取りに行きました。その時は本当にうれしかったです。皆さんもグノーブルのカリキュラムを信じれば合格できます。頑張ってください。麻布で待っています。

常に前向きでなくても良いからあきらめない
麻布中学校進学G君
僕は2、3年生のころは他の塾に通っていましたが、そこで中学受験をする選択肢が出てきて麻布にあこがれたため、グノーブルに転塾しました。4、5年生の時は算数と理科が得意で、国語はそこそこ、社会が毎回足を引っ張るという、理系タイプでした。しかし、6年生の中期から麻布の過去問を始めるとじわじわと国語の成績が上がり、一方で算数と社会と理科がそこそこの成績に変わり、最終的には、グノーブル主催の麻布模試で国語が1位という好成績を収められるようになりました。これは、グノーブルで受けたトップレベルの国語の授業の賜物だと思います。
これからは、僕の実体験に基づく受験のアドバイスです。まず、僕は1月受験で社会の解答用紙の裏面を書き忘れるというミスを犯しました。なので、テストでは裏面まで確認しましょう。そして、テスト会場で万が一名前を書き忘れてもどうにかなることが多いので、不安にならないで、目の前のテストに集中しましょう(でも覚えていたら書きましょう)。あと、テストの終わりに「簡単だった」と言って周りを不安にさせる人がよくいますが、これは大体当てにならないし、僕の受験の時も「簡単だったわ」と言っている人がいたにもかかわらず、平年よりテストの合格者平均点は低かったです。なので、そういう人たちのことは気にしないようにしましょう(テストの答え合わせをしている人も)。最後に、この体験記が誰かの役に立てば幸いです。
栄光学園中学校
起死回生の中学受験
栄光学園中学校進学A君
僕は3年生からグノーブルに通いました。
3、4、5年生の頃は、グノーブルは授業日が少ないこともあって、多くの時間を遊んで過ごしました。しかし「基礎力テスト」や「計算マスター」「G脳ワークアウト」をためてしまったことで、算数が苦手になりました。なので3、4、5年生の間は「基礎力テスト」や「計算マスター」「G脳ワークアウト」にきちんと取り組んだ方が良いです。そして、6年生になると遊ぶ時間が少なくなるので、思う存分遊んだ方が良いです。
6年生前半は土曜特訓が始まることで通塾日が週3回になり、負担が大幅に増えます。この頃から、僕はテキストをためるようになってしまいました。
そして、中学受験の天王山と呼ばれる夏期講習が始まり、僕はまたここでもテキストをためてしまい、今までより偏差値が5低くなってしまいました。今まで自分に甘くしてきたつけがまわって学力に不安があったなか、6年生後半が始まりました。
日曜特訓は、初めは問題が通常授業や土曜特訓より難しい上、優秀な人ばかりで自信を無くし、一番目のクラスと二番目のクラスをさまよっていたので、コースを変更しようと迷いました。しかしコースを変えずに勉強して、冬期講習と正月特訓あたりでやっとそのコースに慣れることができました。ユニークな仲間や先生方が面白く、最後は自分もこの人たちと同じ学校に行きたいと強く思うようになりました。日曜特訓のコースを変えようか迷っても、簡単にあきらめない方が良いです。
僕は土曜日の栄光特訓に通いました。栄光特訓は、6年生後半の家庭学習の時間が減ってしまうけれど、行くべきだと思います。栄光特訓は今まで解いたことのない形式の問題で、初めは苦戦したけれど12月頃にはだんだんコツをつかめてきました。栄光特訓で取り組んだことは受験本番での自信につながりました。
冬期講習が終わり、大詰めの1月を迎えました。僕は今までとは比べものにならないくらいひたすら勉強しました。1月は2校受験しました。1校目は合格しましたが、2校目は対策が足りず、不合格でした。1月後半の不合格に、2月も不合格が続くのではと不安になりました。
2月の受験本番では、1日午前校の受験で苦手だった算数が足を引っ張ってしまい、不安なまま午後校に向かいました。過去問では高得点が取れていた午後校は、本番で時間配分を間違えてしまいましたが、ある程度は取れただろうと思っていました。2日の朝、起きて1日午後校の結果を確認するとまさかの不合格。本来はここで合格をもらって自信をもって栄光に向かうつもりだったので、自分でも信じられませんでした。不安を抱えたまま試験会場に向かいました。けれど、会場に入る直前に父から「栄光と1日午後校は別の学校だから朝見た結果を気にしても無駄だよ」と言われ、うまく切り替えられました。“都合の悪いことはすぐに忘れる”という自分の長所が役立ちました。入試本番では栄光特訓で培ったことを発揮でき、手ごたえを感じました。そのため、3日校に安心して臨むことが出来ました。
3日校の試験が終わり、1日午前校と栄光の結果を見ました。先に結果が出た1日午前校はひょっとしたら合格できたのではないかと思っていましたが、不合格でした。その1時間後、外部模試で合格可能性が80%だったし、本番も手ごたえがあったから合格できるはず! と思って栄光の結果を見てみると、またもや不合格でした。さすがに、4回連続の不合格にショックを通り越して絶望しました。
僕のこの4年間は水の泡になったのかと思いました。3日までに合格をもらえなかったので、当初予定していなかった4日校を受けることになりました。3日は家に帰ってきて、今までの人生で一番泣きました。翌日、暗い気持ちで4日校に向かいました。4日校の試験も算数で手ごたえを感じず、どうせ4日校も不合格だろうという思いで帰りました。
しかし、ここで転機が訪れました。なんと、栄光から繰り上げ合格の連絡がきたのです。こうして、僕の壮絶な4日間の戦いは終わりました。
最終的に4日校は合格、チャレンジ校の3日校は不合格でしたが、僕の受験は栄光学園へ進学という結果で終えることができました。
僕がこの4年間の受験生活を終えて感じていることは、あきらめなければ結果はおのずとついてくるということです。さぼってばかりだった僕が言えることではありませんが、中学受験に逆転合格は存在すると思います。これから受験をする皆さん、自分の志望校に向けて希望を捨てずに頑張ってください。
最後に、長い間支えてくださった先生方や受付の方々ありがとうございました。
激動の4日間
栄光学園中学校進学A君の保護者様
入試期間から1週間が過ぎ、兄弟達と肩を並べてゲームに熱中する息子の姿に、2月1日からの4日間、12歳の子が受け止めるにはあまりに過酷な現実の試練をよく耐え抜いた、と胸が熱くなります。グノーブルでは受験勉強にとどまらず、“学びに対する姿勢”を教えていただきました。この先環境が変わっても、グノーブルに授けていただいた“一生の財産”は、これからの息子の人生を豊かにしてくれると信じています。
■息子が栄光学園に惹かれたところ:自由、開放的で横に長い二階建ての平屋の校舎、広い芝生、森、畑!! 目に入るものすべてが息子にハマり、何度も訪れました。また文化祭で見た先輩たちの生き生きとした様子に憧れ、本人は早い段階で「2日は栄光学園を受験する!」と心に決めていたようです。
■志望校選択:栄光学園の他に、4、5年生の間に、時間の許す限りいろいろな学校へ足を運び、息子に響いたものは何だろう、と考えました。打放しコンクリート素材の壁の学校が気に入っていたこともありました。校舎や校庭が狭い学校は、楽しそうな部活など他に魅力があったとしても本人には物足りなさそうでした。説明会後は東京タワーや水道博物館に寄ったり、電車の路線図に強い息子のリクエストで帰宅時の交通ルートを変更したりと、+αで寄り道をして、束の間のレジャーを親子で楽しみました。
6年生になると、成績が不安定な時期もありましたが、最終的にチャレンジ校を含め本人が決めた学校を受験することになりました。(数年後に今を振り返った時)悔いの残らないような、納得のいく併願校選択ができました。
■日曜特訓:普段通う校舎の垣根を越えて、同じ学校を目標に掲げた子たちと切磋琢磨している様子が、帰宅後の夕食の会話からうかがえました。息子はおとなしい性格なので、同じコースの子達とワイワイやっていたかはわかりませんが、クラス特有の“先生との掛け合いのような合言葉”を自宅学習中によく口にしていました。受験が終わっても「日曜特訓は学校みたいで楽しかった!!」と話しています。受験勉強に関してほとんど口を挟まない父親は、日曜特訓の朝は息子のために野菜の肉巻き弁当を作って陰ながら応援していました。
■栄光特訓、個性豊かな先生方:栄光学園の入試問題は暗記や小手先のテクニックでは通用しない、とても特殊な問題です。栄光特訓では、問題の特徴を知り尽くした普段厳しい理科の先生が、直前期に提出した過去問添削のコメントに「Very Good!!」と書いてくださったことを本人は大変喜んでいました。栄光特訓で鍛えていただき、本人も合格への自信がついた状態で本番の試験に挑むことができました。
息子の知識欲を満たしてくださった社会の先生方。息子の得意科目である社会の引き出しに、溢れそうな程たくさん詰めてくださいました。4年生の時に「地理の授業で『四国の川がとてもきれい』と習ったけど、どれくらいきれいか見に行きたい」という本人の希望で、夏休みに家族で“テキストに出てきた四国の太字ワード・水めぐりの旅”をしたことは良い思い出です。国語の先生には、息子が提出した過去問に「これではあなたが掲げた志望校は目指せません。猛省するように」と厳しく、愛のこもった添削をしてくださいました。「次こそは先生に認めてもらいたい!」と、これまで見たことのない程の集中力で解答欄に鉛筆を走らせる息子の姿を誇らしく感じました。4年間、先生の国語の授業を受けて、大人顔負けの「論理的に読み、書き表す能力」がつきました。また、先生が紹介してくださったたくさんのおすすめの本を息子はメモして帰り、図書館でリクエストしたものを娯楽の一つとして楽しみました。
2月3日まで不合格が続くことの親子の精神的ダメージは、想像を絶するものでした。成長過程において、様々な経験を積んだ大人達からすると「長い人生の一部で×がついても、その先挽回のチャンスはいくらでもある」と気持ちを切り替えることができます。しかし12歳の子にとっては突きつけられた結果がすべてで、すぐに前を向くことなど到底できませんでした。3日の夜、息子は泣き崩れ、私も夫も失意のどん底にいました。翌日、食事を全くとらず、目を真っ赤に腫らしたまま4日の試験会場に入っていく息子の姿に、どうして早い段階で日曜特訓のコースを変更しなかったのか、もっと戦略的な併願校選びをしていれば、息子をここまで苦しめることはなかったのに、と私達の采配ミスに、深い後悔と自責の念に駆られました。4日校受験後に、弱りきった私の心の声をお電話でグノーブルの先生にお話しし、今後の息子との向き合い方などご相談させていただきました。それから5分ほどあとに、移動中の駅のホームで栄光学園から繰り上げ合格の連絡が入りました。すぐにグノーブルへお伝えしたところ、電話越しに先生方の歓喜の声が聞こえ、ポカンとする息子の横で私は人目もはばからず泣いてしまいました。
息子の今までの成績結果や、授業態度をふまえた上で、無駄を省いたアドバイスをくださった面談担当の先生の見立て通り、今回合格を勝ち取ることができました。本人は繰り上げ合格ということに少し引け目を感じているようですが、決してまぐれの合格ではなく、グノーブルで4年間積み重ねた成果が出たのだと思っています。
これから先の長い人生で、グノーブルで授業を受けて、自ら目標を立てて精いっぱいの努力をしたことを、何かの節目に思い出すことがあるでしょう。息子を未来へ導いてくださったのはグノーブルで出会った先生方であることは、息子も私達も忘れません。
最後に、受験を共に戦った同じ教室の仲間達、日曜特訓で机を並べた同志の皆さんの今後の活躍を心から応援しております。4年間ありがとうございました。

楽しかったグノ
栄光学園中学校進学B君
僕は3年生の時に入塾しました。
最初のテストの結果は散々で、一番下のクラスでした。でも先生の話を聞いて自分から勉強するようになるとテストの成績が上向き、一番上のクラスに入ることができました。
僕がこれまで気を付けてきたのは以下です。
🔳算数
・5年生の算数は最低でもテキストを3周か4周解く。
・夏期講習のテストで居残りしないように頑張る。
・「基礎力テスト」を毎日やる。
・過去問の点数は気にしすぎない(僕は最初栄光の算数が70点中18点でした)。
🔳国語
・漢字を毎日こなして覚える(栄光は大問三に漢字が10問出る)。
・記述はとにかく書いて練習する(僕は記述が苦手だったけど、練習したおかげで国語が得意になりました)。
・過去問を出して返ってきたら、先生のコメントを見て次に過去問を解くときに活かす。
🔳社会
・栄光では幅広い知識が必要なので「知識の総確認」の地理・公民・歴史を何度も声に出して読み、問題をたくさん解いて覚える。
・記述では、本文の内容をそのまま書くだけの問題もあるので、本文をよく読む。
・最後の記述では、これまで解いてきたことのまとめを書くことが多いので、書く前にある程度整理する。
・分からなかったら絵を描いて考える(僕はそのおかげで本番でも救われました)。
🔳理科
・5年生の時はノートをしっかりと書いて頭に入れる。
・栄光ではグラフを書くので、栄光特訓で書き方を聞く。
・栄光の理科は何が出るか分からないので、普段から身の回りの色々なものに興味を持つことが重要だと思います。
僕は不合格を経験して落ち込むこともありましたが、終わってしまったことをいくら考えても仕方ないので、次の試験に向けて準備をし、できることをやりました。
グノの先生は自分たちのことをよく見てくれています。皆さんも本番のときは先生の言葉と自分のことを信じてがんばってください。応援しています。祈合格!
グノという居場所
栄光学園中学校進学B君保護者様
コロナ禍の2022年2月、わが家は中学受験という道を歩き始めました。親である私たち自身が中学受験を経験したことが無く、グノの先生に保護者会や面談を通じて受験のイロハを段階的に教えていただき、3人で乗り越えることができた3年間でした。息子にとって、グノは勉強をする場所であると同時に、切磋琢磨する仲間とともに、自分の限界に挑戦できる「居場所」でもありました。
第一志望に合格したときの息子のうれしそうな、充実した顔を一生忘れません。グノの先生方、同じ道を歩んだ友人たちに心から感謝しております。本当に、ありがとうございました。
海城中学校
毎回の授業がとても楽しみでした
海城中学校進学A君
僕は社会や理科を学びたいと思い、3年生の夏から塾選びを開始しました。他塾と迷っていたのですが、体験授業がとても面白く、授業の日数が少なくて自分がしている習い事との両立ができると思い、グノーブルに決めました。
グノーブルは少人数の授業であるため、友達と競い合って、良い刺激を受けることができました。また、質問がしやすいというのも良いと思います。長い列に並んで待たなくてもグノーブルではすぐに質問ができ、助かりました。しかも、グノーブルには熱血な先生が多く、授業が楽しいので、毎回の授業がとても楽しみでした。
グノーブルの先生方は、いつでも受験生の味方です! 困ったことがあったら先生に聞いて、グノーブルを信じて学び続けてください!
開成中学校
受験でうれしかった瞬間
開成中学校進学A君
・基本的なことをおろそかにせず、「基礎力テスト」をやりましょう。
・苦手な教科があったら重点的にやりましょう。
・先生に指示された問題は必ずやりましょう。
・ゲームをやりすぎないようにして、休憩は適度に取りましょう。
・塾には時間に余裕を持って行きましょう。僕は本番10日前に、塾へ行く途中急いで駅の階段を下りたら足をねんざしました。
・試験の時緊張するのは当たり前なので、なるべく普段通りを意識して、取れる問題を確実に解きましょう。
受験でうれしかった瞬間は、合格発表で自分の受験番号を見つけた時と、難しい問題が解けた時です。大変だったことはゲームをやめること、自分の時間がなくなることです。
受験が終われば遊べるので、その時を楽しみにしながらがんばってください。
できる生徒と机を並べることが大事
開成中学校進学A君の保護者様
息子は3年生の冬期講習から入塾しました。
当初は都立受検を考えていましたが、選択肢を広げるために私立受験の勉強を始めることにし、説明会で志の高さを感じたグノーブルに通塾を決めました。
5年生までは親が学習の進捗管理をしていました。しかし、新6年生になると学習量が大幅に増加し、同時に反抗期が始まったのか、親の管理を嫌がるようになりました。とはいえ、自走するにはまだ幼く、春から夏にかけて家庭学習がうまく回らない時期が続きました。
6年生の9月、夏の疲れやストレスもあるのか、心のエネルギーが枯渇しているような息子の様子を見て、このままではあと5か月持たないのでは?という危機感がありました。成績が落ちた場合に備えて、受けられそうな学校を一生懸命探す一方で、日曜特訓のコースを、先生にお勧めいただいていた開成コースへ変更してみることにしました。
息子は親から見ると競争心が強いタイプではありませんが、周りに自分よりできる子がたくさんいる、でも得意な算数ではまあまあ勝てることもある、そんな開成コースの環境で競争することがとても楽しかったようです。10月には「開成の過去問をやってみたい」と言うようになりました。
その頃はまだ都立を第一志望としており、開成を受験する予定はありませんでしたが、息子のやる気が出るならと思い「次の模試で50%を取れたら考えてみる?」と提案したところ、たまたまなのか頑張ったからなのかわかりませんが、過去最高の成績を出して50%をクリアし、そこから開成を目指す日々が始まりました。
息子は出不精で学校見学には行きたがらず、自分の気持ちもはっきり言わないタイプなので、本人の意志はよくわからないまま親が志望校を決めていたのですが、このとき初めて本人の目指す学校ができ、受験が親のものから子どものものへと切り替わったようです。
とはいえ、劇的に学習姿勢が変わったわけではなく、それからも家庭学習はマイペースを貫き通しました。それでも、真夜中にゲームしているところを発見される、「基礎力テスト」をやりたくないので隠す、過去問の途中で飽きて放り投げる、といった行動は見られなくなり、少し前向きに取り組めるようになってきました。
冬期講習と正月特訓の期間中は拘束時間も長く、親としてはきついだろうと思っていました。しかし、息子は「今日も頑張るぞー!」と元気に出かけ、充実した日々を過ごし、良い流れのまま1月を迎えることができました。
理科・社会については直前の1月に集中的に取り組み、できる限り過去のテキストを復習しましたが、夏までの勉強不足がたたり、最後まで不安定なままでした。過去問の出来を見ても、親としては合格は難しいと感じていましたが、結果は合格。親は息子の力を少し見くびっていたのかもしれません。
6年生になって受験が本格化してから、塾の先生方のアドバイスには本当に助けられました。特に日曜特訓のコースについて、「できる生徒と机を並べることが大事」という先生のお言葉は、予言のようにぴたりと当たり、我が家の受験の方向性を決定づける分岐点となりました。
皆さん同じかと思いますが、6年生の秋以降は怒涛の日々で、親子ともに想像以上に大変でした。それでも、終わってみれば、本当に濃密で思い出深い時間を息子と過ごせたと感じています。
我が家らしく行き当たりばったりの受験でしたが、振り返れば、自然と1本の道がつながっていて、今の場所にたどり着いたようにも思えます。お世話になった先生方、本当にありがとうございました。

本番が第一
開成中学校進学B君
僕がグノに入ったのは、ちょうど新4年生の時でした。その時の入室テストから、僕は国語が取れて、算数が取れないという傾向がありました。これから皆さんに、やっておくべきこと(必要最低限のことです)を伝えます。
🔳算数:毎日の「基礎力テスト」は、朝やるのを当たり前にしておきましょう。ちなみに、僕は最後の2週間前ぐらいまでずっと朝に出来ず、苦しみました。あとは、6年生の秋から始まる日曜特訓の学校別の算数がとても大事です。本番の前に出来なかった単元を見直しておきましょう。
🔳国語:特に記述に関して、僕はどうこう言えないです。漢字に関して言えることは、1回自分のメンタルを破壊するぐらいの厳しさで丸つけをしてみてください。そうすると必然的に綺麗に書けるようになります。ことわざや知識は楽しんで覚えていきましょう。
🔳社会:地理、歴史、公民、すべてまんべんなくやりましょう。きちんとやらないと、本当に苦手な分野で差が大きくなります。地理の分野では、自分が好きなものから覚えると武器になります(鉄道とか)。歴史は語呂合わせで覚えるのが大事! 公民はとにかく問題を解くことが大事です。
🔳理科:力学、化学、生物、地学と大きく分けて四つのなかから、自分の好きなところを極めてみましょう(だからと言って他の分野をおろそかにしてはダメですが)。毎日の「基礎力テスト」に出てくるような基礎は、落としたらそこを絶対に復習しましょう。
🔳模試、過去問の話:僕は外部模試であまり良い成績が取れず、最後の合判でも30%ぐらいでした。でも、大丈夫。自分の苦手なところを一生懸命にやったら結果はついてきます。逆に、合判が高くても油断すると本当に落ちます。80%取り続けていても、努力し続けてください。過去問も一緒です。僕は10年分解いて、合格最低点に届いたのが2年分だけでした。だから、過去問、模試の結果はあまり気にしない方が良いです。
🔳本番の話:僕は正直、2月1日の受験校の結果に自信がなく、母に「落ちたかもしれない」と言っていました。そして、2日の学校を受け、終わった時の手ごたえとしては1日よりも2日の方が手ごたえがあったし、事前の合判でも2日の学校の方が良かったので、2日は受かったと思って3日の試験を受けました。2日の学校の方が合格発表が早かったのですが、落ちていました(この話がさっきの話につながっているのですが)。それで、母はどちらも落ちてしまったと思ったそうです。でも…まあ、今僕がこれを書いている時点で皆さんはお分かりでしょう。意外に自分の手ごたえはあてにはならないです。皆さんも、受験の時は自分の手ごたえで一喜一憂しないようにしましょう。
🔳最後に:これから受験する皆さんは、偏差値が伸び悩んだり、どうしてもわからない問題に不安になってしまうこともあると思います。でも、大丈夫。グノの先生を信じて自分の苦手なところを一つずつつぶしていけば、絶対に受かります。頑張ってください!!
息子との中学受験生活を振り返って
開成中学校進学B君の保護者様
まず、お世話になったグノーブルの先生方とグノーブルでの時間をともに過ごしてくれた友人の皆様に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
家庭での勉強中、息子は集中力が続かずにフラフラと立ち歩いてしまい、しょっちゅう親に注意されてはヘソを曲げているので、家に居るときはあまり機嫌が良くないことが多かったです。ただ、どんなにしんどくても、グノーブルを休みたいとは1回も言ったことがなく、グノーブルから帰ってくるときにはいつもニコニコ顔なのがとても印象的でした。きっと、グノーブルで良い先生方と良い友人たちに恵まれたのだと思います。
わが家は新4年生になるタイミングで塾通いを決めましたが、他塾の大人数制での指導は息子には合わないだろうと思い、本人の希望もあって、一人ひとりに目が届く少人数制での指導をされているグノーブルへの入塾を決めました。先述の息子の様子を振り返ると、やはりグノーブルにして良かったなと思います。
中学受験に対する家族の関わり方は各家庭で異なるかと思いますが、体験記ということなので、参考としてわが家のことを少し書きたいと思います。
まず、勉強の中身についてはグノーブルの先生方に完全にお任せしていましたが、息子は5+3の暗算を間違えたり、たけし君の歩く速度を求めるのにひろし君の歩く速度を答えてしまうような不注意なところが多く見られたので、私はいわゆる「もったいない」ミスが少しでも減らせるように、次のような声かけをずーっとしていました。
・文字を丁寧に書くこと
・解答欄をはみ出さないこと
・計算の途中式を書くこと
・筆算、たしかめ算をすること
・問題文や自分の解答を見返すこと
言ったところですぐにできるようにはならないのですが、しつこく言い続けた甲斐があってか、6年生の冬ごろには、以前よりもったいないミスが減ったと思います。
ちなみに、学年が上がるにつれて家庭での学習量が増えて、保護者会の中でも「最低限やること」「できればやること」「余裕があったらやること」のように説明をしてくださるのですが、息子は「最低限やること」も1週間のサイクルの中で終わらずに負債を抱えることが多々あり、他のご家庭ではどうしてるんだろう、というのがいつも疑問でした。どうすればこなせていたんだろう、というのは今でも答えがないのですが、そんな家庭もあったのだなという参考になればと思います。もちろんやらなくても大丈夫という話ではなく、どうしても子どもの勉強の進み具合が良くなくて焦ってしまうようなときに、苦しんでいるのは自分たちだけじゃないんだという気休めになればと思います。
勉強面以外では、必要以上に子どもを追い詰めてしまわないように気を付けていました。言ったことができていなかったり、ダラダラしていたりすると、ついつい声を荒げてしまうこともあるのですが、そのようなときには、受験生活の大変さ・難しさや、それに対する息子の努力に改めて目を向けて、敬意を持ってひとりの人間として接することを心がけていました。私自身、中学受験の経験者ですが、今の子どもたちは自分のころよりも非常に難しい内容でとんでもない量をやっていると思います。本当に尊敬できます。
自分たちが苦労したこと悩んだことを書いた方が参考になるかと思い、息子ができていなかったことを多めに書いてしまいましたが、それ以上にできるようになったことはたくさんあって、大きな成長をすることができた3年間だったと思います。改めてグノーブルの先生方と友人たちに感謝です。
最後に、これから受験を迎える皆様が本番当日に全力を出せること、納得感を持って中学受験を終えられることを祈っております。中学受験は親子が協力して数年かけて一つの目標に取り組む数少ない機会だと思います。大変なことも多いかと思いますが、少しでも明るく楽しく前向きに頑張ってください。

先生の言葉を信じて
開成中学校進学C君
友達が通っていたから僕も塾に通いたい!そう思い、新2年生の時に別の塾に入塾しました。習い事の関係で、4年生のタイミングでグノーブルに転塾しました。漠然と「受験」をするだろうなとは思っていましたが、「受験」を本格的に意識し始めたのは6年生のGW講習の頃です。GW講習では開成コースを選択し、その際、国語の先生が開成の魅力を教えてくれました。また実際に開成の学校説明会で新校舎を見学し、この学校に合格したいと思うようになりました。
家での勉強はとにかく毎週グノーブルで出される宿題をこなすことに専念し、復習テストで満点が取れるように努力しました。また、毎月行われるGnoRevテストで、どの程度身についているかを確認していました。復習テストや実力テストでは、点数に一喜一憂するのではなく、自分の勉強方法のどこが悪かったから点数が取れなかったのかを考えて、次のGnoRevテストに活かすように心掛けました。もちろん模試の結果が良ければ嬉しいし、悪いととても落ち込みました(笑)。
僕が一番好きな教科は算数で、国語は最後まで苦手でした。6年生後期、日曜特訓が始まった当初、国語の読解記述で75点中2点という点数を取ったこともありましたが、グノーブルの先生の「国語は最後まで伸びる」という言葉を信じて、最後の最後まで諦めずに取り組みました。先生の言葉を信じて本当に良かったです。
今でも忘れられないのが、2月3日、インターネットで開成の合格発表を見た際に、受験番号を間違え一瞬不合格だと悲しい気持ちになったことです。興奮していたこともあり、落ち着いて受験票と照らし合わせたら、自分の番号がそこにありました。とても嬉しかったです。
グノーブルの先生方や親のサポートもあり第一志望である開成中学校に合格することができました。本当にありがとうございました。
精神面でサポートすることが大事
開成中学校進学C君の保護者様
グノーブルには4年生からお世話になりました。当初は志望校を決めていたわけではなく、漠然と中学受験を考えている状態でしたが、毎回楽しそうにグノーブルに通っていました。仲の良い友人に恵まれ、良い刺激を受けていました。グノーブルの授業で教えていただいたことを嬉しそうに話す様子を見て、グノーブルの先生方には、受験するための勉強ではなく、勉強する楽しみを教えていただいたのだと感謝しています。
最後まで苦手だった国語についても、親の方が諦めそうになりましたが、国語科の先生に、問題点や勉強法を根気強くご指導いただいたことで、少しずつ伸びていきました。
親のサポートで大変だったのは、テキスト整理でした。6年生の前半、後半でそれぞれ管理するテキストの量が増え、管理が追いつかない時もありました。秋以降は過去問や合判模試、学校別模試が始まり、テストの点数に気持ちが浮き沈みする子供の様子を目の当たりにし、とにかく精神面でサポートすることが大事だと思うようになりました。間違った問題の解き直しになかなか立ち向かうことができず、悔しくて部屋にこもることもありましたが、最終的に前向きに自分の弱点克服に臨める精神力を備えることができました。子供の受験勉強の伴走をすることで、子供の成長を間近で見守ることができ、中学受験に挑戦して良かったと思いました。
最後になりましたが、お世話になった先生方、本当にありがとうございました。

グノーブルで中学受験に挑戦できたことに感謝
開成中学校進学D君
参考になるのか分かりませんが、僕の勉強方法を書くことにします。
- 塾のテキストだけをやる
市販の問題集を使ったり、他の塾に行くことはやめた方が良いと思う。
なぜなら、そんなに大量のノルマを課してもこなせるわけがないからだ。そもそも、グノーブルの授業は難しく、復習だけでもとても時間がかかってしまうため、僕にそんな余裕はなかった。 - 日常的に地図や資料を見る
僕は小さい頃から生物、小学生になってからは歴史にも興味を持っていたため、日常的に図鑑や歴史に関する本を見ることが多かった。そのため、理科、社会は勉強だと思わずに楽しく学ぶことができた。もっとも、趣味は人によって違うだろうが、地図や資料を日常的に見ていると、関連する授業がとても楽しくなると思う。 - 理解できないことをそのままにしない
僕は聞くよりも見る方が理解しやすかったし、先生に聞くことが苦手だったので質問はあまりしなかったが、算数は疑問を放置せず、解説を読んだり動画を見たりして、後でつまずくことがないようにしていた。あやふやなままにしないことが大事。 - 国語は漢字と知識だけ
やるべきことがたくさんあるのは自覚していたが、面倒だったこともあって、漢字と知識しかやっていなかった。しかし、実際に授業を受け続けていくと、どんどん読解もできるようになっていったので、最低限漢字と知識をやれば多分どうにかなると思う。 - 言われたことすべてができなくても心配しない
1でも書いたとおり、グノーブルのテキストはとても多い。そのため、全部やることは実質不可能だ。だから言われた問題だけをやれば良い。また、言われた問題をすべてできなくても、絶対にやれと言われた問題をしっかりやっていればどうにかなったので多分大丈夫。 - 好きなことは最後まで辞めない
僕はゲームが好きだったので、受験前日まで毎日2時間はゲームをしていた。その時間を勉強に回せば成績が上がると考える人もいるだろうが、息抜きができないと勉強にも身が入らず、結局意味がない。もちろんやりすぎは良くないが、適度に楽しむことも重要だと思う。そうしないと受験当日まで心が持たない。 - 毎日しっかり寝る!
寝る時間を削って勉強するよりも、しっかりと寝ておくことの方が重要だと感じた。睡眠時間が短くなると疲れも取れないし、学校や塾でも眠くなり、集中できない。体調も崩しやすいと思う。
勝手に余計なことをやらず、何とか塾についていければ大丈夫だと思う。先生方の授業は楽しいことも多く、刺激にもなった。グノーブルで勉強して中学受験に挑戦できたことに感謝したい。ありがとうございました。

準備をしたら、あとは楽しむ気持ちで
開成中学校進学E君
僕が6年生になってから受験までの体験をお伝えします。
春は、詳しいことや重要なことが詰まっているグノのテキストに取り組みました。その時に意識したことは、時間を区切って取り組むことです。時間を区切ることで、集中力や処理能力が上がりました。
夏は、夏期講習のテキストが多すぎてサボることが多くなってしまいました。今振り返ると、直しに時間を多くかけすぎず、テキストを一通りするべきだったと思っています。開成中学を受けようと思い始めたのは、9月の日曜特訓が始まってからです。初めはレベルが高くてついていくのに必死でした。それでも、気の合う友達に会えたことで勉強のモチベーションが上がり、周りと切磋琢磨していました。
秋は、志望校が明確に決まったため、過去問をひたすら解きました。過去問は受験する年の問題ではないので、結果に一喜一憂せず、時間配分や問題の構成に注目して解くことを心がけました。この時期は外部模試もたくさん受けましたが、模試の合格判定の結果が悪くても反骨心を持って頑張り続けました。
冬は、冬期講習の後、自分の中で抜けていることを一つ一つ潰していく気持ちで取り組んだので、体感として過去一番伸びたと思います。たとえ成績が悪くても、その分自分にはまだ伸び代がある、と信じて前向きな気持ちでいるようにしていました。
入試の時は、予想していなかったことが起きるかもしれない、という覚悟をもって試験に挑むことで、落ち着いて受けることができます。学力は本当に最後まで伸びるので、諦めず、前向きな気持ちを持って、思いっきり試験を楽しんで下さい!!
中学受験を通して成長できた
開成中学校進学E君の保護者様
息子は新4年生がスタートしたタイミングで入塾しました。入室説明会後に、親子ともにグノーブルを迷わず選んだことがとても印象に残っています。よく練られたカリキュラム、国語の指導をしっかりしてくれること、通塾が週2回で他の習い事を辞めなくてもよいこと等の理由もありますが、何よりの決め手は、説明会での塾の先生の話がとても面白くて親子ともに引き込まれたことです。知的好奇心を刺激してくれる先生方と切磋琢磨する仲間に恵まれ、3年間楽しく通っていました。
もちろん平坦な道のりではなく、授業の復習をするためのプリント整理や、理解状況の把握だけでも大変。学年が上がるごとに問題の難易度と、やらなければいけない課題の量の負担が右肩上がりで、本人も親もやることが山積みになります。振り返ってみると、4年生で大変だと思っていたことも5年生になるとかわいいもので、6年生では、いかにやらないものを選択をするかがとても重要になります。グノーブルでの3年間を通じて、スパイラルで高い質の演習を凄まじい量でこなしますので、処理能力は徹底的に鍛え上げられます。
子供の時間の感じ方が違うためか、のんびりした本人と親の焦りとのギャップで、6年秋は一番衝突が多かったです。息子自身が受験を自分事して取り組むようになった、いわゆる目の色が変わってきたのは、冬期講習からでした。理想はもっと前からエンジンが入っていたらと思わずにはいられませんが、模試ではずっとチャレンジ校扱いだった状況から、最後のコーナーの追い込みで志望校に合格することができました。特に最後の2カ月を乗り切れたのは、塾の3年間で鍛え上げられた受験体力と、6年の6月まで続けていたサッカーで培ってきた体力のおかげだと思っています。体力があれば、最後の追い込みができます。
息子は4教科とも成績が同じくらいのバランスタイプだったため、最初から4教科受験で考えていましたが、特に国語は問題文との相性によって大きく足を引っ張ることもあり(グノレブテストの偏差値40台のことも)、安定していませんでした。また、最初から開成志望ということではなく、当時は海城が第1志望のところ、問題の傾向が似ているとのことで開成クラスに入っていました。過去問を解いていくうちに、開成の問題がおもしろかったことや、志望校別クラスで一緒に学んだ塾の友達からの影響が大きく、冬には本人の中でも気持ちが固まって、そこからエンジンをかけることができたように思います。
以下、我が家での科目別の振り返りと、直前期の対応について記します。少しでも後輩の皆様のお役に立てば幸いです。
■国語:読解は問題文との相性で当たり外れが大きいため、対策の取れる漢字と語彙などで取りこぼしのないよう「漢字道場」と知識のプリントは必ずやらせました。6年生の秋には読解で点数が取れるようになってきたため、国語が安定するようになりました。塾以外の市販教材にも取り組ませましたが、あまり真面目に取り組んでおらず、結局は、塾の添削指導のおかげだったと思います。国語では様々なテーマのジャンルを授業でも扱いますし、保護者会の際には先生のおすすめの本等の紹介もあり、受験の息抜きに読んでいました。
■社会:社会はまんが学習シリーズの「日本の歴史」をほぼ毎日読んでいたので、国語の漢字の間違いは酷いのに、不思議と社会で出てくる漢字を間違うことは少なかったです。ただ、漫画学習の場合は、ストーリー順で覚えてしまっていることがあり、時代の流れを選択する問題でミスすることもあったので、流れを正しく覚えるために塾の教材の「確認プリント」での見直しをするよう親が説得することもありました。
■算数:5年生までの積み上げはもちろんですが、毎日の「基礎力テスト」(6年生時はもはや基礎力とは呼べないほど難しい)で、時間を意識して満点をとることに拘らせました。性格的に計算のケアレスミスが多かったので、おかわり制度をして、満点をとれるまで一日分を追加でやらせていました。
算数で点差がつく受験であること、特にボーダーラインにいるので、そのときの一点の重みを意識させるように口煩く伝えていました。グノーブルの先生の「算数は一番最後に伸びる」という言葉を信じて、直前期には入試演習をひたすら行いました。その中で、問題の構成と配点、時間内に解ける・解けない問題の取捨選択を意識して取り組ませました。開成入試の際には、試験直後に周りの数名の子供たちが涙していたというほど難しい出題がされたようですが、そもそも解けない問題は捨てる意識を持っていたので、自分の中で取れる問題は取ったという感触から、それほど焦らなかったとのことでした。
■理科:先生が細かく問題を取捨選択してくれるので、その指示に完全に従いました。とにかく範囲数が広いので、暗記系の単元は、直前期は「昼テスト」をクイズ感覚で解き、問題集を眺めていました。計算式(水溶液)や理屈のある単元(天体)については演習を何度も行いました。
■直前期・受験に対する意識:直前期は色々気持ちの焦りもありましたが、選択と集中を考えた際に、我が家は日曜特訓の冬期講習の算数教材をひたすら繰り返し解きました。グノーブルの先生が厳選した質の高い問題を繰り返し解くことで手ごたえが生まれ、当日は十分準備をしてきたという自信と、良い緊張感を持って迎えることができたそうです。
また、模試・過去問の結果を見る上では、偏差値や合格可能性のパーセンテージに一喜一憂するよりも、受験者人数と合格人数を見ることが大事だということを伝えました。特に12月・1月には、受験者の中での現在の立ち位置から、合格者ライン(過去の入学者数からの想定)まであと何点あれば良いのか、どの教科のどの問題を取れればその点分を稼げたのかというところまで落とし込んで、模試や過去問を振り返り、必要なカリキュラムを識別しました。
渦中の時は、心配が先立ち、感情的になることも多かったですが、そんな親子をたくさんみてきたグノーブルの先生方からの親身な言葉にもずいぶん励まされ、平静を取り戻せました。中学受験を通じて一回りも二回りも成長した姿を息子に見せてもらい、これから先の困難も色々あるでしょうが、息子が乗り越えていってくれることを信じてその背中を見守っていきたいと思っています。
慶應義塾普通部
自分が好きだった塾 グノーブル
慶應義塾普通部進学A君
僕は3年生の夏からグノーブルに入りました。当時の入った理由は簡単なもの「体験授業が楽しかった」それだけでした。しかし、学年が上がるにつれて増えていく授業、難しくなる宿題……段々と塾が好きな場所ではなくなっていきました。もともと、考えるのは好きだけど勉強は嫌いでした。また、面倒くさがりな性格で生活態度も散々だったので、よく親とけんかしたりしましたが、それでも慶應義塾普通部合格にまでこぎつけました。なぜそんな僕でも合格できたのか振り返ってみたので、ゆっくり読んでいってね!
Q:なぜ、退塾しなかったのか?
A:正直退塾しそうになることは数え切れないほどあった。けれど、4年生で行った普通部の労作展から、この学校に入りたい気持ちと、今までやってきたことを無駄にしたくないという気持ちでぎりぎり踏みとどまっていた感じだった。「志望校に入りたい」という気持ちの存在は大きかったです。
Q:一番つらかったことは?
A:友達からの遊びの誘いを断ること(これが意外とつらい)。僕の学校の友達の中には、もちろん受験生じゃない人もいた。そんな人たちからプールや遊園地に誘われて、行きたくても行けないのがつらかった。その分、僕は6年生の夏まで野球を頑張りました。
Q:テストが悪かった時はどうしていた?
A:すごく落ち込んだ。しばらくはやる気が起きなくてソファーにダイブしていた。しかし、入試当日に算数でミスをしてしまった時はそうするわけにはいかず、直前に社会の先生がおっしゃっていた「教科ごとに気持ちを切り替える」を思い出して、次の教科の試験に取り組みました(好きな曲を見つけておいて、落ち込んだ時に聴くのも結構良い)。
僕はもう受験が終わりましたが、居残りで質問をさせてもらったり、過去問の添削をしてもらったりと、先生には感謝してもしきれないです。とはいえ、後悔していることはたくさんあります(例えば「基礎力テスト」をやり残した部分があるとか…。その部分は入試が終わったあとに全部やりました)。しかし、皆さんにはまだ時間があります。その時間を有意義なものにするのか意味のないものにするのかは、自分次第です。ファイト! 祈・合格
「まさか」を引き寄せる力
慶應義塾普通部進学A君の保護者様
4年生の時から憧れ続けた第一志望校の入試当日。試験会場から出てきた息子は「算数の大問1、やっちゃった」と一言。私は「そっか」とうなずきながら、これまでの日々に思いを馳せて帰宅しました。
翌日の合格発表。絶対に落とせない計算問題を間違えたことで、「もしかして」の期待もなく見た結果は「まさか」の合格でした。運が良かった、と言えばそれまでですが、振り返ると、その運をつかむところまで息子なりに努力を重ね成長していたことはあったように思います。
まさかを引き寄せた力は何か、思いつく限り書き出します。
■グノーブルの授業が毎回楽しかった(迎えに行くと、爆笑しながら授業の面白エピソードを話してくれた)
■校舎の皆が仲良く、毎回小テストの点数を競うなど、切磋琢磨できるお友達がいた
■日曜特訓で、実際に同じ学校を目指す仲間からたくさん良い刺激をもらえた
■入試に面接があったことで、自分の志望動機や将来について真剣に考え、長所・短所などの自己分析もでき、自分について考える機会となった
■算数が苦手だったので、6年生の夏はとにかく算数に取り組んだ。わからない問題をそのままにしないよう、最後まで残って必ず質問に行っていた(先生、遅くまでありがとうございました)
■秋以降は、算数で点を取れない分、得意の社会で「1位を取る!」くらいの気持ちで臨んだ
■過去問の添削:先生方からの添削の言葉は温かく、時には厳しく、冷静に現実を見つめ直すことができました。社会の先生からは細やかな配慮や類題、詳しい資料までいただき、理科の先生からは見直すべき問題の取捨選択をしていただきました。
特に国語の先生からの添削は、息子の解答から本人の性格や本質を突く厳しい言葉をいただき、本当に感謝しています。「なかなかここまで本当のことは言ってもらえない。ありがたいよ」と言葉の裏にある愛情を感じ、親子で真摯に受け止めました。
先生からの厳しい言葉、お褒めの言葉はコピーしてノートに貼り、入試にも持っていき、直前までお守りとなりました。
これらの力を得て迎えた入試当日。帰り道で冒頭の「算数の大問1、やっちゃった」に続いて、息子はこう言いました。「算数の終了ブザー直前に大問1の間違いに気づいて絶望した。でも、休み時間で気持ちを切り替えようとすごくすごく頑張って、最後の理科に全力で臨んだ」
私はこの言葉を聞いた時、息子の成長に「受験して良かった」と心から思いました。
グノーブルは頼れる先生ばかりいらっしゃることはもちろん、笑顔で優しく声をかけてくださるスタッフの方もいて、とても家庭的であたたかく、親の不安や悩みにも本当に親身に寄り添っていただきました。子どもには、勉強の楽しさだけでなく、人としてどう学んでいくかを教えていただいたと思っています。
3年半もの長い間、息子の性格や特徴をよく理解し、一緒に成長を見守りながら子育てをしていただけたと心から感謝しております。本当にありがとうございました。

科目ごとに気持ちを切り替え、気合を入れる
慶應義塾普通部進学B君
僕がグノーブルに入ったのは、新4年生の2月で、そのときの成績はあまり良くなく、一番下のクラスから1つ上でした。最後までその成績に近く、安定した点を取れる科目がありませんでした。
1月校でとても行きたい学校がありました。その学校に受かるため、今までで一番努力したと思います。しかし思い通りの結果にならず、算数の大問1の計算問題をほとんど間違えたことを知り、とても悔しい思いをしました。そこで、サボっていた「基礎力テスト」を毎日しっかりやるようにし、演習のときの見直しなども必ずやるようになりました。すると演習の点数がかなり上がり、自信がもてました。
受験前日になり、算数の先生から「どの科目で失敗してもあきらめなければ大丈夫。勝ちに行ってこい」といわれたので、本番ではそのことを意識し、科目ごとに気持ちを切り替えて気合を入れていました。その結果、普通部に合格することができました。
グノーブルの先生の話をよく聞き、信じていれば必ず合格に導いてくれるので、これからもがんばってください。

受験を終えて
慶應義塾普通部進学C君
僕は4年生から入塾しました。そこから3年間、楽しい授業をしてくれてありがとうございました。
僕が受験を通して思ったことは、テストの結果で一喜一憂しないということです。僕は5年生のころ、理系はほとんど一番上のクラスで、苦手な文系でも上から二番目のクラスでした。それで僕は調子に乗っていたと思います。「この程度でいけるのか」と思っていたので、必死に勉強したというわけではありませんでした。でも6年生になって成績が下がり、4科目の偏差値は55くらいになってしまいました。なので、苦手な国語だけでなく、算数や理科もしっかり勉強しました。そうして成績も安定していきました。それからしばらくたって学校別診断模試がありました。B判定くらいは取りたいと思っていたけれど、得意の算数が不調で結果はD判定でした。さすがにがっかりして自信を少し失いました。ですが、先生に励ましていただき「こんなところで落ち込んでいてはダメだ」と思いました。そして最後は合格できました。
みなさんも、テストの結果が悪くても深く落ち込まず、良くても勉強は怠らずに頑張ってください。グノーブルの先生方、本当にありがとうございました。
攻玉社中学校
あきらめないことが大切
攻玉社中学校進学A君
僕は3年生からグノーブルに通っていました。社会が一番好きな教科で、授業が楽しみでした。3年生の時は受験に対する意識が低く、あまり勉強をしていませんでした。4年生、5年生となり、受験に対する意識が大きくなり、勉強もたくさんするようになりました。6年生では、志望校の合格を目指して勉強をしました。成績が伸びなかったり、下がったりしたこともありましたが、合格を信じて頑張りました。ここに各教科の勉強のすすめ方を書きます。
🔳算数:一番差のつきやすい教科なので、分からない問題は先生に質問するようにしましょう。「基礎力テスト」は、毎日満点を目指してやるようにしましょう。
🔳国語:漢字や知識は確実に覚えるまで取りくみ、漢字テストでは9割以上を目指しましょう。
🔳理科:暗記できることは確実に覚え、グノラーニングチェックを毎回しっかりやるようにしましょう。
🔳社会:地理、歴史、公民の3つがありますが、苦手な単元はしっかりと復習し、復習テストでしっかりと点数を取れるようにしましょう。
あきらめなければ、合格は必ずやってきます。僕は2月1日で第1志望校の結果が不合格でしたが、次の日攻玉社中学校に合格することができました。皆さんも頑張ってください。

諦めない力
攻玉社中学校進学B君
僕は新4年生の2月から、親に勧められてグノーブルに入塾しました。
4、5年生の時の成績は、だいたい偏差値55〜60を推移していました。科目によって得意・不得意はあるものの、6年生の前半も同じく4科目の合計偏差値は55〜60を維持していました。しかし、6年生の夏からは成績が急激に下がり、毎月のグノレブテストでは偏差値50を下回るようになりました。
原因は明らかでした。6年生になると問題がどんどん難しくなり、夏期講習にしっかり取り組むことができず、勉強へのモチベーションも低下していきました。また、特に後期は演習が中心になって、今までの知識をフル活用する必要がありました。そして、それまで4科目の中で得点源にしていた算数の成績が大幅に下がったのです。
そのような中で、先生から声をかけてもらい、面談をしました。その時自分の現状に気づかされ、ハッとしたのです。それをきっかけに一気にやる気が出て、以前の調子を取り戻すための努力を始めました。
しかし、成績が下がった影響で、志望校を見直す必要がありました。1日目の第一希望を下げて確実に合格できる学校を狙い、3日目に本命校にチャレンジするという方針に変更しました。入試本番、2日目に攻玉社を受験しました。特に算数では解き終えたあと時間に余裕があり、3回ほど見直しをして、高得点を取れた手応えがありました。結果、合格することができて安心しました。3日目の本命校には実力が及ばず、不合格となったことはとても悔しい気持ちが残ります。もっと強い気持ちで夏休みにしっかり取り組めば良かったと改めて思いました。でも、算数の成績低下を克服して攻玉社に合格できたことで、大きな達成感を得られました。
この経験から学んだのは、どんなに成績が下がっても、諦めないで最後まで頑張れば努力は必ず報われるということです。皆さんも困難に直面した時こそ、粘り強く頑張ってください。
駒場東邦中学校
楽しく勉強できた
駒場東邦中学校進学A君
僕は新4年生の2月からグノーブルに通い始めました。遊ぶ時間を確保しながらでしたが、何とか食らいついていました。
5年生の秋ごろ、駒東の文化祭に行き、とても楽しかったので「駒東に行きたい!」と思うようになりました。5年生の終わりごろからクラス昇降が始まり、得点が伸びなかったら落ちるというプレッシャーがかかりました。6年生になると土曜特訓が始まりました。そのため、サッカーに行く回数も少なくなっていました。受験が終わった今だから言えるのですが、「受験の天王山」と呼ばれる6年生の夏は、意外とあっさり終わってしまいました。なので、不安になる必要はないと思います。
6年生後期になって、日曜特訓が始まりました。日曜特訓は同じ学校を目指す仲間がいたので楽しく勉強できました。僕のグノレブテストの結果は、だいたい偏差値が57くらいでした。僕は最初、国語と算数と理科がいまいち伸びませんでした。社会だけが頼りだったのです。そんな僕でも、日曜特訓が始まってからは国語が少し伸びてきたような感じがしました。グノの学校別診断模試ではC判定でしたが、それでも合格することができました(ちなみに、本番でも理科の大問5を全て空欄にしたまま終わっていましたが、他教科で挽回できていたようです)。模試等の結果は気にしなくても良いし、本番でミスしたことにあとで気づいても、変えられることではないから大丈夫だと信じて発表を待ってください。きっと合格しています。祈合格!
楽しく学べたからこそ
駒場東邦中学校進学A君の保護者様
グノーブルには新4年生からお世話になりました。受験のための勉強というよりは、学ぶ楽しさを味わいながら、勉強した先に受験というものがあれば良いなと考えていたので、“知の力を活かせる人に”というグノの理念に惹かれたこと、通塾回数が少なくサッカーを長く続けられそうなことが主な決め手となりました。
勉強系の習い事はしておらず、入塾テストもギリギリ合格のラインでしたが、その後のグノレブ偏差値はだいたい55~60前後で推移。実力テストだけは4年生から一度も60を切ることがなく、6年生後期は全て実力テストのため、最終的な5回平均偏差値は63となりました。我が家は、年度のはじめに私が1週間の復習予定表を作り、息子は毎日毎週それを実行するというスタイルが6年生まで続きました。だいたいテキスト2周、学年が上がり量が増えてくると、理科を1周に減らし数日に分散するなどして夜の2~2.5時間のみで回せるように調整し、放課後や土日の昼間は遊んだりサッカーに通ったりしていました。
5年生の夏休み明け頃に算数に苦手意識を感じ始めたのか、問題が解けずに泣いたり塾を休みたがるようになりました。先生には「自信をつけるしかない」と言われ、苦しみながらもコツコツとやるべきことをこなしました。息子はどちらかというと国語の方が苦手で、算数は高低差はあれど相対的に見ると苦手ではなかったと思います。実際に模試や過去問でもA問題は取れていましたが、図形や思考力のB問題に悩まされ、それは入試直前まで続くことになります。
6年生になると土曜特訓が始まり、演習の成果か、国語の客観問題がよく取れるようになっていきました。毎回席順昇降があるのがどうかなと心配しましたが、息子は意外と楽しんでいたようです。もちろん、全然できなかった…と泣いて帰ってくることもありましたが。
6年生後期、通塾日も復習量も更に増えましたが、クラスの子達との仲間感もでてきたようで、息子は今までのグノ生活で一番楽しそうに見えました。日曜特訓に通うにつれて、駒場東邦に行きたい気持ちも高まっていったようです。9月から過去問も開始。都市大付属と農大一中を2~3回分ほど解き、その後駒東の過去問に取り掛かりました(都市大付属と農大一中は志望度が高かったので、10月以降の模試の日の午後や冬休みにもやりました)。6年生後期の息子は、偏差値や判定だけ見れば駒場東邦に合格できそうな数値でしたが、とにかく過去問の算数が全然取れず、理科も不安定でした。土曜特訓の平面図形マスターは必ず2周やり、講習前など時間がある時には先生に指示された回の平面図形マスターや日曜特訓の算数駒東プリントをもう一度全てやり直したり、それまで復習していなかった開成プリント内の授業で扱った問題の解き直しをするなど、冬休み明けまでとにかく算数を頑張りましたが、1月中旬に実施した最後の過去問も結局受験者平均に届きませんでした。算数の先生には、駒東の算数は本当に難しいので取れる問題をしっかり取って捨て問選択がきちんとできれば大丈夫、と励ましていただき、息子もこの言葉をお守りにしていたと思います。土曜特訓の実践テストなどで鍛えられたのか、模試や過去問でも、捨て問選択はきちんとできているように思いました。理科は、授業と宿題と『有名中学入試問題集』をこなし、グノラーニングチェックの知識回を夏以降にも繰り返しやることで、いつの間にか伸びていました。
1月に入って、今まで細々と続けていたサッカーを休会しましたが、学校には試験4日前まで行っていたので、埼玉受験後は日々の復習に追われて過ぎていきました。11月の模試で偏差値64、駒東学校別80%に対して、12月は56、グノ学校別模試の結果はC判定と、周りがギアを上げてきた気がしてならず、私は内心とても不安でしたが、息子は特に焦る様子はありませんでした。日曜特訓の演習や席順で自分の位置を毎回確認できていたからかもしれません。学校を休んだ最後の3日間は、1月分の日曜特訓算数の駒東プリントの解き直しや、理科重大ニュースプリント、有名中の理社、都市大付属の理社過去問、「漢字道場」で間違えた問題などをやり、前日に一緒に荷物と当日の流れの確認をしました。
そして迎えた2月1日。息子は「全然実感ないな」と言いながら夫と一緒に駒東に向かいました。私は、どんな顔で出てくるかな? 全然できなくて泣いて出てきたら何て声をかけよう…そんなことを考えながら息子を迎えに行きました。そして待ち合わせ場所に来た息子の第一声は「理科の終了時間を間違えて大問5全部空欄にしちゃった」でした。衝撃的すぎて、それまでにシミュレーションしていたことも忘れてものすごく動揺しました。しかし1日の午後は第二志望の都市大付属の試験があります。なんとか気持ちを下げずに午後受験に向かわなくてはという思いと、あまり期待させては可哀想だという思いが自分の中でせめぎ合いました。息子は他の3教科には手応えを感じていたようで「20点だったら算数2問分か~」「他の教科でカバーできてないかな~」と明るく振る舞っていましたが、ふとした時に涙を見せないようにするそぶり。それを見た瞬間に、息子が必死で切り替えて前を向こうとしていることに気付き、息子の成長に胸が熱くなると同時に、その気持ちに気付けず弱気になってしまった自分を猛省しました。そして「大問1つで20点分もないと思うし、それを皆が満点取れるわけじゃないから、10点分もないくらいじゃない? きっと他の教科でカバーできてるよ」と言って午後の試験に送り出しました。息子は「うん、大丈夫だよね!」と自分に言い聞かせるように言って都市大付属に入っていきました。
そうは言ったものの、私はそこから翌日の発表まで生きた心地がしませんでした。どうやって合否を伝えるか? 不合格の画面は本人に見せるか否か? 不合格だった場合のことばかり考えていました。
しかし翌朝、結果はまさかの合格…! 息子も私も嬉し涙を流して喜びました。
泣き虫だった息子がこんなにも強くたくましく成長したこと、これまで本もほとんど読まず記述も一行書くのがやっとだったのに、たくさんの文章に触れていろいろなことを考え世界が広がったこと、様々な知識を得て世の中の解像度が上がったこと、全てグノーブルで素晴らしい先生方に出会い、仲間と共に楽しく学べたからこそだと思っております。息子がここで得た知の力を活かして生きていく今後が楽しみです。本当にありがとうございました。

他人のことは気にするな
駒場東邦中学校進学B君
僕は、3年間勉強したことを2月1日に発揮しないといけない大変さを知ったので、受験直前、受験中のことを挙げます。
🔳受験直前:
・「漢字道場」を1周しました。
・僕は理科が得意だったので、9月から理科はやらず、算数や国語、社会に全振りしました。
・胃腸があまり強くなかったので、1週間前からR-1を飲み始めました。
🔳受験中:
・当日、手洗いなどで自然と耳に入ってくる他人の評価は全部無視しました。
・駒東のテストは長いため、軽食を持っていきました。食べすぎ注意!
・日曜特訓で鍛えられます。自分が解けないものは他の人にも解けるはずがないです。
・早めに手洗いに行くことで、休憩時間を効率的に活用できます。
・会場で会う友達には基本的に話しかけませんでした。
・雪が降るかもしれない、何があるかわからないので、早めに家を出ました。
・解答用紙の回収と配付に5分ずつかかるので、休憩時間は実質5分です。
あとはGnoの先生を信じるだけです。健闘を祈ります。
子どもの意思を大切に育てた中学受験
駒場東邦中学校進学B君の保護者様
🔳出会い:グノーブルとの出合いは、8期生の卒業生を持つ知人からの紹介でした。
「すごく良い先生がいて、親子でファンなの!グノーブルに惚れ込んだ!ぜひ入会して!」
その通りでした。本当に、グノーブルを選んで良かったと思います。私には「良い修行をさせてもらった」という言葉がしっくりきます。グノの勉強は厳しいですが、指導は的確で、魅力的な先生のおかげで子どもは耐え抜く力が養われ、私は次々やってくる試練を乗り越える子育ての忍耐力がついたように思います。
🔳子どもの特性:知的好奇心が旺盛で、自分が決めたことを全うする頑なな子です。3年生になったら受験するか決めるねと2年生で言われ、そして、3年生秋に塾に行きたいと言いました。都立受験も含め6か所の塾の体験に行き、新4年生で本人が選んだのがグノーブルでした。「先生が面白いの! あの先生に習いたい!!」。この、「あの先生」に最後の最後までお世話になりました。なんと8期生の知人から聞いていた先生でした。ご縁もありがたく、本当に感謝しております。
🔳我が家の方針:①「勉強しなさい」は言わない ②中学受験が全てではないことを家族の共通認識とする ③2月1日を笑顔で迎える ④悔いの残らない受験にするために出来ることを考える。この4点でした。子どもが決めた受験だったことと、その後の人生を考えての方針です。
🔳5年生の秋:毎回楽しそうに塾の話をするグノ生活でも、習い事や学校の行事など忙しくなると、体が追いつかず、気が向かない時期がありました。行かないと大変だから無理やり行くものの笑顔がなくなり、次第に子どもの目が死んでいきました。これはサインだなと思いました。
1カ月塾を休ませようと思い先生に相談すると、「来年のことを思うと勉強の体力をつけておきたいので、出来るだけ来てください」と言われました。悩んで考えたのは、罪悪感なく休める『塾の有給休暇制』を我が家で導入することです。月2回まで休んで良いことにしました。「最終的に6年生2月に仕上がっていれば良いのだよ!」と早寝させましたが、実際は「休むと更につらい」のです。授業動画を見るのに時間がかかり、見ない単元はグノレブに響くという悪循環。しかし、ほどなくして復活。それ以降、すっかり休まなくなりました。修行の第一関門突破です。
当初、新4年生から勉強する必要はあるのかな?と思っていましたが、①グノに通うことに慣れる ②勉強することに慣れる ③勉強から逃れられない現実を受け入れる。この3段階に必要な期間だったと思いました。
🔳6年生:友達にしばらく遊べなくなると宣言してきた新6年生。5年生までは、外遊びにゲームに習い事を楽しみ、家での勉強量は週2日×2時間くらいだったこともあり、慣れるまで2カ月は大変で、必死に勉強をしました。
【国語】夏頃、国語の読解が出来なかった(正確に言えば復習をしていなかった)ので、グノーブル主催の学校説明会で、国語の勉強法について駒場東邦の先生に現状を伝え、相談しました。すると「そういう子は多いのですよ。大丈夫、理数系の子の国語の読解のポイントは根拠を見つけること。根拠にマーカーで線を引いてあげてください」「何が足りなかったか、考えさせてください」と言われました。「親が手助けするのか…!」と思いました。それから、復習を30分だけ一緒にやりました。それなりに手ごたえはつかめたようですが、波があり、勉強しなさいと言わないようにする工夫がしんどかったです。これは私の修行、第二関門でした。
私の頭の血管が切れないようにしながら、国語の勉強を促す修行です。私の声掛けは以下のような感じです。「30分国語やるか、やらないで動画かテレビみるか選んで! だらだら迷っている時間がもったいない! 迷うなら遊びなさい! 待っている時間がしんどい! 1分以内に決めて座らなかったら今日の勉強終わりにしてテレビを見て! 私はお風呂入るから!」と言ってタイマーを1分かける…国語はそんな声掛けを山ほどしました。4年生の頃は、ふて寝から朝まで本気で眠りこけることもあり本当に苦労しました。6年生になると、声掛けからだいたい1分以内に座るので、30分カウントダウン方式で勉強することになるのですが、態度が悪く、この修行中はストレス緩和のサプリを飲みました。
【理科】6年生の秋から、家では勉強をしなかったのですが、大丈夫でした。ベーシックというテキストをあますことなく復習したこと、わからない単元(5年生で休んだ回)は探究学習のように調べたことが効いたかなと思っています。何より吸収が良かったです。
【算数・社会】やることがわかりやすかったこと、好きな先生の授業を受けたい気持ちが原動力になっていたことで、6年生では目の前の復習を自らやっていました。算数は、たまに子どもからバックナンバーをリクエストされ、5年生のテキストを復習することがありました。
【志望校選び】少しチャレンジで設定、ぶれずにいこうと家族で決めて駒場東邦にしました。文化祭で中学1年生の生徒さんに国語について相談したところ、「理科が出来れば国語は出来なくても受かるよ!」とアドバイスをもらったことも、背中を押してくれました。たしかに、算理好きにはぴったりな学校で、6年生の秋から日曜特訓が始まると、水を得た魚のようでした。今考えると、駒東の問題が合っていたのですね。「鬼のように勉強させられるー」と楽しそうに話していて、1年前が嘘のようで、頼もしく感じました。
【1月】最後の修行、第三関門は1月でした。過去問や授業の復習はやっているもののまだ時間があり、過去問は合格点に届いているので、子どもは合間に家で映画を観たりしてのんびりしていました。直前期に、私がヒステリックになって勉強をやる方向へ持っていくのは得策ではないとわかっていたので、見守っていたらいつのまにか緊張感がなくなっていました。「このまま過ごすと悔いが残りそう…」とハッとしました!
【10日前】「もう散々勉強したけど、完全にやり切った思いで入試に向かえるように、今までにない充実した10日間にしよう! もう一度一緒にがんばろう!」と伝え、何が有効か考えさせました。すると「国語の知識は語彙以外出ないから片付けて視界から失くして、国語の前のテキストを持ってきて」と子どもからリクエストが出て、自発的に入試前に見るための間違いノートを作り、漢字の総復習や、寝る前に時事や公民の総ざらい等をし、勉強もほどほどに早く寝ていました。子どもが先に緊張感を取り戻し、その姿に励まされました。
【当日】2月1日朝、子どもが目覚まし時計の音と共に「やっときたーーー!!」と言いながら楽しそうに起きた時、もう目標の半分は達成したと思いました。夕食時、入試どうだった? と聞くと「過去イチ算数めっちゃ楽しい問題が出て解けた! どの過去問より面白かった!」と晴れやかな表情で言った時、あ、もう受験は成功だった! 落ちても悔いはないと思いました。自然と家族で乾杯していたあの光景は、とても幸せな記憶として私の人生に刻まれました。良い受験だったと思います。力がついて楽しめたのは、日曜特訓のおかげ、切磋琢磨した仲間のおかげ、そしてやる気にさせてくださった4科の先生方のおかげでした。4~6年生の間にグノの時間が増え、積み重なることで、私の見えないところでしっかりと成長していたことに気が付きました。
自立が始まっているけれど、まだ親の助けが必要な過渡期に、一緒に受験に向き合い、試行錯誤しながら取り組めたことが、親子のかけがえのない経験となりました。親にも子にも寄り添い、励ましてくださった先生方、本当にありがとうございました。

受験に必要なこと、それは自信である
駒場東邦中学校進学C君
いくら模試の結果が悪かろうと、体調がすぐれなかろうと、自信さえあれば、思った以上の力を発揮できるのである。
では、どうすれば強い自信を手に入れることができるのだろう?答えは簡単、自分が「これで十分だ」と納得できるだけの努力をすれば良いのだ。それが、たとえものすごい勉強量でなくとも、必要最低限だとしても、自分がズルせず、さぼらず、課題を達成して、またひとつ自分の実力が上がったと信じることができれば、それは必ず自信となり、合格、更にその先への架け橋になるのだ。
これを読んでいる人にも、最後まで『俺・私には実力があるんだ‼』と、自信を最後まで持ち続けて受験してほしい。
本当にありがとうございました
駒場東邦中学校進学C君の保護者様
受験直後の感想と情報を4点ご報告します。みなさまの参考になりますと幸いです。
①わが家の受験方針は、授業の復習や宿題をきちんと行うことは必要最低限としつつも、できるだけ親がプレッシャーをかけることはせずに、その範囲で合格できる学校を目指すというものでした。そのため、6年生の冬まではそこまで大きなストレスを感じずに過ごすことができました(グノーブルの先生方の、4教科全体を見渡しながらの課題の出し方に、心から感謝申し上げます)。
しかしながら、1月受験の日が近づいてくると、上記のような自信を持っていたという息子も、夜中に何度も目が覚めてトイレに行くようになりました。1月31日と2月1日の夜は、より頻繁にトイレに起きて、過去最高に寝不足な状態で、2月1日と2日の試験に臨みました。親は正直、「試験で実力を発揮するのは難しいかもしれない…。」と心の中で思っていました。
しかし、なんとか2月1日と2日の合格をいただきました。グノーブルの先生にそのことをご報告すると、「行きたかった学校だから、たとえ寝不足でも、“負けてたまるか!”という思いで試験に取り組んだのだと思いますよ」と言ってくださいました。おっしゃる通りだなと思いました。きっとどのお子さんも、そのお子さんにとっての「ここぞ」という場面で、底力を発揮してくれるのではないかと思います。
②1月の渋幕の受験の際には、算数の試験中にトイレに行きたくなり、猛スピードで全ての問題を解き、挙手をしたそうです。そして、トイレが終わると、別室に連れて行かれ、トイレに立った時間は試験時間に含めず、純粋に残っていた試験時間が終わるまで、問題を解かせてくださったそうです。そのおかげもあって合格できました。1月の栄東もそうでしたが、1月受験校の受験生へのあたたかな配慮は、本当にありがたかったです。
③受験当日は、試験と試験の合間に「軽食」を食べても良いという学校がいくつかありました。息子は「疲れた脳には、すぐに吸収されて栄養になるブドウ糖を補給したい」とラムネを食べていました。
④午前受験と午後受験の間は、ホテルを確保して過ごす方もいらっしゃるようです。わが家はレンタルスペースを予約しました。なかなか狭くて事務的なスペースでしたが、家族だけでのんびりとお昼ご飯を食べて、リラックスできてとても良かったです。
最後に、子どもたちの知的好奇心を育ててくださるグノーブルの先生方、そしていつも優しく明るく対応してくださったスタッフの皆様、本当にありがとうございました。グノーブルで授けていただいた思考力、知識、そしてユーモアを交えた様々なお話が、息子がこれからの人生を生きていく上での、とても大切な礎になると確信しています!

いつでも前向きに
駒場東邦中学校進学D君
僕は新4年生のときに入塾しました。4年生の最初は4教科ともよくできましたが、後半に入ると理系、特に算数の雲行きが怪しくなってきました。5年生の前半に算数が平均の少し上くらいになってしまいましたが、文系、特に社会がかなり得意だったので、5年生の最後の偏差値は55から58くらいでした。
しかし、慢心してしまったのか、算数だけでなく、理科と得意だった国語の偏差値もどんどん下がってしまいました。模試では算数の偏差値は30台を連発してしまいました。その後、算数の演習を積んだりしたことで回復しました。
そして1月受験で良い結果を残し、無事に2月1日の駒東にも合格できました。皆さんも、成績が下がっても諦めずに頑張ってください。合格を祈ります。
楽しく充実した中学受験
駒場東邦中学校進学D君の保護者様
「力は出し切った。清々しい気持ち」
駒場東邦中学の受験後に息子が言った言葉です。この言葉を聞いて、どのような結果になろうとも、息子の中学受験は成功だったと確信しました。
グノーブルには新4年生から3年間お世話になりました。グノーブルを選んだ理由は、通塾日数が少なく他の習い事と両立が可能であったこと、文系と理系でクラスが分けられていたことです。息子は文系と理系で力の差が大きかったのですが、グノーブルでは学力に合った授業を受けることができました。
しかし、受験までの道のりは決して平坦ではありませんでした。6年生になり、苦手な算数が足を引っ張り、文系はαコース、理系はα3コースとなりました。夏休みまではテキストにひたすら取り組み、秋以降は加えて過去問にも取り組みましたが、算数のグノレブ偏差値はずっと50程度、学校別では30台を何度も記録しました。駒場東邦中学は算数が難しく、算数で合否が決まると言われていたので、志望校を変えた方が良いのではないかと悩みました。しかし、息子は熱望している駒場東邦中学を絶対に受けると強い意志を持っていました。
その後、算数は入試直前に開花し、どの中学でも合格者平均は取れていたようです。受験生は直前まで伸びるという話は本当でした。最終的に、熱望していた駒場東邦中学をはじめ、受験した4校全てから合格をいただくことができました。志望度が高かった1月校にも受かったことで、2月は行きたい学校に絞って受験をしました。
息子はグノーブルが大好きで、3年間ほぼ休まずに通いました。6年生の日曜特訓の駒東コースでは、お互いに切磋琢磨し合える素敵なお友達にも恵まれました。「グノーブル最高。中学受験楽しかった」という息子の言葉のとおり、非常に充実した中学受験でした。単なる暗記だけでなく、深い授業をしてくださったグノーブルの先生方、クラスのお友達に心から感謝しています。
グノーブルを選んで本当に良かったです。グノーブルの益々のご発展と、後輩の皆様が笑顔で受験を終えられることを心から祈っております。本当にありがとうございました。

努力は必ず報われる
駒場東邦中学校進学E君
僕がグノーブルに入塾したのは、4年生の2月でした。一度目の入塾テストでは不合格となり、二度目の挑戦でようやく合格しました。そのため最初の頃は、長い間、一番下のクラスでした。そんな僕が駒場東邦に合格し、筑波大学附属駒場にも挑戦できるまでになったのは、グノーブルで努力を積み重ねたからです。
ここでは、僕がグノーブルでどのように勉強していたのかを紹介します。
🔳算数:授業に集中し、家庭学習では問題を完璧に解けるようになるまで繰り返しました。また、計算力を強化するために「基礎力テスト」にも取り組みました。
🔳理科・社会:授業では先生の話をしっかり聞き、家では宿題をすべてこなし、間違えた問題を覚えるまで復習しました。さらに二回ほど解き直しを行い、理解を深めました。
🔳国語:僕は読解が特に苦手で、他の教科と比べても圧倒的にできませんでした。そこで先生と何度も面談を行い、解き方を修正しながら練習を重ねました。その結果、試験本番では国語が一番うまくいきました。
では、どうやって解くようにしたのか?
・大問ごとに使う時間を決める
・問いの近くの文章を特に注意して読む
・読みながら重要な部分に線を引く
・簡潔明瞭な記述を心がける
こうした工夫を続けたことで、国語の得点が安定するようになりました。
駒場東邦を目指す人へアドバイス
🔳算数:グノレブよりやや易しいので、日々の授業をしっかり理解することが大切です。
🔳国語:授業に集中し、解き方を身につけることが重要です。
🔳理科・社会:問題が特殊なので、過去問を解きながら出題傾向を把握することをおすすめします。
僕がここまで成長できたのは、グノーブルで努力を続けたからです。「努力は必ず報われる」と信じて、これからも頑張っていきたいと思います。
息子を信じて
駒場東邦中学校進学E君の保護者様
私たち夫婦はともに中学受験の経験者でした。そのため、受験の良い面も悪い面も理解しており、息子に中学受験をさせることが本当に良いのか、何度も話し合いました。なかなか意見は一致しませんでしたが、最終的には息子自身が受験を希望したため、塾に通わせることにしました。しかし、最初の入塾テストでは不合格。時代が変わっても、中学受験の厳しさは相変わらずだと実感しました。幸いにも二度目の試験で合格し、4年生からグノーブルに通うことになりました。
4年生の頃、息子はサッカーに夢中で、ほとんど勉強をしていませんでした。その結果、コースはα5とα4を行き来していました。それに加えて、彼にはSとDという「重要なクラス」がありました。Sはサザエさん、Dはドラえもん。録画して何度も繰り返し見ていたため、学習への集中力が持続しなかったのかもしれません。受験には向いていないのではないかと考え、「やはり無理にやらせる必要はないのでは」と、親として何度も悩みました。
そんな息子が少しずつ変わり始めたのは、算数との出合いがきっかけだったと思います。グノーブルの授業を通じて算数の面白さに気づき、さらに「自分には意外と算数のセンスがある」と思い始めたようです。算数だけは自主的に勉強するようになり、その結果、5年生の夏ごろには算数のコースがαにまで上がりました。αでは切磋琢磨できる新しい友達もでき、塾に通うこと自体が楽しくなったようです。その影響で、他の科目にも少しずつ取り組み始め、全体的に偏差値も上がっていきました。
とはいえ、家での勉強に関してはあまり熱心ではなかったように見えました。「ちゃんとやっているのか?」と何度もしつこく聞いてしまい「言いたくないけど、言わざるを得ない」と感じる場面も多々ありました。それでも息子は「授業はとても楽しいし、授業中にしっかり集中しているから大丈夫」と自信満々。そのような状況でしたので、息子も一緒に先生に面談していただき、少しでも家で勉強する気になるようご相談しました。先生はとても真剣に息子と向き合い、どのようにすれば1分でも長く机に向かうことができるか話していただきました。また、国語は特に苦手でしたので、国語の解き方についても丁寧に教えていただきました。そのおかげで、グノレブテストの偏差値は上がったり下がったりを繰り返しながらも、徐々に向上しているようでした。
そして迎えた受験直前。驚くべきことに、息子は受験ギリギリまでSとDを続けていました。さすがに6年生の冬「そんなの見ていて大丈夫なのか?」と聞くと、息子は堂々と「もうやめたよ。Dは録画から消した」と宣言。しかし、結局入試前日までSは視聴していました。
親は子どもの生活のすべてを見守ることはできません。だからこそ、最終的には「信じること」が大切なのだと感じた受験でした。息子は常に自信満々で、どこか楽天的でしたが、それでも自分のペースで努力を積み重ね、結果を出してくれました。これもすべて先生方のおかげと感謝しております。どの教科の先生の授業も楽しく、勉強の楽しさを知ることができたようです。
最後に、一番苦手だった国語も本番ではよくできたと喜んでおり、先生に感謝の気持ちでいっぱいです。3年間、本当にありがとうございました。

過去問が合格への近道
駒場東邦中学校進学F君
僕は新4年生の頃に入室しました。コースはα1あたりにいたのですが、6年生になると不得意な国語が足を引っ張るようになり、また他教科でもミスが増え、成績が少しずつ下がってしまいました。模試では微妙な成績の時もあれば良い時もあり、学校別模試では毎回合格可能性50%という不安定な状態が続きました。12月までは勉強もやる気が起こらず、自分でもそのことに気づいていたので焦っていました。
しかし、1月に埼玉で初めての受験本番を経験したことで、自分の立ち位置がわかり、だんだん受験が自分事になってきて、やる気もわいてきました。そこからようやく勉強に集中できるようになっていきました。
2月1日の受験本番を迎え、なぜか僕はあまり緊張しませんでした。しかし、試験を終えると算数以外が全然できなかったような気がして、両親も試験後に青ざめた表情の僕を見て、落ちたかもしれないと思ったそうです。その日は午後も受験があり、どうにか気持ちを切り替えました。
そして結果は、駒場東邦も午後校も2日校も合格。まったく自信がなかったので、合格発表を見た時はとても嬉しかったです。
僕は模試では微妙な成績ばかりでしたが、過去問では常に合格最低点を上回っていて、苦手な国語も駒場東邦の問題だけは回を重ねるごとに合格平均点を上回るようになっていたので、しっかり過去問を解くことが合格までの近道になったのだと思います。
グノーブルでは、楽しい先生や良い仲間に出会えます。不安なことやスランプも色々あると思いますが、自分とグノーブルを信じて皆さんもがんばってください。

グノーブルを信じて
駒場東邦中学校進学G君
僕は3年生の季節講習からグノーブルに入りました。初めのころは、グノーブルに行く日数も少なかったので、あまり中学受験を意識しておらず、楽しく授業を受けていました。しかし、4年生、5年生と学年が進むにつれて、成績やテストのことも考えるようになって、クラスの昇降も気にするようになりました。そこで僕が頑張ったことや、やっておいた方が良いと思ったことをお伝えします。
◼️算数:算数は得意科目でしたが、基礎があまり身についていませんでした。僕はあまりやらなかったけれど、計算ミスなどが目立つ人は、「計算マスター」や「基礎力テスト」をきちんとやると良いと思います。駒東では複雑な発展問題などもあるので、日頃の授業や家庭学習などで、難しい問題があったら放っておかずに、解き方を調べたり先生に聞いたりするようにしましょう。
◼️国語:僕は文章読解より漢字が苦手でした。駒東では漢字が30問も出て、1問のミスが合否に直結します。「漢字道場」はなるべく複数回やって、全て覚えるようにしましょう。また、駒東は物語文が1本で、記述問題も多めです。比較的長めの文章のことが多いですが、物語全体を踏まえて書く記述問題もあるので、本文はちゃんと読むようにしましょう。
◼️理科:理科は得意でした。駒東の理科は、大問1が小問集合、大問2〜5が生物、地学、化学、物理のどれかになっています。大問1の小問集合は、模試や演習ではずっと難しかったので、後回しにした方が良いのではないかと思っていました。しかし、本番の駒東の入試では、大問1の小問集合は基礎問題で、あまり難しくありませんでした。僕はこのことにより、点数が少し下がったような気がします。皆さんも自分が受ける年になって出題傾向が変わるかもしれません。そんなときも、焦らずに問題を解くようにしましょう。
◼️社会:社会は、分野ごとの得意不得意はあまりありませんでした。駒東の社会は、とにかく記述が多く出題されることが大きな特徴です。提示された資料から情報を読み取って、うまくまとめられるようになりましょう。また、どうしてもわからない記述問題は、あまり悩まずに、答えを見て覚えることをお勧めします。
入試本番は、周りの人が気になったり、緊張したりすることもあると思います。それでも、これまで教えてくださったグノーブルの先生と自分の努力を信じて入試に臨めば、必ず良い結果が待っています。頑張ってください。🌸祈 合格

受験勉強のアドバイス
駒場東邦中学校進学H君
僕は新4年生の2月にグノーブルに入塾しました。3年間グノーブルで勉強したおかげで駒東に合格できました。
その中で僕が実際にやったことや、やっておけば良かったと思ったことをお伝えします。
【勉強のアドバイス】
■国語:苦手だった科目です。僕は文章の得意不得意の差が激しく、成績が安定しませんでした。僕は途中からやり始めたのですが、4、5年生の時は、授業でやった文章の問題にもう一度取り組み、先生に見てもらうと良いです。そして、駒東は漢字の配点が大きいうえ、小学校で習ったものが出るため、漢字の問題は落とせないです。そのため、読解が苦手でも漢字や知識はしっかりやりましょう。
■社会:最も得意で好きな科目でした。4、5年生の時は、地理・歴史の知識をとにかく覚えましょう。6年生からは記述問題の練習もしたほうが良いと思います。そして、日頃からニュースを見て社会の動きに関心を持ちましょう。
■算数:苦手だった科目です。しかし、6年生の途中から必死に頑張ったことで、10月のグノレブテストで成績が大きく上がりました。毎回の授業の復習にしっかりと取り組み、テストで良い点を取れるように頑張りましょう。日曜特訓の教材は志望校対策で重要なため、直前期に、できなかった問題を繰り返し何度も取り組むと良いと思います。
■理科:初めは得意でも苦手でもなかったのですが、途中で偏差値が大幅に下がり、最後まで足を引っ張り続けました。知識をおろそかにしていると成績がとても悪くなるので、グノラーニングチェックにしっかり取り組み、知識を頭に入れておきましょう。
【入試についてのアドバイス】
■もし上手くいかなかった科目があっても、次の科目では気にしないようにしましょう。残りの科目に集中できなくなるし、気にしても良いことはありません。
■入試会場では必ず試験のことについて話す受験生がいました。そういう人たちが言うことは全て噓だと思ってください。
■試験の間の時間はグノーブルのテキストを見るなどして有効活用しましょう。
皆さんの合格を祈っています。
サレジオ学院中学校
中学受験をして本当に良かった
サレジオ学院中学校A君の保護者様
本人が中学受験をすると言いだしたのは、2年生の頃だったと記憶しております。母親は関西で中学受験をした経験がありましたが、父親は地方の公立中学校に進み、高校受験が最初の受験だったこともあり、小学生のうちから勉強させることについて、全く意味が分かりませんでした。そろばんや公文は保育所の時から行かせていましたが、小学生のうちは外で遊んだり、スポーツをしたりするもので、机の上で勉強なんてしないものだと思っていました。
しかし親としては、子供がしたいということを否定するものでもない(ましてや、勉強するなんて、願ったりかなったり!)ことから、グノーブルに入塾しました。近隣の塾でも良かったのですが、家から30分くらいかけて通塾させる条件として、「神奈川男子御三家に進学する」を目標としました。
グノーブルを選んだ理由は、
・週2回(午後5時から午後8時(5・6年生は9時))で、トイレ以外は休み無し
・クラスも中小規模で面倒見が良い
・国社と数理でコース分けがあり、得意科目は高みを目指し、不得意科目は基礎をしっかり固められる
・テキストは、大手塾に近い
など、勉強する環境としては十二分な塾だったと感じております。
新4年生(小学3年生の2月)から通塾し、家での復習は下記の通り(新6年生の春頃まで)していました。
・算数は、テキストで授業と裏面復習。あと「基礎力テスト」。
・国語は、文章を読むのが苦手だったので、テキスト中心。
・社会は、テキストの問題を3回する。
・理科は、テキストの問題+GNOラーニングチェックの問題を3回する。
社会・理科(暗記系)は、3回やれば大体は覚えられると思っていたので、
・1回目は授業後数日のうち
・2回目は1回目の1週間後
・3回目は2回目の1週間後
という日程で、コピーしたものに日付を記入しておきました。
コピー機は、A3コピーができるものを購入しました。絶対に必要ですので、入塾と共に購入をお勧めします。
4年生の時には、真面目に取り組んでくれていたので、マンスリーのグノレブテストも、国語を除き平均以上を取っていました。5年生になると問題が難しくなり、勉強しろという親への反抗心もあり、秋頃から成績は右肩下がりの状態になりました。特に理科は得意としていたのに急降下で、5年生の保護者面談では理科の先生が担当ということもあり、檄を入れてもらおうと思っていました。ただ、塾に行くまで、本人が逃げ回るという心の弱さが見えていました(小学生だから仕方のないことかもしれませんが、これが、最後に勝ちきれなかった原因だったのかと思っています)。
2025年2月5日の受験終了のタイミングで、中学受験を回顧してもらい、5年生の時は勉強が難しくなって辞めたいと思っていたと聞きました。確かに、塾の無い日の勉強量が少なく、PCの履歴を見ると、ゲームをしていました(PCの閲覧制限を行っていたのですが、それを搔い潜っていました)。また、4年生で勉強する土台ができたと親は思っていたのですが、5年生の秋からの問題の難しさへのサポートをしてこなかったことが、成績が下がってきたことに繋がったのではないかと思います。
6年生になって土曜特訓も始まり、否が応でも勉強漬けになりましたが、勉強1時間・休憩1時間(PCゲームやテレビ)を繰り返す日々でした。そんな状況でしたので、4月・5月には、「塾を辞めなさい」と本人に迫りましたが、辞めない(「勉強するから」という前置きはありません)の一点張りでした。成績としては、春以降、持ち直したこともありましたが、勉強1時間・休憩1時間を繰り返す日々と、勉強もダラダラ(寝室で寝ながら、時にはそのまま眠ってしまうことも多々)する状況でした。秋以降は、学校別の日曜特訓も始まり、また、大手塾の模試を受けることとなりますが、当の本人は、やる気になっていない状況でしたので、当初の目標は無理だと考え、グノーブルへメールしました。
「(中略)グノーブルの通塾は続けますが、中学受験はさせません。公立中学校から高校受験をさせます。」
本人にメールしたことを伝え、「あとは自分がこれからどう頑張るかだ」と言いました。これには、精一杯頑張っているのに、何故こんなことを言うのだろうと思っていたようです。
また、テストの結果が分かるまで、見直しどころか親が採点するのを嫌がって、問題用紙と解答を隠すことを繰り返していました。テスト終了後、直ぐにどこで間違えたのか、正解割合が50%を超えるもので×となっているものはないか等、入試本番では他の受験生ができる問題を落とさないことが合格に近づくと伝えていましたが、結局やっていませんでした。これも自分ごととしてやる気になっていなかったためと思います。
親から見て、最後の最後まで自分ごととしてやる気になっていたようには見えませんでした。しかし、2025年2月1日から5日まで戦い抜いた息子を褒め称えたいとともに、これがゴールではなく「ご縁があった学校」でスタートするのだと思ってもらえたら、親としては、中学受験をしてきて本当に良かったと思えます。
最後になりますが、3年間、息子を叱咤激励していただいたグノーブルの先生方、どうもありがとうございました。
聖光学院中学校
グノーブルと自分を信じて
聖光学院中学校進学A君
僕は3年生の夏期講習からグノーブルに入塾しました。グノーブルの勉強は量が多く大変でしたが、なるべく持ち越さないように取り組むことを心掛けました。算数と理科の「基礎力テスト」は、朝やってから登校していました。
6年生になってからは、朝の勉強に漢字を加えました。授業中間違えた問題の復習と解き直しをしっかりすることは本当に大事だと思います。6年生で始まる日曜特訓の復習は特に大切です。6年生の日曜特訓が始まってからはより忙しくなりましたが、算数を伸ばしたいと思ったので、月曜特訓の聖光学院の算数を取ることを決めました。ここで聖光学院の算数対策をしっかりとできたことも、合格につながったと思います。
成績は安定していたものの、6年生後半では外部模試で良い結果が出ず焦っていました。そんな中、最後の外部模試で良い結果を取れて油断したのだと思います。最後のグノレブテストではBブロックに落ちてしまいました。その時は、今までの自分の行動をただ悔やむばかりでしたが、受験まであと少しだったため、すべての授業の復習を今までより丁寧にやり、できる限りの努力をしました。また、過去問も継続し、今まで培ってきた感覚を忘れないようにしました。
そして迎えた2月1日。開成中学校の入試です。緊張はしていましたが、会場に入ると集中することができました。しかし2月3日の入試後に親から伝えられたのは、残念な結果でした。悔しくて、家に着くと泣いてしまいました。電話で先生に結果を報告し、明日のために何をすればいいのかというアドバイスと、励ましの言葉をいただきました。そんな不安定な気持ちで迎えた4日の聖光学院中学校。もう残り日数が少なかったこともあり、一番集中することができました。感触も今までの中で一番良く、終わったあとはやりきったと思えました。5日の試験を終えたあと、聖光学院中学校の合格を伝えられ、2月になって初めて安心することができました。その後、合格したことを先生に伝えました。
僕が中学受験で学んだことは、たとえ良い結果が出なくても、自分を信じてやり続ける大切さです。皆さんも決してあきらめず、最後まで戦い続けてください。そして、困ったら先生に相談しましょう。僕は直前の1月に相談しましたが、そのことも合格につながったと思っています。行きたい学校に皆さんが行けますように。祈合格!
人としても成長できた中学受験
聖光学院中学校進学A君の保護者様
グノーブルには3年生の夏期講習からお世話になりました。先生方の楽しい授業と、苦楽を共にした生徒の皆さんのおかげで、大変ながらも楽しくグノーブルに通うことができました。勉強だけでなく、諦めない精神力や地道な努力を身につけて、成長させていただいたと思っています。
学習面では、毎日の「基礎力テスト」は必ずやる、宿題で出た必須の問題は必ず取り組む、苦手な算数は間違えた問題を中心に複数回解く、という流れで授業の復習や教材に着実に取り組んだおかげで、グノーブル一本で最後まで走り抜けることができました。
3、4年生の頃は親がサポートする場面も多くありましたが、5年生になると徐々に自分なりのペースや取り組みのルールが出来上がってきたようでした。6年生になると、大枠の勉強スケジュールは相談して決めるものの、授業中に特に重要だと言われたこと、自分の苦手とする分野を息子なりに判断して重点的に取り組んでいました。国語が得意、算数が苦手という息子でした。国語は、グノーブルの問題文や志望校の過去問で、息子が興味を持った文章の出典元の書籍を購入して勉強の合間に読んでおり、絶え間なく長文に触れる機会を持ち続けたことは、やって良かったことの一つかなと思っています。算数は最後まで苦戦していましたが、それでも諦めることなく難度の高い問題にも何度も取り組んでいた姿勢が印象的でした。苦戦しながらも、最後まで粘り強く取り組んだことが最後の合格へと繋がったかと思います。
志望校は、5年生までに様々な学校の文化祭や見学に行き、息子に合う学校・興味を持った学校を見つけ、絞っていきました。6年生になり、外部模試の結果がなかなか思うように出ない時もあり、学習方法などに悩む時もありましたが、先生方にご相談をして的確なアドバイスをいただき、克服していくことができました。また、受験の直前期にスランプに陥った際にも親身にアドバイスしてくださり、勉強だけでなく精神的にもサポートしていただきました。
受験前半で志望度の高い学校が不合格になり、息子だけでなく親も不安になっていた際にも温かく力強いアドバイスをいただき、気持ちを切り替えて聖光学院の入試に臨むことができました。ここに通いたい! という思いを持って息子が受験した学校に合格できた時は、今まで関わってきてくれた方々に感謝の気持ちでいっぱいになりました。受験期間は、息子も悔しい思いをしたと思いますが、不安に押しつぶされることなく、自分で気持ちを切り替えて試験に臨む中で、人としてもとても成長できたと思っています。
3年半の受験生活では、グノーブルの先生方とその学習内容を信じて取り組むことで、息子に努力することの大切さと成功体験を味わってもらうことができ、とても良かったと感じています。また志を共にする生徒の皆さんと切磋琢磨することができたおかげで、とても楽しそうに通塾をしていました。一緒の目標に向かって頑張る仲間がいるという経験ができたことも、息子の人生の大切な一部になったと思っております。
先生方、グノーブルで関わってくださった皆様、本当にありがとうございました。これから受験に向かう皆様、頑張ってください。

合判はあくまでも一つの指標にすぎない
聖光学院中学校進学B君
自分は3年の11月にグノーブルに入りました。入った時から算数は比較的得意だったため、算数を伸ばしつつ、苦手な国語や理科を少しずつできるように努力しました。
2年間勉強して初めて受けた合判は20%。その後も20%〜40%をうろうろしていました。さらに最後の合判も20%でした。しかし、それでも合格することができました。もちろん合判の結果は大事ですが、本当に大事なものは入試です。ですので、合判はほどほどに気にしつつ、その先にある合格に向かって走り続けてください。
必ずみんなで2月の笑者になりましょう。
グノーブルを信じて
聖光学院中学校進学B君の保護者様
グノーブルには3年生の秋からお世話になりました。日々の復習やグノレブ前の勉強は大変ではありましたが、塾の授業には刺激もあり楽しそうに通っていました。
6年生になると思うように成績が伸びず、また反抗期も重なり、衝突することも多くなりました。その度にメールや電話で相談し、息子に直接話をしてくださりました。
特に受験直前期では、あくまでも難関校にチャレンジしたいという息子の意思を尊重したい一方、現実的な適正校を受けてほしいという気持ちから不安定な状態が親子ともに続きましたが、先生方の適切なアドバイスもあり、覚悟を決めて受験に挑むことができたと思います。
結果として、受験して良かったと晴れやかな表情で笑う息子の姿を見て、グノーブルに通わせて本当に良かったと思いました。心のこもったご指導ありがとうございました。
世田谷学園中学校
最後まであきらめない!
世田谷学園中学校進学A君
僕は新4年生の2月からグノーブルに入塾しました。元々他の大手塾への入塾を考えていましたが、「グノーブル」と聞いた時に、名前の響きが良いという単純な理由で通いたいと思ったのが入塾のきっかけでした。
実際に通ってみると、少人数で先生が一人一人のことをよく理解してくれているし、授業(特に文系科目)が面白かったので絶対に最後まで通うと決心しました。
そこで3年間通って思ったことをいくつか挙げます。
■4、5年の時に先生から指示されたことをしっかりやりましょう。僕は理系をやっていなかったので、6年生で同じことが繰り返し出てきた時に後悔しました。毎回しっかりこなせば、あとになってつらさがだいぶ減るはずです。文系はしっかりやっていたので楽でした。
■6年生は、どの時期でもまだ時間はあると思って諦めずに勉強に取り組みましょう。直前まで時間はあります。
■知識は最後まで伸びます。身につけた知識は裏切りません。
■国語は日頃から本を読み、社会はできれば楽しみながらコツコツとやりましょう。
最後に、常に僕を気にかけてくれた先生方への感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
紙ヒコーキからの
世田谷学園中学校進学A君の保護者様
中学受験。我が子とのバトルが繰り広げられるご家庭も多いかと思います。息子は理系科目が苦手だったため、算数の答えが合わなければ大騒ぎをする。理科が分からなくても質問に行けない。その繰り返しでした。
新6年生の授業がスタートする直前には、私に向かって紙ヒコーキが飛んできました。計算マスターの答えが合わないと言って騒ぎ出し、その紙で丁寧に折られた紙ヒコーキでした。我慢の限界だった私は、息子を連れてグノーブルへ向かいました。すると偶然ではありましたが算数科の先生がいらっしゃって、私の話を聞いてくださり、またその横で怯える息子に怒りもせず淡々と話をしてくださいました。そしてその翌週からは、算数の居残りを期間限定で先生の所で一緒にやることになりました。正直、集団塾でここまで面倒を見ていただけるとは思ってもいなかったことで、まずここでグノーブルという塾の面倒見の良さを実感しました。そしてこのことがきっかけとなり、私自身も理系の先生方とお話ししやすくなりました。
「知識は裏切りません」保護者会で先生がおっしゃった言葉です。
2月1日、「さぁ、行け!」と国語科の先生が書いてくださったファイルに息子は受験票を入れて試験会場へと向かいました。試験終了後、電車に乗って一度帰宅する間も無言。理由は得意の国語の試験中に気分が悪くなってしまったために、国語で少しでも点を取りたいのに出来たかどうかも分からないからということでした。そしてその日の夜、翌日に向けた準備をしながら合格発表のページを開くと「合格おめでとうございます」の文字が! この日の状況を考えると、そのあとの科目の理科の知識が裏切らなかったからだと、そう思いました。苦手な理科の日曜特訓の授業中、常に冗談を交えながら息子を当て続け、熱心に知識を叩き込んでいただけたおかげだと思いました。
最後の最後まで息子のことを見放さずに寄り添って指導してくださった先生方へ、心から感謝申し上げます。
中学受験という経験が、保護者の皆様にとって、また子供達にとって、これから先の人生の中でチャレンジして良かった、そう思える経験となりますことをお祈りしています。
筑波大学附属駒場中学校
結果はあとからついてくる
筑波大学附属駒場中学校進学A君
僕は4年生の春期講習からグノに通い始めました。勉強法や入試の心得を伝えたいと思います。
<各科目の勉強法について>
■算数:普段のテキストをこなす。
・自分の中で解説する、親に聞いてもらうなど、問題が自分に定着するようにする。
・日曜特訓のテキストを優先的にやる。
■国語:普段から読書をして過ごす。
・自分の感覚では書かず、文章に基づいて書く。
・漢字はていねいに(ていねいときれいは違う。自分のなかで最高の字を書くと良い)。
・グノの文章を読む。(今年の栄光でグノの授業で扱った文章が出題された。文章を知っているからといって有利になるわけではないが、知っている文章と出合うと、精神面でほっとできるかもしれない)
■理科:グノラーニングチェックをしっかりこなす。
・テキストや土曜特訓、日曜特訓はやり残さないようにしっかり復習する。
■社会:知識で落とさない。
・基礎力確認問題!をしっかりやる。
<筑駒に向けてのアドバイス>
■算数:時間配分を意識する。
・調べ上げる根性を持つ。
■国語:ハイスピード、かつ正確に。
・詩は一歩踏み込んで解釈する。
・漢字の書き取りは、送り仮名も含めてバランスを意識する。
■理科:物理はあとに回す。地学はほぼ同じ問題が繰り返し出題されることもあるので、過去問で対策する。
・物理に時間をかけるため、他はスピーディーに解く。
・化学は場合によっては時間がかかることもあるので、飛ばす勇気も持つ(本番でも最後の設問は飛ばした)。
■社会:本文を隅まで読み込む。
・年号は暗記して良いと思う。
・選択肢をしっかり判断する。
<受験直前期について>
・受験直前期でも、どの教科も伸びる。僕は直前期にやった算数で、筑駒やその他の学校の点数が格段に上がった。
・理社の過去問をやる。特に筑駒は、過去問をやることで問題に慣れることができる。てこや地学だけでも、遡ると良い。
・読書をする。読解の勘は、解かないとすぐに鈍ってしまう。僕は最後の特訓以来、過去問の文章を読んだり、最終日は残った過去問の詩を眺めたりした。
・諦めない。僕は入試直前にやった過去問でボロボロの点数を取ってしまった。しかし、その悔しさから必死に勉強した。そのおかげでかなり伸びたと思う。直前までやって諦めるのはすごくもったいないと思う。
<入試本番の心得>
・トイレの場所の確認をしっかりする。
・休み時間のトイレの待ち時間に、問題について話している人が必ずいる。不安にならないよう、時間をあけていくのも良いかもしれない。
・時間があったら、深呼吸や瞑想をすると、落ち着いて試験が受けられる。
・合否のことは気にしない。終わった試験のことは忘れる。
・採点者へのメッセージだと思って、答案の氏名はていねいに書く。
と、偉そうに言いましたが、実際には僕はすぐに調子に乗る、やる勉強に偏りがあるなど、癖のある勉強をしていました。夏休み明けのグノレブで成績が良く、調子に乗って次のグノレブテストで偏差値が12近く落ちたこともありました。それでも、自分の勉強には責任を持って、計画は自分で立てるようにしました。
これからグノで受験勉強をする人に、伝えたいことが3つあります。
・グノの先生を信じる
・両親を信じる
・自分を信じる
とにかくグノの先生はすごいので、信じて頼った方が良いです。そして、自分を支えてくれた両親、なにより自分を信じて全力をつくせば、結果はあとからついてくると思います。悔いの残らないよう、全力で、頑張ってください!
最後に、最後まで支えてくれたグノの先生方、本当にありがとうございました。
グノーブルだからこそ、のびのびと学べた3年間
筑波大学附属駒場中学校進学A君の保護者様
夫も私も地方出身で、右も左もわからないまま飛び込んだ中学受験の世界。「塾に行ってみたい」と息子が言い出したのが新4年生の3月で、そこから慌てて中学受験について調べ、塾探しを始めました。様々な塾の体験授業を受けた結果「圧倒的に楽しかった!」というグノーブルに通塾することに。
中学受験をする上で、我が家でいくつかルールを作りました。ここでは二つほど紹介いたします。
① 勉強は本人主体で:小さい頃から、好きなことを見つけると、それを自分なりに深掘りして楽しむタイプだったので、そのスタイルを崩さずに塾の勉強も楽しんで欲しいと思っていました。本人も親に干渉されずに進めたい、ということだったので、4年生から自分で計画して宿題を進める方法を採りました。
こう書くと立派に聞こえますが、4、5年の時は計画倒れの日もたくさんありました! 小学生ですから当然のことだと思います。ただ、グノーブルは5年生まで通塾日数が少ないので、帳尻合わせができるのがとても良かったです。
息子の主な勉強方法は、理解したことをアウトプットすること。例えば算数の問題。復習して理解すると、すぐに親に説明してくれました。4年生の頃までは理解でき、時には突っ込んだ質問もできたのですが、5年生からこちらの理解力が怪しくなり(難しくなり)、6年生になると分かったフリをしていることに気づいたのか、その辺にあるぬいぐるみや、やかんを生徒に見立てて説明していました。これは1月31日までやっていました。
好きなやり方で、自由にのびのびと勉強できて良かった反面、グノレブテストなどの結果にも本人が責任を持たないといけないので大変だったと思いますが、3年間のこの経験は今後も役立つと信じています。
といいつつ、何の迷いもなく息子なりの勉強を見守れていたわけではありません…。4年生の頃から、筑駒への強い強い憧れを持っていたのですが、果たして息子流の勉強法で筑駒を受験できるレベルに達するのか、定期的に不安になったものです。そのたびにグノの先生に相談し、背中を押していただきました。
② 中学受験を家族の良い思い出にすること:4年時の保護者会で紹介いただいた、朝比奈あすかさんの『翼の翼』は、大きな衝撃でした。中学受験は翼くんの親のような心境になっていく側面があると知り、これまで培ってきた親子関係を壊すことだけはしない!と決意。
もちろん3年間ずっと笑顔だった訳ではありませんが(反抗期VS更年期の戦いもありましたし、6年生の秋に私の小言が原因で家族喧嘩になったこともあります…)、塾の先生の面白い授業内容を教えてもらって大笑いしたり、家族で文化祭に出かけたり、息子が頑張る姿に夫婦で感動したりと、通塾前よりも家族仲が良くなったように思います。
夏期講習中や直前期には、昼ごはんを食べに行く、カラオケに行く、大好きなラジオを一緒に聴くなどの息抜きの予定を意識的に入れました。きっと中学生になったら遊んでくれなくなるのだろうなぁ、と想像すると、貴重でありがたい思い出ができました。大袈裟ではなく、②が達成できたことが一番嬉しかったです。
息子がグノーブルを選びましたが、最初の説明会で先生のお話が面白すぎて、私も一気にグノーブルファンに!その時は、理科の先生が生物の分類について説明してくださり、熱を帯びてきて「理科に関することだと、あと3時間くらい話せますが、どうしますか?」と仰っていたのですが、今思い出しても面白いです。
保護者会でも、毎回思わず吹き出してしまうことがあったので、いつも楽しみでした。最後の保護者会のあとは、もうグノーブルの先生のトークが聞けないのか、と寂しく思ったものです。
息子伝手にどのような授業をされているか聞いていましたが、本当に楽しそうで、グノーブルに巡り会えてラッキーだったなと思っています。惜しむらくは、親は授業を受けられないということでしょうか(グノーブルの先生に教わっていたら、高校で物理に苦戦しなかったのでは…)。それほどユニークで、「学ぶことはワクワクすることである」と教えてくださり、最後の最後まで熱心にご指導いただいた先生方には、感謝の気持ちでいっぱいです。
最後に、お互いに高め合い、励まし合ったグノのお友達にも心から感謝いたします。お友達の存在があったからこそ、息子も最後まで頑張ることができました。
グノーブルで培った「知の力」を糧に、これからそれぞれの未来で活躍することを、僭越ながら願っております。
これから受験を控えている親御さんへ
直前期、これからの戦いに備え、闘志に燃える息子が武士に見えてきて「そうか、私は中間(ちゅうげん)だ」と気づき、人知れず中間ごっこしていました(あれこれ心配し始めるとキリがないので、息子を信じて、楽しみながらサポートをしようと思ったからです)。
常に中腰で、息子が必要なプリントを必要なタイミングで手渡す、息子がご飯を必要としたタイミングで温かい料理を提供する、寝る前に布団をふかふかにする……等々、立派な中間役を果たせたと思っています。
受験が終わり、今は一週間ほど経過していますが、想像を超えた疲労感がドッと出ています。中間を頑張りすぎたのか、糸が切れた凧のようです。私も緊張状態が続いていたんだな、と気づきました。
受験を通して痛感しているのは、子が心身ともに健康でいるためには、親が元気でいなければいけないということです。反抗期を迎える年頃のお子さんのサポート、イライラすることもあると思いますが、どうかリラックスできる時間をしっかりと取って、ご自分を労わってください。

すばらしい友達・ライバルに恵まれた
筑波大学附属駒場中学校進学B君
僕は3年生の2月からグノーブルに通い始めました。A 君とはよく隣どうしの席になり、切磋琢磨しながら楽しく学んでいました。A 君は算数がとても得意で、グノレブでも算数はいつもA 君に勝てませんでした。その後、A 君は事情があってグノを去ってしまいましたが、次に会った時に「なんだ、算数、そんな問題で苦戦してるのか」と笑われないように、僕も算数の実力をもっと高めようと心に決めました。算数の難しい問題に挑戦している時、心の中でA 君を思い出すことがよくありました。6年生の夏休み明けに「A 君どうしているかな」と思って連絡を取ってみたら、志望校に向けて受験勉強を頑張っていると返事があり「お互い頑張ろう!」と励まし合いました。受験が終わって再会した時には、久しぶりにいろいろ話せてうれしかったです。
6年生のGW講習では、僕のコースはいろいろな校舎の生徒が渋谷校に集まりましたが、その中にB 君がいました。B 君のことは前から噂で何となく知っていましたが、会うのは初めてでした。休み時間に勇気を出して話しかけてみたら話しやすく、話していて楽しかったです。たった3日間でしたが一緒に学べて充実した時間でした。その後、志望校別の外部模試を受けに行ったら、たまたま隣の席がB 君で、同じ志望校を目指していると分かって励みになりました。年が明けて1月になり、最初に受けた学校の入試に無事受かって浮かれていたら、B 君のことを思い出しました。それで「浮かれている場合じゃない」と気を引き締めて、次の受験校の準備に励むことができました。受験が終わってからB 君にも偶然再会できたのですが、その時は感謝を伝えそびれてしまったので、次に会う時に伝えるつもりです。
そのほかにも、6年生のGW講習で初めて会い、9月からの日曜特訓でほぼ毎回隣の席(成績順)で切磋琢磨してきたC 君。授業のあと校舎の最寄り駅まで一緒に帰ったD 君、E 君。いつも授業を盛り上げてくれた天性のムードメーカーF 君。同じクラスで共に受験勉強を頑張ってきた戦友の面々。一人一人、ここには書き切れないほどたくさんの思い出があります。すばらしい友達・ライバルに恵まれたおかげで、自分は受験勉強を乗り切れたと思っています。先生も良い先生ばかりで、友達や先生に会えるのが楽しみでグノーブルに通っていました。3年間どうもありがとうございました。
グノーブルとご縁をいただけて良かった
筑波大学附属駒場中学校進学B君の保護者様
子どもが6年生になり過去問に着手しはじめた頃、グノーブルに関して改めて理解したことがありました。それは、あくまでも子どもの「地力」を高めることに主眼を置き、既存のテクニックなどで手っ取り早く点数を取ることを良しとしない方針であること。
そんなに「地力」重視で大丈夫なのだろうか、志望校対策として薄いのでは、と不安を覚えたことも正直ありました。ただ、受験を終えて振り返ってみると「グノーブルとご縁をいただけて良かった」と思うことばかりです。
まず、先生方が優しく穏やかな雰囲気の方ばかりで、それが子どもの性格に合っていたこと。これは3年生の塾選びの際に入塾の決め手になった点でもあります。本人がグノーブルの穏やかな環境で、必要以上のストレスを感じることなくのびのびと受験勉強を続けられたことに感謝しています。
また数多ある中学受験塾のなかで、あえてグノーブルを選んだ他のお子さんたちとは通じ合うものがあるようで、仲の良いお友達もたくさんでき、大きなトラブルもなく3年間楽しく過ごせたことは、本人にとって良い思い出になっているようです。
そして何より、普段のご指導や教材の数々から暗に発せられる「自分の頭で考えることから逃げるな」という強烈なメッセージ。先生方も一見するとドライで、先回りしてお節介を焼いてくださるようなことは全くと言って良いほどありません(生徒の性格や状況によって対応を変えていらっしゃるのかもしれませんが、我が家の場合はそうでした)。至れり尽くせりとはある意味真逆で、本人や保護者が他力本願の姿勢でいたりすると痛い目に遭います。
それでも、どの先生もこちらから何かご相談すれば、お忙しいなかでも真摯に対応してくださいました。そして、正解をポンと教えるというより、子どもが自力で答えを見出すための手助けを惜しまないというスタンスでした。先生方は個性豊かでありながらそういった部分の指導方針に一貫性があり、授業中の子どもの様子もよく見てくださっていて、保護者として全幅の信頼を寄せておりました。
そのような環境のグノーブルで学び続けた我が子は「自分の頭で考えるのは当たり前」と考えられる逞しいグノっ子に育ちました。
彼の集大成とも言えるのが志望校対策(試験時間の使い方)の戦略です。時間配分、後回しにすべき問題の判断基準、見直しを行なうタイミングなど、それぞれの学校・科目ごとに戦略を立てる必要がありますが、過去問に取り組み始めた当初はそんなことは考えもせず、丸腰で突っ込んでいって打ちのめされたりしていました。しかし、ある時誰に言われるでもなく自分で戦略を考え始め、試行錯誤しながら修正を加えていき、世界に一つのオリジナルの戦略でそれぞれの入試へ立ち向かっていきました。
もともと勉強に関しては受け身な子で、言われたことしかやらないようなところがありましたが、特に最後の1年間でずいぶん成長したと思います。反抗期(自己主張の強まり)も彼の場合はプラスに働いた気がします。
ちなみに6年生の途中までは「グノレブテストや外部模試で良い成績を取っても先生はぜんぜん褒めてくれない」とこぼすこともありましたが、ある時期からは言わなくなりました。「テストで良い成績を取るより大切なことがある」という先生方の想いに本人も気づいたのではないかと思います。
また、4、5年生のうちから、弱点克服などの課題解決のためにどうすれば良いかを親子で一緒に考え、試行錯誤してみることもありました。そのように自力で最適解を探っていく経験を家庭で重ねたことも、結果的に子どもの成長につながった気がします。
体質的に毎日10時間ほどの睡眠時間が必要だったり、6年生の秋までスポーツ系の習い事を続けていたりした関係で時間の管理は大変でしたが、総じて充実した受験生活を送れたと思います。お世話になったグノーブルの先生方、スタッフの皆様に深く感謝しております。

自分の力を出し切れるように
筑波大学附属駒場中学校C君
僕は教科ごとにやる内容を決め、勉強しました。
■算数は平面図形や数の性質など幅広い分野から出題されるため、グノーブルのテストだけでなく、基礎力テストなども欠かさずやりました。
■国語は通常授業での記述の解き直しや、知識のラーニングチェック、日曜特訓で配られる語彙力強化プリントなど、知識をしっかりと覚えられるように頑張りました。
■理科ではテキスト、グノラーニングチェック、グノベーシックだけでなく、てこなどの力学や電気など筑駒でよく出てくる問題を重点的にやりました。
■社会は歴史上の出来事一つ一つの年号の暗記や、『有名中入試問題集』をやったりすることで知識を定着させ、筑駒の対策として正誤問題をやったりしました。
入試本番では気をつけなければならないことがあります。それは「緊張しすぎない」、「周りの人を気にしない」、「終わった教科のことをずっと引きずらない」、「忘れものをしない」などです。入試本番でも緊張しすぎず今までやってきたことを思い出し「自信」を持って自分の力を出しきれるよう頑張ってください。祈 合格
最後まで勉強を楽しんでいました
筑波大学附属駒場中学校C君の保護者様
最後の1か月、まるで突如として覚醒したかのように急成長し、大逆転での合格をつかみ取りました。
息子がグノーブルに入塾したのは新5年生から。入塾テストには1回落ちてしまい、リベンジして入塾しました。5年生の間は、1年生から続けていたサッカーに週2〜4回通っていたので、グノーブルの復習もままならない状況でした。当時は、まずは通塾しているだけで良い、という認識だったのですが、算数の復習テストが40点だった時には、さすがに算数科の先生が心配してお電話をくださいました。
6年生からサッカーはお休みし、グノーブル一本に絞りました。得意の理数は成績が伸びてきましたが、国語は相変わらず低迷しており、夏休み中の『有名中入試問題集』の添削をはじめ、過去問の添削も非常に丁寧にグノーブルの先生方がみてくださいました。
6年生の秋になりグノーブルの模試では偏差値が安定してきましたが、第一志望の開成にはまだ手が届くレベルにはなく、他塾の模試、特に学校別模試はボロボロで、合格可能性40%以上を取ったことはありませんでした。12月下旬のグノーブル筑駒模試では時間が全く足らず、まさかの最下位(偏差値 32.5)でした。しかし、本人は決して諦めませんでした。自分の出来ることをやる、という息子の姿勢をみて、親も100%応援しようと決めました。
日曜特訓や正月特訓では、授業内で開成対策の問題を扱い、授業点も上がってきたと聞いていましたが、12月の終わりにあったグノーブルの学校別診断模試でも成績は芳しくなかったため、不安な気持ちと闘いながら2月1日を目指して毎日出来る限りのことを続けていました。そんな日々に転機が訪れました。渋幕の合格です。渋幕に合格をいただいてからの1週間は、本人も(親も)少し自信をつけたようで、猛勉強しました。この1週間で学力は確実に伸びたと実感しています。最後の2日間(1月30日、1月31日)は、息子に全力を尽くしたいと思い、仕事を休んで一緒に勉強しました。今まで勉強をみてあげることはほとんどありませんでした。といっても、この2日間でサポートしたことは、丸つけや知識の確認のために問題を出すことくらいです。ただ、問題を出すとほとんど全て答えられる状態になっており、かなり仕上がってきているな、という印象を持ったことは事実です。もう一つ印象的だったのは、最後の最後まで勉強を楽しんでいたということです。いつも、歌を歌ったりして、前向きな気持ちでグノーブルのプリントに取り組んでいました。「勉強を楽しめる」それだけでも大きな収穫だったな、と感じています。
この中学受験を通して、小学6年生の持つ力は絶大だということを痛感しました。最後まで子供を信じることは、親にとっては試練になるかもしれません。しかし、中学受験を通じて子供に寄り添い、成長を近くで感じることができれば、どんな結果であっても親にとっては大切な思い出になるのではないでしょうか。

模試の結果には左右されない
筑波大学附属駒場中学校進学D君
僕は2年間グノーブルに通っていました。6年生の8月までは思う存分、6年生の12月までは細々とサッカーをしていました。6年生の8月まではときどきグノーブルを休んでいましたが、休んだ分のテキストは、空いた時間や、グノーブルやサッカーに行く時間などにきちんとこなしました。動画授業も倍速で見ながら活用しました。
受験を通して大切にした方が良いと思うことを3つまとめました。
🔳休憩もしっかりと取る。睡眠もしっかりと取る:勉強をすることも大切ですが、睡眠や休憩を取らなければ、ストレスや疲れがたまり、勉強に支障をきたしてしまいます。僕の場合は、8時間睡眠、1時間勉強して15分休憩をしていました。休憩とは言っておきながら、入試が近づいてくると、資料集や歴史マンガを読んでいました。
先ほど述べたのは僕の場合なので、自分にとって最適な睡眠時間、勉強と休憩のサイクルを見つけることが大切だと思います。
🔳模試の結果に左右されない:模試の結果で落ち込んだり、油断したりしすぎてはいけません。しかも模試は、塾の先生が作った問題であるため、あまり気にしない方が良い時もあります。理由としては、自分は常に開成の合格判定はA判定で、筑駒の合格判定はB・C・D判定であったのに、開成には落ち、筑駒には受かったからです。
しかし、模試で出題された問題が入試本番に出ないとも限らないため、見直しはしっかりした方が良いです。
また、僕の場合は、開成が受験する学校の中で初めての入試だったので非常に緊張して、隣の人の鉛筆の音が気になってしまい、ペースをなかなか戻せませんでした。志望校を決める時には、そのあたりも考えた方が良いかもしれません。
🔳各教科の勉強法
●算数:計算問題を落とさない。基礎をきちんとこなし、それを応用する。グノーブルの「筑駒の算数」を解く。
●国語:授業やテキストにある漢字・知識をしっかりやる。授業をしっかり聞く。過去問を提出するときは、ノートに要旨などをしっかりまとめる。
●理科:理科資料集を2~3回読む(自分の苦手は範囲は4~5回読む)。日曜特訓の昼テストを2~3回解く。「基礎力テスト」は毎日取り組む。
●社会:歴史資料集、重大ニュース、「統計データ」を2~3回読む
*大前提として、宿題は全部やる。
目先の成績ではなく、その先まで考えて並走してくださった
筑波大学附属駒場中学校進学D君の保護者様
グノーブルには新5年生から2年間お世話になりました。2年間をいくつかの点から振り返らせていただければと思います。
🔳グノーブルを選んだ理由:グノーブルは5年生の段階であっても平日2回のみの通塾で、勉強以外の活動と両立しやすいカリキュラムでした。受けられなかった授業に関しては動画の配信があるため、その動画を見たり、先生に質問したりしながら宿題を進めていました。
また理系・文系科目でクラスが分かれているため、文系科目が苦手な息子にとっては、段階を踏んで勉強をすることが出来たように思います。
🔳受験がゴールではない指導:すべての教科について同じことが言えると思うのですが、グノーブルでは、小手先のテクニックではない勉強を教えていただいたように思います。
算数についても、公式を知っていれば簡単に解ける問題や型にはめれば速く解ける問題もあるかと思いますが、じっくり考える、手を動かすと言う姿勢を鍛えていただきました。
国語についても、授業だけでなく、過去問も丁寧に添削していただいて、真っ赤になって返ってくるノートを通じて、問題文とじっくり向き合う姿勢を鍛えていただきました(このノートは入試日にも欠かさず目を通しており、お守りのような存在でした)。また、国語に関しては、課題文の選択が素晴らしいため、息子が読書好きに成長したことも嬉しい誤算でした。結果が出てくるのが少し遅くなる方法かもしれませんが、一生モノの武器を手に入れることが出来たのではないかと思っております。
🔳粘り強く頑張る姿を信じる:息子は、6年生に上がるころから筑駒を第一志望にしておりましたが、親としては、この成績で志望して良いものか躊躇していました。それでも、先生方は6年生の春の段階から「大丈夫。問題ありません。学校別は開成を受けて、ほかの生徒さんたちと切磋琢磨しましょう」とアドバイスをしてくださいました。また過去問の点数、模試の結果が思うように伸びない時も「まだ11月、12月ですよ? 受験は2月ですから大丈夫です」と親よりも息子のことを信じてくださっていました。
あまりにも、親よりも息子を一貫して信じてくださるので「どうして大丈夫だと思うのでしょうか?」と伺ったところ「彼の場合は、なんでも簡単に出来てしまうわけではないけれど、粘り強く頑張る姿勢があるから最後まで伸びるんです」と言っていただきました。目先の成績ではなく、その先まで考えて並走してくださった先生方には感謝しかありません。
東京都市大学付属中学校
最後まで諦めない
東京都市大学付属中学校進学A君
僕は新4年生からグノーブルに入塾しました。3年間を振り返ると、4、5年生の頃は、他の習い事や家庭学習との両立が割と出来ていたと思います。6年生になると、復習や宿題の量に追いつかず、模試の結果も悪かったため、思い通りに行かない焦りと不安ばかりを感じて過ごす時期もありました。ただ、僕には「この学校で部活と勉強の二刀流をやりたい」という目標がありました。合格を勝ち取ることができたのは、最後まで諦めずに食らいついていけたからだと思います。
🔳苦手科目であった国語について:僕は4年生から6年生の最後まで国語が苦手でした。特に知識については、みんなが解けている問題を自分だけが解けなかったことに直面して、初めて真剣に取り組むようになりました。漢字や知識は、嫌い・苦手であってもコツコツ取り組むことをオススメします。
🔳過去問について:僕は過去問を始める時期が遅く、1月中盤以降も解いていました。点数も悪く、1回も合格者最低点を超えることができなかったのですが、過去問を9月からスタートして、1月は苦手分野を完璧に押さえるというように計画的に行っていれば、もう少し気楽に受験本番の日を迎えることができたと思います。
🔳質問について:僕は最初の頃、親や小学校の先生のように毎日話すような間柄ではなかった塾の先生に質問するのが苦手でした。しかし、1度質問をすれば苦手な気持ちなど吹っ飛ぶので、質問が苦手な生徒は、最初の1歩の質問を早めにするのが良いと思います。解けない問題に独りで悩んでいても時間が過ぎるばかりです。質問すればグノーブルの先生が必ず助けてくれます。
🔳最後に:授業中、先生の冗談が面白かったです。3年間、楽しい授業をありがとうございました。
グノーブルでの3年間を振り返って
東京都市大学付属中学校進学A君の保護者様
息子が3年生の冬に、①5年生まで週2日授業、②上位クラスも下位クラスも同じ先生に見ていただける、③理系・文系でクラスが違う、④駅から近い、⑤室長先生のお話しに惹かれた、⑥入室テストの結果だけでなく体験授業での息子の様子もよく見て入塾許可してくださった、等々の理由から、グノーブルへの入塾を決めました。
グノーブルは大変素晴らしい塾ですが、息子には難しすぎるのではないか、と感じることもありました。特に、国語は高難易度の長文読解についていけず、解答欄がほぼ真っ白で帰ってくる日々が続き、レベルが高すぎる授業に出る意味はあるのだろうかと思うこともありました。それでも、土曜特訓や日曜特訓が始まると、自分と周りの子との点数差に直面し、遅まきながら「問題をしっかり読んで点を取ろう」という意識が芽生えたようでした。平日の授業にも徐々に積極的になり、家庭でも自分で復習をするようになりました。国語の先生と「50点を取る」という目標を立て、6年生の冬期講習の頃には、苦手な気持ちを乗り越えて前向きに取り組めるようになりました。
算数や理科は、入塾当初から◎と○の問題をきちんと押さえることを意識して学習を進めました。算数は、長期休みに「G脳ワークアウト」や基本の制覇に取り組んだことが苦手単元の克服につながったと思います。夏期講習の合間(自主トレ期間)には、計画的にこれらの問題集に取り組むことをお勧めします。理科は、受験直前期に、基礎固めのためにグノラーニングチェックをやり直しました。また、冬期講習以降に配られた分野別のまとめプリントがとても役に立ちました。
社会は息子の大好きな科目で、やる気がない日はまず社会から勉強していたこともあり、毎回の復習テストでもしっかり得点できたことで、最後まで得点源でいられました。
過去問について、グノーブルからは、6年生の9月以降に計画的に過去問をやるように指示がありました。しかし、我が家の場合、秋以降も息子に緊張感がなく、家庭では座っているだけのだらだらした時間を過ごしたせいで、過去問への取り組み開始が遅くなりました。第一志望は何が何でもやるしかないのですが、併願校の選定にあたり、過去問との相性を考える余裕がなかったのは反省点です。結果として、見学して候補にした学校の中から、主に模試の結果のみで併願校を決めることになりました。また、1月後半に、模試で安全校だった学校の過去問に初めて取り組み、思いのほか得点できなかったときには、詰んだ…と思いました。過去問は、少しずつでも計画的に進めるべきだったと痛感しました。
最後に。受験後に気づいたことですが、進学先の中学校から読書の宿題が出て、初めて息子が文庫本を読んだところ、思いのほかすらすらと読み終わり、内容も理解していたので驚きました。算数の宿題でも、図形問題に「グノーブルで習った」というアプローチを試していました。また、日々の会話でも社会や理科に関連する話題が増え、グノーブルの授業を通じて、受験の先につながる学習の基礎が培われていたことを改めて感じる日々です。息子の成長に全力を注いでくださったグノーブルの先生方には心から感謝しています。この先も、グノーブルがその良さを活かして益々発展し、グノーブルで学ぶ皆さまが納得のいく受験ができることを心より祈っています。

努力は報われる
東京都市大学付属中学校進学B君
僕は3年生の最後に体験授業を受け、その授業がとても楽しかったので入塾しました。
サッカーも遊びもしたかったため、勉強時間をたくさん取れず、また学年が上がるにつれ授業日数が増え、難易度も上がって、なかなかスムーズに勉強を進められませんでした。そのためグノレブテストでも苦手教科の国語は偏差値30くらいの最悪な点数を取っていました。
6年生の夏までサッカーをしていたのですが、6年生の初めに怪我をして、怪我が治るまでの1カ月半、勉強に専念することができ、少しずつ平均点に近づいていきました。まさに「怪我の功名」です。怪我をしたころから、読書をするようになりました。読書をするようになると、物語文の読み方やおもしろさが分かるようになりました。家族で同じ本を読むと、感想を交換することができ、さらに内容を理解できるようになります。
夏期講習で通塾の頻度が上がり、たくさん勉強をするようになると、忙しくはなりますがその努力はそのあとにつながります。そして努力をした甲斐があって、国語の偏差値が30近く上がり、最後のグノレブテストでは初めてαコースになりました。先生が熱心に指導してくださることもあり、その成果でもあると思っています。
次に僕が入試前にやって良かったことを書きます。
🔳暗記物をやり直す
・算数:モンモール数、正多面体の一面の形の確認
・国語:「漢字道場」、テキストで昔やった文章をもう一度読む、知識の総確認
・理科:土曜特訓の直前期確認プリントの見直し、グノラーニングチェックの確認
・社会:統計、時事資料の確認、土曜特訓の「知識の総確認」
🔳苦手分野の問題を解く
🔳体力が落ちないようにランニングする などです。
塾に通っていた3年間、塾に行きたくないと思ったことは一度もないくらい、先生たちの授業は楽しかったです。Gnobleに通えて良かったと思います。本当にありがとうございました。
桐朋中学校
いつやるか? 今でしょ!〜受験からの学び〜
桐朋中学校進学A君
僕は3年間のグノ生活の間に、αからα4のコースを行きつ戻りつしています。僕はとにかく面倒くさがり、かつ、家でじっと座って勉強するのが苦手でした。そのため、4年生からのテキストの中には、手付かずのプリントがかなり残っており、今このプリント類を処分するにあたり、とても後ろめたさを感じます。そんな僕のこの1年のグノライフを振り返ってみます。
6年生になり土曜特訓が始まると、これまで以上に努力しなければと思っていました。しかし、心地良い我が家では思うようにはかどりません。ライフワークにしたいほど好きな社会と、居残りの時間をできるだけ短くしたいので算数を、そして『漢字道場』1周の3セットをやるだけでタイムアウトです。理科は先生の顔を思い浮かべ心苦しく思いながら、宿題は見て見ぬふりでした。
夏期講習が始まると、連日の宿題にプラスして社会の有名中の過去問が課され、息も絶え絶えでした。夏期講習明けのグノレブテストでは当然のことながら成績を落としてしまいました。
9月からは日曜特訓が始まりました。僕は記述問題の多い学校を志望していたため、全教科、通常のテキスト以外に、その学校に相応した特別な教材が配られました。今までのテキストすらこなせなかったのに日曜特訓の教材が増えたことで、僕の家にはまだ解けていないプリントがどんどん山のように増えていきました。家に帰って、リュックからテキストを取り出すたびに、今回こそはしっかりやらないと!とその場では決意しますが、結果は無念、改善できないまま、受験まで100日を切りました。先生方から、もう取り返しがつかなくなっていくなどと発破を掛けられても、とにかく算数の次回のテスト範囲、社会の確認テストの範囲のところぐらいしか行えなかったため、その影響はあろうことか冬期講習になって表れ始めました。国語の過去問は自分の思う解答を書いてもあまり点数にならず、理科の問題では先生が簡単という問題さえも間違えてしまうようなありさまでした。この状態はパニックという以外の表現が見つかりません。この期に及んで、今から何をすれば良いのやらわかりませんでした。
そんな気持ちのまま迎えた1月校でしたので、特待で合格できたことは、かなり嬉しく、自信となり、自分の気持ちを立て直すことができました。しかし、1月の受験からやや間延びした感のある2月本番。今思うと、緊張感を保つために、この間にもう1校受けておきたかったと思いました。2月の入試でなんとか合格しなければ、僕は、1月に合格した長野か、父のいるサンパウロに送られてしまう運命だったかもしれません。
2月3日の入試を終えて帰宅し、1日に受けた学校の不合格をパソコンで確認して、絶望のままに2日の桐朋の“合格おめでとうございます。”の明るい色の画面を見た時は、飛び上がるほど嬉しかったです。4月からの中学校生活を全力で楽しみたいと思います。
生まれて初めての受験で、僕は、やれるときにやっておかなければ、後々後悔することを学びました。やり残した宿題をこの先やろうと思っても、次の授業でまた新しい宿題が山ほどやってくるので、やり残したものはずっとやり残したままになる可能性が大です。是非とも宿題はその週にきっちりやり遂げましょう。華々しい合格体験記の中、僕は勇気を持ってここに実体験をしたためました。思い立ったが吉日です。皆さんが少しでも良い結果を迎えられるよう願っています。祈合格!!
我が家はグノーブル卒業
桐朋中学校進学A君の保護者様
3歳上の姉と入れ替わりで弟が入塾し、我が家はグノーブルに6年間お世話になりました。息子は宿題をしていても、いつの間にか本棚の前で寝転がって本を読んでおり、声をかけては机に戻らせるといった調子でしたので、土曜特訓や日曜特訓の長時間をどうやって耐えているのか不思議に思っていました。一度、日曜特訓の授業が始まる直前の教室に忘れ物を届けに行った時のこと、しーんと静まりかえった緊張がみなぎる空気、先生方が作り上げたこの環境こそが、子供達の集中力の源であると合点がいきました。
息子は算数の先生の愛の鞭に心折れそうになっていることがたびたびあり、このまま見守っていて良いものか迷う場面も実際ありましたが、入試直前の頃に漸く、解けるようになってきたことが実感でき、解いていて楽しいと思えるようになったと言いました(もう少し早くその言葉が聞きたかった!)。
入塾してすぐに社会の授業の虜となり、特に歴史は大好きになりました。受験勉強中に漫画は不適切かと思いつつ、起爆剤になるのではと「疾風の勇人」(全7巻)を渡したところすっかり嵌り、更には図書館で「白洲次郎 占領を背負った男」という本を見つけて、夜な夜な読んでいました。中学での歴史の授業を今から楽しみにしています。
さて、算数に苦手意識があるにもかかわらず、1日午後は果敢に算数選抜を受験しました。初日の午前午後共にチャレンジングな入試で疲れ果て、当日夜に出た午後入試の合否は確認せず早めに休み、2日の桐朋に挑みました。結果的にはそれが良かったのかもしれません。
4年生の秋に初めて桐朋を訪れ、通学路の風景、ゆとりある校庭・校舎の佇まい、穏やかな印象の先生や生徒の方々、素敵な学校だと思いました。のびのびと中学校生活を謳歌する息子の姿を思い描いています。
グノーブルの先生方には、姉弟共に良い環境に導いて下さり、心より感謝しております。我が家はグノーブル卒業です。本当にありがとうございました。

効果があった勉強方法について
桐朋中学校進学B君
我ながらすごく頑張った、そう思っている自分にとって効果があった勉強方法を書きます。
🔳全体
●よく寝る。無理しない。
●過去問など、時間を計るもの以外の勉強は1回25分。5分ボケーっとしてまた25分、というサイクルを続けたら、いつの間にかすごい量を演習できるようになった。
●母親が仕事している横で勉強したら、お互い緊張感が出て良かった。
🔳国語
●漢字:100問の「漢字道場」を20分で解き切ることを目標にした。だいたい25分くらいかかるし、出来も30%くらいだけど、3回目くらいで20分を切って95%を超えるようになるからうれしい。間違えた漢字は辞書で調べて、ノートで覚えるまで練習し、先生に見てもらうのを繰り返した。
●記述:先生に何度でも書いて出す書いて出す…を繰り返すしかないと思う。授業中も、過去問の直しも出しまくった。気になる小説家を見つけて読みまくっていると、人が書いた文章を理解しやすくなる。
🔳算数
●計算:ミスをなくす。計算を始める前に、問題の式を計算スペースに正しく写す。間違える原因はだいたい読み間違いだった。お店に行ったときに金額計算を必ずするなどして、計算の感覚を身につける。
●図形:基本的なルールを深く理解して、あとはひらめき。何回もやれば身につく。自分がどう解いたのかを説明できるように書いておくと、あとで見直せるから良い。
●教材:「基礎力テスト」を毎日。
・確認テストと基本の再確認をグノレブテストの前に完璧にする。
・だいたい読み間違えているので、見直しをしっかりする。
・確認テストと基本の再確認の間違えた問題と、過去問の○△マークで間違えた問題を親が切ってまとめてくれていたので、冬期講習のあとはひたすらこれをやった。
🔳社会
●歴史:「日本の歴史」を読んで、ちょくちょく現地にいく。現地の人としゃべると小話を聞けて、それで覚えやすくなる。漢字はどう覚えたら良いかわからなかった。難しい。
●地理:旅して歩いてみる。地図を見ながら歩いていたら、地形がわかる。
●公民・時事:ネット動画などで討論番組を見まくった。国際政治チャンネルも、海外のことをよく知ることができて面白い。
🔳理科
●化学実験の動画や、NHKアプリで生物とかを見る。
●化学も物理も家でできる実験が割とあるので、実際に少しやってみる。
●生物は、図鑑をよく読んで、博物館や植物園に行って本物を観察する。
●地学は、三崎口とか野島崎とか、触れられる露頭に行って楽しむ。褶曲って本物はでかい!
実際の細かい部分は自分なりにアレンジすればいいです!
必要に応じてサポートし、温かく見守る
桐朋中学校進学B君の保護者様
わが家の中学受験は、自由な雰囲気の息子本人がとてもよく頑張り抜いた日々でした。彼は成績に波があり、科目にかかわらず好きな分野には集中して取り組める反面、苦手分野になると一気に落ち込むことも。特に4、5年生の間は国語が苦手で、グノレブの記述回答欄がまるまる白紙で返ってきて、私たちが驚いたことさえありました。しかし、6年生の終盤では国語が武器になるまで成長しました。なぜそうなったのか、その経緯をお伝えしたいと思います。
息子がスイッチを入れた大きなきっかけは、ネット上で桐朋の動画を見つけて気に入ったことでした。自宅から1時間以上かかるので、「遠いからいずれ諦めるだろう」と思い、5年生の夏に説明会に連れて行ったところ、まったく逆効果で、すっかりその学校にほれ込んでしまったのです。説明会後に息子は「俺、ここに通うわ~」と宣言し、本人の中で受験を決心したようでした。当時の偏差値は30台前半で、親としては「さすがに厳しいかも」と思っていましたが、息子の熱意を尊重して「まずは基礎力テストから始めよう」とサポートを続けることにしました。
6年生になると「漢字道場」が始まり、1回100問を20分で解くという学習に取り組むことで集中力が高まり、文字を書くことにやっと慣れて国語力全般が底上げされました。記述への抵抗がなくなり、字をきれいに書くことやスピードが上がったことは他教科にも好影響をもたらしたと思います。6年生になる頃には偏差値が40前後、夏以降は50前後、他塾模試でも調子が良い教科は60以上がちらほら見えるようになっていきました。さらに学校別の日曜特訓で、周りのお友達とのやりとりが刺激になって、いっそう成績が伸びたのだと思います。私たち家族にとっても、驚きと喜びの連続でした。
また、保護者会で「5年生のうちに13~15校は学校見学に行ってください」と先生からアドバイスをいただいたことも大きかったです。実際に数多くの学校を見て回ることで、私たち親も「こういう特色のある学校が息子に合いそう」と具体的なイメージを持つようになりました。土日の見学には息子自身も連れて行ったため、本人にとって「ここに通うんだ」という主体性を持つきっかけにもなったと思います。机上だけではわからない校風や雰囲気を肌で感じられたことが、受験校を選ぶうえでも非常に参考になりました。
実際、受験した学校はどこも「素敵な学校!」と自信を持って言えたので、試験の結果が残念だったとしても「ほかにも素敵な学校がある」と気持ちを切り替え、落ち込みすぎずに次の試験へ臨むことができたのだと思います。その甲斐もあってか、2月2日の桐朋入試は落ち着いて受けることができ、息子自身も「面白い問題が出た!」と、日曜特訓の友達と肩を組んで笑顔で校舎から出てきたのが印象的でした。
塾での学習では、先生方にたいへん可愛がっていただきました。とりわけ印象的だったのは、6年生の夏休み以降にスタートした過去問の提出です。過去問に対する先生方のコメントを、わが家では“ラブレター”と呼んでいました。息子がその一言一言が励みに、毎回張り切って取り組んでいたのを覚えています。
自宅学習で大切だったのは、モチベーションのキープです。ネガティブな言葉をかけないことと、集中する時間を区切ること、そして健康的で活動的に過ごすことを心がけていました。ポモドーロ・テクニックを取り入れ、息子が集中している25分間は、親も自分の仕事に集中して声をかけないようにしました。また、「よく食べて、よく寝る」を徹底し、休みの日には教材や受験候補校に関係する内容があればできるだけ現地に足を運んで“本物”を見せるようにしていました。これは、息子の興味やモチベーションを引き出すうえでも大きかったと思います。
私たち両親は共働きで、6年生になるまではなかなか伴走できずに悩むことも多かったのですが、受験が近づくにつれて我々も在宅勤務をメインにして家族全員で協力し合い、“親子の結束”を強く感じられるようになりました。長かったようであっという間だった受験期の日々は、わが家にとって一生忘れられない思い出です。
今後は新たな学びや出会いを楽しみながら、息子にはさらに成長していってほしいと思っています。受験を通じて痛感したのは、「子どもの力を信じ、必要に応じてサポートし、頑張りを温かく見守ること」の大切さです。苦手があっても、最後まで諦めずコツコツ続けていけば必ず成長につながるのだということを、息子が身をもって教えてくれました。今、受験生をお持ちの方には、子どもと同じ目線で一緒に取り組む姿勢や、家族が同じ方向を向いて支え合う大切さを、ぜひお伝えしたいと思います。
武蔵中学校
基本知識をおろそかにしないようにしよう
武蔵中学校進学A君
僕は新4年生の2月にグノーブルに入塾しました。4年生と5年生の前半では社会や理科の勉強をあまりしていなかったので、6年生からは復習テストやグノレブテストなどでなかなか点数が取れませんでした。そんな僕が危機感を抱いたのは、日曜特訓が始まってからでした。同じ学校を目指すライバルとの差を痛感し、社会の年号や理科の苦手な分野をがんばりました。
皆さんは僕のように社会や理科の基礎知識で失点しないようにがんばってください。皆さんの合格を楽しみにしています。
グノーブルを信じて頑張ってください!
武蔵中学校進学A君の保護者様
「俺、行きたい学校ができたから中学受験したい!」まだ3年生だった息子の発言から我が家の中学受験が始まりました。行きたい学校は武蔵中学。その理由はヤギがいるから。地方育ちの私は武蔵の名前すら知らず、「ヤギがいるなんて、都内から通える学校なの?」と驚きながら検索しました。そこで初めて御三家の存在を知り、さらに武蔵が自宅からそれほど遠くないことに驚き、すぐに説明会を予約しました。
説明会では武蔵の教育方針や学校の設備、雰囲気に感動しました。息子もヤギだけでなく、図書館や校内を流れる川に魅力を感じたようでした。それまで中学受験を考えたことはありませんでしたが「ぜひ武蔵で楽しい中高生活を送ってほしい」と思い、受験を応援することに決めました。
そこから塾探しを始め、いくつかの塾の説明会や体験授業を経て、息子が最も気に入ったグノーブルに入塾を決めました。新4年生の授業が始まり、最初は理系・文系ともにαコースで幸先の良いスタートでした。しかしそれも束の間、息子の成績は徐々に下降。これまで勉強習慣がなかった彼に加え、塾のシステムに不慣れな親。毎回配られるプリントの整理にも苦戦し、試行錯誤を繰り返すうちに5年生になりました。
5年生になっても成績は安定せず、家庭教師や個別指導を受ける友人の話に焦ることもありましたが「グノーブルを信じ、先生の指示を忠実にこなそう」と決めました。息子はもともと読書が好きで、国語の課題のおかげもあり、国語は得意でした。しかし算数と理科はなかなか伸びませんでした。
そんな中、息子が突然グノーブルの授業動画を熱心に見るようになりました。食事中やおやつの時間、ソファーでくつろぐときも動画を視聴。そのおかげで算数の成績が上がり、本人も「勉強が楽しくなってきた」と言うようになりました。とはいえ、成績の乱高下は6年生の最後まで続きました。
日曜特訓が始まって1カ月ほど経ったある夜、息子が突然泣き出しました。「特訓の子たちはめちゃくちゃ賢くて、こんな人たちと同じ学校に受かるわけがない。難関コースに変えてほしい」と言うのです。何とか落ち着かせて寝かせた翌朝「やっぱり武蔵に行きたい」と気持ちを立て直していました。不安になりグノーブルに相談しましたが「このまま見守ってください」という先生の言葉を信じることにしました。
日曜特訓は大変でしたが、時々先生に褒められると嬉しそうな表情を見せていました。正月特訓では特に鍛えられたようで「俺は正月特訓で覚醒した!」と自信をつけていました。
1月の入試は埼玉の1校のみ。息子は「共学だし遠いしなぁ」とあまり気乗りしないまま受験。結果は1点足りず不合格。すぐにグノーブルに電話すると「彼の場合、ここで合格すると調子に乗るので、かえって良かったかもしれません」との言葉。慌てて再度出願し、何とか合格しましたが、加点ありのギリギリ合格。親は不安を覚えましたが、今振り返ると、この経験が息子にとって良い影響を与えたと思います。
2月の本番。武蔵の試験では落ち着いて臨んだはずが、試験後の息子は青ざめていました。なんと、試験中に「お土産問題」の封筒下部の糊を剥がそうと奮闘し、時間をロスしてしまったのです。他の教科も自信がないと落ち込む息子。午後校の試験開始の早い回は見送り、遅い回で受験することにしました。試験までの時間、本屋で以前から読みたがっていた作家の本を買い、喫茶店でクリームソーダを飲みながら読んで気持ちを落ち着かせました。
23時、午後校の合格発表。息子には翌日と伝えて寝かせましたが、結果はまさかの合格。全落ち覚悟だったため、思わず涙が出ました。翌朝、グノーブルの先生の助言どおり息子に伝えると、すっかり自信を取り戻し、2日の試験後には「今日はよくできた!」と笑顔。親も合格を確信しました。
そして迎えた3日の武蔵の合格発表。息子は発表を見ずに小学校へ向かったため、親が代わりに確認しました。クリックした瞬間に見えたピンク色の画面! 念のため受験番号一覧も確認しましたが、やはり息子の番号がありました。入学金をすぐに振り込み、帰宅した息子に伝えると、飛び上がって喜びました。「こんなに嬉しい瞬間が人生にあるなんて」と、心から思いました。
受験中、何度も迷いました。武蔵を目指して良いのか、家庭教師や他塾の力を借りるべきか。しかし、グノーブルと先生を信じて本当に良かった。3年間通えて、心から感謝しています。
これから受験を迎える皆様、先生に何でも相談することをお勧めします。周りの状況が気になることもあるでしょうが、お子さんのことを一番理解しているのは、日々指導してくださるグノーブルの先生方です。どうかグノーブルを信じてください!
皆様が最高の春を迎えられることを心からお祈りしています。

武蔵中学校に合格した方法
武蔵中学校進学B君
僕は10月に日曜特訓武蔵コースから難関中コースにうつった。その後、武蔵とは別の学校の過去問を進めていったが、1月校に受かったので武蔵を受けることにした。2月1日は親が別の学校の出願をしていたが、僕は武蔵に行きたかったので、自分のお年玉で出願することにした。1月下旬から約10年分の武蔵中学校の過去問を進めていった。
僕が、武蔵中学校に合格した方法は、次のとおりである。
■算数
・毎日基礎力テストを怠らなかったこと。先生曰くαコースの人達でも基礎力テストを怠ると入試に落ちたりするそうだ。
・過去問は、武蔵中学校の先生の講評を読みこみ、武蔵の先生が解答に何を求めているのかを確認した。
・入試問題は、最低でも式を書く。それに、少し説明をつけ加える。
・式を書く前に問題で何を問われているかを見直す。また、式一行ごとに(一つごとに)検算をする。文字を読めるようにていねいに書くことで見間違いをなくす。
・夏期講習は内容が一番難しい。また、正月特訓は夏期講習の何倍も大切で、夏期講習でできた差もうめられてしまうため、正月特訓をがんばること。ただし、正月特訓でのびるのはそれまでがんばってきた人だけである。なので、努力を怠らないこと。
・復習を怠らなかったこと。
・最低でも取らなければならない問題を確実に取った(その他の科目が算数を補う場合を除く)。
■国語
・漢字を完ぺきにしたこと。
・問題を先に読み、そのあとで文章を読んだこと。この方法だと問われていることがわかるので必要な所に気付きやすい。
・文章の重要な所に線を引きながら読んだ。とくに逆接の後ろには重要なことが書かれているので逆三角(▽)をつけ、そのあとに線を引いた。
・記号問題は消去法を使った。正しいものにまる(○)、不完全なものには三角(△)、違うものにはばつ(×)をつけた。また、記号を要素ごとに線で分け、比べた。
・自分の書いた文章は間違っていると思いながら読み直した。
・漢字や知識など、努力で何とかなることは完ぺきにしておくこと。
■社会
・武蔵中学校の先生の過去問解説を使い、解答に求められていることを読みこんだ。
・問題を先に読んでから文章を読む。資料や絵などは、ヒントなので読むのは当たり前。また、文章にもヒントが書いてあるので見つけられるようにする。
・複数の問題(大抵2問)で一つのくくり((a)のようなもの)となっている時は誘導で、前問がヒントになっていることが多いので気をつけること。
・最近の武蔵中学校の問題は時事問題が多いので、対策を怠らないこと。また、出る問題は歴史か地理が多く、公民は珍しい。
・量を多く書くのではなく、必要な要素をていねいに詳しく書くこと。
■理科
・武蔵中学校の先生の過去問解説を使い、解答に求められていることを読みこんだ。
・基礎知識の習得を怠らないために、基礎力テストをやりこんだ。
・自分の書いた文章は間違っていると思いながら読み直した。
・問題を先に読んだ。
・複数の問題(大抵2問)で一つのくくり((a)のようなもの)となっている時は誘導で、前問がヒントになっていることが多い。
・問題に線を引いたりするなど、書きこめばできる。
■重要
・他の科目を補える偏差値60以上の科目を一つ以上つくる。
・最後まで努力を続ければ、合格できる。
大逆転の武蔵合格
武蔵中学校進学B君の保護者様
◆落ちた入塾テスト:入塾テスト(3年夏期実力テスト)は算数偏差値30程で落ちた。最初から御三家を目指していたわけではないので、学校以外の計算ドリルを本屋で買って初めてやり、やっと入塾資格を得られたが算数は一番下のクラスだった。グノーブルでついていけるか心配だった。息子がグノーブルが良いというので頑張ることにした。保護者は6年までに20回は転塾を考えました。しかし、息子はグノーブルの友達も先生も授業も大好きで転塾せず頑張りました。
最後まで家庭と子供の意志を尊重し、支えてくださった先生方がいらっしゃらなければ、絶対に得られない結果だったので、つらい時も多々あると思いますが、先生とカリキュラム、そして、子供の伸びる力を最後まで信じて頑張ってください。
◆諦めた武蔵:理系の成績はずっと真ん中あたりをウロウロ。文系は、国語は得意だったが5年生秋からくすぶっていた(時間配分の失敗で終わらない)。地理が苦手で、新6年生の実力テストでは、社会も偏差値30台をたたき出した。本人は気にせず、グノーブルを楽しんでいた。できることを全力でやっているとは言っていたが、家でもぼんやり。夏休みすら気合いは感じられなかった(武蔵を諦めた際に、夏にもっと頑張れば良かったと悔いていたが、時間は戻せないので、次のチャンスに頑張れと伝えていた)。成績はぼんやり度に連動し、日曜特訓武蔵コースで最下位の席次になった。10月には先生とも相談し、息子も納得の上、志望校を変更。難関コースへ移った。今思うと、それが功を奏した。武蔵の問題の雰囲気(ゴール)が分かった上で、難関コースで基礎の穴(特に算数)を埋めることができた。基礎がない上に家は建たない。難関コースのテキストの問題をきちんと身につけたら、それと酷似した問題が併願校の入試に出たということが何度かあった(合格)。
◆武蔵再び。そして、大逆転の6年生直前期:2月1日は別の学校への出願を決めていた。しかし、12月、「1月に目標とする学校に受かったら、武蔵を受験したい」と息子が言い出した。大事な2月1日。迷った。結局「貴方のお金で武蔵へ出願する覚悟なら貴方の人生だから応援する」と伝え、息子は自分のお年玉で武蔵の出願をした(後日親が補填した)。そこから息子は本気になった(自腹だし)。保護者は従来予定していた学校へも出願をした。
1月、文系は念願のαコースの1番の席に座ることもできた(12月最後のグノレブでは、社会は1年前の約2倍の偏差値60を突破。得意の国語はそれ以上の成績になっていた)。最後まで苦しんだ算数は、1月になり一皮むけたように思う。今まではろくに考えず「できない」と投げ出していたのが、1月に合格したら、2月1日は武蔵を受けられると思ったら頑張れるようになり、取れる問題は取り切るような勝負師の顔が見えるようになった。結果、苦しんだ一因のケアレスミス、計算ミスが減った(面倒くさがってしなかった検算をするようになる)。
1月に目標校に合格出来たので、武蔵受験が決まった。1月下旬、わずか数日で武蔵の過去問を解くことになった。あれほど、楽しそうに真剣に勉強をしている姿を初めて見た。苦しんだ算数も、入試3日前にはやっと勝負できるレベルに達してきたように感じた。いつも真摯に対応してくださった先生方には感謝しかなかった。
◆入試当日:4月の他塾模試では、体調不良になってしまうほどの緊張しいだった息子。グノレブテストでも先生に緊張していると言われたが「入試当日に初めて緊張するよりも、緊張する自分で戦う練習が積めるからラッキーだね」と練習をずっと重ねてきた。当日は、多少緊張したようだが、合格できるという自信を持っていたようで、2月3日の発表を楽しみにしていた。
◆各科目の勉強方法◆
【算数】学習時間の8割は算数だったが苦しんだ(図形だけはずっと得意だった)。算数を他3科目でなんとか補填できる形にはなっていたが、併願校含め、最後に合格をあと押ししたのは苦労した算数の伸びだったように思う。ギリギリまで伸びる。苦手ほど伸びしろだと思い、諦めないでほしい。
◆5年までは計算がとにかく大事(計算マスターをもっとやれば良かった)。
◆授業でやった問題だけは完ぺきにする。→皆が取れて当たり前の問題を間違えずに取れるようにする。
◆平面図形マスターを繰り返す。
【国語】読書が非常に好きなので、国語はいくらやっても苦にならないようだった。この科目がなければ合格は不可能だった。
◆読解の解説は、読み込む。
◆必ず、通常授業の記述は提出(直前期は出せなかった)。理解できないことは理解できるまで先生に質問。
◆漢字は満点を目指し、毎日練習。
◆知識のプリントを覚えきるまでやる(授業後1回のみ)。
【理科】算数がドボンしても、引っ張り上げてくれた理系の守護神。生き物が好きで、毎日の外遊びで採集や飼育もよくしていた。博物館、川遊び、キャンプなどが好きでよく連れて行き、図鑑が好きすぎて勉強の支障になるほどだったため、元々知っていることもあったが興味の度合により知識に偏りがあった。先生の話はいつも面白く印象に残ったようだ。
◆テキストは指示された所のみをやった。
◆苦手な化学と物理計算は、テキスト(basic)で固めた。
【社会】偏差値30台から1年で60台まで上がった。年間40泊以上は地図帳を持って旅をした。京都には2週間弱、町家に住み、明日香村では銅鐸などを作ったこともあるが全く覚えず、地理が一番苦手だった。苦手でも嫌いにならなかったのは、各地に良い思い出があるからかもしれない(旅行しすぎは反省)。図鑑や資料集、時事本や新聞も大好きで、暇さえあれば読んでいた。むしろ、読みすぎて困った。テキスト外の先生の話が入試に出たこともあったようだ。
◆苦手(地理)をつぶす。「知識の総確認」と5年生のときの白地図をやった。
◆興味を持ちそうなものは買って本棚においておく。
◆テキストがスパイラルになっているので、指示があったところをしっかり漢字で書けるまで練習。
御三家男子校なんて、生涯ご縁がなさそうだから見ておこうかと行ってみた武蔵の記念祭。武蔵の川や自然、校舎、雰囲気、武蔵の全てを息子は大好きになり、その日から武蔵の虜になりました。グノーブルの先生に(この成績で恥ずかしいと思いつつ)伝えたら「大丈夫です。入りましょう」と言ってくださいました。息子はその言葉に大喜び。「頑張って武蔵に入る!」その言葉と裏腹に、マイペースに好きなことばかりする息子にやきもきすることも多い受験生活でした。出願すらしない予定だった憧れの武蔵の生徒に息子がなれるとは思ってもみませんでした。
先生方には感謝しかございません。本当にありがとうございました。
迷ったときは、先生方にもよくご相談のメールやお電話もさせていただきました。先生方のご指示で、合格に向けた正しい道を選ぶことができました。グノーブルの授業、友達、先生方のことを息子は心から大好きで、帰ってくると先生のお話も沢山してくれました。グノーブルはほぼ皆勤賞でした。挫折も多かった中学受験ですが、大好きという気持ちがあるからこそ、どんなときも息子らしくポジティブにくじけず頑張ってこられました。今もグノーブルの授業を懐かしみ、グノーブルに通う下の子を羨ましがっています。
伴走をされている保護者の皆様も、不安になるときはたくさんあると思いますが、ご自身の心身を優先なさってください。暗くとらえても、明るくとらえても成績も合否も変わりません。最後に保護者ができることは子供が後悔なく力を発揮できるように祈ることだけでした。子供は、最後まで伸び続けます。今苦しい状況でも、グノーブルと先生方を信じて、諦めないでください。

時間はないものという自覚が大切
武蔵中学校進学C君
僕は新4年生からグノーブルに通塾し、入試の結果は三勝三敗でした。不合格はつらいですが、僕の経験を皆さんの受験に生かしてほしいと思います。
■全体を通して僕がやって良かったこと
・学校は自分の目で見て決める(僕は武蔵の文化祭に行って武蔵を志望しました)
・先生から提案される勉強方法には素直に従う
・朝学習は毎日やる(僕は算数と理科の「基礎力テスト」と、国語の漢字・語彙に取り組んでいました)
・前受けをたくさん受験する(第一志望校の前に三校受けて、どのように準備すると良いかを実感しました)
・勉強で、やって後悔したことはなかったので、とにかく挑戦してほしいです
■各教科でやって良かったこと
【国語】
・漢字は、毎回のテストで90点以上取れるように勉強する
・語彙や漢字で間違えたものは、ドアなどに貼って、気づいたときに確認できるようにする
・授業中の記述は、真剣に取り組んで高い点数を取るようにする
【算数】
・授業動画で学習する
・「基礎力テスト」を毎日欠かさずやる
・「G脳ワークアウト」もやっていれば、解くスピードが上がったと思う
・テキストを最優先にする
【理科】
・グノラーニングチェックを完璧にする
・6年生になっても◎まではやる
【社会】
・テストの最後に漢字ミスがないか見直す
・社会は勉強量が大事(僕は勉強量が少なく、社会の点数があまり良くなかったです)
僕の場合、自分はこのままでは合格できないと思い、本気になったのは第一志望校の入試2週間前でした。それまで、まだまだ時間があると思っていたことが間違いでした。6年生の10月から本気になれば良かったと思いました。時間はもうあまりないと自覚してください。そして、受験の時は前の科目の出来がどうであれ、しっかりと取り組んでください。
おすすめすることと、やらなくて良かったこと
武蔵中学校進学C君の保護者様
まず最初に、息子が楽しく受験生活を過ごせたことに、グノーブルの先生、そして子供の友人に感謝申し上げます。息子は新4年生から入塾しました。我が家の場合、4年生の頃は毎日の算数の「基礎力テスト」さえもせず、テキストはほぼ白紙で捨てる状況でしたが、ちょうど新5年生に切り替わる頃、突如息子が第一志望校を決め、それとともに中学受験らしい受験勉強が始まりました。
親の立場から、中学受験生活でおすすめすること、やらなくて良かったと思うことを以下でお伝えできればと思います。
■おすすめすること
・悩んだ時は先生に相談すること:第一志望校を決めた新5年生に進級する際、家庭学習内容に不安が生じた際、子供と衝突した際など、平均すると月一回は先生にお電話で相談させていただきました。先生は子供の成績だけでなく性格も理解してくださっており、どういった学習が良いかなどを適宜具体的にアドバイスしてくださいます。独断で考えず先生に相談したからこそ、適切な勉強内容をすることができたと実感しているため、ぜひ先生に相談することをおすすめします。
・子供に志望校を決めさせること:併願校含め、親が行かせても良い学校を予め選定したうえで、学校説明会や文化祭に連れて行き、子供に受験するかを決めさせました。我々の場合、あとあと慌てずに済むように、併願校の偏差値は第一志望より20以上離れている学校も検討し、5年生のうちに決めました。
・朝学習の習慣化すること:朝学習は新5年生から習慣化できました。もちろん全てできない日もありましたが、あまり気にしすぎないことで習慣化できたと思います。
・前受けをたくさん受験すること:第一志望校の前に三校受けたことで、子供自身が受験への向き合い方を形成できた気がします。前日に早く寝ること、前の科目を気にしないことなど、大人はわかっていても子供は実感しないとなかなかできません。我が家の場合、三校受けることでようやく子供が実感して受験に臨む姿勢を身につけられたと感じます。
■やらなくて良かったと思うこと
・親が教えること:4年生までは日々の学習は目を瞑っていましたが、グノレブテストのやり直しだけは親が介入しました(5年生以降は介入せず、自分で自己採点とやり直しをしていました)。新5年生以降は丸付けはしても、親が教えることはせず、動画や塾で確認していました。結果として子供が勉強で頼ってくることがなく、良かったと思います。
・全てのテキストをやること:テキストを全てやっていたら、受験勉強が続かなかったと思います。先生に優先度を確認しながら勉強内容を取捨選択したことで、無理なく勉強を進められたと思います。
・緻密に計画を立てること:日々の勉強では、どの教科をどの程度するかはだいたい決めても、例えば30分で何をするなど、細かい部分は決めませんでした。また、過去問も、結局一度も一気に一年分を解くことはなく、時間のあるときに一つずつでも進めました。管理するほど親の余力もなかったことが第一の理由ですが、ある程度自由度があったため、子供が主体的に取り組めたり、親も神経質になりすぎなかったりと効果的だったと思います。
何よりも良かったことは、先生に相談したことと、切磋琢磨しあえる友人がいたことです。先生にいただいたご助言をもとに勉強を進めることで、確実に成績は上がりました。また、友人のおかげで、最初から最後まで楽しく通塾できたと思います。本当にありがとうございました。
早稲田大学高等学院中学部
努力は報われる
早稲田大学高等学院中学部進学A君
僕は小学校2年生の最後にグノーブルに入りました。入塾時から5年生までは週1回で、遊びと並行しながら勉強していました。6年生になってからは勉強をしなければいけないのにもかかわらず、勉強をさぼっていました。何とか第一志望に受かることができましたが、今思うとまずかったのではないかと思うので、先生の指示をよく聞いて6年生(特に後半)になったら勉強を毎日最低2時間以上はしましょう。
ここで早稲田大学高等学院中学部の試験でどうすれば良かったかを書きます。
🔳国語:点数が100点満点で漢字・知識の問題は簡単なので落とさないようにしましょう。問題数が多いわけでもなく、50分もあるので落ち着いて取り組みましょう。
🔳算数:例年難しい問題が出題され、今年は特に難しかった印象なので、過去問で点数が悪くても気にしないでください。ですが、大問1は基礎的な問題が多いのである程度時間を使ってでもしっかり取れるようにしましょう。
🔳社会:今年は例年と比較して簡単でしたが、来年どのような問題が出るかわかりません。普段のテキストでしっかりと記述力を身に付けてください。
🔳理科:理科は難しい問題があまり出題されませんが、僕は理科が苦手なので基礎的な問題をしっかりと取れるようにしました。理科が得意な人はこの科目で頑張ってください。
🔳面接:予想外な質問をされることもありますが、心身を整えておけば大丈夫です。気負わずにリラックスして臨みましょう。
受験勉強は大変ですが、しっかりと努力すればいつか報われます。グノーブルを信じて頑張ってください。
紆余曲折の末、乗り越えた受験
早稲田大学高等学院中学部進学A君の保護者様
息子は5年生前期頃まで成績が安定していましたが、家庭学習に真剣に取り組むタイプではありませんでした。大好きなサッカーを思い切りできる時間が減り、ストレスが溜まっている様子も見受けられました。5年生の10月には目に見えて成績が下がったため、思い切って半年くらい塾通いをお休みしたらどうかと息子に提案したほどでしたが、結局グノーブルの先生に相談し、引き続き通うことになりました。
6年生になると更に通塾日が増え、模試等で土日もサッカーができなくなり、家庭学習もますます回らなくなっていきました。親としては、短時間で集中して勉強を終わらせ、自由時間を確保するようにと声かけをするのですが、性格の違いか一向に行動は変わらず、自由行動優先で家庭学習教材が溜まっていきました。
グノーブルの先生に相談したところ、塾では真面目に取り組んでいるのであまり家庭では追い込まなくて良いと言われたので、本人のペースに任せて見守るようにしました。
本番直前の1月最終週になり、親が作った模試の間違い直しノートにようやく取り組み始め、ほとんど間違えなくなっていることを発見して成長を実感することができました。
結局受験の前日までマイペースは続きましたが、合格をいただくことができました。
思い返してみると、苦しいながらも毎朝続けた「基礎力テスト」と、休むことなく通塾を続けたことで実力をつけることができたのだと思います。
グノーブルの先生は息子を子供扱いせず、個性を尊重してくれますし、保護者に対しても親身に寄り添ってくれる方ばかりでした。
伴走は予想以上に大変ですが、子供を信じて頑張ってください。

明るい人は受かる!
早稲田大学高等学院中学部進学B君
僕は4年生からグノーブルに入りました。入りたての頃は、先生方が優しく対応してくれたのでやる気を出して頑張っていました。5年生では、得意科目の算数をさらに伸ばそうと思い頑張って復習をしました。6年生では、外部模試で泣きたくなるような成績を取り、グノーブルの実力テストの国語で体温のような偏差値を取ってしまい、早高院に合格できるのかと不安になることもありました。
しかし、算数の先生に「明るい人は受かる」と言われ、とにかく明るく前向きに復習をしました。1月の後半は、国語が少しでも足を引っ張らないように猛特訓をしました。でも、貴重な睡眠時間はしっかり8時間以上はとるように心がけました。
本番当日は、悪いことは思い出さず、合格することだけ考えて試験に臨み、合格することができました。皆さんも、直前に低い偏差値を取ってしまうことがあっても、とにかく明るく頑張ってください。
早稲田中学校
楽しかったグノーブル
早稲田中学校進学A君
僕は4月から早稲田中学に進学します。2月11日に制服採寸をして、それを実感しました。早稲田中学の魅力は、大学付属でありながら進学校としての特徴も持っていることです。しかし、2か月前まではこのようになることを全く想像していませんでした。その時期にスランプになって成績が落ちてしまい、志望校を変更したからです。志望校の全見直しは父から提案され、ちょっと複雑な気持ちがありました。でも、早稲田大学を卒業した親戚が何人かいたので、頑張ろうと思いました。早稲田中学の問題は過去問含めて僕には解きやすく、2月3日入試の早稲田中学に合格しました。埼玉や九州の学校も受け、全て合格できました。出題されたのは、今までグノーブルの平日テキストで習った問題ばかりでした。
グノーブルはとても楽しかったです。志望校別特訓では他の校舎のいろいろな生徒と友達になることができました。またグノーブルのテキストは解いていて楽しかったです。模試は算数の成績が良く、他の塾で何度も1位になったり、算数オリンピックでも銅賞を取ったりしてうれしかったです。苦手な社会は、先生が何度も記述添削してくれて得意になりました。1年生の時からグノーブルに通っていて、本当に良かったです。
二月の勝者とは?
早稲田中学校進学A君の保護者様
グノーブルで、我が子は素晴らしい仲間、先生に出会えました。グノーブルは、全ての生徒にそのような体験を提供する場だと思いました。入塾のきっかけは、新2年生1月の説明会での算数の先生のプレゼンです。こんな先生がいるならきっと素敵な塾だろうと感じ、2年生の新学期から通塾しました。グノーブルのテキストは、難易度、思考力、全てを網羅する素晴らしい教材でしたが、6年生の夏以降、我が子は全部をこなすのは不可能となり、スランプに突入しました。そのため、先生に問題の優先順位をオーダーメイドに選択していただき、スランプを乗り切りました。
受験直前半年間のスランプは、苦しい時期でした。6年生になり、難易度的に確実と思えた第一志望の対策を開始してから成績が急降下し、6年生の11月、12月の直前の他塾模試では総合偏差値50未満となり、受験校全てを見直しました。その結果、受験した三つの学校全てに合格しました。
つらい時期を支えていただいた先生方、いつも楽しい雰囲気を作ってくれた”塾友君”達に感謝でいっぱいです。最終的に一番好きな学校に進学でき、元の明るい息子に戻って、悔いの無い受験生活だったと思います。音読の重要性を何度も強調していただいた国語の先生、苦手な記述を個人指導していただいた社会の先生のお陰で、苦手な文系科目を克服できました。
そして、1年生の、本当に小さい時から息子を陰日向から支えてくれたグノーブルの多くの先生、紛失したテキスト対応など多種多様なサポートをしていただいたグノーブル職員の皆様、本当に有難うございました。
先日、制服の採寸のために進学先の学校を親子で訪れました。私の膝の上に座って勉強していた息子が、学生服の試着をしている姿を見て、本当に多くの方が息子の成長に参与していただいたと思い、目頭が熱くなりました。
桜蔭中学校
グノーブルでの経験
桜蔭中学校進学Aさん
私はグノーブルで教わり、無事に桜蔭中学校に合格することが出来ました。ここでは、私が受験に向けた生活の中で大切だと感じたことについて書きます。
・授業の時はきちんと集中して勉強するようにし、行きたくないと思う時でも行くようにしていました。
・「基礎力テスト」をしっかり行えば、算数の問題で計算ミスをすることがとても少なくなり、正答率が上がりました。
・志望校別の日曜特訓や、12月、1月の正月特訓、冬期講習では志望校への対策をしっかり行うことが出来たため、自信がつきました。また、演習をたくさん行うことで本番の形式に慣れ、落ち着いて試験に臨むことができました。
・私は算数が苦手でしたが、本番では問題との相性もあるし、年によって受験者の平均点が低くなるような難しい問題もあるため、気にせずに最後まで問題を解き切ってください‼
グノの先生を信じて、行きたい学校への熱意を忘れなければ、きっと道は開けます。皆さんが志望校に合格できるよう祈っています。頑張ってください‼
素晴らしいカリキュラム、的確なアドバイス、本当に頼りになりました
桜蔭中学校進学Aさんの保護者様
🔳入塾から5年生まで:グノーブルに入塾したきっかけは、先生方の各教科への「愛と熱意」でした。入塾説明会で授業の進め方などをお話ししてくださった際の、先生方のキラキラしたまなざしが印象的で、「この塾なら楽しく学べる」と確信しました。読書が大好きな娘にとって、国語の授業で毎回新しい文章に出会えることも、通塾当初の楽しみの一つだったようです。
5年生までは他の習い事を優先しながら通塾できたことも利点でした。6年生になれば通塾時間が増え、自然と勉強時間も確保されると考え、それまでは授業に集中して取り組んでくれればよいという思いで見守っていました。授業中はかなりの集中力を発揮している様子だったため、できる限り授業には出席させるようにしました。
🔳6年生前半から冬休みまで:6年生の前半は、総勉強時間が増えたことで成績も安定してきたかのように思えました。ところが、後半の外部模試が始まると思ったようには成績が伸びませんでした。9月から日曜特訓が始まり、過去問も解き始め、学校行事も多く、毎日へとへとになっている娘を見ていたら、これ以上の負荷をかけることは忍びなく、私は黙って過去問の丸付けをし、粛々と出願準備を進めました。
あっという間に迎えた冬休みは、冬期講習と正月特訓のおかげで家庭内が静かでした。娘も元日だけはゆったりと過ごし、早朝の人の少ない時間帯に初詣に行き、合格祈願をしていました。
🔳1月受験から受験直前まで:親の言うことには耳を貸さず、先生方の言葉も自分の意に沿わなければスルーする娘は、苦手科目の勉強を後回しにし、間違い直しもしない日々を送っていました。そのため、娘にとって1月受験の結果は良い経験になったと思います。それでも、1月中に「通いたい」と思える学校から合格をいただけたのは幸運でした。おかげで、2月の入試には攻めの姿勢で挑む決意を固めることができました。そして、過去の合格体験記で何度も語られているように、冬期講習から入試に向けて、受験生としてみるみる仕上がっていく様子は親の目から見ても驚きでした。
私自身も「最後に悔いを残してはいけない」と思い、受験直前に「合格者の声」や過去の保護者会レジュメを見直しました。その中で、夏休み明けの保護者会レジュメにあった「解き直しをしない生徒の結果は芳しくない」という言葉が強く心に刺さりました。そこで、最後の数日間は時間の許す限り娘と一緒に苦手分野に的を絞って間違い直しをし、周辺知識の確認に取り組みました。
🔳自身の反省点とグノーブルで良かったこと:娘は自学自習ができる子だと思い、自主性に任せていましたが、やはり間違えた問題の解き直しは苦しかったようです。「もっと早くから伴走していれば成績も安定していたのでは」という後悔もあります。ただ、万年反抗期の娘にとって、勉強に口を出されることを受け入れられるのは、本番直前の焦燥感に駆られたタイミングが最適だったのかもしれません。
勉強についてはグノーブルにお任せし、私が3年間ずっと口うるさく言い続けてきたのは、早寝早起きなどの生活習慣でした。3年言い続けても改善せず、試験当日の朝も娘とひと悶着ありましたが、そんな朝のやり取りも「いつも通り」だったからこそ、力を発揮できたのだと思います。
4年生から続くスパイラル学習、日曜特訓、冬期講習、正月特訓といったグノーブルの素晴らしいカリキュラム、そして生徒の様子をよく見て的確なアドバイスをくださる先生方の存在は、本当に頼りになりました。1月の「まさか」のときも、先生方の支えがあったからこそ、笑い飛ばすことができました。
最後になりますが、子どもたちの合格のために全力を尽くしてくださった先生方、受付の皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。この場を借りて、心より御礼申し上げます。

努力を忘れずに
桜蔭中学校進学Bさん
私は2年生の夏からグノーブルに通っていました。グノでは毎回の授業がとてもおもしろく、切磋琢磨できる友人もでき、とても楽しかったです。そして、グノのおかげで桜蔭中学校を含む3校に合格をいただきました。4年半の間支えてくださった先生方に感謝しています。本当にありがとうございました。
ここからは、私が行ってきた勉強法を紹介します。参考になればうれしいです。
🔳算数:計算は間違えないように気を付けました。また、「基礎力テスト」を毎日やるようにしました。「基礎力テスト」のやり忘れが多かった時には、必ずテストでのミスが多く成績が落ちたので、「基礎力テスト」はやるほうが良いと思います。
🔳国語:桜蔭の国語は記述がほとんどです。だから、組み立てをしたり、本文中に線や矢印を引きました。そうすることで、本文の読み間違いなどのミスを減らし、問いに対して正しく答えられるようにしました。また、解答用紙に空白がないようにしました。
🔳社会:私は特に地理や公民が苦手でした。覚えられない単語は、一問一答式の問題集などを使い覚えました。授業中に間違えたところや初めて知ったことがあれば、ノートにメモをして、直前期などに見返すと良いと思います。
🔳理科:苦手な単元のグノラーニングチェックをやることが一番大切だと思います。特に6年生の1月には、夏期講習で配られたいくつかのグノラーニングチェックをまとめたホチキス止めされているものをやることで苦手な単元をあぶりだしました。
6年生になってからの1年間は長いようで短く、短いようで長かったです。はじめのほうは毎回のテストで一喜一憂していましたが、最後の方になると、順位をつけられることが増え、1回のテストで一喜一憂しないようになりました。あまり1回のテストで一喜一憂しないほうがいいです。悪かったら、どこが取れた問題で、どうして間違えたのかを考え、次に生かしましょう。
🔳入試当日について:時計はストップウォッチのようにして使うこともできるので、二つ持って行ったほうが良いと思います。また、私はすべての教科のノートを持っていき、それに加え、算数は「基礎力テスト」、国語は漢字、社会は時事問題と歴史の年表、理科は「基礎力テスト」と、先ほどの夏期講習のグノラーニングチェックの答えを持っていきました。緊張したら、笑えることを思い出したりすると良いでしょう。また、前の教科がダメだと思っても、次の教科でそれを挽回する気持ちで集中して取り組みましょう。
最後に、努力した分は必ず結果につながります。そのため、努力を忘れず、一生懸命頑張ってください。
笑顔で健康にすごせるように心掛けました
桜蔭中学校進学Bさんの保護者様
受験を終えて、まずGnobleの先生方、スタッフの皆様に心よりお礼を申し上げます。親ができることは限られていますが、少しでも参考になることがあればと思い合格体験記を記させていただきます。
まずタスク管理について。5年生までは、毎回の授業の復習テストとGnoRevテストを照準にタスクを決め、スケジュール設定をしていました。タスクの設定は必ず娘主導で進めるよう促し、親は決めたタスクを行うためのサポートとフィードバックの役割でした。曜日毎にタスクを割り振り、やり残しや間違い直しに取り組むための予備日を設定するよう心掛けました。
6年生になると、土曜特訓、過去問、日曜特訓、模試等々、課題は非常に多く、複雑になります。1週間毎にタスク割り振りの習慣をつけておいたことで、都度内容を見直しながら順応していくことができました。
次に志望校選びについて。娘の希望、成績、通学時間、試験日程等である程度絞り込み、候補となりうる学校の説明会にはなるべく参加しました。その中で良いなと思ったところは、娘と一緒に説明会や文化祭等で実際に訪れるようにしました。第一志望以外にも、ここならいきたいと思える学校をいくつか考えておくことが安心につながりました。
あとは食事や生活リズムに気をつけ、なるべく笑顔で健康にすごせるよう心掛けました。
娘はGnobleが大好きで、いつも通塾日を楽しみにしていました。卒塾した今も「もう一度塾にいきたい」と言っているほどです。それには、先生方の個性と熱意溢れる授業、切磋琢磨しあった友人たちの存在があったからだと思います。本当にありがとうございました。

終わりよければ全て良し
桜蔭中学校進学Cさん
わたしは6年生になったとたんに反抗期になり、自宅で勉強をすることが少なくなっていきました。5年生までの積み重ねがあったため、何とか授業についていくことができていましたが、やはり成績は下がっていきました。
家で勉強をしないわたしにとっては、毎回の小テストが本番のようでした。だからこそ本番に慣れることができ、本番に力を出し切きることができたのが合格につながったと思います。
偏差値はただの数字なので、勉強をしっかりしつつも本番に強くなる訓練をして、合格を勝ち取ってください!!
受験は十人十色
桜蔭中学校進学Cさんの保護者様
我が家は新6年生になった3月、家庭内で色々とあり、受験生生活を続けるかどうかというところからはじまりました。
娘が続けたいということだったので受験を続行したのですが、同時に反抗期に入り、たまに休みながらも何とか通塾だけはしている状況が続きました。夏期講習も何とか塾に行くだけの生活で、5年生までのアドバンテージもどんどんなくなり、危機感があるのかないのかもわからず、11月には志望校の変更も必要かもしれないと思いました。しかし、グノーブルの先生方には「今は力を出せていないだけ、出せる時が来るので本人を信じましょう」と言っていただき、当初からの目標で突き進むこととなりました。
結局、本人が本気になったのは、埼玉受験が始まる1月上旬。第一志望以外の受験校は受験直前に問題形式をさらう程度でしか過去問に取り組まず、各受験日は当たって砕けるくらいテンション高めに笑いながら行きました。結果、受験したところはすべて合格をいただきました。
家庭学習の「こうしたほうが良い」がほぼ出来なかった一年でしたが、娘の場合は家でストレスを発散し、塾の授業は集中していたようです。娘の力を信じる大切さを学んだ受験生活でした。

普段通りならば受かる
桜蔭中学校進学Dさん
私は4年生からグノーブルに通い始めました。グノーブルで良い先生方にめぐり会えて、とても良かったと思っています。
受験勉強では大変なこともありました。私の場合、特に社会が苦手で苦労しました。復習テストでは良い点を取れても、グノレブテストなどでは他教科の足を引っ張ってしまっていました。また、それ以外にも理科の暗記系、漢字や知識なども苦手でした。暗記することが苦手で、短期記憶になっていたのだと思います。社会が平均を超えるようになったのは、6年生の後期からです。「地理313題」(「知識の総確認 地理編」)などを繰り返しやるようにした結果、社会の成績が安定するようになりました。
また、私はゲーム、アニメ、漫画などが好きなのですが、受験の直前まで、好きなことをしたいという気持ちを抑えることができませんでした。受験で一番つらかったのは、そこかもしれません。私の場合は、完全に我慢するのではなく、グノレブテストや復習テスト等の成績にご褒美を設定したことで、勉強へのやる気を上げて、乗り切ることができました。
入試本番、私は全く緊張しませんでした。もともとポジティブな性格ということもあると思いますが、「時間配分さえミスしなければ受かる」と謎の自信を持っていました。「緊張するのは、普段以上の力を発揮しようとするから。普段通りならば緊張しないはず。そして、私は普段通りにやれば受かるに決まっている」という気持ちで臨むと良いと思います。
最後に、私が教科ごとに感じたポイントを書いておきます。
🔳国語:漢字と知識は、一回で頭に詰め込もうとすると短期記憶になってしまうので、何回かに分けて繰り返すことで記憶を定着させる。読解問題は語彙力をつけることが大事。また、文章の種類ごとに、授業での先生のアドバイスをしっかりと頭に入れて、自分の苦手なタイプの文章を減らしていくことも大事だと思います。
🔳算数:平面図形でひらめきが必要な問題などは、ひらめかなかったらどうしようもないので、志望校に多く出るパターンを覚えておくと良いと思います。また、算数では問題文の意味を読み取ることがとても重要なので、国語力が必要だと思います。計算ミスなどのケアレスミスが多い場合は、自分が犯しがちなケアレスミスのタイプを意識すると良いかもしれません。
🔳理科:グノラーニングチェックを完璧にするべし!知識系はさぼらず、しっかり覚えましょう。
🔳社会:「地理313題」(「知識の総確認 地理編」)をとにかく繰り返し解く。何度も何度も繰り返しやっていけば、基礎が頭に入ります。知識系は、算国などと違って数をこなせば結果が出やすいはずなので、継続が大切です。気負わずに頑張ってください。

ピアノと勉強の両立
桜蔭中学校進学Eさん
私がグノーブルに通い始めたのは、5年生の春期講習からでした。5年時の通塾日数が少ないことがきっかけでした。通塾日数が少ない分、家庭学習は大変でしたが、一回ごとの授業がとても濃く、分かりやすかったです。通塾を開始してから、6年生の夏期講習までは安定した成績でした。
しかし、9月のグノレブテストで調子を落としてしまいました。その後、いったんは調子を取り戻したものの、12月に、ある中学校の過去問を提出したところ、先生から「いつもと違う」と指摘をいただき、そこから本当のスランプに陥ってしまったのです。しかし先生のアドバイス通り、「いつものことをリラックスして行う」ことを実践したところ、その後、何とかスランプを抜け出せました。
正月特訓ではまた調子を落とすこともありましたが、その後は日曜特訓のテキストの復習、苦手科目のグノラーニングチェックをやり込んだところ、また成績が安定しました。そのまま本番を迎えられたことが功を奏したと思います。
ちなみに、私は6年生の途中までピアノと勉強を両立させていました。グノではそれが可能です!
最後に、受験生の皆さん、グノとグノの先生を信じて頑張ってください!「祈合格」

オススメと反省
桜蔭中学校進学Fさん
私は3年生の夏頃からグノーブルにお世話になり、桜蔭に合格することが出来ました。
私が受験前にやって良かったこと、やっておけば良かったと思うことを紹介します。
<やって良かったと思うこと>
●「基礎力テスト」:毎朝、朝食前にやっていました。朝、問題を解くと目が覚めます。朝にやることで、早起きの習慣が出来ました。
●年号カルタ:6年生の時に配られた重要年号の語呂合わせを元に、母が年号カルタを作ってくれ、遊びながら覚えました。ただ書くより、ゲーム感覚で競争した方が楽しく覚えられます。カルタを作るのが大変だったら、語呂合わせでクイズを出し合うのも面白いです。
●アンテナショップ巡り:アンテナショップは、都道府県ごとに地域の特産品などを販売しているお店です。有楽町駅周辺に多く、旅行より手軽にその地域について知ることが出来ます。アンテナショップで見たものや食べたものが、授業に出てくることもありました。学年が上がると勉強に時間を取られるので、一日中アンテナショップを巡るなら低学年のうちがお勧めです。
●国立科学博物館:通称「科博」、上野にある博物館です。常設展と特別展があり、4歳から通っています。日本館には岩石や鉱物の実物があり、地球館には惑星の模型などがあって、理科の授業がリアルに感じられました。科博に行くと、一日があっという間です。
●東京国立博物館:通称「トーハク」、上野にある博物館です。社会の資料集にある埴輪や土偶の実物などが見られます。トーハクキッズデーの落語も楽しかったです。
●グノーブルの授業:授業は雑談が一番楽しかったと思います。国語は得意で授業も面白かったし、苦手だった算数も授業は少し楽しめました。
<やっておけば良かったと思うこと>
1.平面図形マスターと立体図形マスター:私は平面図形マスターと立体図形マスターを真面目にやっていなかったので、図形問題が不得意でした。特に立体図形は最初の授業で躓き、克服するのに時間がかかりました。初回の授業をしっかり復習すれば良かったと思いました。算数の先生が消しゴムを切って見せてくださり、分かりやすかったです。平面図形でも立体図形でも、実際にやってみると大抵上手く行きました。
2.計算マスター:私は計算のスピードが遅く、もっと計算マスターをやっていれば良かったと思いました。
祈・合格!
グノーブルで「ゆる受験」
桜蔭中学校進学Fさんの保護者様
論語の一節に「知之者不如好之者。好之者不如樂之者」とあります。監獄と揶揄されるような管理型進学校を卒業した母は、母校への反発と反省から、学びを楽しむことを大切にしてきました。入塾当初から桜蔭を目標にしていたわけではありません。むしろ意識的に志望校から外した時期もあります。本人の適性を考えた学校選びに努めました。グノーブルに楽しく通い、親の言うことも先生の言うことも聞かずに、本人が自分のペースで受験に取り組んだ結果、なぜか桜蔭中学校へ進学することになりました。桜蔭の過去問は5年分しか取り組まず、大人の予想に反して合格を得られたのは、グノーブルの上質な授業のお陰だと思います。
<グノーブル入塾まで>
心配性の母には似ず、マイペースな父に似た娘は、造形教室のシールを1枚選ぶのに1時間かかるような子供でした。幼児期より本人が女子校進学を希望し、新3年生で他塾に入塾させたのですが、授業が楽しくないと言い2カ月で退塾しました。ここで算数アレルギーを発症しました。新4年生の入塾テストに向け個別指導も経験しましたが、手応えがなく、通塾の負担の方が大きく感じられ2~3カ月で終了しました。塾選びに悩んでいた3年生の夏前、YouTubeの塾紹介動画を視聴し、通塾日数の少ないグノーブルが目にとまりました。
<グノーブルでの日々>
■3年生:習い事に近い感覚で、楽しく通塾しました。家庭学習は「基礎力テスト」だけ。「基礎力テスト」は受験後の2月5日まで毎日取り組みました。国語は得意、算数は苦手な傾向がありました。
■4年生:受験学年となり家庭学習の課題が増え、算数を負担に感じるようになりました。国語は楽しく、理社もまあまあ楽しいけれど、算数は億劫に感じていたようです。成績は少し下がった程度でしたが、本人の気持ちは段々落ち込み、退塾・転塾を検討しました。1月31日、退塾手続きの締め切りを確認し、判断は受験期間終了後に…となりました。転塾や個別指導も検討しましたが、最終的には本人が「算数以外はグノーブルが良い」と継続を希望し、算数の負担を減らしてグノーブルに通い続けることになりました。
■5年生:新学年のテストでは変化が分かりませんでしたが、4月に算数の成績が劇的に下がりました。学校のクラス替えで、仲の良かったお友達とクラスが分かれた時期でもあり、メンタルの重要性を痛感しました。
娘は転塾も撤退も希望せず、算数の家庭学習を極限まで減らし、基礎中の基礎の習得を目標にして通塾を続けました。夏休み頃には新しいお友達が出来、この頃から塾のお友達の名前が雑談に混じるようになりました。塾にも居場所が出来た時期だったように思います。分かりやすい成績の低迷で本人も多少の危機感を持ち、親は無理のない範囲で課題の進捗状況を確認し、家庭学習を指示しました。最低限の学習すら完遂出来たことは少なかったと思います。それでも5年生の夏休み以降、6年生に進級するまでは、少し安心して家庭学習を見守ることが出来ました。
■6年生:5年生後半の様子から、受験生らしい自主性を期待していましたが、そう上首尾とはなりません。受験生になっても読書をやめられず、隙あらば本を読んでいて、家庭学習量が減少しました。成績も良かったり悪かったりと一定せず、親は残念に思う一方で、本人は気にとめる様子がありませんでした。反抗期らしい言動が増え、塾でも不遜な態度を見せていたと伺いました。卒塾生の応援を喜び、桜蔭に興味を持つきっかけになったようです。
<志望校の選び方>
娘の志望校選択基準は、①女子校!②校庭あり=伝統校、③宗教系ではない(浦和明の星は図書館が大好きなので可)、④図書館の充実でした。総合的に判断し、当初の第一志望校は学習院女子でした。学習院女子の国語はほぼ記述で桜蔭と形式が似ていたので、難易度は大分上がりますが、志望校別特訓は桜蔭コースに入れて頂きました。自立した女子の多い桜蔭コースは静かで、居心地が良かったそうです。日曜特訓も桜蔭コースにお願いし、いつの間にか何となく桜蔭に心が傾いてきた様子でした。
4年生から桜蔭の文化祭には行っていましたが、せっかくだから1回くらい行ってみる?(4年)、父も行ってみたいから付き合って(5年)、桜蔭コースの学校を見てみる?(6年)と言うのんびりしたものでした。
6年生の12月まで、学習院女子に行きたいのか、桜蔭に行きたいのか明言しませんでした。図書館を基準に志望校を選ぶなら、学習院女子より蔵書の多い浦和明の星が良いと言う話になり、浦和明の星に合格したら桜蔭に挑戦することを一つの目安にしました。本人の口から「第一志望は桜蔭」と聞いたのは、浦和明の星の合格後です。
<親の諦観>
9月以降、12、1月も波瀾万丈でした。9月以降に女子特有の体調変化があり、大変悩ましい状況でした。12月は腹痛や貧血で家庭学習が手に付かず、模試の結果も散々でした。教室長の先生は家庭の選択を承認、親子の背中を押して下さり、とても有り難く思いました。親は諦めの境地で、とりあえず元気に受験会場に連れて行くこと、受験を無事に終えることを目標に、体調管理に注力しました。漢方薬でアレルギー反応が出てしまい、最終的にはホルモン剤で治療し、無事に受験に臨む事が出来ました。12、1月、大人が全く期待をせず見守りに徹したことが、結果的には良かったのかもしれません。「たかが中学受験」と腹をくくりました。
<娘の幸運>
規模の小さい校舎だったので、クラスのお友達や先生方の大半が顔見知りで、安心できる空間でした。雑談をするほどの時間はなくても、同じ方向を見て一緒に学ぶ同志と、先生を介してやりとりを楽しめ、塾に愛着を持つことが出来ました。自習室がないのは残念でしたが、小学校の同級生と一緒に会議室を借り、過去問演習を行いました。保護者が交代で見守り、緊張感を保って演習することが出来ました。誰よりもまっすぐに娘の受験を応援してくださり、合格を一番喜んでくださったのが小学校の担任の先生です。面接の服装について母が同僚に相談すると、お嬢様(桜蔭生)のお下がりのジャケットを送ってくれました。何よりのお守りになりました。大勢の方から温かい応援とお力添えを頂き、とても有り難かったです。
<本好き少女の下剋上?>
2025年入試の国語の物語文は、娘のお気に入りの漫画の原作でした。試験終了後「バードさんがでた! 読んでみて」と試験問題を渡されました。娘は本が好きで、区立図書館から借りる分だけで年間300〜400冊+学校図書館から借りた本や自宅の蔵書、漫画まで含めると年間500冊程度の本を読みます。小学校6年間で読んだ本は2000〜3000冊でしょうか。そのくらい読書に浸れば、予想外の幸運に恵まれることもあるようです。お勧めはしません。
本を読み耽る時間があるなら、算数をやろうか?と、度々衝突しました。取り上げても隠しても、図書館に返却しても一向にめげず、受験前日ですら平然と2冊も読んでいました。
娘は2歳頃、自然に平仮名が読めるようになり、幼稚園入園前に約1000冊の絵本を暗記するくらい、本を好みました。同様のエピソードを、桜蔭の合格体験記で度々お見かけしました。
<結果自然成>
道元禅師は「全ての結果は自然に出てくるものであって、人間の作為や努力とは無関係」と説かれています。受験勉強をせずに入試で結果を出すことは難しいと思いますが、努力が全て…でもない、のかもしれません。受験以外の場面でも、天に任せるような心持ちで執着を手放した時に、最適な結果に落ち着くことは、意外に多い気がします。縁、のようなものがあるのかもしれません。ご縁を頂いた学校がきっと、最善の学びの場なのだと思います。
塾の基準では、娘は頑張れない子だったと思います。保護者会で言われた通りの家庭学習を出来たことがありません。成績不振や体調不良で大人が諦めたのちに、娘は自分のペースで自分が望む場所へたどり着きました。大人にとっては予想外でしたが、本人は終始平静でした。
<お勧めの1冊>
『2月の勝者』を暗記するまで繰り返し読み、参考文献の大半を読み、更に孫引きして100冊程度の中学受験関連書籍を読みました。その中で母が受験の軸に採用したのは『中学受験必笑法』です。公立中学校を含めて、どこの学校に進学することになっても、笑って受験を終えることが出来ればそれで良いと思いました。特に最後は、本人の意思を尊重しました。
また、受験終了後に『科学的根拠で子育て』を読み、無意識に第5章の秘策を実践していたことに気付きました。学力向上効果は不明ですが、親のストレス緩和には役立ちました。
<受験終了後の脱力>
お陰様で2月1日に受験を終え、1月受験を含めて全ての学校で合格を頂きました。親子共にそれほど頑張った意識はなく、予想外の良い結果でしたが、2月2日からしばらく「燃え尽き症候群」のような脱力感がありました。休息やマインドフルネスを勧められ、しばらくダラダラと過ごし、新年度準備に追われているうちに、少しずつ気力が回復したように思います。
親の受験を終わらせる意味でも、受験中の冷静を保つ目的でも、受験体験記を書くことをオススメします。我が家の記録もいつか、少しでも、どなたかのお役に立てば嬉しいです。
<結語>
我が家はたまたま桜蔭に合格を頂きましたが、他にも好きな学校がありました。午後受験でそちらに合格を頂いた2月1日夜、受験を終了しました。
桜蔭の合格は喜びましたが、本人も家族も意外に淡々としていました。ゴールという感覚はなく、引っ越しを免れた安堵感と次のスタートが明確になった緊張感が大きかったです。
途中、様々な悩みはありましたが、塾での時間・学びを楽しめたのは良かったと思います。「本人が自力でたどり着いたところに、その子の幸せがある」と考えるよう努めました。
末筆ながら、グノーブル生の皆様が通塾、中学受験を楽しめるようお祈りしています。
鷗友学園女子中学校
予想外の2月1日
鷗友学園女子中学校進学Aさん
私は3年生の5月にグノーブルに通い始めました。入塾したときも6年生になっても得意とすることができなかった国語。入試本番ではその国語が私を鷗友合格へと導いてくれました。ここでは、私が受験するにあたって大切だと思ったことを教科ごとに紹介します。
🔳国語:4教科の中で一番苦手でした。グノの授業は記述が中心で、他の塾よりも記述対策に力を入れており、授業の解説をじっくり聞くことで徐々に記述に強くなります。私は記述のみの鷗友の国語で点数が取れるか不安でしたが、グノの授業をしっかり聞いておけば大丈夫だと思っていました。漢字は得意な方で、1月は毎朝「漢字道場」の01から2回分ずつ取り組んでいました。
🔳算数:4教科の中では得意な方でしたが、ケアレスミスは最後までなくなりませんでした。鷗友は今年から小問を増やすようになったため簡単に解けると思っていましたが、意外と時間がなく、最後の方はあまり時間をかけることができませんでした。「基礎力テスト」は必ず朝にやり、100点を目標としていました。鷗友は平面図形が確実に出るため、土曜特訓の平面図形マスターと立体図形マスターを全てやり直しました。
🔳理科:知識を覚えることは得意だったけれど、化学計算や浮力が大嫌いでした。理科も朝「基礎力テスト」をやり、目標は95点でした。グノレブテストの最後3回では、理科が50点、60点台を取るなど、全体の成績が下がる原因でした。1月は日曜特訓と土曜特訓の理科を全てやり直し、計算問題に慣れました。
🔳社会:社会は得意な方で、復習テストでは100点を目標にしていました。しかし、統計データが苦手で、「日本のすがた」を熟読して覚えました。また、明治時代の後半の年号が苦手で、寝る前に一人で確認していました。入試は、語句を答える問題は全問正解するという気持ちで挑みました。鷗友の記述対策は、土曜特訓の記述をやり直していました。
入試本番や過去問、模試などでは、自分ができないものは他の人もできないと思って解いた方が良いと思います(実際に入試本番でできなかった算数は平均点が低かったです)。
文章のはじめに書いたように、合格へと導いてくれたのは苦手な国語でした。鷗友でも、午後に受けた学校でも、国語ができたため合格したと感じています。入試本番は何があるか分からないので、目の前の問題をとにかく一生懸命解いてください。
みなさんの合格を祈っています。

自信を持つことが大切
鷗友学園女子中学校進学Bさん
私は、2月1日と2日の第1志望校、受かると思っていた第2志望校の入試で落ちました。私は第2志望校は受かると信じていたので、落ちたことを知った時、ものすごくショックでした。もう落ちて悲しい気持ちにはなりたくないと、そのあとの受験をあきらめかけていました。
そんな時、両親に「今までの3年間を思い出して、最後まで頑張ってほしい。」と言われ、グノーブルの先生方には「とにかく自分に自信を持って、楽しんでおいで。」と言われたことで、自分の自信を取り戻して、3日の第1志望校をもう一度受けに行くことができ、合格することができました。
皆さんも、入試の時あきらめそうになっても最後まで頑張り続ければ絶対に受かります! とにかく、自信を持つことが大切です。
吉祥女子中学校
自分を信じて頑張って!
吉祥女子中学校進学Aさん
私は新4年生の2月にグノーブルに入塾しました。
私が合格できたのは最後まで励ましてくださった先生方のおかげだと思います。受験生の皆さんに学習の仕方や入試のアドバイスをしたいと思います。
🔳国語:大好きな科目でした。文章の復習を毎週しっかりやりましょう。入試直前は文章を復習する時間がなかったので、テキストの中のお気に入りの文章を読んでいました。私は入塾時、記述が大の苦手でした。面倒くさかったけれど、全ての記述を何度も書き直しをしていたら6年生の時には得意になっていました(記述が得意になってからは6点以下の記述だけを書き直しました)。また漢字は毎日やりました。
🔳算数:得意な科目でした。テキストはコピーせずに裏面を家で解いていました。私は朝早く起きて、父と一緒にN授業のテキストを何度も解いていました。しかし「基礎力テスト」をサボっていたせいで、簡単な問題を間違えたりすることが多かったです。だから「基礎力テスト」は毎日取り組んだ方が良いと思います。
🔳理科:とても苦手な科目でした。私から言えることは「基礎力テスト」をしっかりやりましょう、ということだけです。理科が苦手なのに、ずっと「基礎力テスト」をサボっていたので、入試前日になっても6年生の5月号が全くわかりませんでした。
🔳社会:公民以外は得意という微妙な科目でした。先生の授業が面白かったです。テキストの復習をすれば点数は伸びます。
🔳過去問:私は1月の最終週にようやく合格者平均点を超えました。だから点数が悪くても最後まで諦めないでください。
🔳入試前日:社会の補習に時間を割きました。先生から「受かる実力はあるから基礎を落とすな」と言われていたため、算数は「基礎力テスト」を解いていました。また理科は「基礎力テスト」でやった(ひとつも解けなかった)血液の問題が本番で出たのでやって良かったと思いました。夜は消化に良いものを食べて、お風呂でリラックスして9時半に寝ました。
🔳入試当日:自分は一番頭が良い! と思いましょうといわれても私には無理でした。だからせめて、隣の人よりは頭が良いと思って試験に臨みました。また前日から緊張してお腹の調子が悪かったので、当日は薬(眠くならないもの)を飲んでから行きました。試験開始までの時間は、「お守りカードブック」を読んで緊張をほぐしていました。
🔳試験:第一志望の吉祥女子の算数はとても手応えがあり、全て見直しをして100点の自信がありました。しかし最後にやった理科の手応えがなく、理科が悪すぎて不合格かも…と思いました。しかし他の科目が良かったから大丈夫! と思って午後入試に行きました。午後は安全圏内の学校だったため余裕で合格できるはず! と思いました。その日は、吉祥女子の結果だけを見て寝る予定でしたが合格だったので、午後の試験の結果が出る11時まで夜更かしをしました。
🔳最後に:模試の結果は気にしないで自分を信じて! 模試で80%の1月校は不合格でしたが、最後に20%が出た吉祥女子は合格しました。親に1日は安全圏内の第二志望を受けるように強く勧められましたが、自分を信じて志望校に受かりたいという気持ちを大切にして、最後まで頑張ってください。
祈 合格!!
子どもの意志を大切に
吉祥女子中学校進学Aさんの保護者様
グノーブルには新4年生からお世話になりました。グノに行きたくないと言ったことは1回もなく、毎回楽しそうに通い、学校の先生の話はほとんどしない娘がグノの先生の話はよくしてくれました。ユーモアに溢れた温かい先生方や一緒に勉強するお友だちに恵まれ、楽しい受験生活を送ることができたと思います。多少のクラスの昇降はありましたが、娘の受験生活は、成績も精神的にも概ね安定していたと思います。
6年になる頃が一番成績が良く、その頃第一志望を吉祥女子に決めました。そこから、同じペースで勉強を続け、娘の様子もいつも淡々として特に変わらないように見えました。しかしながら成績は緩やかに下降していき、秋からの他塾模試での成績は一向に振るわず、吉祥女子の合格判定は最高で60%、12月中旬の最後の模試では20%でした。
親としてはだいぶ焦りましたが、当の娘の様子は変わらず「大丈夫だから」という調子で、やきもきしたものです。
当初から2月2日も吉祥女子を受ける予定でいましたが、この頃になって、3日からの併願校を再考したほうが良いということに遅ればせながら気づき、12月になってからいくつか新たに併願校の見学に行きました。
幸い娘は併願校を気に入り受験することに決めましたが、過去問に取り組み始めていた時期でもあり、かなりドタバタしてしまったというのは反省点です。しかし、ぎりぎりの時期の学校見学というのは、親子共々かなりの現実感を持って学校を見ることができるので良かったと思います。
1月に入り、受かるかなと考えていた最初の入試が不合格でした。得点開示された結果を見ると、かなり悪かったので、私は悲観し、グノの先生に3日の併願予定だった学校を1日に変更するのはどうかとご相談しました。「塾としてご家庭の方針を否定はしませんが、ずっと吉祥女子を目指してきた娘さんがそれをすぐ受け入れるのは難しいことだと思うので、よく相談してください」と先生は仰り、冷静になって娘と話し合うことにしました。
普段、控えめで自分の意志を強く主張することの少ない娘が、そこでどうしても吉祥女子に挑戦したいと宣言したので、そこから親としては腹を括ろうと決め、親子共全力で残り3週間を送りました。
過去問に取り組み始めるのが遅かったこともありますが、合格平均点を出せるようになったのは本番の約1週間前でした。今思えば、ピークを2月1日に運良く持っていくことができたのだと思います。
2月1日、普段は模試等で見送るときもかなりの塩対応な娘が、何度も私のほうを振り返って手を振ったあと、ずんずんと進んでいった姿を見て、これだけ全力でやったのだから後悔はない! と強く思いました。
1日の夜、合格の画面を見て家族皆で狂喜乱舞しました。5日までの長期戦になることも覚悟していたので、本当に今日で終わって良いのか、と信じられない思いもありましたが、そこで娘から聞いたのは「たぶん算数は100点だったからね」との言葉です。
やきもきして右往左往していたのは親のほうで、娘はずっと自分を信じ続けて、着実に力をつけていました。無理やり志望校を変えさせなくて良かった、娘が意志を貫けて良かった、と強く思います。
親御さんは特に直前期は模試の結果等で不安になることが多いかと思いますが、お子さんを信じ、お子さんが強い意志を貫いた先に、きっと良い結果が得られるのではないかと感じます。色々と手を広げたくなりますが、グノーブルの授業と先生方を信頼し、目の前にあることにコツコツと取り組んでいくことが一番大切なのではないかと思います。頑張ってください。

密な2月1日
吉祥女子中学校進学Bさん
2月1日午後9時、家族みんなが大泣きした日。
「合格おめでとうございます」その文字を見た時のことは、今でも忘れられません。
ああ、良かった。私の努力は報われたんだなぁと、喜びと安堵の気持ちでいっぱいになりました。あの時、私は他のことは何も考えられず、ただただ「良かった! 良かった!」と、泣きながら大騒ぎしました。
私は4年生の春からグノーブルに入りました。すでにグノーブルに入っていた友達もいて、新しい環境に不安な気持ちはありませんでした。ただ、初めの成績が良かったためか気を抜いてしまい、5年生から特に算数の成績が低迷しました。5年生前期は特に決まった志望校はなく、やる気も起きませんでした。そのため、5年生後期から本当に苦労しました。勉強しようにも、やっていないものが多すぎて何から手をつけていいのかわからず、やれなかった教材が何冊あるか…。そんな中で参加した学校説明会で、吉祥女子に一目惚れしました。吉祥女子に合格するために日曜特訓をどのコースにするか迷っていたところ、グノの先生に勧めてもらい、女子学院コースを選択することに。
そんな状態で迎えた最初の模試。結果は、合格可能性40%!違う塾の模試になるとこんなにも落ちるのかと少しショックでした。その次の模試から2回は、70%、60%と好成績でこのまま行けば順調と思っていた時、次の模試ではまた40%に戻ってしまいました。最後のグノレブテストでも、これまでの上がる一方だった成績から偏差値が10ほど落ちてしまい、自信がなくなってしまいました。時はもう1月。ここからはただただ合格するための勉強を積み重ねるだけ。日曜特訓も、少しずつ前の方の席に座ることが増えていきました。
そして、受験当日。全部不合格だったら…私の中は嫌な妄想ばかり。前日の夜も電車の中でも心臓がバクバクしていました。
入試が終わり、算数が足を引っ張らなかったようなので、手応えはありました。でもやはり不安。3人に2人は不合格なのです。合格発表の午後9時になったというのに、私は恐怖からタブレットを開くことができず、一人で部屋で見るつもりが母と一緒にリビングで見ることになったものの、結局は母が一人で見るということに。結果は合格。あの1日は私にとって一生の宝物になりました。ここまで来られたのはグノーブルのおかげです。最後までありがとうございました。
ここからは、私の日々の勉強方法を皆さんに伝えます。
【各教科の勉強方法】
■算数:とにかく授業でやったことの復習をしましょう。算数は、たとえ授業でやった問題が直接入試に出なくとも、基本的な考え方が応用に結びつきます。私は6年生後期に入ってから、日曜特訓の復習を優先しました。吉祥女子の入試には、最後の日曜特訓で習った問題がそのまま出てきたり、通常授業の問題の応用が出てきたりもしました。苦手な算数を制すことができたのは、日曜特訓のおかげです。
■国語:比較的得意な教科でした。吉祥女子の入試は処理能力が合格のカギとなります。国語が苦手な人も得意な人も、普段から文章を速く、正確に読む練習をすると良いと思います。また、読解だけではなく、漢字や言葉の意味なども大事です。身の回りの言葉を、意味とセットで覚えましょう。語彙力は記述のときにも役立ちます。漢字は、毎日「漢字道場」を解いていました。
■理科:単元ごとの差が激しかったです。計算や知識、実験など、幅広く出題される吉祥女子の理科で合格点を取るためには、自分の得意な分野を選んで伸ばすより、嫌いな分野を克服しながら、さまざまな問題を経験しておく必要があると思います。私は、1月に今までやってきた理科のグノラーニングチェックを見直し、知識の穴埋めに取り組みました。
■社会:好きだけど得意ではありませんでした。私の場合、まず授業の復習テストで100点を取ることを目標にしました。入試の社会にも、日曜特訓で聞いたた小ネタが出てきました。社会も他の教科と同様、日曜特訓の解き直しが最優先です。社会は時事も出るので、普段からニュースを見るようにしたり、時事の本を読んだりすると良いと思います。
【1月の過ごし方】
○朝に慣れるために少しずつ早起きをすると良いです。
○1月は今までの知識を詰め込むだけでなく、体調に十分に気をつけなければならない大事な時期です。1月にたくさんの課題を残しておくと、全部やり切ることが難しいです。過去問や溜まっていた問題などは、1月までにある程度終わらせておきましょう。
【入試当日どう過ごしたか】
○とにかく落ち着きましょう:私は緊張で、激励電話の時も先生とうまく話せませんでした。緊張がおさまらない時、電車の中で音楽を聴いたり、今までの自分の努力を思い出したりすると良いです。
○休み時間の軽食は好きなもの!:私はカステラを選びました。好きなものを食べることで、少し緊張が和らぎますし、お腹も膨れます。
○着いたらまずトイレ:休み時間のトイレはとても混雑します。また、限られた時間にトイレに行くとなるととても焦ってしまいます。時間に余裕がある、着いてすぐの方が良いと思います。
入試はとても緊張しますが、最後まで諦めない、行きたいという気持ちがあれば、絶対に合格できます。受験勉強は大変ですが、努力には必ず結果がついてきます! 皆さんの合格を願っています。
女子学院中学校
私の合格体験記
女子学院中学校進学Aさん
私は小学3年生の12月からグノーブルに通い、第一志望の中学校に合格することができました。
🔳第一志望の学校を選んだ理由:私が第一志望を女子学院に決めたのは、次のような理由からです。
●土曜日に授業がないこと
●自宅からの通いやすさ
●文化祭に参加したときの雰囲気の良さ
●「すごいな」と思う人たちが志望していたこと(この人たちと一緒なら楽しく学べそうだと思った)
🔳グノーブルでの学習について:これから中学受験に挑戦する皆さんへ、私がグノーブルでどのように学習したかを教科ごとに紹介します。人それぞれのやり方があると思いますが、参考になれば嬉しいです。
【算数】:私は居残りが嫌だったので、「居残りを回避する!」 という気持ちで取り組んでいました。具体的には、以下のことを徹底しました。
●解き直しをしっかりやる
●解けなかった問題の確認をする
●計算ミスを減らすためにチェックをする
●「基礎力テスト」を毎日やる
すぐには成績が伸びませんでしたが、受験直前に一気にできるようになり、第二志望校の過去問では100点を取ることができました。最後の最後まで実力は伸びるので、諦めずに取り組むことが大切だと思います。
【国語】:漢字は毎回、出題範囲をしっかり勉強しました。グノーブルのテキストに出てくる文章はとても面白く、興味を持って学ぶことができました。特に気に入った文章は、受験のあとも続きを読めるようにテキストを保存してあります。
【理科】:私は、理科が一番モチベーションが上がらない教科でしたが、次のことを意識して取り組みました。
●「基礎力テスト」を毎日やる
●復習テストで満点を取ることを目標にする(実際にはほとんど100点は取れず、特に6年生の前期は難しかったです)
苦手な科目でも、わかるようになると少し面白く感じることもありました。「嫌いだからやらない」のではなく、まずは授業をしっかり受ける、テキストを読むことが大事だと思います。
【社会】:社会は、地理・歴史・公民のどれも授業が楽しいと感じる科目でした。復習テストで100点を目指して、復習を中心に学習しました。受験直前期になると、歴史の年号を覚えるのが大変でしたが、年号を覚えることで歴史の流れが理解しやすくなると気づき、最後まで取り組みました。また、ニュースや大河ドラマ、時代劇を観ると興味がわいてくるので、おすすめです。
🔳受験を通して学んだこと:私はこれまで習い事やスポーツをしていなかったので、中学受験が初めて本気で挑戦したことでした。受験勉強を通じて、たくさんの知識や考え方を身につけました。たとえば、
●天体の動き方や天気・風の仕組み
●さまざまな漢字や語彙
●政治の仕組み
●組み合わせの考え方
など、世の中の見方が広がったと実感しています。
これから、中学校でさらに学ぶことが楽しみです。グノーブルでは、その「学ぶ楽しさ」を教えてもらえたと思います。
🔳最後に:受験の結果には運もありますが、受験を通して得たものは、きっと将来の役に立つと思います。後輩のみなさんがグノーブルで良い学びを得られることを願っています。頑張ってください!
グノーブルでの学びと成長~学ぶことを面白いと感じ、負けて悔しいと思う
女子学院中学校進学Aさんの保護者様
🔳中学受験を決意したきっかけ:娘が通っていた幼稚園では、跳び箱や鉄棒などについての目標が設定され、それに向かって一生懸命取り組む環境がありました。しかし、公立小学校に入学すると、周囲に合わせて楽をし、手を抜いて過ごしているように感じました。「もっと様々なことにチャレンジできる環境を」と考え、中学受験を考えるようになりました。
🔳グノーブルとの出会い:塾を探していた際、「自宅での予習が大変な塾は避けたい」と考えていたところ、復習中心で大規模ではない塾としてグノーブルを知りました。そして3年生の11月に入塾テストを受験。結果は、算数の偏差値は35程度。「この成績でついていけるのだろうか?」と不安がありました。しかし、初めての体験授業を終えた帰り道、娘は目を輝かせながら「授業、本当に楽しかった!」と話し、社会科の授業で学んだ「なぜ現在は妖怪がいなくなったのか」というテーマについて熱く語っていました。その姿を見て、「この塾なら大丈夫だ」と確信しました。
🔳学ぶ環境が変えた娘の意識:小学校では周囲に合わせていた娘も、グノーブルでは楽しく学びながらも競い合う環境に身を置いたことで意識が変わりました。特に算数の授業では、周りが解けているのに自分が解けないことが悔しく、泣いて帰ってくることもありました。また、社会科の地理の確認テストで富山県が出題範囲のときは「母の出身地だから100点を取る!」と意気込んで挑戦。しかし、「飛驒山脈」の「飛」の漢字で減点され、100点ならず。帰宅後、悔し涙を流していました。
学ぶことを面白いと感じ、負けて悔しいと思う…。そんな環境があったからこそ、全力で学習に取り組むことができました。
🔳教科の枠を超えた学び:グノーブルのカリキュラムは、単なる知識の詰め込みではなく、科目同士が連携する形で組まれていました。例えば、
● 社会科の「季節風の学習」と理科の「対流の学習」を同時期に実施
● ある数学者の講演会のタイミングで、その数学者のエッセーを国語の授業で扱う
こうした工夫により、知識が単なる暗記ではなく、実生活や他の学問と結びついていることを実感できました。この洗練されたカリキュラムには感心しました。
🔳復習テストに全集中:中学受験に向けて、グノーブルのカリキュラムを信じ、他の教材には手を付けませんでした。毎回の復習テストで100点を目指すことに全集中し、目標を持って学習を進めました。
また、21時まで授業がある日は帰宅後すぐに就寝準備をさせ、とにかく早く寝かせることを徹底しました。
🔳合格発表と涙:迎えた合格発表当日。家族みんなで結果を確認し、万が一不合格だった場合は、娘を励ます準備もしていました。そして、画面に映った桜色の合格通知を見た瞬間、娘は嬉し泣き。私も涙をこらえられませんでした。
🔳中学受験を経験して:「中学受験は大変」とよく言われますが、娘にとっては貴重な経験となりました。これまで、スポーツや音楽などの習い事に本気で取り組んだことがなかった娘が、「嬉しくて涙が出るほど一生懸命になれるもの」に出合えたのは、何よりも価値のあることでした。グノーブルでの学びは、単なる受験勉強ではなく、「全力で取り組むことの大切さ」を教えてくれました。この経験が、これからの人生においても娘の大きな糧となることを願っています。

GNO 合格体験記
女子学院中学校進学Bさん
私は3年生の春期講習からグノーブルに通い始めました。入塾テストを受けたあとの体験授業が面白かったため「入塾したい!」と思いそのまま入塾しました。3年生の時は単純に授業がとても楽しく、先生も面白いので楽しみに思いながら塾に通っていましたが、4年生に上がると、塾も週2回に増え、課題も増したため、楽しさだけではなくなりました。しかし、他の塾と比べて通う日数が少ないところもあり、私は運動系の習い事を週4回行っていましたが、両立しやすく、ほかのことも諦めずに受験勉強が出来たところも良かったです。5年生になると、今まで上のクラスをキープしていましたが算数の成績が下がり、6年生になって、算数の成績が上がり出したと思うと、国語の成績が下がるなど、本当に女子学院に受かるのかと不安になることも多くありました。合格発表を見るためにボタンを押す際も結果に自信が無くて、なかなか押せなかったほどです。
私が皆さんにおすすめしたいと思ったことを教科ごとに紹介しようと思います。
🔳算数:女子学院は試験時間が他の学校と比べ短いため、5年生まである「計算マスター」をしっかりと怠らずに取り組んだ方が良いと思います。また、「基礎力テスト」は朝などのルーティーンにして取り組み、間違えた問題は解説を読んで直しをした方が良いと思います。
🔳国語:私の場合は読解力は演習しても点数が上がりにくかったため、国語を苦手としている人は、漢字や知識を記述も大事ですが、少しだけ取り組む量を増やしてみたり、記述はできるだけ白紙にせず部分点を狙い、初めに自分の中で優先順位をつけてから問題を解くことが大事だと思います。
🔳理科:女子学院は天体の単元が出やすいため、「星」などの勉強を少し多めに取り組んでおくと必ずとは言えませんがテストに出る確率が高いので、心強く、安心材料にもなります。また、よく出てくる記述問題の問題と解答をセットにして暗記し、いつ聞かれても大丈夫なようにすることも大事だと思います。
🔳社会:その学校によって出る割合が違う場合もありますが、多くの学校で歴史の割合が多く、女子学院では半分ほどの割合を占めているため、歴史の勉強はおろそかにしないことが重要だと思います。
また、全教科において、1月は演習ではなく暗記することを優先的に行えば良いと思います。算数であれば、苦手な問題の解法を確認したり、国語であれば漢字と知識、理科は単語や化学計算などの解法、社会は単語や年号などです。
入試直前には緊張する人が多いと思いますが、焦ることなく、今までの自分を信じて、前を向いて頑張ってください! 祈合格!
たくさんの仲間と素晴らしい先生方に恵まれました
女子学院中学校進学Bさんの保護者様
この合格体験記を書くにあたって、お伝えしたいことは、グノーブルのカリキュラムを信じてついていくことが合格につながるということです。
我が家は新3年生の春期講習からグノーブルに通塾を始めました。ひとまず塾がどんなところかお試しのつもりでしたが、娘が「楽しい! 通いたい」と言ったので、そのまま入塾しました。運動系の週4回の習い事を休みたくなかったので、グノーブルは通塾日数も少なく両立できたことも我が家にはありがたかったです。
さて、通い初めのうちは上位クラスにいましたが、5年生の前半は偏差値60前後、後半は55前後になりました。グノレブでも解き直しをすると取れるところを落としていたということが続きました。先生にご相談すると、授業の感触は良いのですがどうしてでしょうね…というお返事が。
本人も初めのうちは落ちてしまったから上がりたいという気持ちから、徐々に必死さが薄くなってしまった感じがありました。ちょうどその頃から反抗期が始まり、なかなか思う通りに家庭学習が進まなくなっていました。
反抗期の娘との関わり方は難しく、家庭内の問題だと考えていたのですが、6年生の春に思い切って先生にご相談しました。合間を見て娘に声かけをしてくださり、少しずつ娘も取り組みが変わってきました。
JGに進学したい気持ちは親子で持ち続けていたのですが、変わらない成績のまま志望し続けて良いのかという迷いもありました。理社は比較的安定していたのでJGの配点も娘には向いていると先生にも仰っていただき、目指し続ける支えとなりました。
6月頃から本人の意識も変わり、ようやくですが「基礎力テスト」を毎日きちんとこなすようになり、算数の成績も徐々に安定してきました。
夏休みは夏期講習と課題に追われましたが我が家なりに走り抜け、夏休み明けから算数は力がついてきたとグノレブテストの結果を見ても感じました。
9月になり日曜特訓が始まりましたが、学校の宿泊行事に習い事の発表会もあり、そのリハーサル等で日曜特訓を途中抜けしたりと、増えた課題、過去問、家庭学習の時間の確保で9月は苦しみました。しかし、結果が良かったから言えるのかもしれませんが、習い事との両立を目指してやってきたので、発表会を諦めずにやり切って良かったと思います。ただその皺寄せ分は、過去問は受験校・教科別に12月までスケジュールを立てたりして、隙間時間を使って埋め合わせしました。全ての課題をこなすことは我が家は難しかったので、優先順位をつけて取捨選択をしました。我が家はJG以外に日曜特訓にない学校も目指していたので、その学校別の算数の講座も10月から追加で取りました。
グノでの成績は徐々に上がる感じでしたが、過去問の結果は年によっては良い手応えがあるときもあり、模試の判定で一度80%を出せたことも、モチベーションにつながりました。
過去問は塾の指示通り、12月まででそれ以降は手をつけませんでした。他塾の受験生が1月ギリギリまで過去問をやってることを耳にしましたが、本人も過去問より演習をする、と言い切りグノーブルを信じて演習を続けました。1月でも算数は伸び続けた実感があります。保護者会で社会の先生が仰っていましたが、どの塾より難しい内容をやっているから自信を持ってください。
2月1日、送り出す際娘は振り向きませんでした。やってきたことを信じて前だけ向いていた背中でした。
結果、JG、2月2日の同じく熱望校からも合格をいただけました。
決してトップを走ってきた娘ではなかったですが、グノーブルの授業、テキストを信じて取り組み続けたことが、結果につながったのだと思います。そして、先生方がよく子どものことを理解してくれているという安心感もありました。
たくさんの仲間、素晴らしい先生方に恵まれ、グノーブルに通えて良かったと思います。本当にありがとうございました。

グノの3年間を振り返って
女子学院中学校進学Cさん
私は新4年生の2月からグノに通い始めました。私の大まかな過ごし方を、4~6年生の夏まで・6年生の後期・受験直前の1月・試験前日~当日の4つに分けて紹介します。あくまで私個人の場合ですが、参考にしていただけたらうれしいです。
<4~6年生の夏まで>
・授業の復習をする:理科や社会は、ノートを読み返すのがおすすめです。
・宿題をしっかり解く:分からない問題があったら、先生に質問したり、図鑑やインターネットで調べたりしました。また、実際のイメージがつかめるので、理科の実験動画もよく見ていました。
・グノレブ前に、知識問題や自分が間違えた問題を解く:知識問題→グノラーニングチェック、復習テスト、漢字テスト、など。自分が間違えた問題→テキストで間違えた問題を家庭学習用テキストで解く、確認テストで間違えた問題をもう一度解く、など。
・毎朝「基礎力テスト(算数・理科)」を解く:習慣にしていました。余裕がある日は丸付け、直しまで朝のうちにしていました。
<6年生の後期>
・グノが無い日に、過去問を解いて直しまでする:直しは、「どうして間違えたのか」「どこで間違えたのか」「どうしたら防げるか」を考えられたらOK。知識問題の時は、ノートや地図帳、資料集などに戻って確認する。
・とにかく過去問を解いて、形式に慣れる:例)Ⅰは計算、Ⅱは小問集合、Ⅲは図形…などの傾向をつかむ。
・授業内容はできる限り授業中に理解する:分からないところはどんどん先生に聞く。
・宿題が終わらない時は:①日曜特訓の問題 ②通常・土曜特訓で間違えた問題、授業で理解できなかった問題(授業で扱わなかった問題や、間違えていても解き方をマスターしていた問題はとばす)③通常・土曜特訓で次回のテスト範囲の問題、の順番で解く
・小学校の宿題は基礎問題が多いので、忙しくても自力で解く:計算力UPと漢字の確認になりました。
<受験直前の1月>
・小学校に行く時:小学校で少し気をゆるめる。家ではメリハリをつけて勉強をがんばる。
・小学校に行かない時:本番と同じタイムスケジュールで過去問を解く。午前中に解き、午後に直しを終わらせる。私の場合、運動不足になりやすいので、20分くらい外を走っていました。
<試験前日~当日>
【前日】
・その学校の直近の過去問を解く。
・本番(明日)の時間配分を科目ごとに考えて、ルーズリーフにまとめる。具体的に「9:30まで!」のように書くと、イメージしやすかったです。
【当日】
・前日書いたルーズリーフを読み込んで、その時間配分を厳守する。
・今までの間違いをメモしたノート(ルーズリーフを束ねて作っていました)を読む。
・自分が苦手なもの(社会の統計データなど)を読む。
・カイロを持っていく(冬なので寒いです)。
私にとって、グノは問題が難しいので大変だけど、先生の話が面白いし友達にも会えるので楽しい場所でした。受験が終わっても、グノの曜日になると「あっグノの日だ!!」と言ってグノに行ってしまいそうになっています。
最後になりますが、右も左も分からなかった私に一から勉強を教えてくださった先生方、そして私の名前を覚えて様々な面でサポートしてくださった事務のみなさん、本当にありがとうございました。私が無事に合格できたのは、先生方と事務のみなさんのおかげです。
それでは、受験生のみなさん! 自分の目標に向かってがんばってください! 応援しています!!
中学受験を振り返って
女子学院中学校進学Cさんの保護者様
娘は新4年生の2月に入塾し、3年間お世話になりました。グノーブルは、1クラスあたりの生徒数が少なく、また、生徒から先生へ質問する時間帯や回数に制限がないことから、面倒見が良さそうとの印象を受け、入塾を決めました。また、5年生でも通塾は週2回のみという点も、家から校舎まで遠い我が家にとってはありがたかったです。個別指導塾や家庭教師を併用することは、最後までありませんでした。
以下、時系列に沿って学習の様子を述べたいと思います。
🔳4~6年生の夏まで:各科目とも、通常授業を受けて次週までに宿題を終わらせる、月1回のグノレブテストに向けて準備する、グノレブテストが終わったら直しをする、といった当たり前のことをするだけで、あっという間に一週間が過ぎていきました。
グノでの授業はとても楽しかったようで、帰宅したら、いつもグノで聞いたことを楽しそうに話してくれました。先生方が生徒を飽きさせないよう、工夫を凝らして授業をしてくださっていることが伝わりました。
特に覚えているのは、理科の楽しい授業がきっかけとなって、てこや電気の単元が大好きになったことです。おかげでその後も、滑車・輪軸、複雑な電気回路の問題も楽しんで解くようになっていきました。また、社会の授業もイラスト満載で大変楽しかったそうで、娘は社会も大好きになりました。4年生の段階で「理科って楽しい」「社会って楽しい」という意識を持てたことで、社会や理科(物理・化学分野)が比較的得意科目となり、その後受験勉強を続けていくうえで大きな支えとなりました。
一方、娘は算数が全般的に苦手でしたので、算数の復習に多くの時間を割くことになりました。先生には、保護者会終了後によく質問させていただいていました。先生方は、どんな質問でも丁寧に答えてくださり、その都度勉強の指針を得ることができました。娘の授業中の様子や、上達の傾向についてよく見てくださっていて、大変心強かったです。
また、娘は6年生の頃から反抗期にさしかかっていましたので、親の言うことは聞かなくても、グノの先生から言っていただくとスッと心に響く、ということが何度もありました。本当にありがたかったです。
🔳6年生の9月から12月:6年生の9月以降は、日曜特訓が始まり、毎月外部模試を受け、さらに自宅では過去問を解くというスケジュールになりました。娘も私もこのハードな生活になかなか慣れず、苦労しました。外部模試やグノレブの偏差値もどんどん下がっていき、12月の外部模試では志望校合格可能性が20~30%。模試の成績で一喜一憂しないようにと言われていましたが、さすがにダメかもしれないと思いました。
今振り返ると、11月の面談で「算数で復習する問題数をどのような基準でしぼれば良いか」「各科目の過去問の直しにかける時間はどのくらいが限度か」等、具体的なアドバイスをいただいたことが転機となったように思います。面談後は、ひたすらグノの問題(日曜特訓が中心)と過去問を解いていきました。
過去問は1週間のなかで4科目とも1回は必ず解くようにし、国語と算数は、解いたら答案を提出して、先生に添削していただきました。提出後、返却された答案に書かれたコメントを踏まえて新たな目標を立て、また過去問を解く、というサイクルを繰り返していくうちに、問題に対する答え方や時間配分等を体にしみこませることができたように思います。
🔳6年生の1月以降:日曜特訓や過去問等で鍛えた成果がようやく表れ始め、1月受験では2校から合格をいただくことができました。
2月受験ではありがたいことに、女子学院と豊島岡女子学園から合格をいただくことができました。豊島岡は、第1回、第2回とも落ち、第3回でようやく繰り上げ合格候補者となった末の繰り上げ合格です。娘は4年生からずっと豊島岡を熱望していましたので、豊島岡に通いたければ合格するまで受けに行くしかないのですが、1回目で落とされ、2回目でも落とされ、それでも3回目を受けに行くというのは、相当つらかっただろうと思います。娘の粘り強さに驚き、心の成長を感じました。
娘の固い意志を知っていましたので、もし繰り上げ合格をいただけたら、迷わず豊島岡へ進学するのだろうと思っていました。しかし、娘は迷いに迷い、最終的に選んだのは女子学院でした。グノの講習へ応援に来てくださった女子学院の方々や、女子学院入試当日のお手伝いの在校生の方々が明るく活発で、その姿に憧れたようです。
🔳受験を振り返って:結果だけ見ると順風満帆な受験生活に見えるかもしれません。しかし、グノでの成績は波がありましたし、娘は家ではよく「解けない問題ばかりでつらい」と言って泣いていました。訳もなく涙が止まらなくなって、勉強が手につかなくなることもありました。
それでも受験生活を最後まで乗り切ることができたのは、グノの先生方やお友達が大好きで、娘にとってグノが大切な居場所になっていたからだと思います。良い先生方、良いお友達との出会いに、心より感謝しております。
今グノに通われている皆さんも、グノの先生方を信じ、グノの授業に頑張ってついていってください。そうすれば、今はつらくても、結果はあとからついてくるはずです。
娘がお世話になりましたすべての先生方、事務の方々に、心よりお礼を申し上げます。3年間本当にありがとうございました。

自分はできると信じることが大切
女子学院中学校進学Dさん
私は5年生の秋からグノーブルに入りました。入塾するのが遅かったので、周りに追いつけるか不安でした。最初の社会の授業で、もうペリーが来航していたので驚きました。国、算、理は授業を理解することはできましたが、自分で問題を解くことはできませんでした。けれど宿題は必ずやっていきました。やめられない学校の課外活動と、やめたくない習い事が3つあったので、両立するのが大変でした。
しかし、先生から習っていない範囲の勉強方法のアドバイスをいただき、空いている時間に取り組みました。国語は、記述がまったく書けなかったこともありましたが、授業を受けるうちに、自信を持って書くことができるようになりました。また、「漢字道場」を3周しました。算数は、あまり苦手ではありませんでしたが、日曜特訓で配られたテキストをもう一度全て解き直しました。理科は、先生が特別に授業をしてくださったおかげで、成績がぐんぐん伸びました。社会は、授業は楽しかったですが、習っていないことが多く、最後まで苦手でした。
6年生の最初のテストで、偏差値が38だったことを覚えています。6年生の秋からは、ひたすら社会の勉強をしていました。さまざまな学校の過去問を解き、先生に勧められた直しノートで直しをしました。そのおかげで細かい知識が身につきました。最後の学校別テストでは、合格確率が30%でしたが、私は合格できないとはまったく思っていませんでした。愛猫の癒しによっても勉強がはかどりました。私が女子学院に合格できた最大の理由は、合格した自分しか想像せずにあきらめなかったからだと思います。絶対に自分はできると信じることが大切です。
受験で学んだこと、挑んだことが今後の成長に
女子学院中学校進学Dさんの保護者様
受験勉強のスタートが5年生の夏休み後からと厳しい戦いでした。この時期からの受験生を温かく迎えてくださったグノーブルの先生方に感謝申し上げます。3年上の子が通っていたのを先生方・事務の方々が覚えてくださっていたので、安心して通塾ができました。
未学習の単元は出来なくてもやむを得ないと割り切って、日々のテキストの宿題を進めました。次の授業までに宿題がとにかく終わるようにスケジュールを立てることと、正解のマルは大きくつけ、間違いのチェックは小さくつけて、気持ちよく間違いを見直せるように努めるのが親の仕事でした。未学習の理社の範囲は、兄が使って保管してあったグノーブルのテキスト、苦手な算数の単元は「グノワークアウト」での学習を長期休暇のときに試みたのですが、思うように進まなかったのが実状でした。
日曜特訓が始まった6年生9月からは、時間も十分にないので、保護者会での説明のどおり、日曜特訓→通常→土曜特訓の優先順位でこなしていたので、土曜特訓の算数は図形、理科はグノラーニングチェック、社会は基礎知識の確認までの学習でした。過去問は良くて週に1年分を隙間にいれてました。
結果として、夏前までは出題範囲の決まっているグノレブテストはまあまあ、全範囲の模試は今一つで、秋になっても社会が足を引っ張る状況は変わりませんでした。テストは、結果を見ると直しをする気がなくなるので、当日~3日以内にやり直し、戻ってきた結果は正答率の低い問題で間違っていなかったかを確認しました。最終的には、最低点での合格を目指して、算数は捨て問の選択ができるようになったかもしれません。結果が良ければファイリングを遅らせ、悪ければ早々にしまい込んで、自信がなくならないように努めました。苦手というより興味がない社会が、国算と同じ100点配分の女子学院を受けるにはかなり不安要素でしたが、テキストの復習問題、過去問の直しノートで何とか試験当日に受験生平均まで達したのかもしれません。
不安がないように「やるべきことは全てやった」とまでは至らなかったのですが、不安に思っても仕方がないのと、子供に不安が伝染するかもしれないので、過去の模試の結果は気にせず、1月末には「合格最低点を10点超えた」ということにして受験となりました。合否とは関係なく、受験で学んだこと、受験に挑んだことが今後の成長に結びつくと考えたことも、平常心で試験を迎えられた要因かもしれません。
グノーブルに子供二人が本当にお世話になりました。上の子は中3となった今も、グノーブルの先生のことや、学んだことを楽しそうに話しております。新学年が始まっていますが、引き続き学びの楽しさを子供たちに伝えていただければ幸いです。

健康第一!!!
女子学院中学校進学Eさん
私は3年生の5月に入塾しました。最初は算数も国語もそこまでつまずかず、塾も楽でした。しかし、4年生になると理社がテストに加わってしまい、全然勉強していない私は少し大変でした。それでも、まだその時は6年生の時と比べれば楽でした。5年生になり、テキストの量が増え、理社はそれまでどおり不安定でしたが、算数もあまり安定せず、先生には「努力不足」と言われました。特にその中でも成績が悪かったのは体調不良だった時で、健康は大切だと思いました。6年生になってもなかなか勉強の量は増えず、算理社の知識系の分野は苦手でした。そのような中、国語が得意になり、算理社が悪くても国語で4科目平均をカバーするようになったことで、国語の先生に「国語に頼りきった成績」、「国語以外も真面目に勉強するように」と言われるようになってしまいました。
中学受験での一つ目の関門は夏期講習だったと思います。夏期講習は時間も5時間30分と長く、4日通って1日休みを何回もくり返していたため、回数も多く大変でした。特につらかったのは算数の復習テストで80点未満だったら居残りになったことです。私も2回か3回ほどひっかかり、居残りが1時間ほどになってしまうこともあり、そうすると帰る時間が遅くなり、また翌日のテスト勉強があって、つかれて…という負のスパイラルになってしまいました。
中学受験での二つ目の関門は、日曜特訓が始まった9月頃です。日曜特訓は、時間が長い上、毎週の復習テストもあり、その度にみんなは点数が良いのに自分は悪いので先生にみんながどれぐらいやっているかを(親が)聞いたところ、「4、5周ですかね」と言われ、親子そろって悶絶。「不可能だね」「うん」という感じであきらめました。ちなみに、その時の私の復習量は2周でした。「みんなすごいな」と他人事のように思えてしまいました。そのような中、私は9~10月ぐらいに体調をくずしてしまい、いつもより長引き大変でした。しかし、そのあとから過去問も始まってしまいました。女子学院の過去問は10月後半からやり始め、本当に受かるのかな…とも思いましたがそのまますごしていきました。
そして、中学受験での三つ目の関門は、冬期・正月特訓です。毎日テストがあり、その上、特に正月特訓は時間も長く、断続的に続くのもあいまってつらかったです。その間に私は2回クラスが落ち、1回目はすぐ上がれましたが、2回目は1回で上がれず2回かけて上がりました。
そのような中、あっという間に1月受験が来てしまいました。2校受験し、1校目は合格できましたが、2校目は不合格でした。しかしどちらも志望度は低かったため、特に何とも思わなかったです。強いて言うなら私は朝が苦手なので(夏期講習の間午前10時まで寝ていました)県外の学校はいやだ!というプレッシャーがあったぐらいです。
2月1日、受験当日が来てしまいました。塾の先生にも「緊張するから!」と言われていたので「緊張するのかなー」と思っていましたがほとんど緊張せず、理科で空らんがあった時や算数で大問がいくつか分からない時はあせりましたが、あきらめず最後までやりました。午後はそのままのテンションだったため、テスト中はなんとも思いませんでしたが、終わったあとに突然疲れを感じました。
つかれたまま受けた2日校。女子学院と1日午後の受験校の結果発表は、2日校試験後でした。2日校が終わり、怖くて結果発表は見られないままお昼を外で食べ、その後家に帰り、だいぶ遅れて結果発表の確認。先に見た1日午後校は家から近く、女子学院ほどではないけれど志望度が高かったです。結果は合格でした。「おお~!!」と家で歓声が上がりました。女子学院はそのあと見て合格でした。家では「お~?」というどちらかというとおどろきの声が上がりました。2日校は不合格でしたが、女子学院をもっとも希望していたのでもう何とも思わなかったです。
〈受験で失敗したこと、良かったこと〉
1.国算は入塾の前にドリルをしたこと。〈良〉
2.勉強量が少なすぎたこと。〈失敗〉
3.途中まで理科の基礎力テストをやらなかったこと。〈失敗〉
4.自分の好きな本を読んでいたこと。〈良〉
5.先生の言った量を心がけたこと。〈良〉
6.グノーブルに入ったこと! 〈良〉
グノーブルでなければ私は女子学院に入れていなかったと思います。グノーブルには感謝しています。
〈受験生の方々へ〉
①塾の先生の言うことを聞く:それでは少ない、と思っても、先生の指示どおりにやらないと負担が増え逆効果になってしまうので、増やしたり量を変えたりする時は先生と相談しましょう。
②健康第一!!:行きたい学校のレベルに届くために量を増やすと、体調をくずし勉強どころではなくなってしまいます。
みなさんの健康と合格を心から願っています!!
読解力は全てに活きる
女子学院中学校進学Eさんの保護者様
グノーブルに通うことを決めた理由は、自宅から通いやすく通塾回数が少ないため、習い事と両立を出来る点が大きな魅力でした。おかげ様で6年生の12月初旬まで楽しく続けることが出来ました。それもたくさんの素晴らしい教材と温かく指導してくださる先生方のおかげです。怠け癖のある娘のことを見抜かれて、声がけをしてくださり、その度に反省して学習量を見直しました。
6年生になると振り返る間もなくテキスト量、塾の授業時間が増え、模試に過去問の取り組みが加わり、正に混沌たる状態です。それでも最後まで苦しみながらも取り組み続けた娘は本当によく頑張りました。一緒に学ぶ仲間にも恵まれ、大好きな国語に出合い、学びを深める楽しさを味わいました。ここで得た物は、彼女の生涯の宝物となるでしょう。グノーブルを卒業して、娘にとって大切な習い事の一つだったと今は実感しております。3年半、優しくお付き合いくださった先生方に心より感謝申し上げます。
来年の受験生の皆様、グノーブルの授業を思う存分楽しんでください。苦しい時は楽しい授業が支えてくれます。娘は理算の日は憂鬱でしたが、国語の日を楽しみにしながら、日々宿題をしておりました。私も娘から授業中の話を聞くのを待つようになりました。
僭越ながら一つアドバイスできるとしたら、5年生までは国算を中心に学習し、理社は6年生から集中して取り組めば追い付けます。最終的には国語の読む力が算数、理科、社会にも活かされました。難関校の過去問を解いた時に知識だけではなく、その場で考える力が問われており、そのようなことを意識しながら、楽しくカードゲームをしたり、本人の好きな本を自由に読ませる時間を持つのが一番の近道だと思います。
テストが上手くいかなかった時は、親よりも子供の方が反省していると思いますので、温かく接してあげてください。出来た時は大いに誉めて喜び合うと、子供もまた次への挑戦が楽しみになります。私は「大いに喜ぶ」があまり出来ていなかったと反省し、中学生になった娘を大いに誉め、喜びたいと思います。
親も一人の人間で失敗も度々あります。その度にグノーブルの先生方に相談するのがおすすめです。様々な引き出しをお持ちなので、何らかの解決法を教えてくださります。中学受験の結果が本人の希望が叶わなかったとしても、学んだ様々なことは中学、高校、大学にも続いていくと信じております。結果が全てではなく、子供と一緒に頑張れた時間が一番大切で価値あるものだと学びました。親も3年半、学び、悩み良い時を過ごせた場所です。来年受験生の皆様、小学校最後の時間を大いに学び、楽しんでください。陰ながら娘と応援しております。

自分が積み上げてきたもの
女子学院中学校進学Fさん
私は新4年生の時にグノーブルに入塾しました。初めてグノで受けた国語の授業がとても印象的で、ここは自分にピッタリだと感じたことは今でも覚えています。
5年生の後期に、女子学院の生徒会主催の学校説明会に行き、グノに入りたいと思った時のようなピタッとくる何かを感じ、女子学院を目指すようになりました。皆さんもたくさんの学校見学に行くと思いますが、自分が感じたその学校の雰囲気や直感を大切にし、目指したい学校を見つけてみてください。
私は特別なことをしていたわけではないですが、大切だと思ったことを書いておきたいと思います。少しでも皆さんのお力になれたら幸いです。
🔳国語:私は読解で苦労することはあまりありませんでした。なので、授業で出た記述の解き直しをガッツリやるなどはしませんでしたが、読解のテキストは読んでいました。これは全教科に共通することですが、入試では取れるべきところをいかに落とさないかが重要だと思います。なので、漢字や知識では確実に点が取れるよう、詰めておいた方が良いと思います。
ちなみに、私は「漢字道場」を通常授業のテストの前に2~3回、1月くらいからはもう1周し、間違えたところをピックアップして、できないところがなくなるまで繰り返しやりました。知識は、通常のテキストの最後の方のページに載っているものを完璧にしていました。そして、女子学院ではよく語彙が出るので、日曜特訓などで配られる語彙力プリントもやった方が良いと思います。
🔳算数:通常のテキストがとても大事だと思います。過去問や入試問題を解くことも大切ですが、早くから始めすぎて通常授業での基本がおろそかになっても応用問題には対応しにくいと思います。逆に、4、5年生からやっている基本的なものが身についていれば、それを使いこなして応用問題にも立ち向かえると思います。なので、通常の復習は4、5年生のうちは2~3回は必ずやった方が良いと思います。6年生は時間に余裕がなくなってきますし、特に夏期講習は毎日復習テストもあります。ですが、通常の場合は不安なら間違った問題だけ2回、自信があるなら間違った問題を1回のみやり、夏期講習の場合は帰ってきて1回、次の日行く前にもう1回と、最低2回はやった方が良いと思います。夏はやりこむことが本当に重要だと思います。9月から始まる日曜特訓では、私の場合、授業点は悪かったです。でも、家での復習は欠かさず、次回の復習テストは満点を取るつもりでいました。話が長くなりましたが、分からないところがなくなるまで先生に質問し、復習し、丁寧に字を書くことが大切です。
🔳理科:本当に苦手でした。でも、私がそうだったように、ギリギリまで伸びます。なのであきらめないで算数と同じように質問し続けてください。先生は分かるまで教えてくれるはずです。
🔳社会:4教科の中では得意でしたが、ひたすら、ひとつひとつ丁寧にやるだけだと思います。公民ではややこしいものもあり苦労しますが、歴史は関連づけて年号も覚えて、地理は白地図に書けるレベルにすると良いと思います。
私は1月26日に熱がでて、3日間下がらず、直前は何もできませんでした。2日校の過去問などは1年分しかできなかったです。でも平常心を保ち、今まで積み上げてきた力、グノを信じて臨み、受験した全ての学校から合格をいただくことができました。
皆さんもグノで積み上げてきた力を信じて臨んでください。絶対に大丈夫です。
皆さんの合格を心からお祈りしています。
大切にしてきたこと
女子学院中学校進学Fさんの保護者様
1月26日。最後の日曜特訓から帰宅した娘は開口一番「具合が悪い」でした。2月1日まで残り5日。その日に感じた恐怖は、例えようのないものでした。結果的に娘は腸炎にかかり、3日間熱が続き、腹痛がある中での受験となりました。
高熱でベッドで横になりながら涙をポロポロこぼし「こんなんじゃテストを受けられない。もうダメだよ。受からない」という娘の悲痛な叫びに、私もただただ一緒に泣くことしかできませんでした。為す術がないということは、とてもつらいです。ケガも含め、どうか体調にはお気を付けください。
しかし、そのような体調、精神状態の中でも、第一、第二志望両校から合格をいただくことができました。ナゼなのか。私見ではありますが、今までの授業の積み重ねと、頼りになる先生方がいてくれたからなのではないかと思っています。
熱が下がってからの残り3日間も、最後の土曜特訓、日曜特訓で先生から指示が出ている箇所の復習。出席できなかったラストの文系授業のテキストをやることにしました。
特に第二志望の学校は、算数と理科の過去問を1回しか取り組んでいなかったので、過去問に取り組むことも考えましたが、今までも先生の指示(親は保護者会で、娘は授業で)に基づいて、授業を大切に取り組んできていたので、最後まで授業をやり切ることを娘と相談して決めました。
そう決断したのは、普段から真摯に対応してくださる先生方への信頼があったからです。
算数と理科は何度となく質問を。国語と社会の過去問では、一般的な解説とは違う、娘のためのとても丁寧な解説をしてくださいました。
受験に挑めるのは、決して本人の努力だけではないということを娘も感じていたからこそ、授業を蔑ろにしたくないと思ったのだと思います。
このように、我が家は先生方にたくさんのお力添えをいただきながら、授業を中心に取り組んできました。これから受験を迎える皆様も、ご家庭に合った学習スタイルを見つけ、後悔のない受験となることを心からお祈りしています。

楽しかった塾生活
女子学院中学校進学Gさん
私は1年生の夏からグノーブルに通っていました。算数が特に好きでした。難しい問題を解けた瞬間が好きで、算数は苦だと感じることなく勉強をしてきました。
私が受験直前期にやって良かったことを書きます。
■国語:漢字と知識
■算数:ミスに注意しながら計算
■理科:グノラーニングチェックや「基礎力テスト」で基礎を固める
■社会:基本を入れなおす
最後の1週間は特に苦手教科に力をそそぎました。
私は1月校では良い結果を出すことができませんでした。でも「受けなければ受からない」と思い最後まであきらめずに挑戦しました。受験中は「自分ができない問題はみんなわからない!」と思い込みました。
グノーブルでの塾生活は本当に楽しかったです。楽しんで勉強すればきっと良い結果に結びつくと思うので、とにかく先生のことを信じて最後まで走り抜いてください。祈、合格!
娘の成長を感じることができました
女子学院中学校進学Gさんの保護者様
娘はグノーブルでは長い間大変お世話になりました。楽しく、そして少し緊張感のある授業と、悩んだ時、不安な時は的確なアドバイスで助けてくださった先生方には心から感謝しております。
朝の苦手な娘をなんとか朝型にさせたのは1月からでした。この期間特に家族で気を付けていたことは
1.勉強に口出しをしない
2.親子ゲンカをしない
3.娘に小言を言わない
4.22時には寝させる
5.今まで以上に意識して家族仲良くする
この5点でした。
娘の精神面が崩れると勉強のパフォーマンスが下がるので、それは一番もったいないと思い、精神的にフラットでいてもらうように努めました。
決して余裕のある成績ではありませんでしたが、最後の30日間は、自分なりに計画を立て、苦手教科に力を注いでいたようでした。
「これでダメなら自分の責任。やるだけやったからもうこれ以上時間はいらない。」と言って本番を迎えていました。
当日は体調が万全ではありませんでしたが、今までにないくらいの集中力が出たらしく、不思議な感覚だったようです。
世間では中学受験に対して賛否両論あるようですが、我が家では家族で多くの体験ができ、娘の成長を感じることができたので、挑戦して良かったと思っています。
最後に、先生方、娘をここまで支え導いてくださり、本当にありがとうございました。

最後まで諦めない
女子学院中学校進学Hさん
「もう落ちたわ…」これが、女子学院の受験が終わった直後の私の心情です。絶望的な結果で、私はもう完全に落ちたと思っていました。しかし、逆にもう確実に落ちたのだからと気持ちを入れ替えられました。そして2月2日の午後に受験する学校に行く途中の電車内で、家にいた父からなんとなんと「受かってたよ」と電話がきたのです!こうして2月の受験校はたったの1つで、私の受験は全勝で終了しました。
私はずっと本が大好きで、勉強しないで本を読んでばかりいました。けれど、父に言われていた通り、6年生の夏から苦手分野の苦手単元だけをやる特訓をしたり、1月にも基本的な問題や大事な暗記ものなどをたくさんやって頑張って追い上げたら、模試では合格可能性が最大40%、C判定だった私もなんとか第一志望に合格できました。
このため、これを読んだ皆さんも、いくら成績が振るわなくても、本番で手応えが無くても、自分がこれまでやってきたことと、その学校と自分との縁を信じて頑張ってください!祈・合格!
田園調布学園中等部
自分を信じて
田園調布学園中等部進学Aさん
私は4年生の5月からグノーブルに通い始めました。クラスは中間にいて、初めの頃は国語が得意教科でしたが、それ以外は全くできていませんでした。
さまざまな学校の見学に行きましたが、良いと思っても条件が合わなかったりしてなかなか志望校が決まりませんでした。結局、第一志望が洗足学園中学校、第二志望が田園調布学園中学校になりました。志望校は決まったものの、レベルに大きな差があり、グノーブルの先生方にも「この間の志望校があれば良いのにね」と言われていました。それ以外に行きたいと思える学校がなく、2校しか受けないと決めていましたが、直前で最初少し行きたいと思っていた中央大学附属中学校も受けることにしました。
🔳国語:まずは授業をしっかりと受けて、漢字のテストは高得点を取れるようにしていました。帰ってから、親にその日の問題の文章の内容について感想を述べたり、見直してみたりすることもおすすめです。4年生のときは、毎回の授業でもう一度記述を全て解き直し、先生に提出していました。
🔳算数:6年生になるとテキストも難しくなり、1問により時間がかかるようになりました。基本の確認もあり、宿題も多くなります。私はわからない問題を解けるようにするために、解き直した次の日、1週間後、1カ月後、とどんどん期間を長くして、できるようになるまで何度も同じ問題を解いていました。「基礎力テスト」は6日ごとに同じジャンルの問題が繰り返されているので、解けない問題があった日の6日後の同じ問題にマーカーをして、前回解けなかった問題を解けるようにしていました。
🔳理科:6年生では、確認シリーズやグノラーニングチェックなど、直前期になるとたくさん配られるので、何度も復習することができます。間違えたところを何度もやって解けるまで繰り返すことや、わからないところは4、5年生のテキストに戻ってもう一度確認したりすることが大切です。
🔳社会:土曜特訓で配られる基礎力確認問題を、口答でも良いので何度か繰り返したり、地図帳などの資料を読み返してみたりしていました。復習テストなどの授業内テストで高得点を取れるように、帰宅後に授業の復習を行うことをおすすめします。
【試験当日について】
🔳持ち物:お菓子…試験の休憩時間で食べられるように持ってくることをおすすめします。私のおすすめは干し芋です。糖分も補給でき、少しお腹が満たされます。でも、少し手がベタつくので、ラムネやチョコレートなどさっと食べられる物もおすすめです。
・テキスト…普段見慣れたノートや資料集などを持っていくと良いです。また、志望校の赤本で最初のページ(問題の傾向が書いてあるページ)を読み返すことも重要です。
【直前にしておくこと】
🔳算数:「G脳ワークアウト」で自分の苦手な単元を中心にやりました。
🔳国語:漢字を絶対に落とさないように「漢字道場」を使って復習しました。
🔳理科、社会:知識を最後まで詰め込みました。
いつでも味方になってくれるのは自分です。最後まで自分を信じてがんばってください。応援しています。皆さんの受験に少しでも役立てばうれしいです。
豊島岡女子学園中学校
授業を大切に
豊島岡女子学園中学校進学Aさん
私は、新4年生の2月からグノーブルに入りました。体験授業を受けたときにグノーブルに入りたいと思ったのが理由です。
🔳4年生:最初は一番下のクラスであるα2でした。授業を楽しく受けて、復習テストで満点を取れるように、指示されたことをしている程度でした。国語が苦手で、語彙力を上げるために辞書をすぐ引くということを最後までしました(最終的に、最高偏差値と最低偏差値の差は30ありました)。また、ケアレスミスはなくなりませんでした。クラスは大体α1かα2で、本当にたまにαという感じでした。また、色々な学校のイベントに参加しましたが、どの学校も良い! と思ってしまい、志望校がなかなか決まりませんでした。
🔳5年生:αに入れた際に他の子達の頭の良さに圧倒され、αに入りたいと思うようになりました。それでも、4年生のときとあまり変わりませんでした。
🔳6年生:土曜特訓が始まり、勉強する時間は増えたものの、習い事はまだ続けていました。第1志望校を豊島岡女子に決めたのは6月くらいでした。後期に入り、日曜特訓が始まったり過去問を解くようになってから、成績が上がり始めました。豊島岡の過去問は、最初全然できなかったのですが、(特に算数は) 先生が詳しく教えてくださり、最後はできるようになっていったのがわかりました。また、めったに国語の記述で丸をつけない先生から丸をつけてもらったことは、すごく嬉しかったです。
1月校では大問を一つ落としたり、算数と理科が難しかったりして落ちたと思ったこともありましたが、どちらの学校も受かっていました。感覚はあてになりません。また、第2志望校が最後まで決まらず、1月にやっと決めました。
私は2月2日と3日の豊島岡女子はどちらも落ちてしまいました。それでも「絶対受かるから」と自分に言い聞かせて2月4日の試験に臨みました。合格でした。
グノーブルの授業が受けられなくなってすごく寂しいです。それくらいグノーブルが好きだったのだなと終わってから思いました。集中して授業を受けることが一番です。皆さんも諦めずに頑張ってください。
信頼する先生と楽しい友達との出会い
豊島岡女子学園中学校進学Aさんの保護者様
3年生の2月からグノーブルにお世話になりました。入塾するにあたり他の塾も検討しました。グノーブルの体験授業を受けたあとの本人の楽しそうな様子を見て、迷わずグノーブルを選択したことは、中学受験を終えた今、間違っていなかったと思っています。
習い事を続けたかった娘にとって、通塾回数が他の大手塾と比較して少ないことも、通塾の決め手となりました。6年生の最後まで楽しそうに通塾することができたのは、信頼できる先生、良い友達に恵まれたお陰です。
4年生から6年生まで共通の先生から少人数制クラスで授業を受けることができたのは幸運でした。娘の特性を理解してくださり、最後の最後まで精神的な面も含めてサポートしていただけました。保護者に対しては、受験校の選定や6年生以降の勉強の仕方などについて、説明会・面談の際に適切なアドバイスをいただけました。
豊島岡女子を第一志望に決めた際には「3回の受験をセットですべて受けて合格するつもりで」とアドバイスをいただいたお陰で、親も本人も諦めず、粘り強く3回目で合格を勝ち取ることができました。6年生の春の時点では豊島岡女子は厳しいかなと思っていました。6年生になり、少しずつ自宅での勉強への取り組み方も良くなってきていましたが、「まだ、本気を出していない」という本人の発言の通り、夏休みの自宅での勉強も安定しない様子がありました。初めは静観していたものの、6年生秋終盤についにしびれを切らした父親が、これまで塾のお迎えしかしていなかったにもかかわらず、付け焼き刃で急に勉強に口を出し始めたところ、(今考えれば当然の結果ですが)娘の反発を受けて、うまくいきませんでした。そこで定例の面談以外で初めて塾にご相談させていただいたところ、すぐにご対応いただき、先生からの直接本人への適切な声がけをしていただき、直前期には授業外で過去問を見ていただくことができました。信頼する先生からサポートしていただけたことは、本人にとって大きな力になりました。
塾が終わったあとに、仲の良いお友達と楽しそうにおしゃべりしながら歩いてくる姿を見ることができなくなり寂しいです。グノーブルで楽しく学ぶことができた経験は、彼女の今後の人生にとって貴重な財産であると確信しています。これからは、新しい環境で良い出会いに恵まれ、さらに発展した勉強を楽しんでほしいと思っています。最後になりますが、3年間誠にありがとうございました。

グノを信じて頑張ってください!
豊島岡女子学園中学校進学Bさん
私は新4年生の時に入塾しました。最初は勉強へのやる気が出なかったのですが、5年生のとき学校見学に行き、志望校が決まってからは勉強に主体的に取り組むようになりました。
日曜特訓では女子学院コースでしたが、女子学院コースの問題を解くことで、問題を解くスピードがあがり、豊島岡の過去問の点数も良くなりました。社会の暗記が苦手で、夏の年号テストではとても苦労しました。せっかく覚えたのに冬にはほとんど忘れてしまい、1月の直前期に覚え直しました。これは入試でも役立ったと思います。算数は、写し間違え、時間配分、計算ミスがなかなか直らず、冬期講習の算数昼テストで40点台を2回連続で取ってしまったこともあります。その時先生から教えてもらった「答えを入れてみて条件が成立するか?」「解答欄に書く前に問われていることをチェックする」を意識して解くと、最後の日曜特訓では夢の90点台を取れました。入試直前に自信を持つことができたと思います。
また、先生から「豊島岡は3回試験があるのが良いところ。得意な回が必ずある。受ける時は前の科目のことは忘れて、目の前の問題を集中して解く!」と言われて、安心して受験することができました。
2月2日1回目の試験で合格できた時は、あとからあとから実感が湧いてきて、本当に嬉しかったです。
教えてくれた先生、楽しい授業とアドバイスをありがとうございました。両親へ、いつも隣で支えてくれてありがとう。最後に後輩のみなさんへ、グノを信じて頑張ってください!
中学受験をして良かった
豊島岡女子学園中学校進学Bさんの保護者様
3年生の秋にグノーブルの入塾テストを受け、理科の体験授業を受けた娘は、「この塾に通う!」と即決でした。
小学校生活の半分を中学受験に注ぐということは、子供に大きな負荷がかかります。最後は笑顔で「受験して良かった!」と思える挑戦にしたいと思っていました。そのため、偏差値だけではなく、幅広く学校見学に行きました。これが6年生になってからの併願校選びに役立ちました。一部の学校は校内に入れる機会が極端に少ないため、チャンスを逃さずお子さんと一緒に学校見学や文化祭に行くことをおすすめします。
6年生の夏期講習直前のグノレブで、過去最低の偏差値を出してしまい、親子共にかなり落ち込みました。その時先生から「できている所をみてください」とアドバイスいただき、ハッとしました。できない所ばかり気になりますが、「絶対に這いあがる!」と昇降のたびにクラスをあげる娘を見て、「親が安全に走ってはダメだ。挑戦する気持ちを後押ししてあげたい」と思い、相談して第一志望校を豊島岡に決めました。
成績の浮き沈みは最後の最後までありましたが、悪い時はなるべく早く寝て忘れる。良い時も喜びすぎない。娘は良い時のほうが「次取れなかったらどうしよう」と不安になる様子だったので、なるべく平常心を心掛けました。勉強のことは先生にお任せして、親は体調管理とプリント管理に徹しました。先生がコーチ、娘は選手、親はマネージャーのようなバランスを意識したのが良かったかもしれません。
また、3年間を通して言えることなのですが、グノーブルのカリキュラムに頑張ってついていくことで、着実に力がつくと思いました。テキストはグノーブルのものだけ使用し、(正確には他のものを使う余裕がなかったのですが)過去問も各教科の先生が添削してくれました。先生からのコメントはとても嬉しかったようです。
6年生の秋に体調を崩し、2週間授業を休んだ時も「元気になってからで良いですよ」と先生からアドバイスをいただきました。子供によって一番良い勉強方法は違うので、塾の先生に相談することが一番の近道だと感じました。
入試の前日も、結果を待っている時も、「私はもうやり切った!」と満足そうな娘の姿を見て、3年間のグノーブルで、試行錯誤しながら少しずつ成功体験を積んできた、その自信からくるものだなと実感しました。
目標だった豊島岡含め、全ての学校に合格をいただくことができました。お世話になった先生方には本当に心から感謝しています。ありがとうございました。
グノーブルのさらなるご発展と後輩の皆様の大勝利を祈っています。

4年分以上の感謝
豊島岡女子学園中学校進学Cさん
私は3年生でグノーブルに入塾しました。受験自体は2年生のころから考えており、学校でもグノーブルでも、その時は優秀な生徒、いわば優等生だと思われていたように思います。もちろんテストはほぼ毎回満点で、グノレブテストでも首位を守り続けていました。全国模試でも100位以内に入るのが当たり前、といった風に、周りからすれば優等生でした。
ただ、4年生の前期から壁を感じ始めました。「算数の式を書かなかった」ことが主な原因でした。先生の言うことを疎かにしました。首位の座で慢心していたのです。自業自得と言っても良いような成績になりました。5年生で気づいたころには、時すでに遅しといった感じで偏差値が急に転落。真ん中のクラスに入れるかどうかも怪しくなりました。だんだんと成績が不安定になっていき、後期で遂に自分も危機感を抱き始めました。
そこで、式をとにかく書くようにしました。しかし、やはりそれだけではわからないものもあり、先生方に積極的に質問しに行くようになりました。質問はいつでも受け付けてもらえるようになっていて、質問がしやすく、積極的に質問に行きました。質問することでさらに問題に対する理解が深まり、偏差値も上昇し始めました。グノーブルは少人数なので、クラスの仲間の絆も深まり、また1位を目指してライバル同士で競えるのは新鮮で面白いと思えるようになりました。
6年生になると、ついに志望校を固めなければならない時期がきて、回復したとは言えまだまだ第一志望校には程遠い偏差値と偏差値表を見て唸ったことや、先生方が一生懸命志望校を考えてくださったことがまだ鮮明に記憶に残っています。だんだんとテキストが難しくなり量も増えていく6年生でも、先生方の授業が面白かったことで、勉強が楽しいと思えるようになりました。塾に行くことが楽しくなり、量や難易度を苦に思うことはなくなりました。
迎えた受験本番は1月から始まりました。全ての学校で「合格」の文字を見た時は安堵と不安が混じりあった気持ちでいました。1月最後の日、電話がかかってきました。グノーブルの先生方からの電話で、私に激励の言葉をかけてくださいました。私はそれだけで安心することができ、迎えた2月1日も見事合格し、2月2日、豊島岡女子学園中学校に挑戦しました。1回目は合格には至りませんでした。算数が半分以上空欄でした。これまでにない不安を抱えましたが、先生の助言と激励(そして見返した「お守りカードブック」)により決意を固めて、2回目である3日の朝、受験会場に向かいました。
3日夜、私の受験番号(豊島岡は番号発表形式)を見た時は喜びがあふれ、報告の電話をするときも電話を持つ手の震えが止まりませんでした。
最後まで伴走して寄り添ってくれて、質問にも親切に答えてくださった先生方には感謝の気持ちしかありません。もう1回グノーブルに通い直したいくらいです。受験を支えてくださった先生方、本当にありがとうございました。
全勝への道
豊島岡女子学園中学校進学Cさんの保護者様
私がグノーブルを知ったきっかけは、とある駅に貼ってあったポスターでした。そこには私の中学高校時代の恩師の名前が載っており、恩師がグノーブルという塾を立ち上げたことを知ったのでした。
それから数年後、娘が中学受験を強く希望するようになりました。医学部へ多数進学する難関校に入りたいという娘の強い希望があったため、私が通っていた塾の雰囲気に近いグノーブルへ入塾を決めました。
恩師の件もあり、グノーブルは面倒見が良い印象がありましたが、実際に娘が通ってみるとまさにその通りでした。また、塾では気の合う友達も多くできたため、塾に通うのが楽しかったようです。先生方は、一時成績が低迷した娘を気にかけてくださり、6年生の日曜特訓のコース選択に関しても大変親身にご指導いただきました。
おかげさまで、受験校全てに合格という想定していなかったミラクルを達成いたしました。
合格した受験校は全て本気で娘に通わせてあげたいと思っていた学校であり、当初の不安とは全く別の問題に悩まされたのは、グノーブルのおかげといっても過言ではありません。4年間、本当にありがとうございました。

中学受験が深い教養を身につける土台になる
豊島岡女子学園中学校進学Dさんの保護者様
グノーブルには、新3年生の2月から4年間お世話になりました。他の塾を利用したのは模試のときだけで、市販のテキストなども使用しませんでした。そのため、娘はまさにグノーブルで「純粋培養」されたと言っても過言ではないかもしれません(笑)。
4年間を振り返ると、3年生の頃は週1回の通塾で、娘も楽しんで通っていました。4年生になると一気に中学受験モードに突入し、戸惑いもありましたが、3年生の時点で「塾に通うこと」「塾の宿題をこなすこと」「定期的にテストを受け、成績が出ること」に慣れていたため、比較的スムーズに移行できました。このために3年生から通塾を始めたので、まさに狙い通りでした。5年生になると、勉強につまずくことがあり、反抗期も始まり、家庭学習に苦労する場面もありました。
6年生では土曜特訓が始まり、家庭での学習量も増やす必要がありましたが、娘の家庭学習時間はさほど増えませんでした。しかし、春から夏にかけて成績は右肩上がりに上昇。6年生後半も、過去問を解いたり模試を受けたりしながら、ひたすらグノーブルの課題をこなす日々を送り、本番を迎えました。
その結果、受験したすべての学校に合格することができました。期待以上の結果が得られたのは、グノーブルのスパイラル型カリキュラムが娘に合っていたからだと思います。毎週の復習テストに向けた学習と、グノレブテストの前にその範囲の復習を行うだけでしたが、暗記系科目や苦手な単元も、何度も授業やテストを繰り返すうちに自然と知識が定着していったようです。グノーブルでは、目の前の学習を最優先することが最も効率的で効果的なのだと実感しました。
とはいえ、これは結果論でもあります。特に6年生になってからは娘の家庭学習の様子を見てはやきもきする日々でした。必須とされている課題もすべてをこなせていたわけではなく、「いつか成績が急降下するのでは」と常に不安を抱えていました。
そんな私をいつも励ましてくださったのが、グノーブルの先生方です。面談時には「私はあまり優しいことを言わない人間ですが、娘さんは大丈夫です。授業中の様子や問題への取り組み方を見ていればわかります。例えば…」と、娘の塾での様子を具体的に伝えてくださいました。「でも、先生は娘の家庭での姿をご存じないから…」と思いつつも(笑)、多くの生徒を指導されてきた先生の言葉を信じることにしました。
家庭学習の時間があまり多くなかった娘が6年生になって成績を伸ばせた理由を考えると、やはり塾での集中力によるところが大きかったのだと思います。6年生になると塾での学習時間が増え、その分が成績向上につながったのかもしれません。6年生後半は、日曜特訓や冬期講習、正月特訓が加わり、ますます忙しくなりましたが、何よりも「最後まで塾に通いきること」を最優先に、体調管理に努め、ストレス解消の時間も大切にしました。
そして、無事に最後まで走り抜けました。何度「早く受験が終わらないかな」「もう中学受験なんて嫌だ」と思ったことか…。それは、親である私の方が、です!(笑)
受験を通じて、娘だけでなく私自身も多くのことを学びました。一緒に勉強をし、過去問を解く中で、中学受験の学習が深い教養を身につける土台になることを改めて実感しました。これからの中高6年間、娘には自らの意思でさまざまなことに挑戦し、努力してもらいたいと思っています。そして、それができる環境の整った学校へ進学します。中学受験勉強は親も子も大変ですが、それだけの価値があると強く感じています。
最後に、ここまで娘を導いてくださったグノーブルの先生方の温かいご指導とサポートに、心より感謝申し上げます。
フェリス女学院中学校
フェリスを目指して
フェリス女学院中学校進学Aさん
私がグノーブルに入塾したのは、新3年生の2月でした。入塾する前に参加した体験授業がとても面白く「ここで授業を受けたい」と思い、入塾を決めました。塾に入ったばかりのころは、算数の授業にまったくついていけませんでした。しかし、たくさん授業を受けていくうちに、今までの授業の内容も理解できるようになりました。
5年生の時は、今までよりも勉強の量が増えたので、とても大変でした。6年生の時よりも大変だったのではないかと思うほどです。グノレブテストでは、ケアレスミスや転記ミスで合計30点ほど失点することもあったので、成績が低迷していました。
志望校を決めるまでに、たくさんの学校の文化祭や説明会に行きました。見学をしているうちに、女子校でキリスト教系の学校が自分に合っていることに気が付き、その中でも、フェリスがとても良い学校だな、と直感で思いました。
フェリスは生徒の雰囲気が良くて、カイパー記念講堂のステンドグラスがとても素敵で、ここに通いたいと思いました(制服もとってもかわいいです!)。
6年生になって日曜特訓のコースを決める時に、やっぱりフェリスを目指したいと思いました。フェリスの算数は、思考力が問われる問題が多いのですが、私は算数が得意なわけでもなく、グノの先生には「フェリスの算数の対策は大変だよ」と言われました。でも、算数が難しくてもフェリスを目指したい気持ちが強くあったので、フェリスコースに入りました。
日曜特訓では、国語の授業でフェリスの過去問をたくさん解きました。フェリスの国語は200字記述があるので、過去問をやることで200字記述にも慣れていきました。算数は、フェリス対策の算数プリントが毎回配られて、そのプリントを解いていました。算数のプリントがとても難しく、同じ問題で2回質問に行くこともありました。理科は典型的な記述だけでなく、思考力が試される記述もありとても大変でした。私は「水溶液」などの計算系も苦手だったので、本当に苦労しました。社会は他の科目に比べて得意でした。フェリスは統計データの問題がよく出題されるので、統計データの知識をたくさん覚えました。
入試は緊張しましたが、暖房もよく効いていたので、集中して試験を受けることができました。入試当日は、最後の科目の理科で時間配分を間違えてしまい、大問二つをほとんど問題文を読まずに解きました。理科の試験が終わった時、もうだめだ、と思いました。でも、苦手な算数の手ごたえがあったので、そのあとの人物考査は気持ちを切り替えて挑むことができました。
フェリスの入試においては、休憩時間はあるものの、試験監督がすぐに問題用紙を配付するので、参考書を読んだりする時間はありません。気を付けてください。
最後に信じることができるのは、今まで自分がやってきたことと、その学校に行きたいという気持ちです。合格を目指して頑張ってください。応援しています。
フェリスに入りたいという意志が原動力でした
フェリス女学院中学校進学Aさんの保護者様
娘の中学受験は、元々中学受験をすると決めていたわけではなく、やってみようかという軽い気持ちでのスタートでした。そんなスタートだったので、先取りはまったくなし、中学受験の知識も情報もなしという状況で、新3年生の2月にグノーブルに入塾しました。
娘は入塾当初からとにかく算数に苦戦しました。算数のテキストを解くのにも時間がかかり、日々の家庭学習の割合はほとんど算数が占めていました。ケアレスミスの多さにも長い期間悩みました。計算ミス、転記ミス、図に書き込む数字を間違える、比を逆に書くなど、何度注意してもなくなることはありませんでした。ようやくケアレスミスが減ってきたのは、6年生になって過去問を解き始めた頃だったと思います。過去問の点数が受験者平均、合格者最低点に足りないという状況を娘が自分事としてとらえることができて、やっと集中して解けるようになっていきました。
志望校選びについては、ある学校説明会で入試担当の先生が「女子は学校の雰囲気を肌で感じます。必ず本人が学校に足を運んで選んでください」とおっしゃっていたことが印象に残っており、なるべく娘と一緒にたくさんの学校に足を運ぶようにしました。今回ご縁をいただいたフェリスもまさに「肌で感じて選んだ」学校でした。
たくさんの学校をまわっていくなかで、私は中高6年間で人としての基礎を築くことに重きを置く学校に魅力を感じるようになり、娘も同じように感じている様子でした。またグノーブルの先生に志望校の相談をした際、娘には情操教育が手厚い学校が合うのではないかと言っていただいたことも大きな後押しとなりました。
娘はフェリスの校舎や生徒の雰囲気に強く惹かれ、6年生の夏頃に第一志望校として目指すことを決めました。そして、9月から始まった日曜特訓ではフェリスコースに入り、本格的に志望校対策を始めました。
日曜特訓では案の定、算数に苦しみました。はじめのうちは日曜特訓のテキストもほとんど解ける問題がなく、こんな状況で本当にフェリスを目指していて良いのだろうかと非常に心配でした。ですが当の本人はくじけることなく、テキストに向き合っていました。日曜特訓が始まってからは、通常授業や土曜特訓の算数テキストはほぼ手が回らず、できる日があれば復習する程度でした。とにかく、日曜特訓のテキストをやりこみました。算数の過去問の点数も伸び悩んでいましたが、親の目から見ても、手ごたえを感じるようになってきたかもと思えたのは、冬期講習が終わった頃だったかと思います。
いよいよ迎えた1月入試では、過去問ではしっかりと得点できていた学校で不合格となり、まさかの黒星発進となりました。幸い、同じ学校を再度受験した際に合格をいただいたのですが、合格をひとつ取ることの大切さは想像していた以上に大きく、合格をいただいてから娘もやっと不安から解放されて、安心して 2月入試に向かうことができました。つらい経験でしたが後々考えると、この不合格の経験があったからこそ2月の結果が出たのだと思います。入試に絶対はないということ、慢心してはいけないということを、娘は身をもって感じたのだと思います。1月入試終了後からの集中力は目を見張るものがありました。
そして2月1日。緊張しながらフェリスへ向かいました。私はどうやって娘を送り出そうか、いろいろと思案していましたが、娘は「行ってくるね」とあっさり入試会場へ入っていきました。私は拍子抜けしましたが、娘は変に力むことなく臨むことができていたのだと思います。フェリスの入試が終わり、娘と合流しましたが、娘は出来について何も話さなかったので詮索はせず、他愛ない会話をしながら昼食を取り、1日の午後校へ向かいました。入試期間中は睡眠時間をしっかり取らせたかったので、午後校受験を終えて、帰宅後は復習や確認など何もせず早くに寝かせました。夜に午後校の発表があり、主人と一緒に合否照会サイトの合格の二文字を見て喜び合いました。
2月2日。朝に1日午後校の結果を娘に伝え、喜びいっぱいで2日校へ臨むことができました。フェリスの結果は2日の午後に発表されることになっていましたが、2日の午後校前に結果を知るのが怖いという娘の意見で、フェリスの結果は午後校へ送り届けてから見るということに決めていました。無事、午後校へ送り届け、主人と合否照会サイトを開きました。私たちの目の前にピンクの画面の合格の二文字が現れました。あの瞬間は一生忘れることはないと思います。午後校の試験を終え、出てきた娘を急いでピックアップし、合格の画面を見せました。「やったー!!」と喜ぶ娘を見て、努力が報われて本当に良かったと心から思いました。
2日もありがたいことに午前午後ともに合格をいただき、フェリスの合格をもって娘の中学受験は終了。3日以降は受験しませんでした。
娘は決して余裕があってフェリスに挑戦したわけではありません。グノーブルでの偏差値も十分ではなく、模試の合格可能性も波がありました。ただ娘はフェリスに入りたいという強い意志を持っていたので、最後はその気持ちが大きな原動力となり、走り切ることができたのではないかと思います。
グノーブルで過ごした3年間はとても濃い時間でした。中学受験は大変でしたが、娘は努力することや諦めないことの大切さをこの受験を通して経験することができました。これから先もこの経験を糧にしていってほしいと願っています。
最後に、娘がお世話になったすべての先生方、校舎の受付の皆さま、娘と仲良くしてくださった仲間の皆さんへ心より感謝申し上げます。行き詰まった時、校舎の先生方に相談しアドバイスをいただけたことは、本当に心強かったです。娘もグノーブルの先生方が大好きでした。また、仲良くしてくださった仲間の皆さんのおかげで楽しくグノーブルに通うことができました。本当にありがとうございました。

私の中学受験
フェリス女学院中学校進学Bさん
私は3年生の夏期講習から入塾しました。教科ごとの勉強法や直前期の様子を書きます。
🔳算数…苦手な教科でした。グノレブテストでも、外部模試でもいつも足を引っ張っていました。分からない問題が次から次へと出てくるので、私は友達に聞いてできるだけ分かるようにしました。日曜特訓のフェリスのテキストは、次の週までに3周やってテストに臨みました。直前期は、日曜特訓のフェリスのテキストをやり直したり、苦手な単元(立体切断、速さ、文字式など)を復習したりしました。
🔳国語…得意科目でした。特に毎回の文章を読むのが楽しみで、その中には、今でも私の愛読書である本や、続きを図書館で借りたりして読んだ本もあります。直前期は、一日25問以上ずつ「漢字道場」を母とともにやるのと、「知識の総確認ラーニングチェック」の語彙の部分を表にまとめてもらったものを見て語彙に触れることのみを行いました。記述問題は授業でできるだけ完成させて、家で取り組む量を減らしました。(授業を受けることで十分実力は身に付きます。)
🔳理科…苦手な教科でした。毎回の復習テストではいつも低い点数を取っており、また6年生の12月前半まで、知識がズタボロでした。フェリスは理科でも記述問題が出るので、典型記述はできるようにするといいです。直前期は特に苦手な単元(惑星、実験器具、凸レンズ、生物の冬越し、電流と発熱)などのグノラーニングチェック、理社特訓のスイッチ回路のプリントをひたすらできるようになるまでやりました。
🔳社会…得意科目でした。その中でも地理が特に好きで、習った場所へ旅行に行って知識を定着できたと思います。歴史と公民は最初苦手だったけれど、グノの演習問題で少しずつできるようになりました。直前期は、時事問題と夏期講習の統計データテストをやり直しました。
🔳直前期や本番の様子…私は試験前日まで本や漫画を読み続けていました。また、試験会場で見たほかの受験生が賢く見え、受からなかった時の予防線を張るようなマイナスなことばかり言っていました。でもそれは周りの人が苦しくなるので、できるだけ言わないほうがいいと振り返って思います。さらに、試験会場にタイマーがなかったので時間配分を間違えて、ある学校で理科の大問1が全く解けないことがありました。それを機に私はタイマーを使わず、時計を見ながら過去問を解くようにしました。試験後はやり切った感があまりなく、試験が終わったあとも「落ちてると思う。」を連発していました。
🔳フェリスの過去問について…私は国語が得意だったので、国語は1、2年しかやりませんでした。その分を算数に回し2015年まで解きました。理科と社会は30分ですごい量の問題を解かなければならないので、時間配分をつかめるまで取り組んだほうがいいと思います。
🔳皆さんへ…勉強をすることが苦しければ、漫画やドラマを見てもいいと思います。
それらから学び取れることはたくさんあります。ただし、グノの友達はみんな賢いので、その中で漫画、ドラマを見ながら、自分が上のクラスに位置するのは簡単なことではありません。少しずつでも努力すればそれは必ず力になります。だから、めりはりを大事にしながら、楽しく勉強することが、志望校合格の一番の近道です。頑張ってください。
娘の中学受験
フェリス女学院中学校進学Bさんの保護者様
「見守りに徹しましょう。これはご本人の受験です。今更お母さんが張り切って出てきても、本人がびっくりして調子を崩します」
6年生の夏の面談時に「今からでも親ができるサポートがないか」と相談した際に、グノの先生から掛けられた言葉です。その言葉通り、放牧スタイルで取り組んだ中学受験でした。
終盤で私が行ったことは、過去問のコピー・管理、「漢字道場」対決(1日25~50問程度)、国語の語彙の一覧化(「このテキストのこの部分を一覧にしてほしい」という娘からの指示を受けて)のみで、恥ずかしながら曜日ごとのテキスト構成や次の授業までの1週間で何をどの程度復習すれば良いかなどを明確に把握できないまま今に至ります。
娘は1週間の中で日ごとに何に取り組むかをざっくり箇条書きにして復習などに取り組んでいましたが、時間の見積もりが甘く、目標としているタスクが1日のうちで回しきれなさそうに見えることが時々ありました。その際は、状況を一緒に整理し、優先順位付けを行いました。
こんな私でも「これはしっかりやれた」と感じているのが学校見学です。立地やなんとなくのイメージ、偏差値にとらわれず、共学・女子校関係なく幅広く足を運び、少しでもポジティブな要素がある学校には娘も連れて行くようにしました。結果的に「どの学校も大好きだ!」と家族みんなで納得のいく志望校選びができました。
いつもはマイペースにのんびりしているように見える娘も、1月の埼玉受験を終えたころからは本番に向けての緊張からか、ネガティブな発言が目立つようになりました。フェリスは受験者平均点しか公開されておらず、合格者平均点や合格者最低点が非公開なため、どれだけ過去問を解いても達成感や自信を持ちづらかったことも影響したかもしれません。試験終了後も前向きな反応はなく、合格発表も「落ちていると思う」と言われながらの確認でした。無事良い結果が得られて本当に嬉しかったです。
習い事を細々と受験期まで続け、1月31日も含め登校をし、その合間に大好きな読書を続けながらもしっかり結果を出した娘を誇りに思います。放牧スタイルを取りながらも、急に不安なこと(乱高下するグノレブの結果を踏まえての勉強量・取り組み方、志望校選び、ネガティブ発言を娘に連発されたことなど)が出てくる度に話を聞いて励まし、前向きな言葉をくださった先生方、一緒に日曜特訓に通ったり、同じクラスやコースで切磋琢磨したりしたお友だちやその保護者のみなさんに心から感謝します。
これから始まる中学生活も楽しく見守ろうと思います。

最後の最後まで諦めないこと
フェリス女学院中学校進学Cさん
2月2日午後受験の学校に向かう途中、父から合格の電話をもらった時は信じられず、何度も父に確認しました。なぜなら、私のグノレブ平均偏差値は、フェリスよりおよそ10も下回っており、さらに模試での合格確率も最高で4割程度だったのです。
そんな私が合格をつかめた大きな理由は二つあると思います。一つ目は、日曜特訓で下のクラスから上のクラスになり、そこで刺激を得たからです。刺激を得たことによって自分の勉強法を変えたり、勉強への気合が入ったりしました。二つ目は、最後の最後まで諦めなかったことです。前日の1月31日には、フェリスに特化した勉強をしました。例えば200字記述の対策や、日曜特訓で行った問題で何度も間違えてしまったものに取り組みました。そのため、自信を持って試験を受けることができました。参考になるかわかりませんが、私が行って良かったフェリス対策を伝えます。
🔳算数:日曜特訓のテストで満点を取るくらいの気持ちで頑張りました。そのぐらいの気持ちで取り組んだ頃から、フェリスの問題形式にも慣れ始め、過去問の点数も上がっていきました。また、フェリスは途中式も見るので、字や式は丁寧に書くことを心がけました。他にも、解けなかった問題をバインダーに挟んで取り組みました。自分ができるようになった問題を目で見て確認できたので、モチベーションが上がりました。
🔳国語:私はしませんでしたが、4、5年生では毎週の復習テストで満点を取れるようにするとさらに良いと思います。また、毎回の授業できちんと解説を聞いておくことが大切です。なぜなら、家で復習する時に一から考え直すのではなく、先生の解説も踏まえた方が時間短縮につながるからです。配付される解説とは異なる視点で先生が説明をしてくださる時もあり、そのおかげで楽しく授業を受けることができていました。日曜特訓で毎回配られる語彙力プリントは取り組んだ方が良いと思います。なぜなら、語彙力が豊富な方が文章の理解度が深まり、圧倒的に有利だからです。また、フェリスでよく出る200字記述対策として、自分のエピソードを考えていた方が人物考査(面接の代わり)でも役立ちます!
🔳理科:フェリスでよく出る記述のことも視野に入れながら、毎回の授業で配られるグノラーニングチェックを何回も繰り返すことは重要でした。
🔳社会:社会の先生は豆知識も伝授してくださるので、授業を楽しく受けられました。その知識が過去問などの問題集にも出ていたので、授業を聞くことは大切だと思います。また、漢字の練習を怠らずにすることも大切です。
🔳全科目に共通すること:先生の授業をよく聞く。聞いたあとは先生の解説を踏まえ、自分でもう1度考え、反芻してみる。すると復習した時にスムーズに解くことができ、頭にも定着します。
試験が終わる最後の最後まで諦めずに頑張ってください!!祈・合格

私の中学受験
フェリス女学院中学校進学Dさん
私は4年生の頃から、フェリス生に強い憧れを抱いていました。こうして私が合格できたのも、グノの先生のおかげだと思います。これから、私が入試直前に思ったこと、入試の作戦、入試当日のことを書こうと思います。
フェリスの過去問は9月から始めました。一番苦手な理科でも、なぜか受験者平均を上回る年もあり、もしかしてフェリスに行けるかもしれないと有頂天になることもありました。しかし、そんな喜びとは裏腹に、算数がいつまで経ってもボロボロのまま。そんな状態のまま、埼玉受験で初めての入試を迎えることになりました。算数を解く前には「この問題が解けないなんて、フェリス志望生として失格だ」と思いこみました。するとスラスラと前向きに解くことができました。そう思うことを繰り返しているうちに、自分に言い聞かせて演技をしていればスラスラ解けるんだ! ということに気づきました。「フェリス志望生として失格だ」という私にとって大切なキーワードは、2月1日にも力を貸してくれました。緊張することなく、身構えることなく取り組めたのです。
2月1日の朝は、思ったよりも緊張しませんでした。ただ、最寄りの元町・中華街駅に近づくにつれて緊張が止まらなくなってしまいましたが、道端で見つけたものや風景について母とおしゃべりしながら、少しだけ遠回りしてフェリスに行ったおかげで、緊張をほぐすことができました。
私は算数の大問1を、たとえ最後の方の問題が解けていなくても残り3分で見直しをする!と決めていました。ただ、大問1の問題がとても多い場合は、時間を増やしたり調整をすると良いと思います。
人物考査については、それほど心配する必要はありません。2025年の人物考査は「感謝している人について」でした。このように質問は1問だけです。冬期講習でやる人物考査プリントをやれば絶対に大丈夫だと思います。
最後に、自分の成績にめげず、頑張り抜くことが本当に大切だと心から思います。合格率がたとえ低くても、不合格になるかもしれないと思わずに、頑張るためのバネにしてください。ある学校の校長先生が学校説明会で、受験当日まで学力は伸び続けるとおっしゃっていました。だから何があっても諦めないでください。来年の春にもたくさんの笑顔がグノーブルから溢れることを祈っています!
グノの先生方、勉強が嫌いだった私に勉強することの楽しさを教えてくださり本当にありがとうございました!

ありがとうございました
フェリス女学院中学校進学Eさん
私は新4年生の2月からグノーブルに通い始めました。フェリスを選んだ理由は文化祭に行った時に先輩方がとても親切に接してくださったこと、また、木の温もりが感じられる綺麗な校舎や大きな礼拝堂が印象に残って良いなと思ったからです。図書館には自分が興味のある本もたくさん置いてあり居心地も良く、この学校で学校生活を送りたいと思いました。
9月から日曜特訓のフェリスコースに通いました。テストの点数や授業の点数でクラスの昇降があったので大変でした。また、違う校舎の生徒もいて緊張しましたが、週を重ねるごとに仲良くなっていきました。
国語は過去問を多く解いて古い文章や200字記述に慣れるようにしました。また、過去問の解き直しノートを作り、先生に添削してもらいました。そのノートを本番直前まで何度も見直しました。算数では毎週ある復習テストで良い点が取れるように毎週復習を頑張りました。理科では知識が苦手だったので、グノラーニングチェックを何度もコピーして解きました。社会では授業で間違えた問題を重点的に何度も解き直しました。
本番では緊張せず落ち着いて解くことができました。最後の人物考査も日曜特訓で練習をしていたので冷静に考え取り組むことができました。
今は4月からのフェリス生活が楽しみです。いつも楽しい授業をしてくれた先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
雙葉中学校
雙葉への道のり
雙葉中学校進学Aさん
私は、6年生の夏に頑張った成果が9月にすぐ表れ、成績が伸びたことで少し浮かれてしまいました。その結果、10月後半から成績が下がり始め、そのまま低迷する時期が続きました。
ここでは、成績が低迷していた私が1月直前期に強化したことや、大切だと感じたことを書きます。
🔳算数:雙葉の算数では「速さの逆比」の問題がよく出題されるため、夏期講習の「速さ」の単元や、日曜特訓の算数テキストの解き直しを徹底的に行いました。
🔳国語:国語は語彙や漢字の知識をしっかり固めることが大切だと感じました。そこで、6年生の最後に、知識の総確認ができるテキストを繰り返し解きました。
🔳理科:雙葉の理科は比較的相性が良く、過去問でも得点できましたが、ミスした単元や苦手な単元は「グノラーニングチェック」で復習しました。
🔳社会:6年生後半のテキストにある記述問題を、毎晩寝る前に解くことを習慣にしました。時事問題が出題されることもあるため「時事234題」テキストを活用しました。
また、私はグノレブテストや外部模試で間違えた知識や漢字(算数以外)を5年生の初めからルーズリーフにまとめた「ミスノート」を作成していました。模試や本番に必ず持参し、直前まで見直していました。
【入試当日の経験】:入試当日、算数で必ず取りたかった小問のひとつが自信のない解答になり、試験終了後に「落ちたかもしれない」とショックを受けました。しかし、すぐに気持ちを切り替え、理科と社会に全力を注ぎました。結果的に、いつもより理科・社会で手応えがあり、合格することができました。前の教科で思うようにできなくても、気持ちを切り替えることが大切だと改めて実感しました。
グノーブルの先生方のアドバイスを信じて全力で取り組めば、今までの努力は必ず報われます! 受験生の皆さん、頑張ってください!
親子ともに最後まで頑張ることができました
雙葉中学校進学Aさんの保護者様
3年生の夏に入塾して以来、子どもはもちろん、サポートする母である私も、グノーブルの先生方に育てていただき、このたび無事に合格を勝ち取ることができました。心より感謝申し上げます。
特に心に残っている先生方の貴重なアドバイスを以下にまとめました。
・6年生の夏ではなく、5年生の夏にしっかり取り組んでおくと成績が安定する。
・算数のミスは、6年生の直前期に本人の合格意識が高まると自然に減少する。まずはミスを気にしすぎず、処理スピードを上げて問題数をこなすことを優先。女子の場合は、そのあとで途中式を書く練習をしても十分間に合う。
・理科と社会は、偏差値50以上をキープできていれば6年生の追い込みで間に合う。そのため、算数と国語を優先して取り組む。
・日曜特訓の算数は、合否を左右する重要な問題が集められているため、400点を目標に徹底的にやり込む(わが家では、苦手な単元も多く苦戦しましたが…)。
・過去問で点数が取れない併願校は、12月頃まであえて手をつけず放置しても問題なし。日曜特訓で鍛えられるうちに、自然と点が取れるようになる。
先生方にお勧めいただいた学校は過去問との相性が良く、さらに「大丈夫!」と背中を押していただいた過去問で点が取れなかった学校にも合格でき、大変驚きました。
お忙しい中、たくさんの過去問を添削していただき、本当にありがとうございました。先生方のご指導のおかげで、親子ともに最後まで頑張ることができました。心より感謝申し上げます。
立教女学院中学校
努力は必ず報われる
立教女学院中学校進学Aさん
私は4年生の6月からグノーブルに入塾しました。3年生の頃はどこの塾にも通っておらず、通信教育をやっていたのですが、なかなか学力が上がらずに困っていました。そんな時、両親がインターネットでグノーブルを見つけ、興味を持ったので入塾しました。
最初は真ん中のクラスからスタートだったのですが、頭が良い周りの人に全くついていけず、一気に一番下のクラスまで下がってしまいました。その後何とか学力を上げることはできないかと授業動画を見たり、先生に質問をしたり、周りのみんなと切磋琢磨しているうちに少しずつクラスが上がり、5年生の後期にはついに一番上のクラスまで上り詰めました。
しかし、6年生の前期から少しずつ成績が下がっていき、6年生の後期には真ん中くらいのクラスになってしまいました。友達がどんどん力を伸ばすなか、自分だけ成績が落ちていくことに不安を覚えたこともありました。そんな時先生が、クラスが下がっても学力は確実に上がっているから大丈夫だとはげましてくださったおかげで、自分のモチベーションを保つことができ、最後まで受験を続けることが出来ました。
これを読んでいる方も、6年生になると成績が落ちて不安になることもあると思いますが、今までと変わらず勉強を継続していればきっと受かります。勉強は、努力をすれば必ず結果がついてくるのですから。
グノーブルの生徒の皆さん、つらいことがあってもあきらめずに先生を信じて頑張ってください。
親子ともに成長出来た中学受験
立教女学院中学校進学Aさんの保護者様
娘は4年生の夏からグノーブルにお世話になりました。グノーブルを選んだ理由は、自宅からのアクセスが良かったこと、理系、文系でクラス分けがされていること、少人数制で先生と生徒のコミュニケーションが取りやすい環境だと感じたことです。
4年生の夏は「勉強が楽しい」と意欲的で、勉強に興味が向かい、スタートダッシュは完璧に思えました。5年生になり、難易度が各段に上がった算数の授業に付いていこうとする娘の姿に応援の言葉を投げかけることしか出来ませんでした。先生に質問に行くことも多くなりました。6年生の夏は難関中学校のコースを選択し、苦戦を強いられる中、苦手意識の強い科目から目を背けることもなく自己分析をし、授業のテキストやグノラーニングチェックを再度解き直して、解らない問題は先生に質問をして、解るまで丁寧に解説をしていただいたお陰で、過去問も少しずつ点数が上がり「出来るかもしれない」という自信がつきました。苦しい時期も逃げずに立ち向かった姿は勇敢に思え、娘の成長を感じました。
合格は、親のサポートだけでは成し遂げることが出来ませんでした。娘を支えてくださったグノーブルの皆様のお陰です。娘は、先生の授業が魅力的でワクワクするような講義が多いと話してくれました。授業以外でも気にかけてくださり、色々なお話が出来ることが楽しくて、居心地の良い環境を作って頂いたので、楽しく通塾出来ました。受験直前の励ましのお言葉は、個々を見ているからこそ伝えられる、本人に向けたメッセージで、自信と勇気を頂きました。受験当日に握りしめていた、先生方からの応援メッセージが書かれた「お守りカードブック」が本当にありがたかったです。
グノーブルのカリキュラムは、理系と文系でレベルにあった授業を受けることが出来るので、国語が得意で算数がやや苦手だった娘は、高学年になるにつれ自分に適した授業を受けることが出来て良かったです。
今、受験生活を振り返ると、親の考えている以上に子供が成長してくれたと感じます。生まれてから一番近くで見ていて、12歳のこの時期に付きっきりで、常に体調を気にかけ、会話の機会を多くもち、お互いの正直な気持ちを確認して、日々応援の言葉を伝える機会は今後そう多くはないと思うと、素晴らしい経験だったと思います。
私たち親子は感謝をもって中学受験を終え、新しい中学校生活を前向きな気持ちで迎えることができます。未来へ向け素晴らしい糧をくださったグノーブルの皆様に心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。これから受験を控えた皆様もどうかお体に気を付けて、笑顔で終えられることを願っています。
青山学院中等部
まさかの全勝で2月の勝者に!!
青山学院中等部進学Aさんの保護者様
中学受験をすると決めたのは2年生の時。友達に影響されて、自分も中学受験をしたいと言い出しました。それなら娘に合う塾をしっかり選んであげたいと思い、色々な塾の体験に行かせました。グノは入塾テストに受かると1回だけ体験ができると聞き、3年生の夏にとりあえず入塾テストを受けさせました。入塾テストの後に少しだけ解説授業をしていただき、それがとても楽しかったらしく、「この塾に入りたい! もし今日の入塾テスト落ちても、また受けて絶対この塾も入る!」と言い、無事入塾テストに一発合格し、3年生の秋に入塾しました。
算数と理科が得意で国語が苦手な娘には、理系文系でクラスを分けてくれるグノがとても合っていました。理系のコースはαかα1、文系はα1かα2が定位置で、志望校特訓では難関コースの一番上のクラスでした。
我が家の教育方針は「勉強だけではなく色々な経験をさせる」こと。そのため志望校を選ぶ時に重視したのは、大学付属、共学、入りたい部活がある、近さ、色々な経験をさせてくれそうな学校であることでした。
グノの同じクラスの子達はみんな御三家を目指していましたが、中学生になってもまたすぐ塾に入って東大を目指すというのは、勉強がそれほど好きではない娘には向いていないと感じていました。ひたすら勉強だけさせると、追い詰められて最後まで走り切れないと思い、6年生の夏前までは毎週友達と公園で遊んだり、習い事をしたり、受験生でも春休みと夏休みに海外旅行に行ったりして息抜きさせていました。
グノの先生の授業はとてもおもしろく、わかりやすいため、授業だけでほぼ理解して帰って来てくれて、家では間違えた所と授業で扱わなかった所を復習するのみでした。夏の志望校別特訓では、青学コースがないため慶應コースを受講しました。問題がさほど難しくなく、算数の過去問は1問間違いで、4科合計でもクラス最高得点で表彰されたことが本人は嬉しかったようで、「青学ではなく慶應中等部を受けたい」と言われました。
しかし、2025年はプチサンデーショックの年で、例年青学の入試は2日ですが、今年は日曜でキリスト教系の学校は入試日をずらすため、青学の入試日が3日となり、慶應中等部の入試と同じ日のため、どちらかに絞らなければならず、娘と話し合い、模試で合格率80%だった青学を受けることに決めました。
入試1年前の時点で青学は受かるだろうと言われており、過去問をやらせても10月には合格最低点を余裕でクリアしていたのでマイペースに勉強させていましたが、12月末に2023年の過去問をやらせたところ、得意な算数で半分も取れず、合格最低点よりも28点も足りませんでした。慌てて調べたところ、2023年から算数が難しくなっていたようです。得意な算数でこれしか取れないなら合格は難しいだろうなと、その時は親子揃って絶望し、取り乱してしまいました。
グノに電話をして、残りの1カ月ちょっとで何をしたら算数の点数をあげられるか先生に相談させていただきました。
「この時期に算数の難しい問題ばかりやらせて自信をなくすよりも、他の国語、理科、社会で点数を取れるようにしていった方が良い」とアドバイスしていただきました。
・国語は、グノの「漢字道場」など、グノの授業でやった知識と入試に出そうな本を読ませました(小中高生が主人公の作品でその年発売されたもの)。
・理科は、「基礎力テスト」とひたすらグノラーニングチェック。
・社会は、授業で間違えた問題や色々な学校の過去問、食事の間にYouTube等で一問一答をやらせました。
・算数は、「基礎力テスト」と授業の復習や、苦手単元は「G脳ワークアウト」。
入試日程は、1月 早稲田佐賀(首都圏入試)、2月1日AM 法政大学中、PM 農大一中、2日明大明治、3日青山学院、なんと全て合格を頂きました。初日に安全校を受けたため緊張もなく、合格を頂く度にリビングの壁にその学校の校章を貼り、その上に桜のシールを貼っていきました。
合格発表は娘が寝たあとの時間だったため、朝起きてから合格を伝えていたのですが、毎朝起きる度にリビングに桜が増えていって、自信がつき、嬉しくて幸せな気持ちで毎日入試に挑むことができました。
受験が終わった後に娘が、「中学受験楽しかった! 中学受験して良かった!!」と言っていたので、中学受験をさせて良かったと心から思いました。グノには感謝しかありません。本当に楽しい授業をありがとうございました。
余談ですが、入試数日前に青学の過去問を見て、理科は今年どの単元が出るか予想して最後の仕上げをしたところ、予想したうちの三つの単元が出題されました。そのうちの一つが苦手な天体だったのですが、入試当日の朝にやったグノの「基礎力テスト」が天体だったため、朝やったのが出た! と思ったそうです。
また、入試当日に受験番号が書いてあるシールが配られて解答用紙に貼ったそうですが、グノレブでいつも貼っているシールと全く同じ形式で、慣れているため落ち着いて貼れたそうです。
色々な意味でやはり縁があるのだな、と思いました。ありがとうございました。
開智日本橋学園中学校
最後まであきらめず走り続ける
開智日本橋学園中学校進学Aさん
🔳初めに:私は3年生のころ、違う塾に通っていたのですが、4年生の2月にグノーブルに転塾してきました。4年生のころは授業を楽しみ、確認テストに向けて少し復習する程度でしたが、5年生になると授業は面白いので楽しみつつも、受験を意識し始めました。6年生の11月くらいまではそこまで気合が入っているわけでもなく、4教科偏差値は40台が続いていました。しかし、12月になると急に気合を入れ始め、12月のグノレブでは久しぶりに偏差値50を超えることができました。もともと文系は得意で、上から2番目のクラスに入ることができましたが、理系は苦手で下から2番目のクラスになりました。12月のグノレブ後からはもう「外で友達と遊びたい」とは思わなくなっていたように思います。他塾の模試が少なかったため、客観的にとらえることはできませんでしたが、その時期の成長はグノーブル内で1、2位を争うのではないかと自負しています。
さて、これからは私が実際に行っていた勉強法や体験談を書こうと思います。
🔳国語:私は国語が得意だったため、4年生から6年生は漢字や知識をひたすら書いていました。6年生になると「漢字道場」がありますが、それは1週間に最低2周、できれば4週しましょう。4、5年生でもテキストの裏表すべてを(2ページほどあった気がします)テキストに書き込み、取り組みましょう。
🔳算数:テキストをなんとかして完璧にすることを目標としていましたが、達成できたことは少なかったです。しかし、そのテキストの復習を怠っていたこともあり、6年生では下から2番目のクラスに下がっているため、しっかり嫌がらずに行うことを強くお勧めします。授業で習ったところを重点的に復習し、校舎によっては宿題が出されると思いますが、出された場合は宿題も行いましょう。宿題に出されているということは入試によく出る、もしくは入試によく出る問題の基礎となるので、しっかり行うことをお勧めします。
🔳社会:4、5年生のころは15分程度で勉強を終わらせていました。6年生になって基礎力確認問題を40分程度かけ、反復練習するようになって、やっと日曜特訓の演習でも高得点を取れるようになりました。時間をかけて覚えることで、やっと知識が身につきます。私は、4年生のころは授業前に早く来て復習するだけだったので、地理が苦手になりました。学年関係なく、基礎力確認問題や、テキストを読み込むなど、家庭学習を怠らずやりましょう。6年生から覚える年号はしっかり覚えましょう。正誤問題や、並び替えにとても役立ちます。私は最初、年号をあまり覚えていなかったため苦労しました。
🔳理科:4、5年生で行っている授業は、すべて基礎であり、中学受験で必ず身につけておかないといけないものです。身近なもので実験したりして印象付けましょう。4、5年生で怠っていると、6年生でひどい目に遭います。テキストの基本のまとめ、確認問題、グノラーニングチェックをしっかり覚えながら反復しましょう。特にグノラーニングチェックはとても大切です。物理、化学などの計算系は公式をしっかり覚え、書き込みながら行いましょう。てこの問題で例えるならば、矢印や式を書く、などです。植物や星座、生物などの暗記系は、4、5年生のうちにしっかり覚えておくことを強くお勧めします。6年生になるとしっかり覚える時間が取れなくなってきます。頑張って覚えてください。私は覚えていなかったため、6年生になってとても大変でした。私と同じ過ちを犯してほしくないです。
🔳勉強するとき:よく音楽聴きながらはダメだと言われますが、私は構わず聞いていました。音楽を聴いても集中できるという人は、聴きながらでも良いと思っています。自分が集中しているとき、音楽は耳に入らないはずなので、自分が集中しているかを確かめることができます。また、25分勉強して5分休憩というような時間設定はあまりお勧めしません。集中がすぐ途切れると思うからです。調子良く勉強できているところにタイマーがなると「調子良いタイム」が途切れることが何回かあり、残念に思いました。たいてい、その次の25分は調子が悪くなってしまい、「ああ、さっきあのまま続けていれば…」と思うこともたびたびありました。では、どうすれば良いのかというと、集中力が切れたときに10分休憩することです。勉強している間はストップウォッチで計っておいて、休憩するときに止めます。そうすることで、集中力が切れてストップウォッチを見たときに「もうこんなに時間がたったの?!」と達成感を味わい、モチベ-ションを上げることもできますし、「調子良いタイム」を最大限使えるからです。
🔳体験談と注意:塾に早く(30分前くらいに)行って勉強すると、生徒が少なく静かに勉強できます。しかし、そのときテキストを忘れないようにしましょう。生徒が少ないため貸してもらえる人も少ないです。復習できずボーっとしていたら本末転倒です。必ず忘れ物には注意しましょう。歴史資料や地図帳も忘れずに。授業で使うことがよくあるため、追いつかなくなります。友達に見せてもらうことはできますが、校舎によっては禁止されている場合があります。私が言いたいのは忘れ物はしないことです!! 家を出る前絶対に確認してください。また、早く行くと、授業まで時間があるため、次々に来た友達に話しかけ、雑談してしまうことがあります。気を取られないように頑張りましょう!
🔳最後に:みなさん、受験までの道のりはとてもつらいです。ですが、終わったら明るい未来が待っています!「つらい」と感じたら共感できるような音楽を聴きましょう。心が落ち着きます。最後まであきらめず、走り続けましょう!これを読んでいる受験生やその保護者の方の顔や姿は見えませんが、あなたたちなら合格できると信じています!グノーブルは最強です!グノーブルに通って努力していれば、最強になって合格できます! 頑張ってください!祈🌸 合格!!!!!!
川口市立高等学校附属中学校
最後までやりきろう
川口市立高等学校附属中学校進学A君
学校の勉強もグノーブルの勉強もやらなければならず、時間は足りず、体力ももたなくなってしまい、勉強が嫌だという人もいるのではないでしょうか。勉強をさぼってしまいたくなる日もあると思います。でも、やると決めたなら絶対に最後まであきらめないでください。
僕もあきらめてしまいそうになりました。しかし「ここまでやってきたなら最後までやりきろう」と思い、最後まで試験を受け、努力の成果が出て合格することができました。
友達を作って楽しく通うのが僕のおすすめです。そして、先生は最後まで応援してくれます。どんなことがあっても自分のことを信じて、最後までがんばってください!
慶應義塾湘南藤沢中等部
自分を信じて!
慶應義塾湘南藤沢中等部Aさん
私は4年生の時にグノーブルに入塾しました。入塾当初から理系が上の方のクラスで、文系が下の方のクラスでした。その後も文系の国語の成績はなかなか伸びず、苦労していました。
私は記述が特に苦手だったので、SFCの最後の自由作文は心配でした。さらに、外部模試のSFCの合格確率が満足のいく結果ではなかったことも私を不安にさせました。しかし、苦手な国語は、5年生のときには宿題で出る記述を必ずやったり、授業で読んだ文章の要約を書いたり文章を書くことに慣れるように頑張りました。また、最後の期間には過去問や親が作ってくれた問題で自由記述を毎日練習していました。
1月31日に先生と電話をしたとき、最後のグノレブテストでクラスが下がってしまったという不安を打ち明けると「大丈夫だから。焦ることはないから。自分を信じて頑張ってね。」と言っていただけました。そして入試本番のときも自分が一番SFCに入りたい気持ちがあると思って試験に挑みました。そのとき、自分に自信を持つことの大切さを実感しました。皆さんも不安だと思いますが、自信を持って頑張ってください! 今まで支えてきてくださった先生方、本当にありがとうございました!祈・合格!
皆さんの合格を祈って
慶應義塾湘南藤沢中等部Aさんの保護者様
娘が4年生のときからグノーブルにお世話になりました。それまでは兄が通っていた算数に強い小規模な塾に通っていたのですが、体験授業での明るい雰囲気を娘が気に入ったのと、通塾日数が少なく、他の習い事と両立しやすかったのが決め手でした。
3年間を通じて親がサポートしてきたのは、スケジュール管理です。
毎日の「基礎力テスト」、授業翌日の復習、テスト直し、など、曜日ごとにやることを決めて、あとは基本的に本人に任せていました。ただし、「ちゃんとやった」という自己申告を鵜呑みにしていた結果、「基礎力テスト」を全然解いていないこともありました…。
6年生の9月以降は、外部模試や過去問などで、時間管理が一層難しくなりましたが、先生から指導された優先順位を守ることで、何とか日々の課題をこなすことができました。(全部やるのは無理!)
やることに追われる日々をずっと続けてきたのですが、最後の1月になってから宿題が減って、「各自の苦手分野をおさらいしましょう」と言われ、少し戸惑いました。11月の保護者会でも説明を受けていたので、多少の準備はしていたのですが、正しい方向に進んでいるのか不安になりました。何度か先生に学習内容などを相談し、軌道修正をしながら本番に臨みました。最後の1か月は本当に大事なので、困ったら是非、塾を使い倒す気持ちで質問攻めにして良いと思います。『合格者の声』の冊子を読んで、他のご家庭とグノーブルの距離感は参考になりました。
志望校選びは、通っても良いと思える実力校を1日に持ってくることで、2日、3日にはチャレンジ校に挑むことができました。面接のある学校だったので、親子共に、想定質問集は年末頃から準備しました。
努力が報われて、第一志望校の合格を頂くことが出来ましたが、受験生活を通じて、本人の成長を感じられた点も本当に良かったと思います。グノーブルでは、たくさんの仲間と巡り合えて、先生方にはきめ細かな愛のあるご指導をして頂き、本当に良い受験生活を過ごせました。これから受験の皆さん、体調に気を付けて頑張ってください!

意志を貫き最後まで諦めないで
慶應義塾湘南藤沢中等部進学Bさん
私の受験を振り返ります。決してすんなり合格したという体験談ではないです。でも、こんな受験をした人もいるんだというメモとして記しておきます。
新5年生がはじまる少し前にグノーブルに入塾。塾はグノーブルが初めて。入塾当時はDブロック。まずは授業の内容やテキストをしっかり復習して覚えた。5年初めてのグノレブでAブロックにアップ。しかし、いきなりレベルが上がり授業についていけない。何度説明してもらっても理解できず、先生を困らせた。
ほぼ国語に助けられて入塾テストをクリアし、作文が文集に選ばれたこともあったので国語には自信があった。しかし、入塾してからは、ハイレベルな読解問題や長い文章の速読ができず、とにかく手こずった。
6年生になり初めて他塾の模試を受けた。グノの偏差値より10以上も低かった。国語はどんどん下降し偏差値30台の時も。6年生の夏、毎日の夏期講習を乗り切ったあとは、今までに見たことがないくらい成績が上がった。けれども、それを境に成績が急降下。模試だけでなく、グノレブテストでも偏差値30台、40台を取るようになった。比較的得意だった算数でも凡ミスを連発。12月のグノレブテストは史上最悪の点数を記録。模試も最悪。直前の1月はテストが無いので、自分がどういう立ち位置か分からないまま、家庭学習の時間を日曜特訓に使った。
日曜特訓では最難関コースに通っていたが内容が難しくて、結果的に勉強が進まなくなってしまった。11月にコースを変更。ハイスピードでミスなく解く練習をすることになった。この勉強が、SFCや他の学校に合格できたポイントだったと思う。
そんな私から伝えたいこと
1:自分が目標とする学校を早い段階で決める(私はひとつに決められなかった)。
2:1月受験が自分を伸ばし自信をつけてくれた。1月受験のための過去問や勉強が、そのまま他の学校の入試問題に出てきたこともあった。
3:自分の得意科目を見つけて伸ばす。他の教科が多少悪くても取り戻せる。私の場合は、理科が得意で点数の取れない国語の分を補うことができた。
4:「行きたい学校を受けなさい。学力は今からでも伸びますから」という先生の言葉を信じ意志を通した。
すべてが順調に進むわけではないです。でも、最後まで諦めない。その気持ちが大事です。頑張ってください!
最後まで挑戦に寄り添ってくださった先生方
慶應義塾湘南藤沢中等部進学Bさんの保護者様
「入試スケジュールにヒヤヒヤしていました」とは、娘の受験後にグノーブルの先生の口からこぼれた言葉です。行きたいと思った学校を受けるという意志の固い娘の受験は、それだけに無謀なところがありました。中高一貫の進学校、付属、都立と傾向の異なる三つの学校を受けるという…珍しいケースだったかもしれません。
娘がグノーブルに通い始めたのは新5年生がスタートする少し前から。塾から帰宅すると「楽しかった!」と、その日に学んだことや先生の小話、覚えるための呪文のような歌?を披露してくれていました。勉強=楽しい、それが娘にとってのグノーブルの始まりでした。少し状況が変化したのは、5年生に入りクラスが一気に上になったときです。なんとか食らいつこうともがいていましたが、クラスの中で自分だけ分からない計算式や内容が多く、プレッシャーを感じ始めたようです。しかし、それがモチベーションとなり勉強に対し真剣になっていったようにも感じます。その後の成績は、6年生の終わりまで一定することなくクラスもジグザグに昇降していました。
6年生から受け始めた他塾の模試は散々な結果で、最後まで志望していた学校のほぼすべてで合格率は20~40%。これはさすがに志望校を絞らなければいけないのではと思い、日曜特訓のコースを途中で変更し、2月1日の受験校の勉強に切り替えたのですが、娘は受験対策ができなくても文化祭が気に入った都立小石川は絶対受けると譲らず、第一志望を絞れず幾つもあるような状態で入試に突入してしまいました。
娘は典型的な理系タイプで、とにかく国語ができません。何となくそれが分かっていながらも漢字以外は放置し続けてしまい、千葉の受験後にようやく先生に相談するという…。それでも先生は親身になってくださり、SFCと都立を受けるのであれば、過去問を解いて持ってきてください、と言ってくださいました。そこから記述の猛特訓。2月入試の4日前というとんでもない時期でしたが添削をしてくださいました。また、面接の対策もできていなかった我が家のため、SFCの一次合格発表があったその日に担当の先生が塾で対策をしてくださいました。
結果、1日校は不合格でしたが、SFCと都立はまさかの合格に。過去問については対策が全くできていませんでしたが、日々のグノーブルのテキストでの積み重ねが力になっていたようです。特に社会や理科は一問一答だけでなく記述問題まで取り組んでいたのが結果につながったように感じます。
娘の受験はレアケースであまり参考にならないかもしれませんが、グノーブルの授業とテキストは本当によく練られ質が高いです。傾向が異なる学校を受けることになっても、コツコツしっかりと取り組んでいれば必ず実力がついてくると思います。ただ、行きたい学校をあきらめないという選択をし、途中どんな結果でも2月5日の最後まで受けると決めていたので、精神的にはなかなかつらい日々を過ごすことになりました(おまけに合格発表が2校とも遅かったので)。
「ヒヤヒヤする」娘の挑戦に最後の最後まで寄り添い、指導してくださったグノーブルの先生方に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

やれるだけのことはやってきたと思えるように
慶應義塾湘南藤沢中等部進学C君
僕は理系が得意で国語が苦手でした。算数・理科は答えを暗記するのではなく、なぜそうなるのかという原理を理解するようにしました。国語は特に物語文が苦手でした。その分、漢字と知識は完璧に覚えるようにしました。語彙はもっと早めに増やしておくと良かったと思います
慶應3校の合格のためには基礎をしっかり固めてケアレスミスをしないようにすることが重要です。グノーブルの授業はとても面白く、あっという間に時間が過ぎました。成績がなかなか上がらず苦しい時もありましたが、グノーブルには優秀な仲間がいてくれたからこそ、気を抜かずに3年間走り続けてこられました。
6年生の1月31日に僕は、自分がやれるだけのことはやってきた、これでダメなら仕方ない、と思うことができました。そう思えるまで、諦めずにグノーブルの先生を信じて頑張ってください。
国語でも戦える力がついていた
慶應義塾湘南藤沢中等部進学C君の保護者様
新4年生で理系文系の偏差値に差があった息子には、グノーブルが最適であると思い入塾を決めました。
息子は国語が苦手だったので、記述ばかりのグノーブルの教材に、入塾当初、歯が立ちませんでした。先生からのアドバイス通り、持ち帰った教材を一緒に復習しました。とても良い教材を扱っていて、涙することも多々ありました。しかし、グノレブテストでは記述欄が真っ白な状況が続きました。それでも諦めずに復習を続け、6年生になり、ようやく平均点が取れる回も増えました。
理系は順調に成績を伸ばすことが出来たので、入試は理系が国語を補う形での勝負になると思いました。しかし、いざ入試を迎えると、理系科目のみの受験で連敗しました。4科目で戦う方が安定して合格を取れたことには驚かされました。グノーブルのレベルの高い国語で3年間鍛えられ、最後まで諦めずに取り組んだ結果、国語でも戦える力がついていたことを6年生の2月の入試期間中に感じました。
SFCは作文問題もあり、正直厳しいと思っていましたが、150文字しっかり書くことが出来るようになるまで成長させていただきました。グノーブルなしでは第一志望校合格は成し得なかったです。本当にありがとうございました。
慶應義塾中等部
グノーブルのすすめ
慶應義塾中等部進学A君
僕は1年生の冬からグノーブルに通い始めました。4年生まではやる気も競争心もなく、周りからは「受験にはあまり向いていないかも」と言われていました。
5年生になると実力テストが急に難しくなり、国語では偏差値37という悲惨な結果になってしまいました。そこでまず、一番苦手だった国語を重点的に勉強することにしました。家では母と一緒に語彙を増やし、グノーブルでは読解力を鍛えました。すると、国語が一番得意な科目になり、他の科目で多かった読み間違いも減っていきました。そのおかげでモチベーションが上がり、勉強に前向きに取り組めるようになりました。
さらに、クラスが少しずつ上がるにつれて「周りの人に負けたくない!」という気持ちが強くなり、本気で受験勉強に向き合うようになりました。グノーブルは先生に気軽に質問できる雰囲気だったので、どんどん質問するようになり、そのたびに先生がしっかり教えてくれました。そのおかげで成績も伸びていきました。6年生では過去問をたくさん解き、実践力を身につけました。
しかし、本番の1月受験では、過去問で合格点が取れていた学校に落ちてしまい、ショックで泣いてしまいました。でも、すぐにグノーブルに行くと、たくさんの先生が励ましてくれました。そのおかげで気持ちを立て直し、残りの1週間、全力で勉強を続けることができました。
そして、先生方に支えられながら最後まで頑張った結果、第一志望校に合格することができました!グノーブルの先生方、本当にありがとうございました!
グノーブルに心から感謝しています
慶應義塾中等部進学A君の保護者様
我が家は1年生の冬からグノーブルに通い始めました。というのも、6歳上の兄の受験対策が遅れてしまった経験があり、2回目となる中学受験では早めに準備をしようと考えたからです。
4年生から本格的な学習が始まりましたが、何度も挫折しそうになりました。そのたびにグノーブルの先生に相談し、科目ごとの対策について的確なアドバイスをいただきました。そして、6年生になってから本気になっても間に合わないとわかっていたため、特に5年生の夏休みは「これでもか!」というくらい、各科目に徹底的に時間をかけました。すると、夏休み明けから成績が伸び始め、最も苦手だった国語が、いつの間にか一番大好きで得意な科目になっていました。何か一つでも得意な科目ができると「他の科目もできるようになりたい!」という気持ちが高まり「クラス落ちしたくない!」という意識も強くなっていったと思います。
志望校については、6年生になってから決めました。息子は「野球が強い付属校に行きたい」という希望を持っており、それを知ったグノーブルの先生が「慶應はどうだ?」と声をかけてくださったのがきっかけでした。そこから「慶應に行って甲子園に出場したい!」という強いモチベーションが息子の中で芽生えたように思います。
しかし、夏休み明けに一度気が緩み、成績が落ちたことがありました。そのときもすぐに先生に相談し「一度の結果で決めつけず、数カ月様子を見ましょう」と励ましていただきました。そのおかげで慶應コースに所属し続けることができました。優秀な生徒さんが多い中で大変ではありましたが、先生のアドバイス通りに努力を続けた結果、少しずつ苦手な科目も成績が上がっていきました。
1月受験が始まり、予想外の不合格に涙を流していた息子が泣きながら電話をかけたとき「今から塾に来て、少し話そう!」と先生が声をかけてくださいました。そのおかげで気持ちを立て直すことができました。親子ともに不安でいっぱいだったとき、グノーブルの先生方には何度も救われました。
生徒と先生の距離が近く、親にも寄り添ってくださるグノーブルの先生方は、本当に最高です!子どもの頑張りを認め、励まし、伸ばしてくださった先生方に、心から感謝しています。本当に、ありがとうございました。
渋谷教育学園渋谷中学校
グノーブルを楽しんで
渋谷教育学園渋谷中学校進学Aさん
私は今回「4教科の基本的な勉強法」、「日曜特訓と過去問の勉強法」の二つについて説明しようと思います。渋渋に確実に合格する方法はありませんが、少しでもヒントにしてみてください。
【4教科の基本的な勉強法】
■算数:私は算数で特にケアレスミス(問題の勘違い、条件の読み飛ばし、計算ミス)がひどかったです。その対策として計算マスターと「基礎力テスト」は必ずやると良いと思います。「基礎力テスト」は、絶対100点を取るという集中力でやるようにしましょう。やがて、その集中力でやることに慣れてきて、ケアレスミスが減ります。実際に、私もケアレスミスが減りました。特に直前期は点数にこだわりましょう。
■国語:とにかく語彙を徹底しましょう。語彙力がつくと、文章に出てくる言葉の意味がわかるようになり、必然的に文章の理解度が上がります。先生は「国語の90%は語彙力」と言っていました。私も意味をうまく説明できない言葉を調べて書き留めるようにしたところ、成績が上がりました。意外とわからない言葉って多いものです。皆さんも、辞書をうまく活用したり、グノのテキストの知識の欄を読み込んだりして、語彙力を鍛えてください。きっと授業がもっと楽しくなります。
■理科・社会:知識の確認を徹底しましょう。テキストや地図帳・歴史資料・理科資料を読み込む、グノラーニングチェックや社会の問題集を解くなどして知識を確実なものにしてください。
【日曜特訓と過去問の勉強法】
■日曜特訓について:日曜特訓に渋渋のコースがないということで不安を感じている人も少なくないと思います。ですが、冠コースがないからといって受験に支障はありません。他のコース(私は桜蔭コースを受講しました)で出される問題も難問が多く、その問題を解いているうちに渋渋の問題にも対応できるようになるからです。そんなに不安を感じず、日曜特訓に打ち込んでください。
■過去問演習算数について:基本的にはグノのテキストを解いていれば大丈夫です。しかし、渋渋には記述の問題があるので、普段から途中式を書くことを癖にしてください。その癖がなかった私は苦労しました。また、立体切断の問題がよく出てくるので、立体切断マスターは解くようにしましょう。
■過去問演習国語について:渋渋には難しい選択肢問題が出てきます。その問題は記述ができれば対応できるので、焦らなくても大丈夫です。不安な人は、土曜特訓の演習に出てくる選択肢問題で練習しておきましょう。また、渋渋で出てくる説明文は、よくわからない難しいものが出てきます。でも大丈夫です。自分と同じように、解いている人全員が難しいと思っているので、落ち着いて対応してください。
■過去問演習理科と社会について:渋渋の理科と社会はかなり独特で、読解力が求められる時もあります。数をこなして慣れておきましょう。しかし、そのような問題でも、基礎がしっかりしていないと解くことはできません。入試直前まで理科と社会は伸びます。知識を確実なものにしてください。
最後に、グノの先生方はユニークで、教わっていてとても楽しかったです。学ぶ喜びを忘れず、楽しんで授業を受けてください。それこそが学力upの最大のカギだと私は思います。渋渋で後輩が入学してくるのを楽しみにしています。
グノーブルという最高の学び舎
渋谷教育学園渋谷中学校進学Aさんの保護者様
1月31日にいただいた激励のお電話で、「どんな時も明るく楽しく過ごす娘が居たことが周りへ良い影響を与えていて、とても良い学びの場なっていた」と言っていただきました。親にとっては宝物のような言葉をいただいたと思います。今思えばあっという間ですが、3年間という長い道のりの中で、グノーブルで過ごしていた時間は、娘にとってはかけがえのないものだったのだと思います。ご指導いただいた先生方、ともに切磋琢磨してくださったお友達に深く感謝申し上げます。
我が家の受験体験記(気付きの抜粋)が、どなたかの参考になれば幸いです。
【4~5年生】
■先生方の勧めどおりに取り組む
家庭学習方法は、保護者会や授業で説明いただいたとおりに取り組むことを心掛けました(うまくいかないことも多々ありましたが…)。また、取り組み方を親子で何度も確認し、自分事となるように促しました。
■「授業での全集中の取り組み(全力で楽しむ)の振り返り」と「親子での音読」
単身赴任中だったこともあり、娘とのコミュニケーションの延長として、どんな授業だったか、どのような発言をしたのか等を、振り返りとして対話するようにしていました。また、国語だけでなく、理科や社会のテキストも親子で音読しました(内容が秀逸だったので、音読は親の私も楽しかったです)。その中で、理解の浅い箇所や苦手な箇所は、なんとなく分かります。今から思うと、その箇所を親が教えようとせず、先生に任せるべきだったなと反省をしていますが、親も楽しいと思っていることが伝わったのは、とても良かったと思います。
【6年生】
■白紙のテキストたち:新6年生になると未消化のテキストが増えますが、先生方の指示通りの量をこなすのも、娘は苦労しているように感じました。不安に思い面談時に確認すると、取り組み内容・量ともに問題ないとアドバイスをいただきました。何よりも授業に全集中するのが大切とのことでしたので、積みあがった白紙のテキストはなかったことにするぐらいで良いと思います。
■都立一貫校の対応:娘の第一志望は、渋渋と都立小石川でした。そのため、都立一貫校の対策をどのようにするかは我が家にとっては大きな悩みでした(4~5年生は他塾の講座を受講していました)。6年生になる前に相談をさせていただき、日頃の授業や家庭での復習そのものが、適性検査で要求される読解力や分析力、表現する力に繋がっていること、過去問の添削をしていただけることから「グノーブルの授業以外に特段取り組みをしない」という決断をしました。過去問では問題に慣れるまで苦戦しているように見えましたが、アドバイス通り特別な取り組みをせずとも対応が出来ておりましたし、無事合格をいただくことが出来ました(都立用の模試は、他塾の学校別模試を一度だけ受験しました)。
■先生方への相談:過去問に取り組むと、娘の大きな課題が見えてきました。難問に時間を掛けすぎることと、いわゆるドボン(問題の読み間違い、思い込み、計算間違い)が多いことでした。先生に相談させていただくと、日曜特訓(桜蔭コースを受講)の取り組み現状、進捗、娘の性格と今後の対応を説明してくださり、受験に向けて仕上がっていくから問題ないこと、前向きな声かけの実施をとアドバイスいただきました。娘の性格をしっかり把握されていることに驚かされるとともに、それを踏まえたアドバイスは、親としてはとても心強かったです。この課題は最後の最後まで悩みの種ではありましたが、高い集中力で解いている状況では致し方がないことと思い、前向きな声かけを心掛けるようにしていました。

とにかくあきらめない
渋谷教育学園渋谷中学校進学Bさん
私は5年生の6月にグノーブルに入塾しました。初めての塾でしたが、先生方はとても優しく、質問に嫌な顔一つせず答えてくださり、どうにか授業に追いつくことができました。
私は算数が苦手で、宿題は授業動画を見ながらこなしていました。時間がいくらあっても足りなく、10分ルールを設け、わからないときは潔く解説を見ました。また、計算ミスが多く、気が緩むと、最後の最後でケアレスミスをしばしばしていました。最後の1分は解き直しの時間に充てていました。過去問も最後まで苦しみましたが、8年分帰国生枠の問題も解いたことで、最後は8割を超えるようになりました。
大変だったのは6年後期の日曜特訓です。私は桜蔭コースに所属していました。桜蔭コースの国語は、解答欄がお弁当箱と言われる、マス目のない何文字でも書ける解答欄で、文字数が足りず時間配分が難しかったです。しかし、何度も解くうちに重要な場所がわかるようになり、書くスピードも速くなりました。算数は、問題が多くて時間の足りなくなる難しいテストがあり、大好きなお弁当を昼に食べる時間が少なくなってしまいました。社会の正誤問題は問題数も多く、一つ一つの問題が重く、難しかったです。
~6年生の勉強について~
■算数:「基礎力テスト」はためずに毎日やったほうが良いです。私は夏休みためこんでしまったため、その後が大変でした。また、私は立体切断が苦手で、直前期に土曜特訓の立体切断マスターを解き直したことにより、過去問の点数が上がりました。苦手な単元は解き直しをお勧めします。
■国語:「漢字道場」は毎週やったほうが良いです。私は記述は得意でしたが、漢字や語彙は苦手で、日々の積み重ねが大事だと感じました。また、記述は直感で解きすぎず、手掛かりを探して書くのが良いと思います。
■理科:グノラーニングチェックをしっかりやったほうが良いです。グノラーニングチェックは各単元の重要なポイントがまとまっているので、とても大切です。夏休みと直前期に先生に言われたところを取り組んだことで、学力が上がりました。
■社会:年号テストの復習は定期的にやったほうが良いです。全く復習しないと、半年で半分も忘れていました。また、時事ニュースのキーワードや公民の選挙については、覚えておくと役に立ちます。
~入試について〜
入試には体温調節のしやすい服装で行きましょう。教室によって暑すぎたり、寒すぎたりするので、私はいつも一番下に半袖を着ていました。また、当日の失敗に左右されない強い精神を持つことが大切です。私は筆箱を忘れて慌てましたが、無事合格にたどり着けました。とにかく慌てないことが大切です。そして、ラジオ体操は朝取り組んでから出掛けましょう。頭がすっきりし、回転が良くなるのでお勧めです。
~最後に~
とにかくあきらめないこと。あきらめなければ合格が目の前にあります。応援しています。祈 合格
毎回とても楽しみに通っていました
渋谷教育学園渋谷中学校進学Bさんの保護者様
入塾したのが遅かったため、習ったことのない単元は苦労し、中学受験を最終的に決めたのは6年生の夏頃でした。とにかく負けず嫌いな性格で、どうにか上位のクラスに入りたいため、授業前にあるテストの勉強を必死でこなしていたのを覚えています。
何といっても親として一番良かったことは、毎回塾をとても楽しみに通っていたことです。先生方の、それぞれの個性ある授業がとても刺激的で、グノーブル中学があったら良いなと考えたくらいです。本当に面倒見がよく、的確な指導のおかげで第1志望に合格できたのだと思います。最後の授業の日は、母子ともに寂しさで一杯でした。
算数の先生は、生徒の足りないところを把握し、苦手な単元の復習箇所を詳しく教えていただきました。また、授業後の計算プリントはとてもありがたかったです。その日々の積み重ねのおかげで、計算のスピードや正確さがアップしました。
国語の先生、最後の最後まで過去問にお付き合いいただき、睡眠時間が取れていたのか、とても心配になるほどのご尽力、本当にありがとうございました。毎回たくさんのコメントをいただき、とても励みになりました。
理科の先生、いつも娘に目をかけてくださり、娘も喜んでおりました。グノラーニングチェックを二巡することで最後の理科の基礎固めとなり、良い結果につながりました。
社会の先生、勉強だけでなく、いろいろな観点から教えてくださることが娘にとってとても楽しく、授業にのめりこんでおりました。塾から帰ってから母子との会話も膨らみ、結果、考え話した内容は忘れることなく、身についておりました。また、過去問も丁寧にスピーディーに添削してくださり、本当に感謝しております。
最後に、教材が素晴らしくまとまっており、入試直前まで非常に助かりました。他教材や他塾に頼ることなく、先生がおっしゃったとおりに、家庭学習、過去問題に取り組むことが合格へとつながりました。

あきらめず、強い気持ちで前向きに
渋谷教育学園渋谷中学校進学Cさん
私は3年生の6月にグノーブルに入室しました。先生と生徒が話し合いながら、アットホームのような雰囲気で勉強できるのがグノの良さだと思います。雑談が多くて面白い先生や、テキストに載っていない解法をわかりやすく教えてくれる先生もいて、毎回の授業が楽しみでした。
渋渋を第一志望に決めたのは5年生で、文化祭に行ったときです。自由な雰囲気、共学であること、生徒同士が仲良く協力しているところに惹かれました。
日曜特訓の前半は桜蔭コース、後半は最難関コースを受講しました。朝早く起きて夜まで授業、次の日も学校で大変でした。日曜特訓のお弁当と夜寝ることだけが楽しみでしたが、そのつらさを乗り越えたからこそ合格できたと思います。
1月の入試は、前泊してきれいな富士山やイルミネーションを見てリラックスして受験し、合格しました。
1月31日、国語の先生から激励のお電話があり「渋渋に入りたくてこんなに頑張ってきたのだからできるはず。明日一発で合格を取ってこい」と言われました。そのおかげで安心し、やる気がみなぎりました。
2月1日、渋渋の第1回入試は、始まるときこそ緊張しましたが、自分ならできると信じて頑張りました。けれど不合格。2日の第2回があるから大丈夫と思いましたが、その日は思ったより算数が難しく、まずいなと思ったらまた不合格。悲しくて悔しかったです。5日の第3回は、倍率が高すぎて受かる可能性がほとんどないことはわかっていました。でも、私は最後まで渋渋にチャレンジするつもりでした。3日と4日は原宿に買い物に行ったり妹と遊んだりして、ほぼノー勉でした。心は落ち着いていました。迎えた5日の入試は「ここまで来たら受かりたい」という思いで、本気になって解きました。6日は「第二志望校に進学しよう、とにかくやっと受験が終わった」とすっきりした気持ちで小学校に行きました。帰宅し、遊びに出かけようとしたら母に呼び止められ、合格発表の画面を開きました。そこには自分の受験番号がありました。「え、あれ、受かってる」うれしさというより驚きが強く、あとから喜びを実感しました。二度の不合格を経験したけれど、最終的には受験した4校全てに合格し、私の中学受験は幕を閉じました。
学習アドバイスです。
🔳国語:記述は前置きを長くせず、書きたい要素をバランスよく配分し、語尾に気をつける。感情はうれしい悲しいだけでなく、いろんな表現を知っておく。授業中に実践して理解する。選択肢は間違っている箇所に印をつけ、長いときは書いてある要素ごとに区切る。答えは本文に書いてあるのでよく読む。
🔳算数:「速さ」や「相似」は基本をしっかり身につけ、応用の土台を作る。後半になるにつれテキストの量が増えるので、先生に指示された箇所、優先順位の高いものから復習する。授業中に行われる実戦テストや計算力確認テストを、本番と思って緊張感を持って解く。条件や数字をちゃんと読んで考えてから解く。社会:地理は、地名や知識単体ではなく、川が何県を通っているかなど全体を見て覚える。歴史は、年号、出来事、人物単体ではなく、時代の流れをつかむ。隙間時間に資料集を読む。公民は、数字(何分の何、何日以内など)を覚える。関係性を理解(司法権、行政権、立法権。国と都道府県と市区町村など)する。時事は、ニュースを見たり新聞を読んだりする習慣をつける。
🔳理科:計算問題は、型を覚え、数値替えでたくさん練習する。動植物は分類が大事で、特徴を覚える。興味がないまま覚えようとしても頭に入らないので、興味を持つ。地層なども解き方は大体決まっているので頭に入れる。復習テストをしっかり見直す。先生がわかりやすく教えてくれるので、授業を聞いていればできる。
🔳過去問:本番と思って解く。時間配分に気をつけて、解けるところから解く。記述は書くべき要素を考えてから書く。先生に添削してもらったらしっかり見直す。
・国語:文章が長く時間が足りないことがあるので、速く丁寧に読む。抜き出し問題は正確に抜き出す。漢字は丁寧に書く。
・算数:難問ができなくても、取るべき問題を確実に取れば合格点に達する。式と考え方を書く場合、考えた筋道を言葉を添えてわかりやすく書く。
・理科・社会:覚えていなかった知識は、見直しながらその場で覚える。記述の添削では、どの要素が抜けていてどこを直すべきかを先生方が教えてくれるので、正しい考え方と書き方を身につける。
🔳入試直前〜本番:頭を働かせるために、9時間は寝たい。絶対受かるぞという強い意志を持ち、リラックスして平常心で受ける。一喜一憂はダメ。ポジティブに。いちいち落ち込んでいると次の入試に影響が出るので、前を向く。
合格できたのは先生方のおかげです。本当にありがとうございました。グノ、楽しかったです。受験生の皆さん、今は苦しいかもしれないけれど、その努力が報われると信じて頑張ってください。たとえ不合格を経験したとしても、あきらめずに挑戦し続ければきっと合格できます。前向きに、最後まであきらめずに立ち向かってください。来年の春、明るい未来が開けますように。祈合格!
あきらめず、ひたむきに
渋谷教育学園渋谷中学校進学Cさんの保護者様
幼稚園のころから英会話グノキッズに通っていた娘は、自然な流れで3年生の6月グノーブルに入室しました。渋渋への憧れはありましたが、志望校というより、あくまでも憧れ、夢でした。3年生で塾に通うことに慣れ、4年生からテストの点数を意識し、5年生の途中から自走を始めました。親はテキスト整理、スケジュール作成、健康管理、送迎に徹しました。6年生になり、グノレブの国語で初めて1位を取ったことで自信がついたようです。
日曜特訓は先生のご指示に従い、前半は桜蔭コース、後半は最難関コースで学びました。渋渋コースを設置している他塾があることは知っていましたが、余計なことはせずグノを信じてついていこうと決めていました。グノのテキストとカリキュラムはどの学校にも対応できるよう研究しつくされたものであり、先生方は各校の入試傾向を熟知なさっています。
日曜特訓は遠くの校舎に通い、朝が早くて大変でした。6年生は土日も忙しくなるので、親子とも体力をつけておくことをお勧めします。家族の協力も不可欠です。次女は遊びたい気持ちを我慢し、夫も料理と送迎で娘をサポートしました。
勉強する娘の隣に少しのあいだ座り、「グノの先生がこんなこと言ってたよ」という話を聞くのが楽しみでした。絵が好きな娘は、勉強の合間にイラストを描くことが息抜きでした。そこに私も変な絵を描き足して二人で笑ったり、私が冗談を言いすぎて「うるさい、勉強するから静かに」と娘に怒られたり。こんな風に娘と一緒に何かをするのは最後かもしれないと感じながら、今思い返すと幸せな時間を過ごしました。
9月、過去問を始めましたが、算数が合格者最低点に全く届きません。でも娘は「算数をなんとかすればいいんでしょ?」と冷静でした。そして10月から本当になんとかしたのです。初めて合格者平均点を超えたとき、採点していた私が涙ぐんだのを見て、娘は「保護者会で一喜一憂しちゃいけないって言われたんでしょ? しちゃってるね」と冷静でした。朝起きて「基礎力テスト」をやり、過去問を解き、添削を見直し、グノの授業を受けて復習し、空き時間に理社の資料集や国語で出題されそうな本を読む。そんな日々が淡々と流れていきました。
入試前日、国語の先生から激励のお電話で「きみには渋渋が似合ってる。明日、一発で合格してこい」と気合を入れていただきました。
2月1日、第1回入試。まだ3年生だった小さな娘が初めてグノーブルの扉を開けてから3年8ヶ月。心身ともに成長し、先生方に鍛えられ、渋渋の入試を受けられるところまでたどり着きました。憧れだった渋渋が、明確な目標になり、入試に挑むことができる。それだけで奇跡だと私は感謝し、結果は自然についてくると確信していました。
しかし、結果は不合格。
2月2日、第2回入試。結果はまた不合格。娘はクールな表情を崩しませんでした。
それまでに1月校、第二、第三志望校には合格をいただいていたので、私は第二志望校への進学を受け入れ、前を向こうとしていました。2月5日の第3回は倍率が高く、3連続で打ちのめされる可能性が高い。それなら第二志望校で幸せになった方が、これ以上つらい思いをさせずにすむのでは?しかし、理科の先生から「絶対に3回目も受けましょう。受かる力があるから強く勧めています」と言われ、思い直しました。
ただ、弱気になっていたのは親だけで、娘は迷うことなく第3回を受けるつもりでした。3回つらい思いをするかもしれないのになぜ受けるのかと聞くと、彼女は言いました。「渋渋に行きたいから。最後まで受けないとあと味が悪い」
3日は第四志望校の入試をキャンセルし、母娘で原宿の竹下通りに遊びに行きました。4日ものんびり過ごし、過去問を30分だけ見直して、ベッドで理社の資料集を眺めて寝ました。
5日の朝。渋渋の先生方と在校生の皆さんが、この3日間で一番大きな声で、おはようございます、と迎えてくださいました。こんなに素晴らしい学校の入試に本気で挑戦できる、それだけで中学受験をする意味はあった。やりきった、悔いはないと思いました。
とはいえ私は全く受かる気がしませんでした。高倍率というだけでなく、あれだけ努力し過去問の点数も取れていたのに2回も不合格だったのだから、よほど縁がなかったのだろうと納得しかけていたのです。
6日、娘が小学校に行っている間に合格発表がありました。全く期待せずに画面を開くと、そこには娘の受験番号がありました。
いつもクールな表情の娘、小学校から下校し20分だけ家で休んでグノに出発していた娘、眠い目をこすって日曜特訓に出かけていった娘、夜遅く、塾帰りに改札から出てきた娘とコンビニで束の間の息抜きをしたこと、隣に座ってイラストを描いて笑い合ったこと。第1回と第2回の不合格を知ったあとの少しさみしそうな表情。5日の朝、一度だけ振り向いて手を振り、試験会場に入っていった娘。3年8ヶ月の色々な場面、交わした会話、思い出が一気に胸に押し寄せ、私は泣いていました。
小学校から帰り、お友達と遊びに行くという娘を引き留め、画面を開いてもらいました。「……あれ? あった!」控えめな笑顔ですが、心は喜びに溢れていることが私には分かりました。
2回不合格となり、悔しく苦しい気持ちを抱えながらもそれを表に出さず、自分を奮い立たせた娘。3回傷つく覚悟で、第3回に果敢に挑戦した娘を、ひたむきに渋渋を目指し自分の望む未来をつかんだ娘を、私は尊敬しています。あきらめなければ必ず道は開けることを、私は娘から教わりました。
折に触れ励まし、入試で通用する力をつけてくださった国語の先生、5日は受けるようにと強く勧めてくださった理科の先生、過去問の添削に応援コメントを添えてくださった算数の先生、記述を丁寧に添削してくださった社会の先生。土曜特訓、日曜特訓でお世話になった先生方。ご指導いただき本当にありがとうございました。いつも朗らかにご対応くださった受付の方々にも感謝申し上げます。
そして誰より、ともに切磋琢磨したグノ生の皆さんがいたからこそ、娘は最後までやり抜くことができました。皆さんと娘にとって、春からの新生活が楽しく輝かしいものになることを願っています。
これから受験を迎える皆さんにとって、この体験記が少しでもお役に立てば幸いです。息抜きを大切に、苦しいときはグノの先生を頼って、険しい道の先のゴールで合格をつかめますように。心から応援しています。

楽しい授業を思いっきり満喫してください
渋谷教育学園渋谷中学校進学Dさん
私は新3年生からグノーブルに通い始め、5年生の頃から志望校が決まり始めました。私はテストによって国語の成績に波があり、比較的得意な算数と理科と社会でバランスをとっていました。
ここで、私がやって良かったことや感じたことを科目ごとに書いてみました。
【算数】6年生の9月以降は、日曜特訓の復習を優先しました。私は最難関コースを受講しており、配られる開成プリントには難しい問題も多く、復習に時間がかかりましたが、授業中みんなはできて自分はできなかった問題を中心に取り組みました。分からないところは先生に聞けば分かりやすい解き方を教えてくれるため、積極的に質問に行った方が良いと思います。「基礎力テスト」は毎日朝にやる習慣をつけた方が良いです。受験当日は朝が早く、算数は一教科目のことが多いので、朝から頭を働かせることができます。
【国語】私は出題される文章によって出来が大きく異なりました。先生に相談し、解く順番(知識系、物語文、説明文)を意識し、直前期には漢字や知識を中心に勉強しました。
【理科】理科は、通常授業や土曜特訓、日曜特訓の復習を徹底してやりました。先生に言われた優先順位の◎〇△まではやるようにしていました。また、夏からは並行してグノラーニングチェックも何周かするようにしました。それで基礎をかため、実践演習の復習で応用問題にも触れるようにしました。また、理科の基礎力テストを毎日やることでも、基礎を固められます。
【社会】私はもともと歴史が好きで、一番得意な科目でした。旅行でお城がある地域などに行っているうちに、地理の知識も自然と身につきました。特に歴史は暗記が多い分野ですが、その出来事の前後のストーリーを覚えることで順番を覚えられました。公民は選挙に行ったりニュースを見たりすることで身につけました。
【渋渋を志望している人へ】私はGW講習では女子学院コースを、日曜特訓は最難関コースを受講しました。また月曜特訓の渋渋コースを11月から受講し、算数の過去問に触れることができる上、解き方を知っていればできる問題などについても教えてもらえました。
ちなみに私は、勉強の合間に甘いものを食べたり音楽を聴いたり、マンガを読んでリラックスしたりしていました。
グノの授業はとても楽しいです! 受験を乗り越えられたのは、一緒に通塾する友達の存在と、先生方のおもしろい授業やお力添えがあったからだと思います。グノの楽しい授業を思いっきり満喫してください!!合格を祈っています。

大きな経験と財産を得ることができた
渋谷教育学園渋谷中学校進学E君の保護者様
息子は新4年生の2月からグノーブルにお世話になりました。
最初、子供が毎週持ち帰るテキストの管理をどうすれば良いか勝手がわからず、ほぼ全てのテキストをPDF化して保存しておくという気の遠くなるようなことをしていました。コピーを保存しておくことで、何度も繰り返し書き込んで勉強できるようにと思ったのですが、はっきり言って必要ありませんでした。次々と新しい宿題がやってくるので、コピーしたものを繰り返しやる暇はありません。もしコピーを取っておきたいのなら、全部ではなく、特に苦手な科目で繰り返しやりたいところや、理科のグノラーニングチェックだけで良かったと思います。
また、4年生の最初のうちは、小学生が夕食も食べずに8時まで3時間も座りっぱなしで塾の授業を受けていると思うとかわいそうな気がするかもしれませんが、5年生では4時間授業になり、6年生では土曜特訓、さらにお弁当持参で丸1日の日曜特訓が増えるので、だんだん感覚がおかしくなってきて「今日はグノレブテストだけだから早いしラクだね」というような具合に、長時間の塾に子供も大人もだんだん慣れていきます。
ただ、子供を塾に送って行く途中に、近所で同学年の子たちが放課後に楽しそうに遊んでいるところを見ると、なんともいえず淋しい気持ちになり、家で自分ひとりで先に夕飯を食べていると「本当なら子供と一緒に過ごせる時間なのに…」と自然と涙がこぼれてきたことは一度や二度ではありませんでした。
しかし、塾から帰宅した子供を出迎えると、当の本人はいつも元気そうに「ただいまー!」と帰ってきました。元気そうな声を聞くと、きっとグノーブルの先生方が疲れを感じさせないくらい楽しい授業をしてくださっているのだろうと、少し安堵したものです。塾で机を並べて勉強を共にするうちに友人もできて、楽しく通ってくれているようでした。
とはいえ、塾は楽しみに行くだけではなく、きちんと授業内容を吸収してくることも大切です。勉強の仕方については、塾の指示通りに家庭学習を進めれば良いと思いますが、毎回の授業で疑問が残らないように、授業中にしっかり理解して終えなければ自力での家庭学習は難しいでしょう。家で復習するときに毎回わからないことだらけなまま次の授業に行ってしまう、というようなことがないようにしていかないと、あとあとわからないことが積み重なって大変です。1回1回の授業を大切に、授業中に吸収してしまうくらいの気持ちで受けるべきでしょう。
授業も宿題もこなしてはいるもののマイペースな息子で、一体いつになったら本気の受験モードになるんだろうと長い間見守っていましたが、結局、入試前日になっても親から言われないと勉強を始めないような有様でした。中学受験を始めてから終わりまで、終始他人事のような顔をしていた息子ですが、一度も「塾を辞めたい」と言ったことがありませんでした。年相応の遊びの誘惑を振り切って、長時間の授業や膨大な宿題、ほぼ毎週ある模試に取り組まないといけない中学受験という厳しい環境に耐えるのは、小学生には大変な苦難だと思います。それを最後まで続けられたのは、グノーブルの先生方や切磋琢磨してきた仲間たちのおかげでしょう。周りに言われるがまま勉強してきたように見える息子の3年間でしたが、実際はグノーブルで大きな経験と財産を得ることができたと思います。
3年分のテキストを処分しながら、本当によく頑張ったね、これで長いと思っていたグノーブル生活も終わりなんだねと、ほっとした気持ちと淋しい気持ちがテキストを結ぶ紐のように交錯し、我が家の受験を終えました。
皆さんも最後まで諦めずに続けることで、良い結果や結果以上に得られるものがあるでしょう。お世話になったグノーブルの先生方に感謝すると共に、皆さんの合格を祈っています。
渋谷教育学園幕張中学校
諦めないで毎日積み重ねていくこと
渋谷教育学園幕張中学校進学A君
グノーブルでの3年半は、とても大変だったけれど楽しかった日々でした。先生の授業は面白く、クラスメートとはわからないことを教えあったり、授業が終わったあとに一緒に帰ったり、良い仲間になれたと思います。
僕の第一志望校は渋幕でしたが、国語が苦手科目だったので、記述力を強化するために日曜特訓は麻布コースに参加していました。普段通っている校舎とは別の校舎で、いろんな校舎から集まるクラスメートと毎週席次を争うことにもワクワクしました。クラスにいた、算数がとても得意な生徒に時々復習テストの点数で勝てたことは、僕の自信につながりました。過去問や、日曜特訓、模試の問題を解いていて一番楽しかったのは麻布の問題で、学校で貼り出された合格発表の中に自分の受験番号を見つけたときは本当に嬉しかったです。
一方で渋幕の問題では苦戦することも多く、得意科目の算数でなかなか得点が上がらなくて弱音を吐きそうになることもありました。それでも諦めずに、11月からの渋幕特訓には全て参加し、過去問演習、グノの渋幕算数の問題集にも取り組みました。もちろん国語もです。麻布コースでは説明文の対策はしないので、土曜特訓の長文を、授業のあとに解き直して日曜特訓の朝に先生に提出し、帰るまでに添削してもらっていました。また、秋頃に、別の塾の渋幕対策講座に参加することも少し考えましたが、迷っていることを先生にも相談して、グノーブルの授業でどう対策していけば良いかを話して、僕はグノーブル一本でいくことにしました。家で復習をしてわからないことは、次の授業で先生に質問して解けるようになることを徹底しました。ここまでやっても、やっぱり試験の前日には少しだけ弱気になってしまったので、合格発表で僕の受験番号があることを知ったときには天にも昇るような気持ちでした。
これから受験生になる皆さんに僕から伝えたいのは、苦手科目があっても諦めずに取り組むことと、コツコツ積み重ねていくことの大切さです。そうはいっても、苦手科目にばかり時間を取られるのではなく、気分転換に得意科目に取り組み、得意科目での得点力をもっと伸ばしていくことにも力を入れていきましょう。僕は理科と社会の偏差値が良いほうでした。それは先生の授業がとても面白かったからです。ぜひ、グノーブルの先生の授業を受けて、興味を持ったことは家でもっと調べたり、本を読んだりして知識を広げていってください。それから、苦手科目の対策は、何度でも先生に相談して、試行錯誤しながら良い方法を見つけていってください。
他塾の模試は中学校が会場のものも多く、受験本番に備えて現地慣れするためにも受けました。午前中に模試、移動しながらお昼ごはん、午後から日曜特訓を受ける、というようなスケジュールも月に一度くらいありました。その日は、午後の復習テストでどれだけ頑張っても他のクラスメートよりは得点が低くなります。だから、翌週の日曜特訓は最後列になりますが、そこからまた最前列を取り戻す気持ちで取り組むことも良い刺激になりました。また、午前と午後で違う場所に移動して、頭をフル回転させるのは、午前受験・午後受験の予行練習になるので、もし迷っている人がいたらやってみることをおすすめします。
最後に、入試が終わっても、勉強することはずっと続きます。学ぶことを全力で楽しんでください。いつかどこかでこれを読んでくれた皆さんに会えることを楽しみにしています。
日々、楽しく学ぶ延長線上の中学受験
渋谷教育学園幕張中学校進学A君の保護者様
グノーブルに入塾したきっかけは、3年生の夏に買った問題集「G脳–トレーニング」でした。息子が問題を解きながら「とても楽しい!」と話してくれたことから、「グノーブルに通えば、得意科目である算数をもっと伸ばしていけるのではないか」と考えたからです。
もう一つの決め手は、水泳の選手コースとの両立が可能だったことでした。グノーブルの4年生の通塾曜日、そして5年生でも週に2回の通塾であることが、水泳の練習と重ならなかったため、選手生活をより長く続けられると考え、検討を始めました。
とはいえ、3年生の春からお世話になっていた別の塾からすぐに転塾する勇気もなく、秋頃から数カ月間はダブルスクール状態でお世話になっていました。
グノーブルは、文系と理系でクラス分けが異なります。国語は算数に比べると苦手だったので、実力に合ったクラスで適切な指導を受けることができ、一方で得意な算数は国語の成績に左右されることなく、ハイレベルな授業を受講して伸ばすことができました。授業で学んだことや、クラスのお友達とのやりとりを楽しそうに話してくれる息子の姿を見て、新4年生の春からはダブルスクールをやめ、グノーブルに専念することにしました。
授業、自宅学習・映像授業受講、グノレブテストと、やることが盛りだくさんで、大変に感じることもありました。しかし、定期的に開催される保護者会で、各時期の学習への取り組み方を科目別に詳しくご説明いただき、優先順位を明確にしながら進めることができました。また、保護者会後には先生方と直接お話しさせていただく機会があり、それ以外のタイミングでも、電話やメールでご相談すると、すぐに対応してくださり、親子ともどもモヤモヤをすっきりさせて前に進むことができました。
5年生のGW特訓では開成コースを受講していましたが、本人が少しずつ憧れるようになった第一志望校が渋幕だったこと、周囲の方々から本人のキャラクター的に麻布が合っていると言われたことから、以降の学校別特訓からは麻布コースの受講に変更しました。いずれのコースも、自校舎とは別の校舎で、普段と違う同級生と一緒に学ぶこと、志望校に特化した教材に取り組むことで本当に良い刺激を受けておりました。
6年生の秋からは渋幕特訓も受講しました。始まる前は復習と過去問演習が回るのだろうか…と、不安もありましたが、特訓は授業内で完結するので、キャパシティを超えることなく、着実に実力を伸ばすことができました。
受験が近づくにつれ、息子の状態に応じて先生方からさまざまなフォローをいただきました。緊張感が足りない時は、気を引き締めてやる気をもっと出すようにと活を入れていただき、逆に、どこにも合格しない気がすると弱音を吐くような時は、魔法の言葉で背中を押していただきました。グノーブルでなければ、渋幕、麻布、その他の学校からもご縁をいただけなかったと思います。
他塾の模試の結果は、結果が良くても悪くても都度先生にお渡しし、必要に応じて本人にフィードバックをいただいていました。国語が苦手なのに、なぜか麻布の長文記述問題の点が取れることに可能性を見出してくださった先生方、最後まで国語で苦戦していた息子のフォローをしてくださった先生方、提出期限ぎりぎりまで過去問を出し続けた息子の答案を添削してくださった先生方には本当に感謝しております。また、テキストの置き忘れなど、勉強以外のことでもよく通常授業・日曜特訓の校舎の受付の方にはお電話を差し上げたり、直接お伺いしてご相談させていただくなど、大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。
受験を終え、ご縁をいただいた学校の制服に袖を通した息子の姿を見て嬉しくなる一方で、もうグノーブルに通うことはないこと、息子の口から先生方の素敵なエピソードを聞けなくなることには寂しさも覚えます。しかし、塾に行かなくなり有り余るようになった時間を、お友達と遊んだり、放課後・土日のトレーニングに復帰したりするだけでなく、英語や数学の参考書を開いて自主的に取り組む様子に、グノーブルで身についた学習習慣が途切れず続いていることを実感し、とても頼もしく感じます。進学先でも、そして大人になってからも、「知の力を活かせる人に」という思いを大切にしてくれることを願っています。

グノーブル最高‼
渋谷教育学園幕張中学校進学B君
僕がグノーブルに入ったのは、3年生の春からです。きっかけは、兄が入っていたからでした。また、僕は好きな野球を辞めたくなかったので、1週間の授業日数が少ないグノにしました。最初の方はそれほど勉強をしなくてもクラスを保て、ずっと一番上でしたが、4年生の後期になるとクラスが急激に下がってしまいました。それでも、5年生になると算数を伸ばし、クラスを少しだけ戻すことができました。しかし、国語と理科はできないままでした。
6年生になっても成績は変わらないままでした。僕の転機になったのは、GW講習でした。他の校舎の人たちと3日間競い合ったことで、自分に自信を持てるようになりました。夏は勉強三昧の日々でした。僕は体力がないので、勉強さえすればよい夏休みは、学校に行くよりも好きでした。
9月になり日曜特訓が始まると、同じ夢を持った人たちと一緒に勉強することで、モチベーションが上がりました。僕が渋幕受験を考え始めたのは6年生の9月くらいで、それまでは何にも考えていませんでした。しかし、担当の先生に「〇〇(日曜特訓で受けている学校)はいいから渋幕の対策をしなよ」と言われたことで渋幕への気持ちが強まり、やる気が出ました。
11月になると、僕は渋幕特訓に参加。しかし過去問は各校1年分くらいしかやっていなかったため、毎日大問一つずつ取り組み、渋幕の算数に慣れるようにしました。これを1カ月やり、その後の過去問も高得点を取ることができました。
1月になるといよいよ入試です。僕は埼玉受験で前泊し、体力を消耗しないようにしました。また、第一志望校の入試ではA特待を取り、絶好調でした。しかし、千葉受験はそう簡単にはいきません。僕は1月20日の市川を受けましたが落ち、1月22日の渋幕は受かりました。つまり、市川が落ちていても渋幕は無理ではないということです。なので諦めないでください。僕は渋幕の前日にはグノの渋幕特訓の教材をやりこみました。そうすることで、不安なく受けられました。渋幕に受かった時は、とてもうれしかったです。
そして自分の本命だった2月校の2日前、2月1日の学校も順調に受かり、第一志望の2月3日の学校も受かりました。しかし、僕にとってはこれからが一番つらかったです。なぜなら、どこに進学するのか迷っていたからです。僕は、渋幕と2月3日のどちらにするのかを10日まで悩み、渋幕に決めました。
最後に言いたいことは「どこに行きたいかは変わる可能性がある。だから、どっちでも選べるように、努力をしてほしい」ということです。僕も、渋幕なんてどうでもいいと思っていれば、渋幕と2月3日の学校をどちらにするかなんて思わなかったと思います。だから僕は、渋幕を勧めてくれた担当の先生に本当に感謝しています。3年間ありがとうございました。渋幕で待っています。グノーブル最高‼
グノを信じて
渋谷教育学園幕張中学校進学B君の保護者様
2月が終わろうとしている頃にこの体験記を書いています。あの、毎日戦っているかのような気持ちで過ごしていた受験の日々がまだ今月のことだったのか、と不思議な気持ちです。
■3年生:教材を全てやっていたか、やっていなかったか、思い出せないくらいよく見ていませんでした。成績は悪くなかったです。ため込んだ「基礎力テスト」を一気に数日分やるだけの体力はありました。やった週の教材は○付けと直しができたものを先生に提出していたような気がします。
■4年生:土日祝は朝から夕方までスポーツで忙しく、平日だけでやりきれない教材もあったと思います。特に理科はなかなか手をつけられていませんでした。講習期間は絶対にテキストを全部やりきるぞ! と話し合い、チェック表を作ったらそれを全部埋めようと頑張る根性はありました。特に算数は頑張って、NもN家庭用もやっていたと思います。ただ4年生後期は成績が下降していたことに気付いておらず、先生に結構雑ですね(途中式も書いていない)と言われて気付くという状態でした。それを私(母)から聞いてからは、きっちりと途中の式なども書くようになり、あとで自分で間違い直しをするのが格段に捗るようになりました。その時の先生には感謝しております。
■5年生前期:算数は元々好きでしたが、4年生の終わりに上記のように取り組みを改善してから、成績がかなり伸びました。算数が安定してきたので、苦手の理科でも良い成績を取りたい、手をつけようと本人の気合が入りました。算数の先生に「αコースにおいで」と言ってもらったことで、一層やる気になったと思います。理科の先生には、算数ができるのだから理科もできるはずだとの励ましと(算数との偏差値差が凄かったです、今これを書きながら成績を見直して衝撃!!)、分からないところはいつでも質問に来て良いとも言っていただき、それを励みに理科もこなし、質問をして頑張っていました。理科は、どう手をつければ良いのか分からない状態から見てくださった先生に、とても感謝しております。
そうして理科が良くなっても、算数をミスしてあまり良くなく(悪くもないですが)算理が揃わず残念に思う月もありました。しかし算数の先生が、今回悪いのはやらかし程度なので特に気にしていませんと息子を信じてくれたので、私も特に何も言うことはなく、本人も次こそ算理を揃えたいと淡々と頑張りました。「今回は理科をすごく頑張ったから算数が手薄になってしまったのかもしれないけど、この調子で理科を保って、算数もまた力を入れれば両方成績が揃うかもね」と、息子とよく話し合っていたことを覚えています。受験生活を通してですが、やるべきことがあるのに時間をすごく無駄にしていることについて怒ったことはありますが、点が悪くて怒ったことは無いかと思います。一生懸命やった結果、点が振るわず一番悔しいのは本人だと思うので。
■5年生後期:算理は安定して良くなったので、次は国語です(社会は元々得意なのか? テキストを普通に全部やる、グノレブテスト前は範囲の基礎力確認問題のコピーをもう一度やるという学習で、算数に次ぐ安定した成績をずっと維持していました)。国語をどうにかしようと考えた結果なのか、ちょうど面白い本に出合ってハマったからなのか、この頃から小説を読むようになりました。スポーツ関連の本や新聞、知識系の本は以前から割と読んでいたので、字を読むことに抵抗は無いようでしたが、物語を面白いと読むようになったのは5年生の冬休み頃でした。冬期講習の合間に読書をするより勉強をもう少しした方が良いのでは、と思いつつもこれも勉強か、と自分に言い聞かせ、母は見守るのみ。社会の資料集なども同じ扱いで、これで知識を蓄えているんだろうなと思うことにしました。読書をしても国語の成績にすぐ反映はされませんでしたが、授業やグノレブテストで文章を読むのが速くなったよ! と本人は嬉しそうでした。
■6年生前期:「5年生が山場で、5年生の授業でやることを身につければ6年生はラクだ」という母子の共通認識で5年生を頑張ったので、6年生前期は少し気楽でした。4年生夏冬、5年生春夏冬と季節講習も乗り切ってきた自信があったので、6年生春期とその後のグノレブテストも好調でした。しかし6年生は学校生活が大変! 行事の中心となるので、充実してはいるものの、気疲れや居残り作業もあり、なかなか平日の勉強は捗りませんでした。出席日数を提出する志望校もあるからなるべく学校を休みたくないという気持ちもあり、体力と健康の維持が一番の課題でした。スポーツは心身ともに負担になっていたのと、本人も塾を優先したい気持ちが大きかったので春に辞めました。
GW講習では同じ志望校の子たちと顔を合わせて勉強をし、夏期講習でまた会える! と励みになったようで、6、7月は夏期を待ち遠しく勉強をしていました。国語はやりたくないわけでは無いけど、つい後回しになる状況で不安なままでした。理科は気付けば得点源になっていました。5年生の前期、理科が厳しい状況だったのは、苦手な「植物」の単元のせいで、物理、地学、化学の計算などは割と学習がスムーズだったのかなと思います。息子は理科が単元によって成績の変動が大きかったです(なので1回のグノレブテストで悲観なさらず!)。
■6年生夏:6年生の夏は朝~昼まで家庭学習、午後は夏期講習を頑張りました。夏の総勉強時間は○○時間! みたいな話を見聞きするかと思いますが、息子は夏休み約40日、授業と家庭学習合わせて300時間くらい勉強しました。各教科の割合は、算2:国1:理1:社1という感じでした。得点源の算数は全部やりたい、社会も着手しやすい、次いで理科、国語という優先順位になっていました。理科は課題のグノラーニングチェックは数回やりました。国語は有名中問題集の課題が毎日のようにあったので、それで普段よりは取り組めていました。女子校の国語などはなかなかつらそうでした。
■6年生秋:夏もやり切ったので、他塾模試の成績が良くなりました。
ここで渋幕受験が現実的なものとなってきました。2月1日、3日の受験校には安定して偏差値は届いていたものの、志望度の高い両日の間の2日に渋幕チャレンジをする勇気は親子ともにありませんでしたが、先生方から「そこを受けられることが幸せですよ」と言っていただき、決意が固まりました。日曜特訓が始まり、平日、土曜特訓、日曜特訓の復習で手一杯で過去問はなかなか進みませんでしたが、1日校の感触が日曜特訓授業内でも学校別オープンでも良かったことは心の支えでした。もう6年生秋、遅ればせながら息子と一緒に渋幕の学校見学に行き(母だけはグノーブル主催の説明会と学校主催の見学会に行っていました)、見学して本人も気に入り、1日の対策よりも平日に開催される渋幕特訓に行ってみたいと言い出し、気持ちが渋幕に傾いてきました。
渋幕の問題は難しいけど楽しいよ、算数は慣れればできると思う、理社は時間次第、と本人は言い、挑戦の立場ながらも毎回の渋幕特訓を楽しみに受けに行っていました。算数は先生おすすめの「渋谷教育学園幕張中合格への142題」から、渋幕ならではのグラフや作図や図形の問題を毎朝やりました。算数が好きなので、すぐ手を付けられるし短い時間で終わるので取り組みやすく、良かったです。朝から重たいもの(気分もボリュームも)でなく、楽しく続けられたかと思います。
渋幕特訓について先生は「本人がやりたいのなら」というスタンスで、いつも息子の状況を見てくださり、息子の希望を優先するように促してくださったのがとても有難かったです。本人にやりたいという意思がないのに負担を増やしたら潰れることもあるかもしれませんが、自分でやりたい、必要、と思うことだから頑張れたのかなと思います。
スケジュールに無理がなく、興味のあるお子さんにはオススメです!特訓担当の先生方は初めて習う先生ばかりでしたが、丁寧に見てくださりました。11月からやっと過去問もコンスタントに着手できるようになりました。
■6年生冬期~直前:冬期になれば夏期と同じで学校が無いからラクかな? と期待していましたが、講習テキストの物量がすごく、また体調も崩したので大変でした。結局手つかずだったテキストもありますが、この頃には本人がやるものやらないものを取捨選択していました。体調を崩した時は、割り切って回復に努めました。やれない間に焦る気持ちもあるかと思いますが、そういう時に無理にやっても身にならないので、しっかり治してから集中してやる、というのは、体力が無く体調を崩しやすい息子が受験生活で身を以て学んだことでした。調子が良ければできることも、調子が悪ければできなかったりします。グノレブテストが全然良くなかったと思ったら、翌日から発熱なんてこともありました。とにかく体調管理に気を遣った後期だったと思います。
渋幕志望の方は冬期・直前講習に渋幕コースがないので、先生に相談すると良いと思います。どこのコースが合うか、先生が親身になって考えてオススメしてくださったのがとても有難かったです。
■1月:埼玉、千葉入試はなるべく負担を減らして、良いコンディションで試験に臨めるように前泊。万全の態勢で本番に臨めました。ここまで来ると、無理せず睡眠も大事に、実力を発揮できるよう、とにかく健康のことばかり気にしていました。グノーブルの授業は楽しみだったので、試験前日以外は全部出席しました。
■まとめ:親が教えたり、家庭教師や個別指導を受けたりしなくても、グノーブルの教材をコツコツと、指定の範囲は全部やるつもりで(最初はやりきれなくてもできる量は増える!)、間違ったところはしっかりと直す(最初から全部できなくても、間違ったところを修正していくのが勉強!)など取り組んでいけば、学力が身につき伸びていくと思います。
私はテキストの内容を教えることはしませんでしたが、先生とたくさんお話させていただき、現状の確認ややるべきことを教えていただき、それを息子と共有しました。保護者会のプリントやメモなども息子はよく読んで、学期ごとの見通しを持っていました。
グノーブルの先生のことがとても好きだったので、私自身先生の話をよく聞きましたし、自分でも先生とよくコミュニケーションを取っていたと思います。先生と話したことのメモは度々読み、受験当日にも読み返しました。親も支えていただいたと思います。少人数で目が行き届いているグノーブルに通塾して良かったです。これを読んでいただいた方も、グノを信じて真摯に頑張ってください。
千葉県立千葉中学校
伴走して良かった
千葉県立千葉中学校進学A君の保護者様
息子は、3年生の冬期講習からグノーブルにお世話になりました。3歳上の姉も4年生の冬からグノーブルでお世話になっていました。「グノの授業は楽しい。少人数なのでみんなでワイワイ授業に参加できて面白い。先生の知識も半端じゃない」などと言って、嫌がるそぶりもなく元気にグノーブルに通う姉の姿を見て、息子も「グノーブルに行って中学受験をする」と決めたのでした。それ以降、息子も楽しみながら最後の受験まで走り抜けてくれたと思います。
この度グノーブルの指導のおかげで、息子は姉の進学先でもある公立の志望校に合格できただけでなく、複数の併願私立校からも合格をいただきました。ここに至るまでは全くもって平坦な道のりではありませんでしたが、息子の口から「グノーブルに行きたくない」とか「中学受験をやめる」というセリフが出たことは一度もありませんでした。姉と同様に、グノーブルで良い先生、良い演習教材、そして良い友達かつライバルたちに恵まれて、厳しくも楽しい学びを続けることができたのだと思います。
グノーブルの先生方、スタッフの方々、教材やカリキュラムの編成に携わっていらっしゃる方々には、上の娘の入塾から下の息子の合格に至るまでの約5年間にわたり、質の高い学びと成長の場を子供たちに提供してくださり深く感謝しています。
以下、我が家の姉弟2人の受験を通じて感じたことなどを、思いつくままに書かせていただきます。
🔳基本を徹底して定着させることが大事だと思います:ほとんどの中学校の場合、合否は、各科目の基本問題をいかに取りこぼさないかということにかかっているのではないかと思います。算数・理科の「基礎力テスト」に毎日取り組むこと(できなかった日の分は後日頑張って追いつくこと)や、国語は「漢字道場」テキストや通常授業テキストの知識問題等にしっかり取り組むこと。社会通常授業テキストの「用語の確認」や土曜特訓テキストの「基礎知識の確認」等に漏れがないよう取り組んでいくことが大事だと思います。そして、毎週の授業時の確認テスト・復習テスト・漢字テスト等で、なるべく高得点を取り続け、上位クラスに残れるよう頑張ることが、最後には積み重ねとして受験の結果に反映されるのではないかと思います。
🔳やはり算数が大事で、演習量がものを言いました:算数を苦手科目にしてしまうと、受験戦略を立てるうえでなかなか厳しいのではないかと思います。その点グノーブルのカリキュラムは、基本レベルをしっかり押さえつつ、授業で先生からテキストの重要問題・応用問題を反復演習するよう宿題が出されるので、それを頑張ってこなしていけば、少なくとも算数が「大きく足を引っ張る」状態ではなくなると思います。出される宿題の量は多く、全てをこなせないときもありましたが、それでも頑張って食らいついていくしか力を付ける道はないのではないかと思います。
それに加えて、夏休みなど時間に多少の余裕がある時期には、先生から算数のテーマ別「基本の制覇問題集」シリーズや「グノワークアウト」シリーズも解くよう勧められ、それらも可能な限りこなして演習量の積み増しをしました。
それでも我が息子は、グノレブテストや模試等の際に、単純な計算ミスや、問題文中の設定の読み飛ばしなどの「凡ミス」を繰り返す癖がなかなか抜けず成績に波がありましたが、そういったミスについても見直し復習をして、何とかめげずに演習を続けました。
最後は、こうしたたくさんの演習を通じて伸ばした力と、「ここまでやったのだから」という本人の自信がものを言うのではないかと思います。
🔳社会・理科をコツコツやって得意科目にできると有利です:息子は、5年生の途中まで理科が苦手科目でした。しかし、グノーブルの社会・理科は、同じテーマについて時間を置いて繰り返し取り上げる「スパイラル式」で知識の定着を図ってくれるカリキュラムですので、そこで出された課題や暗記物をさぼらず地道に繰り返していくことで、理科も5年生の後半以降から次第に得意科目となりました。6年生の秋以降、入試を見据えた模試が続きましたが、算数や国語の成績には波があった一方、社会・理科が安定して得点源になってくれたので、その力を信じてやや強気に受験校の選択肢を考えていくこともできました。
また、社会のうち公民分野については、受験生全体の傾向として、地理・歴史分野に比べて学習が手薄になりがちだと思います。入試での公民分野の出題の比重は決して軽くないので、公民分野の基本知識について重点的に対策するのが効果的だと思います(某中学校の入試説明会でも社会科の先生がそうおっしゃっていました)。
🔳国語や社会・理科の記述問題は、添削を受け続けることでレベルが上がりました:息子は記述問題が鬼門でした。国語では文章を読み取れていても、社会・理科では、書くべき知識はあってもそれらを採点者に伝わるような分かりやすい文章にまとめることが大の苦手でした。この点についても、グノーブルの国語は、早い段階から記述問題を多く取り上げ、先生方が丁寧に添削してくださるなど、少人数制の強みを生かした指導をしていただけたのが大変ありがたかったです。また、息子は多くの記述問題や作文課題が出される適性検査型入試の県立中高一貫校を志望していたので、記述・論述力を伸ばすべく、6年生秋からの日曜特訓で、記述問題が多い麻布中学の対策コースを受講しました。ここで集中的に鍛えられた結果、秋が深まる頃には、だいぶ読みやすく意図も伝わりやすい記述答案を書けるようになりました。このことは、中学入試にとどまらず、今後の息子の勉学や人生にとって大いにプラスになったと思いますので、とても感謝しています。
🔳過去問指導もきめ細かにしていただき、十分な対策ができました:6年生の夏休み明けからは、保護者会で説明していただいた過去問対策のやり方に沿って、親が計画を立て、可能な限り受験予定校の過去問を解き、その答案を4教科それぞれの先生に提出するということを毎週繰り返しました。返却される答案には、この問題は落としてはいけないので当該分野の基礎知識を要確認、といったような具体的なアドバイスが書かれていたり、記述問題の添削をしてくださったり、算数については、解けなかった分野の「弱点」を補強するため、類題をたくさん付けて答案を返していただきました。このような算数の「類題つぶし」は、最後の受験日直前の1月下旬まで続けていただき、それが合格という結果に結び付いたのだと思います。また、通常の入試とは異なる適性検査型入試の過去問についても先生方に多くの答案を見ていただき、きめ細かに指導していただけました。
このように、受験前の最終段階における過去問対策でも、グノーブルの少人数制の強みを生かした緻密な指導のありがたさを強く感じました。
🔳親はテキスト類や勉強予定の管理と子供の心身の健康管理に徹しました:たくさんのテキストや演習資料が毎週たまっていく中、その整理作業と、家庭学習や過去問対策の計画を立てて実行してもらうこと、そして息子の希望や合否の状況等を踏まえて入試日程の戦略を立てることなどは親の役目でしたが、勉強の内容に関しては、基本的に塾での指導にお任せし、家庭学習で解決しない疑問については、塾で息子から先生に質問をするように言いました(面倒くさがりでなかなか質問に行きませんでしたが)。今の入試傾向や生徒の実力をよく知る先生方による指導の方が、親の指導より適切だと考えたためです。
息子の気持ちが乗らないときや疲れているときなど、それでも課題がたくさんあると、ちゃんとやってほしいと強い口調で言ってしまったり、夜遅くまで勉強させてしまったりしたこともあり、親として反省しています。まだ小学校高学年では体力や集中力に限りがあり、成長途上でもあるので、まずは睡眠を取ることを最優先すべきでしょう。息子の場合、6年生の夏前頃から、その日の課題が終わらなくても強制的にこの時間になったら入浴して寝る、といった方針をできるだけ徹底することにして、睡眠不足にならないよう心がけました。結果的には、そうした方が勉強のパフォーマンスや集中力が上がり、積み残した課題も後から追いつくことができ、成績も比較的安定するという好循環に戻ることができました。
以上、色々と書きましたが、中学受験を通じて一番苦労をし、一番成長するのは、子供自身です。入塾した当初に比べて、本番の試験会場に向かう際の息子は、きちんと自我が芽生え、集中力も増し、目標に向かって進んでいく逞しさを備えていました。そんな子供の成長を日々実感できる中学受験は、厳しくも貴重な経験だと思います。グノーブルに通う生徒の皆さんが、健康で、楽しみながら、学びを積み重ねて目標を達成されること、そして保護者の皆さんも「伴走して良かった」と感じられるような結果が得られることを願ってやみません。
筑波大学附属中学校
多くの人たちに支えてもらった受験
筑波大学附属中学校進学Aさん
私は筑波大学附属中学校に合格することができましたが、1月の埼玉の受験では不合格を経験しました。その時は本当に自信を失い、心が折れそうになりました。しかし、そんな時にグノーブルの先生方の励ましが私を支えてくれました。国語の先生は電話で「ここからがnew〇〇だ!(〇〇は私の名前)」と言ってくださり、落ち込んでいた気持ちをリフレッシュすることができました。また、日曜特訓で塾に行ったときに、社会の先生が寒い1月の朝にもかかわらず、建物の外で待って励ましの言葉をかけてくれました。その温かさに触れ、さらに頑張ろうという気持ちが湧いてきました。こういったことが私にとって大きな励みとなり、受験を乗り切ることができたと思います。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
勉強面でも、グノーブルの先生方の熱心な指導のおかげで基本的な力をしっかりと身につけることができたと思います。特に居残りでつけた算数の力は最後まで私の受験の武器になりました。先生方のサポートがなければ、この結果は得られなかったと思います。
これから受験をする人たちに伝えたいことは、グノーブルの先生を信じて、宿題やアドバイスの内容をしっかりとやり遂げることが大切だということです。そして受験でもし不合格となった時には想像を超えるようなショックを受けることになりますが、それでも最後まであきらめずに頑張り続ければ、必ず良い結果がついてくると信じることです。
最後に、お弁当を作ってくれたり、塾の送迎をしてくれた両親、受験の追い込みの時にテレビとかいろいろ我慢したり私の上履きを洗ってくれたりした妹にも心から感謝しています。家族の支えがあったからこそ、ここまで頑張ることができました。
私の受験は多くの人たちに支えてもらいました。本当にありがとうございました。
子供の手が離れていく瞬間
筑波大学附属中学校進学Aさんの保護者様
グノーブル最後の授業の送迎の時、ふと幼稚園最後の日のことを思い出しました。「こうやって手をつないで登園するのは最後だから何だか寂しいね」と言うと、娘は「小学生になっても手をつないで歩けばいいじゃない。パパはおかしなことを言うね」とケタケタと笑いました。もちろん、小学校に入り成長してくると、もう恥ずかしがって外で手をつなぐことはしてくれません。しかし、中学受験は実際に手をつなぐわけではありませんが、親がある程度のフォローをしながら一緒に歩んだ道だったと思います。
入塾から3年の月日が流れ、ついにやってきた我が家の受験は決して平坦なものではなく、1月受験で立て続けに2校不合格となるところから始まりました。どちらも2点差でした。そのあとに受ける学校はどこも難易度がさらに高くなることもあり、娘は「もうどこにも受からないかも」とすっかり自信を無くしてしまいました。涙で腫れた目をこすりながら、消え入りそうな声で「次は合格する…」と勉強を続ける娘の姿を見るのがとてもつらく、また、親としては併願校の組み直しや、最悪、第一志望校の変更など現実的なことを考えなければならず、厳しい数日を過ごすことになりました。
そのような中、グノーブルの先生から励ましの電話をいただいたことなどをきっかけに、少しずつ娘に活気が戻っていきました。そして、1月受験校で最も合格したかった浦和明の星中学…合格。家族みんなで泣いて喜びました。この後、2月の東京受験までの約2週間ちょっとの間で娘は大きく変わりました。それまでも、塾の宿題をコツコツと頑張る子でしたが、あくまでも「宿題をこなす」という域を出ていなかったように思います。1月受験を超えてからの彼女は、例えば同じラーニングチェックをするにしても、「入試に出るのだ」ということを強く意識し、どん欲に間違えたところをつぶし込んだり、少しでも不安な分野に自ら取り組んだりするようになりました。その姿を見て「まるで大学受験生のような勉強をするね」と妻とともに目を丸くしたものです。過去問の得点力が目に見えて急上昇していき、これはいけるのではないか、という感触とともに1月を終えました。
迎えた2月、熱望していた1日校の不合格。泣き崩れる娘。しかし30分後には「明日の筑附は絶対に合格する」と勉強を始めました。その姿は、1月の不合格時の弱々しいものではなく、高い壁に再び挑戦できることを楽しむような力強いものでした。
筑波大学附属中学、娘の最後の中学受験、私は前日にあれこれ声掛けを考えていました。送り出すとき「この3年間…」と言いかけたところで、娘は「わかったわかった、じゃあ最後は気楽に楽しんでくるね」と言って、振り返ることなく校門に入っていきました。手が離れていくことをはっきりと感じた瞬間でした。 最後に、娘が良い形で中学受験を終えることができたのは、グノーブルの先生方に鍛えられた本質的な力と、受験期の細やかなフォローのおかげだと思います。本当にありがとうございました。

グノーブルでの3年間
筑波大学附属中学校進学B君の保護者様
グノーブルに通い始めたのは3年生の2月からでした。周りのお友達が塾に通い始めているのは気になりましたが、先は長いから途中で疲れないように、塾が負担にならないようにと、我が家はあまり早くから塾に通うのは避けたいと思っていました。説明会でグノーブルの教材を見て、何十年も前の私自身の中学受験の時に、B4版のプリントを一生懸命暗記していたことを思い出し、この教材で勉強したらきっとうまくいく気がして、グノーブルに通うことを決めました。
我が子は、頭の回転は速い、記憶力は良い、同年代の子と比べて少し大人びているところがあるタイプでした。中学受験は精神年齢の高い子に向いていると言われることがあるので、その点では向いていると思いましたが、一方で、面倒くさいことはしたくない、几帳面さがない、字が汚い、計算が嫌い、集中力がない、物事をコツコツすすめる努力型ではない、といった部分があり、のちにこの短所が足を引っ張るのではないかと心配でした。
グノーブルに通い始めると、面倒なことが嫌いな我が子は、グノーブルに行くのを嫌がることがありました。4年生の時は、特にお気に入りの先生がいて、その先生の授業は熱心にノートを取っていたので「塾に行きたくない」と言う時は「○○先生の授業があるから行こうよ」と励ますことが多く、この先生のおかげで大変助けられました。ところがこの先生が5年生に上がった時に、他の校舎に異動されてしまいました。このときのショックは大きく、もうグノーブルに通うのを辞めてしまうのではないかと思うほどでしたが、日が経つにつれ、他の先生方が楽しく授業をしてくださったおかげでショックからは立ち直ったようでした。グノーブルの先生はどの先生も楽しく面白く授業をしてくださり、6年生の時には、土曜特訓や日曜特訓で長時間授業を受けたあとでも、家に帰ると、今日の授業はこんなだったよーと先生のモノマネを交えながら機嫌良く話をしてくれて、良い先生に恵まれて大変良かったと思っています。
あまり几帳面な性格ではなく、字が汚いのが悩みでした。保護者会で、このような解答の書き方はやめてくださいと例に挙げられるような字をよく書いていました。家では「字が判別できません」のマークを作って丸つけの際に使っていましたが、全く効果がありませんでした。入試直前にいただく激励電話でも、先生から「字をきれいに書くように」と言われていました。漢字テストを見ると、6年生の最後の方は丁寧に書いていることもあるので、書けないわけではないようでした。さらに保護者会で言われた「計算が苦手なタイプ」にもぴったり当てはまりました。字が丁寧でない、問題文の上に計算を書く…など。4年生の小数・分数の単元は本当に苦労しました。まためんどくさいからと言って、書くこと自体を嫌いました。理科や社会の問題を解く時は、テキストに書き込むかノートに書くのが普通かと思うのですが、うちの場合は子供が問題を持って答えを読み上げ、私が解答を見て○か×を言うという形式で、6年生の最後まで理社はほぼこの形式でした。覚え方・記憶の仕方は人それぞれだと思うので、彼の場合は書かない方式なのだと思ってやってきましたが、書かないので時間がかからないという利点はあったと思います。
苦手な部分は多々ありますが、5年生の1月の実力テストではメダルをいただき、6年生の4月に受けた模試では偏差値60くらい、志望校の合格判定は60〜80%ほどで順調でした。しかし、この好成績に気が緩んだのか、その後緩やかに模試の成績が下がり、6年生12月の模試では偏差値が4月に比べて10も下がり、志望校の合格確率は20〜30%になってしまいました。グノレブテストの成績も、良い時では65くらいあった算数の偏差値が50以下になったりという、安定しないものになりました。
ただ、模試やグノレブテストでは点数が取れませんが、普段の授業のテストはそこまでは悪くはなく、また、9月から始めた過去問は合格者平均を上回る点数が取れていましたので、志望校を変えることは考えませんでした。そして、6年生12月の最後のグノレブテストの算数は偏差値50以下という成績でした。家では勉強はしていましたが、遊んでいる時間も今まで通りで、受験生とは言い難い生活でしたので、遅すぎるとは思いましたが、ここで心を入れ替えて勉強しようと思い、先生にどうしたら良いかとご相談したところ「基本の確認」をやること、単元別の問題をやること、筑附でよく出る立体の問題をやること、などアドバイスをいただいたので「基本の確認」を一から始め、立体の問題集を買って家でやることにしまいた。さらに、スピード感がない、と指摘されたので、基礎力問題集や「基本の確認」をやる際は制限時間は設けないものの、時間を計ってやることにしました。時期的には遅すぎると思いますが、本人もここでようやく真剣に勉強する気持ちになり、遊びやゲームはきっぱりやめて、真面目に勉強するようになりました。
第一志望校であった筑附の問題は、グラフの問題が出たり、図版の読み取りなどがあるので、公立中の適性検査を解いてみたり、家にあるグラフ資料を使って問題を作成して解いてみたりしました。グラフ問題は小学校の授業で習うので、学校の授業をしっかりやっておくのも良いと思います。また、グノーブルで12月から開講する筑附特訓は、土曜特訓と同じ土曜日の午前中で、受講すると貴重な休みの時間がなくなりますが、問題に慣れるために頑張って受講しました。その甲斐あって、無事に筑附から合格をいただくことができました。
中学受験に関して親のすることは、勉強しやすい環境作りではないかと思います。一緒に問題を解いたり、教えたりもしましたが、実際に授業を受け、家庭で学習し、入学試験を受けるのは子供たちです。彼らを信じて、そっと寄り添って環境を整えていれば良いと思います。一時は成績が低迷し、全落ちも覚悟しましたが、無事に合格して受験を終えることができました。グノーブルの先生方には大変お世話になり本当に感謝しております。
桐蔭学園中等教育学校
奇跡を起こしました
桐蔭学園中等教育学校進学Aさんの保護者様
グノーブルの先生方の粘り強いご指導と素晴らしいテキストのおかげで、持ち偏差値からすると奇跡のような合格を勝ち取ることができましたので、これから受験に臨む方々のために記録を残します。
親の目線で、今回の合格に至ったポイントは、①「基礎力テスト」の間違い問題の解きなおし(何度も繰り返す)、②相性の良い学校の発見、でした。①を着実に行った結果、ラストスパートで、苦手だった算数が一気に得意科目になりました。②は自らの反省も込めて、子どもの興味がある学校の過去問は、偏差値にとらわれずに幅広く着手してみる価値があった、ということです。手が届かないかな、と思っていても、意外と過去問が解けることにより子どもの意識が変わり、「この学校には絶対に合格したい、自分ならできる!」という強い気持ちが、最後の一押しにつながりました。我が家の場合、進学先の過去問に着手したのが1月に入ってから、「意外とできるかも?」が続き、「2月1日に受験しよう」との決断に至ったのは1月28日でしたので、もう少し、特に心の面での余裕を持った準備をしておきたかったです。
怒涛のような最後の1か月となりましたが、2月1日の夜、これまでの成績からはとても信じられないような合格が出ました。
「最後まで成績は伸びる」、この言葉を聞いたときには半信半疑でしたが、目の前の自分の子どもがそれを実現させました。奇跡は起こります。最後まで熱心に教え、的確なアドバイスをくださったグノーブルの先生方と、一緒にがんばり励まし合ったお友だちの力で、ここまで成長することができました。心から感謝しています。本当にありがとうございました。
東京都立小石川中等教育学校
グノーブルを信じて良かった
東京都立小石川中等教育学校進学A君
僕は新4年生からグノーブルに入塾しました。グノーブルに決めた理由は、①(自分の志望校では記述の出題が多いため)記述に力を入れていること②生徒やクラスの雰囲気が良さそうだと思ったからです。
ここでは主に、第一志望の小石川中等教育学校について書きます。小石川中は適性検査という独自の問題を出し、思考力や表現力を見る学校です。僕は私立も都立も受けることから、それぞれの対策が必要なので勉強が大変でした。
特に対策をしたのは「適性検査Ⅰ」です。本格的に都立中の対策を始めたのは、6年生の夏からです。それまでは国語の読解を読み込むようにしていました。
僕は記述が苦手なので、夏頃までの記述はなかなか満足のいくものではありませんでした。秋から適性検査Ⅰの過去問を解き始めましたが、私立中の国語と違って、思ったように書けず悩んだこともありました。しかし、先生に添削をお願いし、もらったアドバイスを意識したことで、書く力を伸ばしました。適性検査Ⅱ、Ⅲは自宅で過去問を解き、対策しました。
僕がグノーブルに通って良かったことは二つあります。
①先生にたくさん質問できることです。一クラスが少人数なので、順番待ちが少ないです。また、いくら質問してもきちんと答えてくれます。
②友達と切磋琢磨できることです。同じクラスで学ぶうちに、周りの生徒と仲良くなれます。仲間だけどライバルなので、「この人には負けたくない」という競争意識が芽生えました。
最後に、これから受験する皆さんに向けてのアドバイスです。
①必要な睡眠時間は必ず確保しましょう。睡眠不足だと疲れやすく、集中力が続かなくなります。
②知識ものはカードなどに書いてゲーム形式で覚えると良いです。僕も年号プリントの内容はカードに書いて覚えていました。
③勉強ばかりではなく読書も楽しみましょう。語いが豊富だと記述力が上がります。
④息抜きも大切です。自分に合った息抜き方法を見つけてください。
入試当日は今まで努力を積み重ねてきた自分を信じて、精一杯力を発揮してください。応援しています。

自分を信じる=受かる!
東京都立小石川中等教育学校進学Bさん
☆やるべきこと
🔳計算練習は毎日やる:私は4、5年生の頃はあまり「基礎カテスト」も計算マスターもやっていなかったため、計算力がとても弱く、適性Ⅱの社会の計算に苦労しました。6年生の秋以降に、過去問演習のかたわら、毎日「基礎力テスト」とは別に計算練習をする羽目に陥りました。
🔳グノの授業の間違い直しと指示された宿題は絶対にやる:それだけで、都立の適性Ⅱ、適性Ⅲに必要な知識が身につきます!
🔳過去問はあきらめずに何度でも提出しよう:返却された答案は見直しして終わりにせず、指摘事項をよく読み、書き直して再提出してもう一度採点してもらいましょう。記述のコツが身に付き、得点力が上がります! 私は適性Ⅰの作文は満足できる点数になるまで3回ほど書き直して再提出していました。
あとは、今までの自分の頑張りを信じるだけ!たとえどれだけ難しいと感じても、そう思っている人は自分だけではありません!きっと、周りにいる他の人たちも難しいと感じているはずです!最後まであきらめず、気を抜かず、一生懸命やれば、きっと受かるので、頑張ってください!!!!

THE凡人の体験記
東京都立小石川中等教育学校進学Cさん
私は、皆さんが驚くほどの努力をしていたわけではないし、習い事も回数を減らしながら6年生の9月くらいまで続けていました。しかも、算数、理科、社会では偏差値50を切ることも多々ありました。ただ、先生の授業が面白く、幼い頃から本を読んでいて、文系が好きだっただけです。
そんな凡人にもかかわらず、私はだいぶ強気な、自分が行きたいと思う学校だけを志望校にしました(もちろん様々な偏差値帯の学校は組み込みましたが)。それでも、グノの先生は念を押しながらゴーサインを出してくれました。結果は意外なことに、受験した学校全てにご縁を頂きました。その理由を自分なりに考えると、二つ挙げられます。
一つ目は、グノの授業中に出された宿題を、全てはできなかったもののなるべく終わらせたこと。
二つ目は、一つ目のことをある程度できていたからこそ、緊張はしたけれど平常心に近い状態で試験を受けられたこと。
ここから先は、前の二つのことに関して、私はやらなかったけれどやっておいた方が良かったことや、自分のちょこっとした経験を書こうと思います。
🔳一つ目に関して:私は通常授業に関しては、△や×以外はほとんど終わらせるようにしていましたが、日曜特訓や土曜特訓では後半から時間がなく、一番苦手科目だった理科は○も終わらせられないことがありました。そのため、理科と社会は4・5年生からグノラーニングチェックや社会の知識の問題冊子を何度もやり、6年生になったら更に知識の総確認や昼テストなんかもやっていれば全く違ったな、と思います(時間がないのは痛いほど分かるけれど、将来の自分のために、短い時間でも良いから頑張ってください!)。
結局、日々の宿題をしっかりと理解しながら終わらせるのが大切。グノの宿題をしっかりとやっていれば、夢は叶うはずです。
🔳二つ目に関して:平常心でいられた一番の理由は、家族がいつも通りだったことです。そう言われても難しいかもしれませんが、「自分を受からせないでどうする?」と強気で過ごしましょう!
私は、試験前の時間に先生が添削してくれたものを見たり、先生や好きなアーティストの顔を思い出したりしていました。
🔳最後に:テストや模試の結果が悪くて落ち込む時もあるけれど大丈夫。グノの先生や家族は頑張っていることを知っているし皆応援しています。
その原因を自分で調べて忘れなければ良いだけです。私の場合は、ほとんど計算ミスと思い違いで、最後までなくなることはなかったです。でも、丁寧に、誰よりも丁寧に努力して書こうという気持ちがあれば、こんなうれしい結果になることもあるんです。どうか、最後まで笑顔で走り抜けてください。グノーブル、先生方、ありがとう。
「明日は明日の風が吹く 報われずそっとナミダ零れても この背中を自分で押さなきゃ誰がやる いつかは空にも虹が出て それだけをきっと願い続けてる 答えは風の中 道は続いていく」(好きなアーティストの1曲より)必(🌸)合格
東京農業大学第一高等学校中等部
後悔がないように暗記問題に励む
東京農業大学第一高等学校中等部進学Aさん
私は社会が苦手でしたが、入試の一か月ほど前から、今までの暗記問題を再度書いて覚えているかを確認し、覚えていないものは繰り返し書きました。その結果、入試一か月前には解けなかった問題が、受験直前には解けるようになりました。また模試で間違えた問題を直前にまとめて解き直すことで、何回も間違えた社会の問題ができるようになりました。それによって自信をつけることができました。さらに、毎朝「基礎力テスト」を欠かさないことも大切だと思います。私は実際に入試で理科の「基礎力テスト」の問題が出ましたが、その日は丸付けができていなかったので正解が分からず、とても後悔しました。
受験生の皆さん、社会と理科の暗記問題は本番が始まる直前まで伸びます。私は、そのことを身をもって実感しました。後悔がないように、落ち着いて暗記問題に励み、力を出し切ってください。
グノーブルの先生を頼って
東京農業大学第一高等学校中等部進学Aさんの保護者様
私と娘がグノーブルを選んだポイントは、先生方や教室の雰囲気の温かさでした。初めての保護者会での「お子さんの心のサポートは親御さんにしかできない部分がある。親御さんの心のサポートは私たちを頼ってください」という先生の言葉がとても心にしみました。
いざ始めてみると、成績はその時によって差がありすぎて、志望校のレベルが全く分からない状況でした。けれども面談時、先生に国語と算数の出来を褒めていただけたことで、社会の成績が壊滅的だったにもかかわらず、志望校に希望を持てるようになりました。
本人の強い希望で東京農業大学第一を第一志望校に据え、結果によって受験校を変えるという日程で挑むことになりました。
1日目は午前午後とも東京農業大学第一を受けましたが、結果は不合格でした。それによって2日の受験校が変わりました。それを2日の朝に本人に伝えなければなりません。それを本人がどう受け止めるのか。この日を迎えるまでに何度も何度も頭の中でシミュレーションをしていたにもかかわらず、私の中の不安や動揺は消えませんでした。
変更後の受験校へ向かう電車を間違え、雨の中タクシーを長時間待つことになってしまいました。娘を受験会場へ送り出したあと、自分のふがいなさに涙が出ました。
午後は東京農業大学第一を受けましたが、娘の様子は芳しくありません。3日目の受験校を見直した方が良いのではと思い、結果を見る前でしたが気持ちが焦り、グノーブルへ相談をしました。焦っていた気持ちは、先生に今できることを示していただけたことで、何とか落ち着きました。
計画を練り直し、明日へ向けての準備に取り掛かろうとしたとき、ダメもとで見た東京農業大学第一の結果が「合格」でした。
あまりのうれしさに、かなり遅い時間ではありましたがグノーブルへ電話をかけてしまいました。それにもかかわらずワンコールで出てくださり、一緒に喜んでくださいました。こんな時間まで私たちと同様に考え悩んでいてくれていたのだと思うと、さらに感謝の気持ちがこみ上げてきました。
親が、平常心で大きく温かく子どもの受験を見守る、ということの大変さをとても強く感じる経験でした。そして、それを最初の保護者会での言葉通り支えてくださったグノーブルの先生方には本当に感謝しております。ありがとうございました。
これから受験を迎える皆さんも、心乱れることが多いとは思いますが、自分を信じ、子どもを信じ、グノーブルの先生に頼って、乗り切ってください。

私の受験
東京農業大学第一高等学校中等部進学Bさん
私は3年生の冬からグノーブルに入りました。最初の頃は、グノの授業を聞いてはノートに写す、それしか行っていませんでした。4年生になると課題の量も増えました。しかし、「基礎力テスト」や計算マスター、テキストの復習をきちんとやると、常に上のクラスにいられるようになります。5年生になると単元も難しくなり、どれだけ勉強したかがテスト結果に反映されやすくなります。私は5年生の夏休みに人並みの努力もしていなかったので、当然クラスは落ちました。6年生の前半は、土曜特訓があるだけで5年生の時とあまり変わりません。しかし、後半になると、過去問や日曜特訓が始まり、なかなか大変になります。ここで、私が6年生の後半にやっていた勉強法を教えます。
■国語:私は国語の記述は得意だったので、漢字と知識を受験本番まで重点的に行いました。できなかったところは、ノートにまとめておくことをおすすめします。
■算数:「基礎力テスト」は絶対(私は6年生の後半からようやく毎日やり始めました)。 復習テストは必ず行う。テキストも絶対に一周は復習する。後半はこれをやるだけで手いっぱいになります。
■理科:「基礎力テスト」は絶対。知識の単元の場合は、グノラーニングチェックと基本問題を行うことがおすすめです。また、物理や化学の単元は、テキストの基礎力問題と、先生に指定された応用問題を行いましょう。
■社会:とにかく漢字を間違えないようにする。直前の時期は、苦手な分野をとにかく解く。過去問で練習することもおすすめ。
■土曜特訓:平面図形マスター、立体図形マスターを重点的に解く。理科は、グノラーニングチェックと授業で解いたところと、優先順位が高いものを解く。社会は、テキスト全てを解いた方が良い。
■日曜特訓:大切なので授業で解いたところや、先生に指定されたところを必ず解く。とにかく重要。
ここからは、私の入試期間中のことについて書きます。
1月受験では、普段通りにやれば合格できると思っていた学校で不合格になってしまいました。敗因は単なる努力不足です。ここから、このままでは絶対に2月の学校も不合格だと思い、ようやく最後に過去問をもう一周し始めました。
そして、2月1日の当日発表で合格をもらえました。その時の嬉しさは忘れられません。その後、偏差値的にもチャレンジになる学校を受け不合格。とても悔しかったですが、この受験に後悔はしていませんでした。
新6年生の方へ:受験期間中、不安なことがあればグノーブルに電話することをおすすめします。いろいろ相談にのってくれますし、応援もしてくれます。最後に受験で合格できる子は、その学校に行きたいという意志をもって挑む子だと思います。その意志と、積み上げてきた努力があれば、第一志望校に落ちてもどこかで絶対合格できます。どんな形であれ、悔いのない形で受験が終わることを願っています。最後まで諦めずに頑張ってください。応援しています。
広尾学園小石川中学校
されど1点
広尾学園小石川中学校進学A君の保護者様
「おめでとうございます。繰り上がり合格です」この電話で、私達親子の受験は幕を下ろしました。
私達親子の希望は共学校。もちろん成績は大事でしたが、共学校では読みやすい丁寧な字が求められ、読めない記述は採点すらしてもらえないそうです。稀代の悪筆だった息子は、国語どころか算数の先生にも注意を受けない日がないほど。受験当日に見送る最後の時まで、字を丁寧にね! と声を掛け続けました。
息子は先に合格していた学校はありましたが、納得のいく中学に行きたい、と2月6日まで頑張りました。
最後の日は午後受験のみ。午前中は字の練習(笑)だけして早めに到着。親子で周囲を散歩し、リラックスをしたのが良かったのかもしれません。気合い充分で試験に向かって行きました。結果は不合格。実に14倍の激戦でした。
ところが4日後、携帯に最後に受けた中学から電話が! 先生からは万が一のこともあるかもしれないから携帯は肌身離さずにとは聞いていましたが、まさかの電話でした。
息子はその夜、グノの先生からで電話で「聞いたよ! やったな‼ 凄いぞ‼」と褒められて漸く実感出来たのかうれしそうに照れていました。後日聞いた話によると、繰り上げは僅か1点差だったそうです。グノの保護者会で何度も聞いた「されど1点なんです」これをここまで思い知らされるとは。
続く不合格にも諦めず腐らず、最後の最後まで気力を尽くした息子は、グノで積み重ねてきた知識と努力、そして先生方の熱意でその1点をつかみ取ったのだと思います。
息子、家族、何よりグノの先生方には感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。

広尾学園中学校
最後まで諦めない
広尾学園中学校進学A君
僕は新4年生の2月にグノーブルに入塾しました。4、5年生の間は家では塾の復習をしていました。6年生の夏休みは、夏期講習の塾以外の時間はあまり集中できず、成績も伸びませんでした。しかし、9月からは算数はテキストの◎の付いた問題はすべて解き、○は時間がある限り解き、毎朝1時間程度「基礎力テスト」をやりました。国語は、その回の「漢字道場」を2、3回繰り返すことで、授業の漢字テストの点数が伸び、自信を持つことができました。また、授業で解いた文章を毎日繰り返し読むことで、本番の文章に慣れることができたと思います。理科では植物の分類が苦手でしたが、グノラーニングチェックの内容をノートに書いて覚えました。本番当日にもそのノートを持参し、理科の試験前に確認しました。
僕はあえて1月受験をしませんでしたが、12月までにグノレブテストや外部模試をたくさん受けていたため、2月の本番でもあまり緊張しませんでした。2月1日午前は広尾学園の本科、午後は広尾学園の「SGコース」を受けました。本科は合格しましたが、SGは落ちてしまいました。しかしそこで落ち込まず、チャレンジする気持ちで2日の午後の「医進・サイエンスコース」を受験し、合格することができました。
グノーブルで3年間みっちり勉強したことで自信がつき、最後まで頑張れました。最後までサポートしてくださった先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
みなさんもグノーブルで学んだことを信じて、最後まで諦めずに頑張ってください。
子供の成長を実感できました
広尾学園中学校進学A君の保護者様
グノーブルに3年間お世話になりました。6年生の夏休みの終わりまでは家では集中できない時間も多くありましたが、グノーブルの授業はとても楽しそうでした。先生方にやる気が出るように上手に励ましていただき、切磋琢磨できる環境もあって、徐々に家でも授業の復習や過去問に集中して取り組めるようになりました。そして1月31日にグノーブルの先生から激励のお電話をいただき、本人も落ち着いて受験に臨むことができました。高い目標を設定して月曜特訓の渋渋算数クラスに通い続けることにより、秋から入試直前まで成績は着実に伸びましたし、広尾学園本科と医進・サイエンスコースの合格に繋がったと思います。
お世話になった先生方、事務の方々、最後まで本当にありがとうございました。
基礎をやって良かった!
広尾学園中学校進学B君
僕は新4年生の2月にグノーブルに入塾しました。6年生の夏くらいまでは、学校見学にはたくさん行っていたものの、正直なところ「行きたい学校」というものがよくわかりませんでした。ですが、はじめて見学した学校で良い雰囲気だったということもあり、10月ごろに広尾学園の受験を決意しました。しかし、過去問では最も合格者最低点に近づいた時でも20点ほどの差があり、最後の模試でも合格可能性40%でした。でも、そこから基本問題を練習したり、知識の穴埋めを行ったりしたことで1月校、2月1日の広尾学園にも合格することができました。
以下、参考程度に僕の勉強法を書いておきます。
🔳国語:漢字、知識は取れた方が良いのでテキスト、「漢字道場」はしっかりやっておくといいでしょう。読解は、日頃から文章を読むことで読解力や語彙力を身につけることが重要だと思います。特に長文がオススメなのでシリーズ物など良いと思いますが、難しい場合は少し簡単なものから始めてみても良いかもしれません。
🔳算数:最も苦手だったので、たくさんのことをやりました。特に12月ごろからは毎朝起きたあと、基礎力テストと計算問題をやり、広尾学園で出る場合の数、苦手な規則性と数の性質を1問ずつやるようにしました。
🔳理科:グノラーニングチェックの知識系をタブレットの暗記アプリに入れることで、寝る前にベッドで確認していました。また、直前期には苦手単元を書き出してその回のテ キストをやり直したりもしました。
🔳社会:理科と同じように、タブレットにアプリを入れるなどしていました。また、資料集を見たりするのも意外に役立つので試してみてください。
<最後に>
僕はお腹が弱かったので、試験の時に痛くなることもありました。でも、カイロを貼ったりするなどして対策をすることができました。皆さんの中にも緊張しがちな人がいるかもしれません。でもそんな時は深呼吸するなどしてリラックスしてください。そうすれば実力を出し切ることができます。皆さんも受験を頑張ってください。そして、僕を支えてくれたグノーブルの先生方、ありがとうございました。
三田国際科学学園中学校
一喜一憂せずに、志望校を目指す
三田国際科学学園中学校進学Aさん
私はグノーブルには4年生の頃からお世話になりました。4年生で入塾した時は、文系がαコース、理系がα5コースと明らかな文系女子でした。どの科目も家庭で復習はしていましたが、特に算数のわからないところを突き詰めて解決していなかったせいで、理系の成績は伸びませんでした。
そして、そのまま5年生になり、理系がα5コースあたりから脱却できない状況を改善したいと思い、算数の「基礎力テスト」の間違えたところを何度も復習し、疑問点は先生に質問するなど工夫して、対策するようにしました。おかげでα3コースに上がれるようになりました。
一方文系は、国語の読解は得意で高得点が取れていましたが、漢字に苦戦したため、毎日漢字練習を欠かさず、間違えた箇所を何度も書いて定着を目指しました。
6年生になってからは、算数のテキストを何度も復習して抜け漏れをなくすようにし、最後まで継続して取り組みました。加えて、夏休み明け以降は、志望校の過去問を繰り返し解いて傾向に慣れるようにし、基礎問題は確実に得点できるように努めました。その結果、1月には算数の点数は安定するようになってきました。
最後に一つ、みなさんにアドバイスがあります。入試直前まで、成績は上げることができます。個別の模試の合格可能性を見て一喜一憂せずに、あくまでも志望校を目指し、過去問など自分がやれることをやりきりましょう。みなさんの合格を願っています。
グノーブルで良かった
三田国際科学学園中学校進学Aさんの保護者様
娘がグノーブルに入塾したのは新4年生の2月でした。グノーブルに入塾を決めた理由は文系理系とそれぞれの成績でクラス分けされる特徴に惹かれたからです。入塾後のクラス分けで、本を読むのが好きな娘は国語は上位クラスになりましたが、算数は苦手だったので下位クラスとなりました。文理成績別クラスのおかげで、算数はやさしめに教えてもらうことができ、一方得意な国語はより楽しめるという環境で、娘の自己肯定感が下がりすぎることもなく塾の授業を受けることができたのは良かったです。
しかし、算数は入塾後も苦手なままで、4年生の入塾した頃には宿題に取り組ませても「わかんない」と言われ、「昨日授業で習ったでしょ」と言っても「忘れた」と言われるような始末でした。授業動画や解説を一緒に見たりして、泣きながらなんとか半日くらいかかって復習させても、翌週の復習テストでは1、2問しか合っていないこともあり、「この間は解けたのにどうしてできなかったの?」と聞いても「え…」と言うだけで、自分でも何がわからないのか、どう勉強したら良いのかわからない様子でした。授業を受け、指示通りに宿題をやっていくことで精一杯という様子でしたが、なんとか宿題とテストの復習は欠かさずやるようにしていきました。
学校見学などにいくつか行ってみたらモチベーションが上がるのではないかと思って、4年生の頃から何校か連れて行ってみました。「素敵な校舎だね」「制服かわいいね」など何かしら興味を持つかと思ったのですが、どこを見せても「別に…」と反応が薄く、娘がこの学校に行きたい! と思える学校はなかなか見つかりませんでした。
こんな幼い様子で中学受験には向いていないのではないか、と受験撤退を何度か悩みましたが、本人は「グノーブルを辞めたくない」といつも泣いて嫌がったので、本人の希望通りグノーブルを継続し、真面目に宿題に取り組み続けました。しかし、算数はずっと伸び悩み、色々と先生に相談するなど試行錯誤してきましたが、顕著な成果は表れませんでした。色々と苦手な単元を残したまま6年生後期の過去問に取り組む時期がきてしまい、どうしたものかと思いましたが、徐々に解ける問題が増え、ここにきてやっと理解が深まってきた様子でした。スパイラル方式のテキストで繰り返し同じ単元を学ぶことにより、遅まきながら結果が出てきたのだと思います。
また、特に気をつけていたのは、算数の「基礎力テスト」は毎回100点を目指すこと、土曜特訓の図形マスターと日曜特訓テキストでは、わからないところがないようにきちんとこなすことです。グノーブルのハイレベルなテキストに頑張ってついてきたことで、「これ、この間日曜特訓で出た問題だった。」と過去問も軽く解けたりすることもありました。
志望校については親子でよく話し合い、6年生に上がる頃には行きたい学校が絞られてきて、最終的には「ここに行きたい!」という学校を見つけ、熱意を持って入試に挑むことができました。
4年生の最初の頃には、この子には向いていないのかも…と思った中学受験でしたが、ゆるやかに、学力も精神的にも成長していたのかもしれません。
受験が終わったあとに「グノーブルで良かった。少人数クラスで良い先生ばかりで、グノーブルじゃなかったら心折れて中学受験を辞めていたかもしれない」と本人の口から聞いたときに、入塾したての頃あんなにつらそうに算数の宿題をしていた娘だったけれど、辞めずに続けて良かったんだと親の私も救われた気がしました。少人数による文理成績別クラス、楽しい先生方の授業のおかげで、娘も親もグノーブルで良かったと思えて中学受験生活を終えることができました。グノーブルには本当にお世話になり、先生方をはじめ、皆様に感謝しております。
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校
グノをやめたくない!
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校進学Aさん
私は4年生の冬期講習からGnobleに入塾しました。Gnoに入ろうと思ったのは、「学校で手を挙げすぎて指名されなくなり、つまらなかったから」でした。また、習い事との両立が可能な通塾日だったからというのもあります。私はGnoって楽しいという気持ちで授業を受けていました。家庭学習では「1人で勉強なんてつまんない‼︎」という思いから名目上は1日1時間(実質30〜40分程度)しか勉強しませんでした。
6年生の前期くらいまではそれで何とかなっていたのですが、夏期講習中や土曜特訓、日曜特訓が始まると時間が足りず、「復習テストがヤバい‼︎」ということが起きるようになりました。集中できたときは70〜80分くらい勉強するようになりましたが、友達の勉強時間が3〜5時間と私よりはるかに長く「大丈夫か?」と心配になることもありました。 そんな気持ちを解消し、リラックスするという名目で、毎週月曜日は必ず友達と放課後に遊んでいました。私が「受験生モード」になったのは12月終わり〜1月初めくらいです。逆にいうとそれまで受験生モードではないので、そこまでの模試の結果は関係ないといえるでしょう。事実、私は合格率30%の学校に合格できました。だから模試の結果に一喜一憂する必要はないです‼︎
【まとめ】
●模試の結果に一喜一憂しない!!
●勉強時間は「量より質」!!
●適度な息抜きも大切!!
●とにかく授業に集中!!
●そして、楽しみまくれ!!
私は今、「グノをやめたくない!」です。みなさんも「グノをやめたくない!」に共感できるよう受験に全力で挑んでください!! 応援しています‼︎
最後に、今まで受験を支えてくださったGnobleの方々本当にありがとうございました。
楽しく、刺激的な授業をありがとうございました
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校進学Aさんの保護者様
長女は、どうしても辞めたくない習い事があったため、5年生を週2回の通塾でカバーできるGnobleに転塾致しました。最初は算数の進度の速さと、社会のカリキュラムの違い(歴史の早期着手)に戸惑いましたが、先生方の手厚いフォローのおかげですぐに塾にも慣れることができました。何より、確認テストで得点できれば家庭学習の時間の長さは問わない、という実力主義が娘にはとても合っていたようで、確認テストやグノレブテストに向けて効率的な学習を進めるという習慣づけもできましたので、今後中学・高校に進んでからの勉強方法、勉強スタイルの確立にも役立てることができるように思います。
勧められて受験した他塾の模試では、難関校の合格判定が20~30%と振るわなかったものの、Gnobleの先生からは充分な合格可能性ありと勧めていただき、見事そのうちの1校の渋幕に合格することができました。結果としてそちらには進学しないことになりましたが、受験生活の総括という意味では本人の大きな自信につながったものと思います。受験を後押ししていただきどうもありがとうございます。
進学先の公立中高一貫校については、独特な出題形式を採っているものの、Gnobleで日ごろから私立対策を行う中での基礎力の養成を通じて(読解・作文・計算・図形・歴史・公民など)、特別な対策をほとんど行うことなく合格をいただくことができました。娘も通塾を通して志望校や趣味嗜好が様々変化していきましたので、このようなあらゆる受験にも耐えられるユニバーサルな基礎力を養っていただけた、という意味でもGnobleに大変感謝しています。
残念なのは、現在受験を終えた直後の娘の様子をうかがうかぎり、Gnobleの授業が突然終わってしまった「グノ・ロス」状態になっていて、何か寂しそうな・物足りなそうな印象を受けることでしょうか。いかにGnobleが楽しかったのか、娘と相性が良かったのかを感じさせます。もうすぐ中学校の新生活で、刺激的な日々が始まればそれも解消するものと思っています。
Gnobleの先生方、楽しくて刺激的な授業を、また、効率的な通塾システムを提供してくださり、そして、志望校合格という結果をもたらしていただき、どうもありがとうございました。
早稲田実業学校中等部
みなさんの合格を祈って
早稲田実業学校中等部進学Aさん
私は4年生の時にグノーブルに入塾しました。毎回の授業が楽しく、学ぶ楽しみを感じました。しかし6年生になってから勉強量も増え、成績が安定せずクラスが落ちることもありました。私の受験勉強方法を紹介します。
■国語:各回の解答解説を熟読する。これは先生に教えてもらったことですが、他の問題で似たような心情を記述するときに役立ちます。選択肢問題では必ず事実確認をします。消去法だけでは正解を選びづらいです。様々なジャンルの本を読み、語彙力を増やし、分からない語彙は必ず調べましょう。漢字はコツコツ努力して取り組んだほうが良いです。私は取り組み始めたのが遅かったので、受験当日まで苦労しました。
■算数:計算マスター・基礎力テストをやる。計算ミスをしてしまうと、解き方は分かっているのに失点になってしまいます。私は入試の時に1問目で約分を間違えていることに見直しで気がつき、試験終了30秒前に慌てて直したことを今でも覚えています。また、平面図形マスターもしっかりやりましょう。早稲田実業では平面図形の問題が出題されやすいため、頑張ってください。
■理科:間違えた問題を正解するまでやる。なぜここで間違えてしまったのか理由を明確にし、納得するまでやりましょう。テキストは先生から指定された範囲を必ずやり、苦手分野はベーシックを必ずやりましょう。苦手だった物理や化学の計算問題も、基本問題をやり直すことにより最終的には得点源になりました。
■社会:時代背景を理解する。ただ単に年号やこの人が何をしたのかと覚えるのではなく、その時代の流れを理解しましょう。歴史漫画を読むのもおすすめです。状況を結びつけることで、並び替え問題などが得意になります。
運も実力のうちと先生に言われましたが、試験前日にたまたま5年生の理科のノートで見返していた問題や、休憩時間に読んでいた本が物語文で出題されたりしました。これから受験をする皆さんも、運を味方につけ、グノーブルのテキストをしっかりやり、先生方を信じて頑張ってください。私はグノーブルに入ってとても良かったです。応援しています。
かけがえのない時間
早稲田実業学校中等部進学Aさんの保護者様
体験授業を終えて開口一番、ここの塾にする!授業がすごく楽しかった!と目をキラキラ輝かせて出てきてから、3年間毎回の授業をとても楽しんでいました。
娘の成績は6年生になるまでは比較的安定していましたが、それゆえに本人の慢心と勉強へのモチベーションの低さが課題でした。6年生の秋になっても、反抗期と重なり本人は変わらずマイペースで、私たちが思うような努力の形は見られなかったです。保護者会で先生からの「うちの子ならもっとやれるはず、できるはず、と思うかもしれませんが、それは親のエゴです。子どもたちは懸命に頑張っています。」という言葉に、それまで娘の態度にやきもきしていましたが、納得しました。最後の最後まで朝型生活にシフトすることはできませんでした。12月、学校でのトラブルに巻き込まれ娘のメンタルが落ち着かず、全く勉強も手につかず、成績は急降下。このまま受験ができなくなるのか、仮に受験できなくてもこれまでの頑張りはなくなることはないと腹を括るしかないのかと思っていました。何よりも娘のメンタルケアを一番にと、グノーブルの先生方も一丸となって支えてくださいました。
娘は1点に対する執着心の弱さが課題でした。問題の読み取り不足に、簡単な計算間違い。漢字のとめ、はね、はらい。本人が1点の重みに気付くことが一番大切で、そろそろ気が付くからと先生に言われ続け、気が付いたのは1月半ばでした。そこからは、今まで思うように取れなかった過去問の点数が安定し、当日も算数簡単だったと出てきました。漢字に関しては最後の最後まで振り回されました。
親が逃げ出したくなるような時でも、娘は受験を諦めないという気持ちだけは頑なに持ち続け、どんな時でも逃げずに立ち向かいました。娘の成長に驚くと共に、誇りに思います。 2月の数日間で全ての結果が出揃い、緊張、高揚、不安、戸惑いと、こんなにも短期間に感情が大きく振れたことはなかったように思います。グノーブルを選んで、信じてやり遂げたことで、目標の結果につながりました。中学受験だけでは終わらない知識、その得た知識を元にその先の世界を娘なりに見ていく方法を育んでいただいたと思います。子どもや各家庭で、漠然とこういう受験がしたいという思いがあると思います。前受校、併願校の選定など、いわゆるセオリーから外れるととても不安になるでしょう。あらゆる情報が溢れ、軸がぶれそうになるかもしれません。ここで挑戦したいという子どもの気持ちを何よりも大切にしてください。そして、迷った時、不安になった時は、グノーブルの先生を頼ってください。いつも真摯に受け止めてくださり、的確なアドバイスと励ましの言葉に心が軽くなり救われました。娘の性格を理解し、娘の良さを引き出す声がけをしてくださり、自信をつけてくださいました。先生方との出会いに親子共々心から感謝しております。ありがとうございました。
グノーブルで学んでいる皆様が合格を手にされますよう、そして卒業生の皆様の人生がより豊かなものでありますよう心から願っております。